===================
※この物語は完全なるフィクションです。
===================
川沿いの公園で、僕は少女に想いを伝えた。
「西岡さんのことを、もっとたくさん知りたいです。もし良ければ……今以上の関係になってもらえますか?」
少女は水面に映る月を見ながらこう答えた。
「……ごめんなさい。ずっと黙っていたことがあります」
その時の少女の悲しそうな顔が、何よりも印象的だった。
僕は26歳の会社員。彼女がいなければ友達もいない。趣味がなければ貯金もない。
毎日朝から晩までアクセク働いて、こんなに何もない人生。僕は一体何のために生きているのだろう。
「ピンポーン」
自らの現状に絶望していたある日、一人の少女との出会いがあった。
「はじめまして。隣の202に越して来た西岡結衣です」
早くも僕の心は揺れ動いた。それまでに出会った女性の中で一番可愛く、一番スカートが似合っていたのだ。
「あ、ど、どうも、中村雄介です、よ、よろしこ願します」
ただでさえ女性に免疫のない僕は、あまりの緊張に呂律が回らなかった。
「これ、つまらないものですがどうぞ」
ラッピングされた箱を受け取った僕はお礼を言い、もう一度「よろしこ願します」と言ってドアを閉めた。
いつまでも止むことのない異様な緊張感の原因は、明らかに一つしか考えられなかった。少女の顔が頭から離れられない。
その夜。明日は月曜日だと思うと僕は鬱になった。毎週これの繰り返しだ。本当にうんざりする。
だが、その日だけはいつもと違う夜だった。
「ピンポーン」
本日2度目のインターホン。そして再びあの少女だった。
「今、暇ですか?」
え? いきなり何を言い出すのか。
「もし暇なら、ちょっと出かけませんか?」
え!? これは夢なのか?
「あ、ハイ……イヤその、暇ですけど……一緒にですか?」
「私も暇なんです。行きましょうよ」
「あ……ハイ。いいですね、行きましょう」
あまりの超展開に僕は動揺を隠しきれなかった。さらには少女の自家用車に乗せてもらうことに。他にも友達がいるのかと思いきや、まさかの2人きりである。
僕は思わずカッコつけて「スタバなんてどうですか?」などと行ったこともない店を提案し、そこに入ったはいいものの、ミルクと砂糖の場所が解らずにオロオロしてしまう。だが少女は「ここにありますよ」と優しく教えてくれた。
僕等はお互いのことを聞き合った。少女は21歳、私立の大学に通う4年生だという。
「何で今になって引っ越してきたんですか?」
「ウーン……何故だと思います?」
「あ、イヤ、すみません、言わなくていいですよ」
スターバックスを出るとどこにも寄らずアパートに直行し、夢のような夜は幕を閉じた。
もう少女には嫌われているのかもしれない。過去の経験からそんな気がした。いつも上手くはいかないのだ。でもそれでいい。一日だけだけど楽しかったから。もういいんだ……。
しかし、3日後の夜。アパートに帰ると、なんとドアの前に少女が立っていた。
「階段を昇る音が聞こえたから出てみたんです。やっぱり中村さんでしたね。ちょっと出かけませんか?」
「え、いいですけど……えっ?」
「私、基本暇なんです。というより寂しがり屋なんですかね」
今度こそ夢だと思った。状況が飲み込めず、事実だけがどんどん先に進む。
しかも、ドトールの店内でさらなる奇跡が。
「私、毎日寂しいんで、メールとかしません?」
「えっ、いいんですか?」
少女は自分のメールアドレスと電話番号を赤外線で送ってくれた。何故こんなにも積極的なのか。
「あ、届きました。俺のも送りますからちょっと待ってて下さい」
しかし、アドレス交換などほとんどしたことのない僕は、赤外線送信のやり方すら解らなかった。
「エーット……あれ? こうじゃないか……あれ? あ、すみません、メールでもいいですか?」
「ンフフ。いいですよ」
僕の情けない姿を見ても、いつも笑ってくれる。可愛いだけでなく、すごく優しい。
その後、毎日のようにメール交換が行われた。
あまりにも上手くいきすぎて疑問にさえ思う。僕は騙されているのか、それとも遊ばれているのか。
「次の土曜日に映画に行きませんか?」
思い切って誘ってみた。少女は快くOKしてくれた。
当然何を観るかという話になり、ヤフーのレビューを参考に選んだ作品を提案すると、「私もちょうど観たかったんです」などと言ってくれて、それが本心かは解らないが、少女の優しさに僕は更に心を打たれた。
そして土曜日。映画は邦画の純愛もので、終盤で少女は涙を見せていた。僕は思わずひじ掛けに置かれた少女の左手を握ってしまった。が、嫌がられることはなかった。
「すみません泣いてしまって。私も高校時代にあんな恋愛してみたかったなあって思って……」
「イヤ何を言ってるんですか。これからあるかもしれないですよ」
その後も何度か2人きりで会った。その都度僕は性格ゆえの不手際が目立ったが、少女は僕の全てを受け入れてくれるかのように何も文句を言わなかった。騙されているとか遊ばれているとかそんな考えは次第に頭の中から消えていき、純粋に少女を想う気持ちだけが残っていた。臆病者の僕が思い切って少女に告白しようと心に決めるまで1ヶ月もかからなかった。
「……ごめんなさい。ずっと黙っていたことがあります」
2月の風が吹き抜ける川沿いの公園で、悲しそうな顔を浮かべる少女。告白は失敗に終わったかのように思えたが……。
「……私の命、そんなに長くないんです」
「えっ!?」
「私、末期の肝臓がんなんです」
(つづく)
===
第2話
===
※この物語は完全なるフィクションです。
===================
川沿いの公園で、僕は少女に想いを伝えた。
「西岡さんのことを、もっとたくさん知りたいです。もし良ければ……今以上の関係になってもらえますか?」
少女は水面に映る月を見ながらこう答えた。
「……ごめんなさい。ずっと黙っていたことがあります」
その時の少女の悲しそうな顔が、何よりも印象的だった。
僕は26歳の会社員。彼女がいなければ友達もいない。趣味がなければ貯金もない。
毎日朝から晩までアクセク働いて、こんなに何もない人生。僕は一体何のために生きているのだろう。
「ピンポーン」
自らの現状に絶望していたある日、一人の少女との出会いがあった。
「はじめまして。隣の202に越して来た西岡結衣です」
早くも僕の心は揺れ動いた。それまでに出会った女性の中で一番可愛く、一番スカートが似合っていたのだ。
「あ、ど、どうも、中村雄介です、よ、よろしこ願します」
ただでさえ女性に免疫のない僕は、あまりの緊張に呂律が回らなかった。
「これ、つまらないものですがどうぞ」
ラッピングされた箱を受け取った僕はお礼を言い、もう一度「よろしこ願します」と言ってドアを閉めた。
いつまでも止むことのない異様な緊張感の原因は、明らかに一つしか考えられなかった。少女の顔が頭から離れられない。
その夜。明日は月曜日だと思うと僕は鬱になった。毎週これの繰り返しだ。本当にうんざりする。
だが、その日だけはいつもと違う夜だった。
「ピンポーン」
本日2度目のインターホン。そして再びあの少女だった。
「今、暇ですか?」
え? いきなり何を言い出すのか。
「もし暇なら、ちょっと出かけませんか?」
え!? これは夢なのか?
「あ、ハイ……イヤその、暇ですけど……一緒にですか?」
「私も暇なんです。行きましょうよ」
「あ……ハイ。いいですね、行きましょう」
あまりの超展開に僕は動揺を隠しきれなかった。さらには少女の自家用車に乗せてもらうことに。他にも友達がいるのかと思いきや、まさかの2人きりである。
僕は思わずカッコつけて「スタバなんてどうですか?」などと行ったこともない店を提案し、そこに入ったはいいものの、ミルクと砂糖の場所が解らずにオロオロしてしまう。だが少女は「ここにありますよ」と優しく教えてくれた。
僕等はお互いのことを聞き合った。少女は21歳、私立の大学に通う4年生だという。
「何で今になって引っ越してきたんですか?」
「ウーン……何故だと思います?」
「あ、イヤ、すみません、言わなくていいですよ」
スターバックスを出るとどこにも寄らずアパートに直行し、夢のような夜は幕を閉じた。
もう少女には嫌われているのかもしれない。過去の経験からそんな気がした。いつも上手くはいかないのだ。でもそれでいい。一日だけだけど楽しかったから。もういいんだ……。
しかし、3日後の夜。アパートに帰ると、なんとドアの前に少女が立っていた。
「階段を昇る音が聞こえたから出てみたんです。やっぱり中村さんでしたね。ちょっと出かけませんか?」
「え、いいですけど……えっ?」
「私、基本暇なんです。というより寂しがり屋なんですかね」
今度こそ夢だと思った。状況が飲み込めず、事実だけがどんどん先に進む。
しかも、ドトールの店内でさらなる奇跡が。
「私、毎日寂しいんで、メールとかしません?」
「えっ、いいんですか?」
少女は自分のメールアドレスと電話番号を赤外線で送ってくれた。何故こんなにも積極的なのか。
「あ、届きました。俺のも送りますからちょっと待ってて下さい」
しかし、アドレス交換などほとんどしたことのない僕は、赤外線送信のやり方すら解らなかった。
「エーット……あれ? こうじゃないか……あれ? あ、すみません、メールでもいいですか?」
「ンフフ。いいですよ」
僕の情けない姿を見ても、いつも笑ってくれる。可愛いだけでなく、すごく優しい。
その後、毎日のようにメール交換が行われた。
あまりにも上手くいきすぎて疑問にさえ思う。僕は騙されているのか、それとも遊ばれているのか。
「次の土曜日に映画に行きませんか?」
思い切って誘ってみた。少女は快くOKしてくれた。
当然何を観るかという話になり、ヤフーのレビューを参考に選んだ作品を提案すると、「私もちょうど観たかったんです」などと言ってくれて、それが本心かは解らないが、少女の優しさに僕は更に心を打たれた。
そして土曜日。映画は邦画の純愛もので、終盤で少女は涙を見せていた。僕は思わずひじ掛けに置かれた少女の左手を握ってしまった。が、嫌がられることはなかった。
「すみません泣いてしまって。私も高校時代にあんな恋愛してみたかったなあって思って……」
「イヤ何を言ってるんですか。これからあるかもしれないですよ」
その後も何度か2人きりで会った。その都度僕は性格ゆえの不手際が目立ったが、少女は僕の全てを受け入れてくれるかのように何も文句を言わなかった。騙されているとか遊ばれているとかそんな考えは次第に頭の中から消えていき、純粋に少女を想う気持ちだけが残っていた。臆病者の僕が思い切って少女に告白しようと心に決めるまで1ヶ月もかからなかった。
「……ごめんなさい。ずっと黙っていたことがあります」
2月の風が吹き抜ける川沿いの公園で、悲しそうな顔を浮かべる少女。告白は失敗に終わったかのように思えたが……。
「……私の命、そんなに長くないんです」
「えっ!?」
「私、末期の肝臓がんなんです」
(つづく)
===
第2話
===










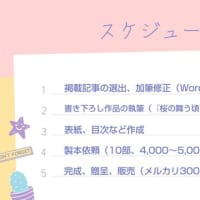









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます