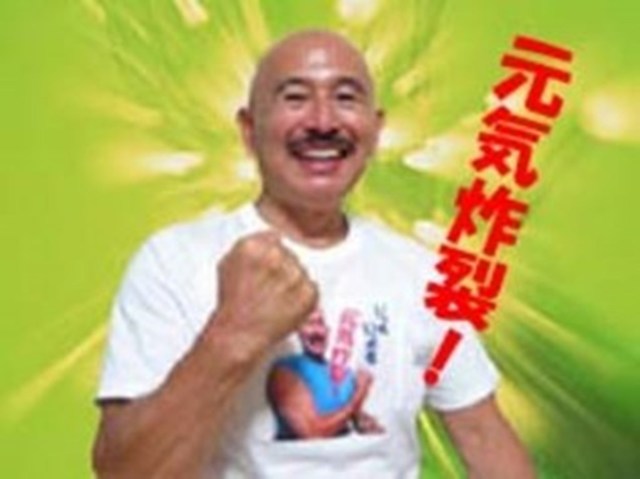私は仕事を辞めた現在もパソコン作業や文字を書いたり書類を整理したり
するときは自分で改良したパソコンデスクを使っている。
これは自分の部屋はあまり広くないので机も天板(甲板)や足を取り外して
片袖の抽斗(ひきだし)部分だけを使い、スペースの有効活用するためで、
ベッドの下は勿論、空間を最大限に利用し、種々雑多なものを収納しているのだ。
普段必要な文具や書類ケースなどは改良パソコンデスクの周辺に配置して
あるので机の抽斗を開けることはあまり多くはないが、久しぶりに机の引き出しの
中を整理しようと思い、細かく分けられた仕切りや箱の中のものを取り出し始めると
パソコンデスク周りにまとめてあるつもりの鉛筆の残り2本が出てきた。
その2本はいずれも芯が折れた状態で、普段はほとんど使わない三角スケールや
折尺やコンパス類と一緒に細長い箱の中に入っていたのだ。
すぐに削りなおして鉛筆類が入った箱に移そうと思い、手回しの鉛筆削りを
手にしたのだが、その鉛筆の先はナイフかカッターで削られたものだということに
気づき、懐かしさや幾つもの小さな思い出が蘇ってきた。
出てきた2本の鉛筆の削り方を見ると六つの角から芯の部分までの削り幅や
長さや角度が不揃いで明らかに自分が削ったものではないことが判り
『誰が削ったものだろう?・・・』と思った。
その鉛筆には『高崎芸術短期大学』の名前が入っていたが家族や友人関係との
関連も思いつかず、また『高崎芸術短期大学』を検索すると2008年に廃止されて
いることなどから10年以上前から我が家にあったものだと思われる。
どんな経緯で私の机のなかに入ってきたのか不思議なのでいずれ判明するまで
これはこれできちんと(?)保存しておこうと考え、あらためて正しい私の削り方で
保管することにした。
さて、削るとなると・・・
最近はほとんどの場合早くて便利な鉛筆削りを利用するので私自身も久しぶりに
鉛筆を削ることへの「わくわく感」のようなものを覚えた。
そして数多い私の道具箱の中から「切り出し小刀」を取り出し既に削ってある
部分に刃をあてて右手で持った小刀の柄と刃の接合部分をしっかりと押さえ、
左手の人差し指の第一関節から小指の付け根にかけて斜めに握った鉛筆の先の
削る箇所に刃をあてて親指で刃の峰の部分を押しながら削っていく・・・
という懐かしい動作。
久しぶりの小刀だが、刃先の向きや角度と削る量などの微調整のようなものは
やっぱり忘れていない。
現代の若者にも小刀などをうまく扱える人はいることと思うが、私たちやその
前後の世代の人たちは子供の頃から自分で鉛筆を削っていたので今でも上手く
削れるのではないかと思う。
まさに『昔とった杵柄』と言えるのではないだろうか。
私が使った小刀は一般的に「小刀」や「切り出し」「切り出し小刀」と言われている
ようだが「切り出し」と「小刀」は違うらしい。
切り出しは『切り出しナイフ』『共柄切り出し』などと呼ばれ小刀は『鎖入れ小刀』
『繰小刀』『横手小刀』と呼ばれるものという説明があった。
切り出しは刃と柄が一体になっているもので小刀は鞘のあるものというのが
わかりやすいのだろうか。
いずれ切り出しについてもっともっと調べてみたいと思うが・・・
私たちが小、中学生の頃は『肥後守』が普及しており、この切り出し小刀よりも
肥後守が多く使われ、必需品のようだった。
この言葉でいろんな懐かしい思い出が蘇ってくる人たちも多いことだろう。
鉛筆を削るだけではなく、いろんな工作や遊びの材料を作るのにも軽量で
使いやすく、ポケットにも入り、「危険」「犯罪」などの感覚など全くなく、便利な
道具としての認識しかなかったが現在の中学生がポケットに入れて持ち歩く
ことは許されないのかもしれない。
私が持っている『肥後守』は子供の頃のものではなく30年以上も前に買った
ものだが一般の人には考えられないほど種類も数も多い道具や工具を持っている
私の道具箱の数があまりにも多いので常日頃きちんと分類と整理はしていても
『肥後守』はすぐに見つからず、今回は『鎖入れ小刀』を使って削ってみたのだ。
『肥後守』の行方をゆっくりと探してみて見つからなければネットで購入し
追加保存しておこう。次はいつ使うかわからないが・・・。
するときは自分で改良したパソコンデスクを使っている。
これは自分の部屋はあまり広くないので机も天板(甲板)や足を取り外して
片袖の抽斗(ひきだし)部分だけを使い、スペースの有効活用するためで、
ベッドの下は勿論、空間を最大限に利用し、種々雑多なものを収納しているのだ。
普段必要な文具や書類ケースなどは改良パソコンデスクの周辺に配置して
あるので机の抽斗を開けることはあまり多くはないが、久しぶりに机の引き出しの
中を整理しようと思い、細かく分けられた仕切りや箱の中のものを取り出し始めると
パソコンデスク周りにまとめてあるつもりの鉛筆の残り2本が出てきた。
その2本はいずれも芯が折れた状態で、普段はほとんど使わない三角スケールや
折尺やコンパス類と一緒に細長い箱の中に入っていたのだ。
すぐに削りなおして鉛筆類が入った箱に移そうと思い、手回しの鉛筆削りを
手にしたのだが、その鉛筆の先はナイフかカッターで削られたものだということに
気づき、懐かしさや幾つもの小さな思い出が蘇ってきた。
出てきた2本の鉛筆の削り方を見ると六つの角から芯の部分までの削り幅や
長さや角度が不揃いで明らかに自分が削ったものではないことが判り
『誰が削ったものだろう?・・・』と思った。
その鉛筆には『高崎芸術短期大学』の名前が入っていたが家族や友人関係との
関連も思いつかず、また『高崎芸術短期大学』を検索すると2008年に廃止されて
いることなどから10年以上前から我が家にあったものだと思われる。
どんな経緯で私の机のなかに入ってきたのか不思議なのでいずれ判明するまで
これはこれできちんと(?)保存しておこうと考え、あらためて正しい私の削り方で
保管することにした。
さて、削るとなると・・・
最近はほとんどの場合早くて便利な鉛筆削りを利用するので私自身も久しぶりに
鉛筆を削ることへの「わくわく感」のようなものを覚えた。
そして数多い私の道具箱の中から「切り出し小刀」を取り出し既に削ってある
部分に刃をあてて右手で持った小刀の柄と刃の接合部分をしっかりと押さえ、
左手の人差し指の第一関節から小指の付け根にかけて斜めに握った鉛筆の先の
削る箇所に刃をあてて親指で刃の峰の部分を押しながら削っていく・・・
という懐かしい動作。
久しぶりの小刀だが、刃先の向きや角度と削る量などの微調整のようなものは
やっぱり忘れていない。
現代の若者にも小刀などをうまく扱える人はいることと思うが、私たちやその
前後の世代の人たちは子供の頃から自分で鉛筆を削っていたので今でも上手く
削れるのではないかと思う。
まさに『昔とった杵柄』と言えるのではないだろうか。
私が使った小刀は一般的に「小刀」や「切り出し」「切り出し小刀」と言われている
ようだが「切り出し」と「小刀」は違うらしい。
切り出しは『切り出しナイフ』『共柄切り出し』などと呼ばれ小刀は『鎖入れ小刀』
『繰小刀』『横手小刀』と呼ばれるものという説明があった。
切り出しは刃と柄が一体になっているもので小刀は鞘のあるものというのが
わかりやすいのだろうか。
いずれ切り出しについてもっともっと調べてみたいと思うが・・・
私たちが小、中学生の頃は『肥後守』が普及しており、この切り出し小刀よりも
肥後守が多く使われ、必需品のようだった。
この言葉でいろんな懐かしい思い出が蘇ってくる人たちも多いことだろう。
鉛筆を削るだけではなく、いろんな工作や遊びの材料を作るのにも軽量で
使いやすく、ポケットにも入り、「危険」「犯罪」などの感覚など全くなく、便利な
道具としての認識しかなかったが現在の中学生がポケットに入れて持ち歩く
ことは許されないのかもしれない。
私が持っている『肥後守』は子供の頃のものではなく30年以上も前に買った
ものだが一般の人には考えられないほど種類も数も多い道具や工具を持っている
私の道具箱の数があまりにも多いので常日頃きちんと分類と整理はしていても
『肥後守』はすぐに見つからず、今回は『鎖入れ小刀』を使って削ってみたのだ。
『肥後守』の行方をゆっくりと探してみて見つからなければネットで購入し
追加保存しておこう。次はいつ使うかわからないが・・・。