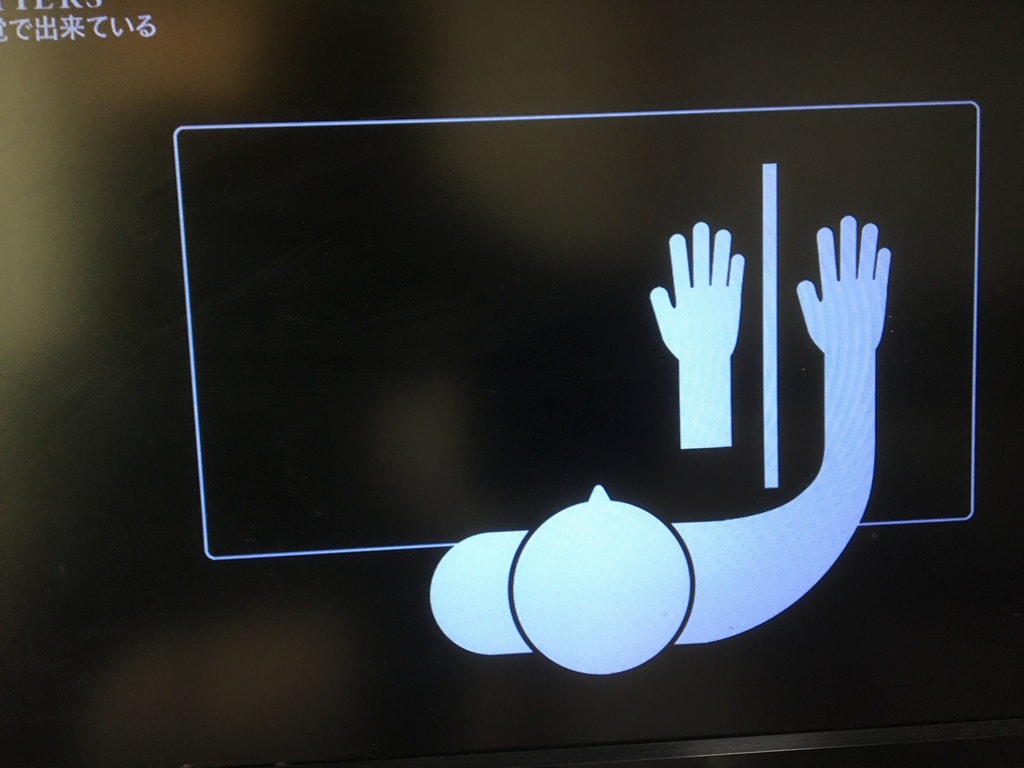先日久し振りに友人と会ったのだが、彼が「お釈迦さんが言うてた教えと日本の仏教とは全然別のものと違うんか?」 と言い出した。例えば浄土系の宗派ではやたら念仏と言うけれが、はたして釈尊が実際にそうしたことを説いたのかどうか疑わしいというわけである。禅宗と浄土真宗では線香をたくのと読経するという点においては似ているだけで、中身は全然違う。阿弥陀信仰を説く浄土真宗などは外形的にはむしろキリスト教のような一神教に近いように思える程である。
仏教という宗教のあり方が緩やかなのは、その原理が無と空であるということに由来するのは間違いのないことだと思う。「無」というのは主体が究極的には存在しないということ、「空」というのはなにごとも固定的な実態というものは存在しないことを意味する。「無」からは我欲というものが実は幻想であり、「空」からはなにごとも言葉によって断定されることがないということが導かれる。 つまり、おのれを空しくし他に優しくするということで既に仏教の必要条件を満たしており、言葉によって他を排斥しないということであれば、それはもうすでに仏教としての十分条件を満たしているのである。
禅宗では坐禅を通じて自己を内観し、その結果究極の主体としての無に行きつく。その時新たにこの現実の世界が妙に満ち溢れたものとして顕現する、その感動がこの世界への感謝つまり愛となる、それを悟りというのだろう。浄土真宗の場合はひたすら念仏を通じて阿弥陀仏に帰依することによりおのれを空しくするのである。はからいを一切捨てた時、すでに阿弥陀如来によって救われていることを実感する、というのは禅宗の悟りと何ら変わることはない。どちらも釈尊の説く教えに沿っているのである。
キリスト教はどうか? 新約聖書「ヨハネによる福音書」第1章 の冒頭は「始めに言葉(logos)ありき」で始まっている。 キリスト教は神の言葉である膨大な聖書の言葉のどれもおろそかにはできない。解釈が違えばそれは異端ということになる。過去にはそれが原因の争いで多くの血が流されてきたことは周知のとおりである。言葉はイデオロギーとなる、イデオロギーは争いを生むのである。言葉によるイデオロギーは畢竟臆見を含む、それに固執すれば有無の邪見となるというのが釈尊の説かれる所である。
仏教においては特に中庸ということを重視する、だから決して異端というものも生まれない。重要なのは人々が幸せであることである。そこに至る径は一本道ではない。最近よく言われるダイバーシティ(多様性)という言葉は仏教ととても相性の良い言葉だと思う。