ドイツ行きに備えて読んでいたヘッセの2冊、特に「知と愛」は旅行までには読み終わらないだろう・・・と思っていたら、意外と読みやすくて旅行前に読み終えることができました。
まず「車輪の下」。中学生の頃かなりハマっていた時期があったのですが、その後トーマス・マンにハマって、「ヘッセは軟弱だから好みじゃない」とか豪語してすっかり読まなくなっていたのでした。ヘッセったって「車輪の下」しか読んでなかったくせに・・・(汗)
とっても久々に読んでみて、やはり「車輪の下」は面白いなあと思いました。ハンスの少年らしい細やかな心情がありありと描かれていて、共感というよりも同情を覚えるし。
何よりも、夏休みに魚釣りや川泳ぎをする様子の描写が活き活きとしていて、とても魅力的でした。
神学校でのハンスとハイルナーの、少年らしい未成熟で激しい友情にも、今読んだらどうかな、と思ったのですが、素直に好感を持って読めました。
中学生の頃は、ハンスが学校を辞めてからのエピソードにはあまり興味がなく、結末も忘れていたくらいでしたが(汗)今回は、かわいそうに、と思えました。
当時はうつ病についての理解なんてほとんど全くなかったでしょうから・・・周囲に理解してくれる人がいれば、なんてかわいそうに思いました。つーか、ハイルナーがもうちょっとなあ・・・(汗)やっぱり子供なんですなあ。
ハンスのうつ病はヘッセ自身の体験でもあるそうですが、ヘッセは母親の愛情で回復することができたそうですからなおさらです。(牧師である父親もハンスの父親とは全く違ったでしょうし)
作中に、神学校時代にもハンスに同情的で親切な助手が一人いたということが書いてありましたが、ヘッセ自身にも実際にはハンスよりも理解して暖かく見守っていてくれる人は多かったのではないかと思いました。
この作品、日本ではヘッセの作品中一番親しまれていると思いますが、ドイツでは8番目に読まれているとかだそうです。(邦訳当時のデータなので古いと思いますが)
確かに日本人向きな作品かもなあと思いました。
続いて「知と愛」。「車輪の下」にも出てくるマウルブロン修道院をモデルにしたマリアブロン修道院というのが出てくるというので、マウルブロン修道院に行く下準備として読んでみました。この作品はドイツではヘッセの作品中2番目に読まれているそうで(これも邦訳当時のデータですが)、ヘッセと親交の深かったロマン・ロランも絶賛しているらしいです。
最初読んでいて、ゴルトムントはなんで試験もなしに神学校に入れたんだろう、なんて思いましたが、騎士が出てきて初めて気づきました。これかなり古い時代の話なんだということに・・・(笑)
読んでみての私の感想は、うーん、やっぱり私にはヘッセは向かないなあ、ということでした(汗)
軟弱とまでは言いませんが・・・(汗)やっぱりトーマス・マンの方が好きだなあと。
しかし、なんだかんだとかなり読みやすく、とんとんと読み進むことはできました。
あまり共感が得られる話ではなかったのですが(汗)最後の方、ナルチスがゴルトムントを看取る場面にちょっと感動しました。このシーンを書くためにそれまでの話があったのかな、と思うとちょっと納得なのですが。
ナルチスが静かにゴルトムントに「私が愛というものを知っているとしたらそれは君のおかげだ」と告白する場面を読んでいて、これSTUDIO LIFEでやってもいいかもなあと思いました・・・というか、ナルチスを林勇輔さんで見たい(汗)もっと言うと、あの最後の方のナルチスの台詞を林勇輔さんの声で聞きたい・・・(笑)
ゴルトムントの「君は母を知らないとしたらどうやって死ぬのだ? 母がなければ生きることはできない。母がなければ死ぬことはできない」という最後の言葉が「ナルチスの中で火となって燃え続けた」というようなラストも良かったかな・・・
この作品で描かれているのは、「芸術と信仰」という二極対立だと思いますが、芸術家って皆こういう風に悩むのかな・・・と思ったくらい、トーマス・マンが抱き続けていた二極対立と同じだったのが興味深かったです。
芸術を一種罪を伴うものだと認識していて、健全で正しい生活との両立を夢見るけれどできないという・・・
牧師の家庭に育ったヘッセにはその健全な生活とは信仰で、裕福な商人の家庭に育ったマンにとっては立派で社交的な社会生活、ということになるでしょうか。
そして、二人とも学業には挫折して作家、詩人を志していますね。まあ、トーマス・マンは最初から学業に興味がなく落ちこぼれていたようですが。
こういうのを読んでいると、大学教授の椅子という、学術的にも社会的にも立派な地位をしっかりゲットしたトールキンやルイスは「芸術家」とは違う人種だなあと思わざるを得ませんね。彼らにはヘッセやマンのような葛藤はなかったでしょう。
こういうところが、トールキンを「作家」や「小説家」とは呼べないように思うとろかなあと思ったりします。
話が逸れましたが(汗)そういうテーマを持ったこの作品、私の好みではないけれど(汗)確かに芸術家としてのヘッセの入魂の作品ではあるなあ、というのは感じました。これと比べると「車輪の下」は名作ではあるけれど小品だなあと。
でもそういう意味でも、やっぱり私にはヘッセは合わないなあ、と思いました(汗)
この二つの作品の舞台となったカルフとマウルブロン修道院に行った時のもようは、後日旅行カテゴリにUPする予定です。いつになるかな~(汗)
まず「車輪の下」。中学生の頃かなりハマっていた時期があったのですが、その後トーマス・マンにハマって、「ヘッセは軟弱だから好みじゃない」とか豪語してすっかり読まなくなっていたのでした。ヘッセったって「車輪の下」しか読んでなかったくせに・・・(汗)
とっても久々に読んでみて、やはり「車輪の下」は面白いなあと思いました。ハンスの少年らしい細やかな心情がありありと描かれていて、共感というよりも同情を覚えるし。
何よりも、夏休みに魚釣りや川泳ぎをする様子の描写が活き活きとしていて、とても魅力的でした。
神学校でのハンスとハイルナーの、少年らしい未成熟で激しい友情にも、今読んだらどうかな、と思ったのですが、素直に好感を持って読めました。
中学生の頃は、ハンスが学校を辞めてからのエピソードにはあまり興味がなく、結末も忘れていたくらいでしたが(汗)今回は、かわいそうに、と思えました。
当時はうつ病についての理解なんてほとんど全くなかったでしょうから・・・周囲に理解してくれる人がいれば、なんてかわいそうに思いました。つーか、ハイルナーがもうちょっとなあ・・・(汗)やっぱり子供なんですなあ。
ハンスのうつ病はヘッセ自身の体験でもあるそうですが、ヘッセは母親の愛情で回復することができたそうですからなおさらです。(牧師である父親もハンスの父親とは全く違ったでしょうし)
作中に、神学校時代にもハンスに同情的で親切な助手が一人いたということが書いてありましたが、ヘッセ自身にも実際にはハンスよりも理解して暖かく見守っていてくれる人は多かったのではないかと思いました。
この作品、日本ではヘッセの作品中一番親しまれていると思いますが、ドイツでは8番目に読まれているとかだそうです。(邦訳当時のデータなので古いと思いますが)
確かに日本人向きな作品かもなあと思いました。
続いて「知と愛」。「車輪の下」にも出てくるマウルブロン修道院をモデルにしたマリアブロン修道院というのが出てくるというので、マウルブロン修道院に行く下準備として読んでみました。この作品はドイツではヘッセの作品中2番目に読まれているそうで(これも邦訳当時のデータですが)、ヘッセと親交の深かったロマン・ロランも絶賛しているらしいです。
最初読んでいて、ゴルトムントはなんで試験もなしに神学校に入れたんだろう、なんて思いましたが、騎士が出てきて初めて気づきました。これかなり古い時代の話なんだということに・・・(笑)
読んでみての私の感想は、うーん、やっぱり私にはヘッセは向かないなあ、ということでした(汗)
軟弱とまでは言いませんが・・・(汗)やっぱりトーマス・マンの方が好きだなあと。
しかし、なんだかんだとかなり読みやすく、とんとんと読み進むことはできました。
あまり共感が得られる話ではなかったのですが(汗)最後の方、ナルチスがゴルトムントを看取る場面にちょっと感動しました。このシーンを書くためにそれまでの話があったのかな、と思うとちょっと納得なのですが。
ナルチスが静かにゴルトムントに「私が愛というものを知っているとしたらそれは君のおかげだ」と告白する場面を読んでいて、これSTUDIO LIFEでやってもいいかもなあと思いました・・・というか、ナルチスを林勇輔さんで見たい(汗)もっと言うと、あの最後の方のナルチスの台詞を林勇輔さんの声で聞きたい・・・(笑)
ゴルトムントの「君は母を知らないとしたらどうやって死ぬのだ? 母がなければ生きることはできない。母がなければ死ぬことはできない」という最後の言葉が「ナルチスの中で火となって燃え続けた」というようなラストも良かったかな・・・
この作品で描かれているのは、「芸術と信仰」という二極対立だと思いますが、芸術家って皆こういう風に悩むのかな・・・と思ったくらい、トーマス・マンが抱き続けていた二極対立と同じだったのが興味深かったです。
芸術を一種罪を伴うものだと認識していて、健全で正しい生活との両立を夢見るけれどできないという・・・
牧師の家庭に育ったヘッセにはその健全な生活とは信仰で、裕福な商人の家庭に育ったマンにとっては立派で社交的な社会生活、ということになるでしょうか。
そして、二人とも学業には挫折して作家、詩人を志していますね。まあ、トーマス・マンは最初から学業に興味がなく落ちこぼれていたようですが。
こういうのを読んでいると、大学教授の椅子という、学術的にも社会的にも立派な地位をしっかりゲットしたトールキンやルイスは「芸術家」とは違う人種だなあと思わざるを得ませんね。彼らにはヘッセやマンのような葛藤はなかったでしょう。
こういうところが、トールキンを「作家」や「小説家」とは呼べないように思うとろかなあと思ったりします。
話が逸れましたが(汗)そういうテーマを持ったこの作品、私の好みではないけれど(汗)確かに芸術家としてのヘッセの入魂の作品ではあるなあ、というのは感じました。これと比べると「車輪の下」は名作ではあるけれど小品だなあと。
でもそういう意味でも、やっぱり私にはヘッセは合わないなあ、と思いました(汗)
この二つの作品の舞台となったカルフとマウルブロン修道院に行った時のもようは、後日旅行カテゴリにUPする予定です。いつになるかな~(汗)











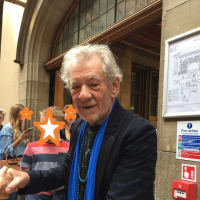



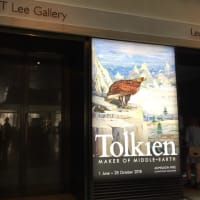










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます