前回、宣長の筆写した景山の『不尽言』をご紹介しましたが、今回は宣長が写した場所を示します。箇条書きの全文のうち、写さなかった箇所を小文字にして、色を薄く表示します。なぜこのような一見無駄な、非効率的な方法を選択したのかというと、宣長の理解のためには、彼と同じ経験を味わう、一種の追体験にまさる理解はないと考えるからです。では『不尽言』は箇条書きではなく、全文をそのまま読んでもらうべきではないかという意見もあるでしょう。まったくその通りです。これは原文で何度も読む価値のある作品であり、当時の江戸中期だけでなく、平安朝から黒船来航、明治維新後の日本の歴史が想起される内容です。原文は書籍でぜひお読みください。ただし当ブログでは、データ容量がたくさんないこと、原文中に内容の重複がかなりあること、データの入力や読む人の手間、著作権などを鑑みてこのように妥協しています。
○不盡言
1.日本人の学問の入り方は、まず字義と語勢をよく弁じ、それを和語に翻訳して、合点するのが、最も第一の事である
・元来、書物はみな中華の物であるので、まず下地に中華の文字の意味によく通達しなかったら、書は読まれない。
・文字という物は元来中華の物であり、日本へ伝来したものである。
・我国には文字の音というものはかつてなかった。文字の音は呉音と漢音の二つがある。
・日用書通の文字も、その本はみな中華の草書の体である。
・筆法はみな中国より伝授したため、古人はみな手跡古雅にして唐流である。
・文字というものは、元来一つも日本の物ではなく、そのため中華の文字四十八字を借り用いて、以呂波とした。
・書を読むとはいうは、その意義を合点して吟誦する事である。
・和訓というものは、即ち字義にして、また和語である。しかし和訓ばかりでは、文字の意味には通達できない。心で合点せねばならない。
・中華は天性文字の国なるため、だれもが文字の意味に通達している。林羅山など、日本の大儒といわれる人でも、羅山文集の内には大きな転倒が多くある。
・日本人の学問の入り方は、外の事はまず差し置き、文字の意義をよく味い合点するのが、第一の事である。
・古聖賢の語は書を離れて外にはなく、その書という物はみな中華の物である。
・かの字義を弁ずる内には、また中華の人の語勢を合点しなかったら、書は読まれない。
・元来文字というもの、神妙不測なるありがたき物であり、天地の間に一日もなくては叶はない。
・書を読むには日本人の心持ちをはなれて中華人の心持ちになり代わらねば、正真ではない。
・日本人の学問の入り方は、まず字義と語勢をよく弁じて、それをずいぶん違わぬように徐々に和語に翻訳し、合点するのが、最も第一の事である。
・書を読まずして学文という事はない。
・理というものは畢竟極まったようなもので極まらぬもの、空なるものであるため、その内に正真の理を知るというのは、聖賢でなくてはならない。
・日本の儒者のいうものに、ただ仮名抄であり講釈の弁書きを、その師匠より互に秘伝し口訣とし、学文という事をそれですまし、孔子の意にも朱子の意にもかつてない事などを、私意より造り拵へ、人を面白がらす弁をふるい、俗人を誤まらす輩などが多くある。
・日本に剣術者流というものは、それぞれ理屈を造り拵へて、一種の道を説くものが多く、文盲なる武士をあざむく類もあり。近頃には京師に茶道といって、点茶の道の根源は論語の理より出たる事とて、孔子の語を借り用ひ、その理を弁ずる事甚だ面白く、人の耳を驚かし、間に文盲な者はもっともなる事と感服する輩もあり、京ではこれを茶儒と称する。
・三代先王・孔夫子の書を借り用い、己れが私意をもって下賤なる家業の飾とし、人を騙弄する事、さてさて悲むべく物体ない。
2.道理よりも歴史を先に学ぶべし
・古来、経と史とは、車の両輪、鳥の両翼の如きものである。
・経はみな、そうでなくてはならぬはずの定まりたる道理を説いて、兼々に人に教訓しおきたるものである。
・史はみな、古より近代迄の代々の時勢風俗、事により時に臨んでの人の言行、善悪ともにありのままに記録し、代々の君臣の政治、行跡、人情の変態を、ことごとく知らしめるものである。
・中人以下の人は、平生あまりに理ばかり詮議しすぎ、それに拘泥して理屈臭くなるので、必ず時に臨み事によりて、結局偏屈であり通用しない事が出てきて、理を取り惑い、悪くしては、しそこなう事もある。
・人君と立ち、国家を支配する人は、まず古今の事実、時勢の成敗をよく考え知らねばならない。
・たいていの人にとって、『大学』の教は聞いても理解が難しく、優れた人でなければ、『大学』の教えを聞いても役にたたない。
・『小学』の教は、あらゆる人の教であり、まずたいてい普通の人は、『小学』の教だけで足りる。
・すべて人は幼少からの教が一番大切であり、その教というのは心の敬より外にはない。
・何芸を学んでも、その師匠に習うばかりで、弟子朋輩なく友の吟味がなければ、励みなく勢なくて、その芸もあがらぬものである。
・日本、武家の政治になってこのかた、しっかりと師傅・友の役人も設る事なければ、近代の大名の世子は殊さらおおかた幼少より我儘に育て上げ、傍から善悪ともに言わせぬようにし、人を何とも思わず、学文は精が尽きるので悪いものとして、幼少の時はさせずにおき、ただ勝手次第、そのままに成長させるので、かの我慢の性根、はや幼少より我しらず出来て、習慣自然となるはず。
・『貞観政要』という書は、議論の文章なので、諫諍する事の理屈、入組みたる事のみ多く、工面を始終よく合点しなければ、なかなか心やすくは通しない書であるため、この字義語勢に通じなければ、その意味を合点しがたい。
・初心の人、下地に一向字義語勢の合点なき人に、入組たる議論の理屈を、たとえ講釈しても、その心にとくとは徹しがたい。
・すべてどんなことも、心易き方よりいたって難き所へ入りこむのが順理である。
・事実の成敗を記録した書は、畢竟、昔物語や今日の世上咄を聞くことと同じものであり、誰でもまず耳近く面白く、その慰にもなので、かの精を尽かし書を疎むわずらいも少く、それよりに学文に取り付きやすくなる。
・学文というものは、少でも心の内に楽しみ、面白いと思い、感徹したいと思うものが一つ生じ出来てこなければ、少しも進まない。
・『資治通鑑』という書は、人君たる人の左右には一日もなくてならぬ物であり、古来の政治の得失、事跡の成敗、臣下の忠邪をありのままに記録した書である。
・古の成敗得失の実を今日の政治の上に通じて鑑み合せ見れば、大きな政治の資助となる。
・およそ史書を読む心持ちは、まずその時代の様子をよく考え、次にその時の天子と臣下の身の上を想像し、直に我が身の上に引き当て、万事その心になり代わって、その時の政事を今日の事と思い込み、我が処置心になりきって見るべし。
・未だろくに字義語勢をも弁ぜぬ内に、難しき議論ある書を読めば、必ず我意をもって理屈を作るようになり、その書の本意にない事を掘り出し、聖人の意にもなき事を心得るようになるため、書を読まぬも同然である。
・我意が混じれば、必ず我慢(高慢)になり、学文をした益はなく、結局却って理屈臭き害がでてくる。
3.人君は下の意見にしたがい、諫を容れて用いるべし
・古来よく諫を用いる人君は甚だ少ない。殊更に日本の武家の風として、すべて人に智恵をつけられた事をその通りに受けて用い、自分の仕損、誤りを改めなおす事を、人の卑下恥辱とする習慣があった。
・世に忠臣孝子一人でもあれば、即ち観賞を加え、天下に表彰する事は、古代よりの政治であるのに、どんな事があれば、かかる赤穂の四十七人の忠臣に罪をかぶせて、一人も残さず一時に殺すとはいかなる政治か。
・武威熾盛なる世に、また近代は軍学とて、かの権謀功利の道に仁義の名を借り、面白く理屈を通り合わせ、これをもって武家の大事とし、甚だ尊敬する事、聖人の教を越えている。軍学に仁義の理を傅会することは、前に言った茶儒の同類である。
・日本の武家は武威を護する為に、治世に成ってもやはり一向に軍中の心をもって政治をしている。
・軍学をもって吾道であると心得、これを尊信するため、ついにいつとなく我知らず人の心術を悪くし、ただ人に卑下しないようにし、何事でありも人に勝つ事を専らとする気になり、人に智恵をつけられる事を大きな恥辱と思い込み、現在に悪くても我を立て通すようにみな人の心がなったのは、軍学の失である。
・武を忘れぬと言うのは、平生じっと心に武を忘れず、用心せよという事ではない。治世にも、武備を一向に思いも出さぬようにして怠り忘れぬように、時々吟味せよという事である。
・朝夕片時でも万一の事あろうかと用心要害し、寝ても覚めても武を忘れぬ事と思うは、文盲も甚だしい。
・今の軍学がどんなものかは知らないが、孟子の「人の和に如かず」と言ったことこそ真の軍学である。人和がなくては、何流の隊立、いかなる城立も、崩れ易いだろう。
・中華の風俗として、町人百姓の内でありも、誰でも、所存があれば、遠慮なく上書して、公儀の政治の悪き事を申し上る事がある。たとえ表向きにすでに勅詔の下った事であっても、その非を申し上る風になっても、咎めはない。
・日本の武風において、下として上の仕置をとやかく批判するのは、理非の差別なしに、まず慮外無礼の至極とする、急迫厳酷なる風習があれば、たいていの気量の人君では諫を容れることはない。
・人君として下を下知し、自由に引きまわす身で、我がしようと思いこんだ事を止めて、下の意見に従い、諫を容れ用いる事は普通はない。聖人という者の、凡人と各別なるというは、このような所の違いばかりである。
・聖人というは、その心は公平であり少も我意がなく、かの我慢なる気味は微塵もなく、気量が大きいばかりである。
・漢の文帝と唐の太宗の諫を容れ用いられた。
・日本は中華に合すれば小国なるため、自然と人の気量も狭く、かの武風も畢竟みな気量が狭いことから起こる。
・漢の高祖に実徳はないが、自然と気量のひろい人だったために、円い物を転がすように、よく人の諫を用いられ、我が過ちを早く悟ったために、良き人も手下に多く集り、小軍をもって項羽の大軍に勝ち、漢の四百年の基を開かれた。
・項羽には勇気はあったが甚だ気量が小さく、物を容れる事ができず。人に疑い深く我慢なる人だったため、ただ我が武威が強く、人の恐れるのを恃みとし、大軍でありながら人和なく、好き臣下もみな失い散り、ついに高祖に亡された。少量なる人は必ず我慢なるものである。
・威光のみを恃みとして国家を治めるは、危なきものである。徳をもって国家を治めるべし。
4.武威よりも徳をもって国家を治め、民を安んずるべし
・武士というものの武士たる所以の理を言えば、軍旅の事、弓馬の事ではない。では義に臨み一命を捨てる事を主とする事か。これを武士だけの道と思うのは甚だ狭き見識であり、文盲である。
・和流軍学者とて、権謀功利の学を主とし、表向きに仁義の説を借りて、飾り拵えたものを武道と言えるが、これは即ち孫子がいえる詭道であり、「夫の人の子を賊う」の学術なので、聖人の仁義忠臣の道とは氷炭胡越のように相違し、少しも論ずるに足らない。これらの他に武士の道とする事に何があるのか。いつも不審に思う。
・「士」という字を、和訓には「さぶらひ」と言うが、士の義は元来男子を通じておしなべて称する字であり、大夫以下の官位俸禄ある人を、貴賤を問わず普通に士と言い、士の内には文官も武官もあって、武官に限らない。
・「侍」の字の「さぶらひ」という訓は、侍衛の心であり、番兵警護の事なので、大将分上の人を仮初にも称する言葉ではない。
・日本は清盛、頼朝以来は、王政の衰たるに乗じ、武家の威勢が盛んになり、武力弓馬でなくては天下は取れぬと思い込み、その武功を誇ることが、自然と風俗となり、武力を面々に鼻にかけ、ただもの武威を張り耀かし、武士という名目を結構なることと心得た。
・日本でも、太閤秀吉公なども「将に将たる」の気量があった。これこそ武家に慕い学ぶべき事なのに、どうしてただ武士ということを面目とし、これに安んずるのか。
・英雄名将の威力にて天下を取り、兵戈の事が終って、国家を治め民を安んずる場になっては、一途に武力ばかりではなかなか国家は治まらない。
・ただむきに武威ばかりを恃みとし、無理やりにおしつけ、人を威勢でもって服させるは、なるほど一旦は人の服するものでも、少しでもその威光が落ちれば、そのままに人心は離れ天下が乱れる。
・徳をもって人心を感服させれば、人が実に服するため、気遣いなく安穏であり、その徳の光耀すなわち威光となって、自然の威光なので何があっても冷める事なく、人が遺背する事がなく、これこそが真の威光と言う。
・『中庸』に言える智仁勇の三徳の名も、三つ相並び、智だけでなく、仁だけでなく、勇だけでなく、三つでちょうどつり合い、一つでもなければ用にたたない。
・聖人の武勇はその徳の光輝にして、内より自然と持って出たものなので、いつまでも衰え変わることはない。
・武士の武勇と思うは、みな人の血気より出来たる客気というものであり、いつまでもあるものではない。
・日本を武国であると言って自慢すれども、元来日本は聖人の国なる事、いやといわれぬ近き証拠はあるが、人は気づかない。
・武家の天下とて、武威をもって天下の政治を自由にしても、とにかく表向きの名代は、天子を君と仰ぎ、自身は臣下となっておらねばならないという事は、どうしても止められず、嫌とは言えない。
・我国人皇は、天照大神より今上皇帝までは三千年に及び、皇統相承けて一王の血脈を相続し、万民これを天子と仰ぐ事、実は中華にも例がない。
・清盛、義満、秀吉も、皇統を絶ち、天子に取って代る事は恐ろしくて出来なかった。
・「天照大神、女体ということでも、呉の太伯である」という説と、その神道者からの反論について。
・和語の解も、神道者の言うことは、みな理屈をもって我意であり拵えたるものである。
・神は即ち古の聖神なので、いかさま天照大神の聖徳が、数千年の間、人心に染み込み失なわなかったというのは、神妙不測のことであり、神国と言われるのも理があり、かの武国と言うよりは一理ある。
・すべて聖徳の武威はだれにも何もせず、世話をやかずに自然と人が懾服し、その人がすでに世を没して後も、なお人を畏れさせる。
5.人情の本を知り、五倫の間の人の実情を察するべし
・儒者の業は、五倫の道を知り、古聖賢の書を読み歴史に達する事なので、世間の人よりは各別によく人情に通達せねばならない。
・儒医などという名目は、文盲の甚だしい。或は出家の僧徒や、山居の隠居や、亦は一芸を業とする文人詩人や、射御の師、医などの類は、世上の事を打忘れ、一向三昧に心を我が業に専らとし、他にする事もないため、自然と世上の事に不案内になるが、成程妙手にもなるはず。
・人情を知る事は、「仁を求む」の手がかりであり、学者の最初の工夫である。
・恕は即ち「仁を求む」の方術であり、人情に通じると言うのは、恕を致す方術である。
・孔子の門弟子の学文として書を読むというのは、まず『詩経』からである。
・『詩経』は人情を知る為の書である。学者の第一に業とするものは、『詩経』である。
・詩を学ぶというは、全く人の五倫、世上朝夕の間において、貴賤上下、色々様々なる人情の善も悪も酸も甘いも、委細に知り通じるためである。
・和歌というものも、本は詩と同じものであり、紀貫之が古今の序に、「人の心を種として、万の言の葉とはなれりけり」と言い、「見るもの聞ものにつけていい出せる」と言えば、詩の本意と符合する。
・人の思いは知らずにふっと実情を言い表す事である。これが詩となるものであり、人の底心骨髓から出でたるものである。しかればその詞を見るによって、世上の人情の酸も甘いもよく知ることができる。
・詩は三百篇あれども、詩というものはことごとく、ただ一言の「思邪無し」の三字より出て来ない詩というものは、一篇もない。
・善悪邪正ともに、人の内にひそめたる実情の隠されないものは、詩にある。
・詩の教は、人の実情を察し明らかにするため、仁恕もこれより求め得る手がかりとする。元来詩を学ぶというのは、学者以上の事であり、なべて世俗の人の学ぶ事ではなかった。
・人の上に立て国家の政治をする人は、必ず学文をして人情をよく知り、下の委曲の情をとくと察しなければ、だれも実に帰服しないため、人情に通達せずして、国家の政治は必ず定まる事はない。
・「邪」の字の義は、邪悪、邪佞などの字の気味だけではない。邪行、邪視、または邪幅などといえる邪の字の義もある。元来邪字の音義に斜の字あれば、斜の字の意が即ち邪の字の本義である。
・人の心の思う通りずっと出てすぐに行こうする所を、すぐにやらず、内で横筋違に言い換え、ひと思案し按排料理するは、邪である。その思う通り我しらず内から自然に真っすぐに出て、実情を吐露した所を、「邪無し」と言う。
・和歌の道もこの通り少しもかわる事はない。ただ中国大和と人の言語の違いがあり、共に人の「思邪無し」になる所より発出する。
・万葉集時代の和歌は、『詩経』の詩によく似たるもの、殊勝なるものである。
・『礼記』に「飲食男女は人の大欲存す」とある聖語のように、人情の最も重く大事なるものは男女の欲である。そのため、夫婦の間ほど人の実情深切なるものはない。
・欲と言えば悪き事のようにのみ心得るは、大きな違いである。欲は即ち人情の事であり、これがなければ人ではない。欲は天性自然に具足したるものなので、人と生れて欲がないものは一人もない。
・色々様々に己が身勝手な事と思い、私の料見を出して造り拵え、理義にそむき、ない事を欲して願うために、私欲と名がつけば、悪しきものになる。
・男女の欲は、人たるもの誰であってもこれには溺れ惑って良いものであり、人は最も第一にこれを大事として、慎み畏れるべきである。これはとても危ない所であり、これにおいて克念すると聖となり、でなければ狂となる分かれ目である。
・聖人も欲は凡人とかわる事はないけれども、その欲が凡人より甚だ少なく、どんなことでも溺れ惑う事はない。これこそ聖人の聖人たる所以である。
・夫婦の間に楽しむと淫するは、どうやら似たようなもので、悪くしたら踏みそこないそうな危ない場であり、しかもその情思の邪正相判れる事は氷炭の違いであり、こここそ聖人と凡人との境めである。
・敬というは、物事を畏れ慎み、前方に気をつけることである。
・夫婦の間には常に別を立てる事を忘れてはいけない。
・和歌は、日本古来宗匠の論にも、恋の歌をもって大事とし、重き事としたる事も、夫婦の情は人情の本源であり、和歌のよって起る所なので、万葉集にも、相聞とて恋の部の歌を巻首に載せ、全体に恋の歌が多く入れられ、後の代々の撰集にも、恋の歌を多く載せてこれを主としている。
・万葉時代の恋歌は、後世の恋歌とは違い、その様子は質直であり、かの温柔敦厚の雅なる風に見えるが多くして、楽という気味に似たるものもある。
・俊成卿の歌に「恋せずば人は心のなからまし物のあはれはこれよりぞ知る」と詠まれたものは、それほど秀歌ではないが、その意趣は向上であり、人情によく達している。
・和歌は古くも日本の治道の助けとなり、その時代の和歌の風を見て、政治の善悪、世の盛衰がわかる。
・俗人の汚き心は、夫婦の実情は淫慾より生ずることなので、交会する事なければ、実情は出てこないと考える。
・親の子を思う心、兄弟の間、君臣朋友の交にも思慕深切の実情あれば、またこれも恋である。
・人の思慕深切の実情というものをよく考えれば、即ち孟子のいわゆる「人に忍びざるの心」というものであり、これが仁の本体であり、人の本心、性の善なる所である。かの「物のあはれを知る」と俊成卿の詠まれたのも、この場を見つけ得られたので、殊勝なること、尊仰すべき歌と、いつもめでたく思える。
・人情に通じるのは仁を求めるための方術である。
・今世に流行る三線は、打ち聞くに人の心を蕩し躁がし、起こりもせぬ淫欲を誘うものである。
・琵琶というものは、紫式部も「らうらうじきもの」と言い置き、高古遠雅にさびて、しめやかなる音であり、打ちあがりたるものなので、聞く内には自然と人の心も静まり落つき、いつともなく清浄になるように覚える。
・琵琶は古楽・雅楽であり、三線は鄭衛・鄭声である。聖人の教にも、「鄭声を放つ」とはあるが、鄭声を嫌い悪くむとは結局言わなかった。その鄭声を、人が雅楽である、真の音楽であると思い込み、混乱させるのを悪くむと言ったのである。
・総じて音楽の音節繁急にして面白すぎるものは、すぐに人心を浮き躁がし、それより起らぬ淫欲も感動させるものなので、音楽は人心を感動させる事が素早いものであり、人心に関係する事の、重く大切なものである。
・古の聖人が天下を治めるのに、礼と楽との二つをもってした。礼は人の行儀の作法の教、楽は人の心を正しくさせる教である。
・人というものは、常住窮屈な、折詰めた事ばかりでは続き難きものなので、必ず打くつろいで心を和らげ、遊び慰む事がなければならない。その心が和らぎ打ちくつろいだ時には、黙っていられぬものであり、必ず音声を発し拍子を通り、歌い舞わねばいられない。これが自然である。
・聖人は情によって人を教えるので、楽をもって教として、人の心をそれでほぐすようにした。かの鄭声を放ち遠ざけ、平生に正しき雅楽を人に聞かせ、いつともなくかの鄭声の事を打忘れさせ、雅楽を面白いと思わせるようにさせる。
・金銀財宝、富と言えば、人欲の最も目当てにする事であり、聖人も凡人も同じである。しかし聖人は、貧賤に耐えかねて、富を無理に求めようとせず、我が心の真実に面白いと思い好む事は、古聖人の書を読み、学文をし、義理を分別し、心を清浄にする方を選ぶことが、凡人と異なる。
・和歌の道に大事とする恋というものは、夫婦思慕深切、天性自然の実情なるものであり、かの今様の淫慾交会の事のみを恋と思い込むのは、見当違いである。
・五倫の内では夫婦の間の思慕深切なる実情は、一番重要なことであり、日本の和歌の道も、自然とここをもって大切とするのである。
・人情の本を知り、五倫の間の人の実情を明らかに察すれば、心が公平になり、気量が大きくなり、料見よく物を受け容れ、すべての人を憐憫し、自然と人の諫をも受け容れ用いるようになる。
・国家の政治をするというのは、古聖人の徒ともなるべき事なので、人情に達する事は、また政治の本に達するという事である。
6.和歌は日本の大道であり、秘伝はあってはならない
・和歌の道は日本の大道なので、元来和歌の道に秘伝があらねばならないとは思われない。八雲の伝は全く後世の拵え事なので、一向に議論には及ばない。
・和歌の道は以心伝心なるもので、委細に言句伝授などで言い伝えられるものではない。詩の道もまた同じ事であり、天然と和漢符合しているわけは、人情が同じだからである。
・近代に及んでは古今伝授などが出来て、和歌は詠まれないもののように難しくなり、公家でなくては歌は詠まれず、地下の人は歌は詠まれないと言っているのはどういうことか。
・百人一首、古今集、廿一代集をみても地下の人の歌は数しれずあり、昔は堂上地下の差別はなかった。
・古今伝授の由来の説は、後人の偽造であるという証拠はそろっている。
・古今伝授という事は、元来は地下より公家へ伝えたもの。古今伝授しなくても和歌は詠まれる事は明白である。
・和歌を良くするのは我が朝の大道と思われるが、どうして秘伝と言って自ら狭く小さくするのか。嘆くべく悲しむべき事である。
・秘事として伝授するのは、陰謀を主意とする軍学である。和歌には秘伝はあってはならない。
7.心を平らかにして、我を立てて私意を指し出さぬようにせず、聖人の道は見つける学文をすべし
・学問をすれば必ず人を非に見るようになり、人柄が悪くなるという事は、俗論でも、現在俗人の内に多くある事である。俗人に限らず、なかなか学者にさえ多い。
・その病根は、我慢高慢という病より起こる事であり、学問をもって口実としただけである。
・一片を聞いて、下地の我慢の助けとして、書を読んでも、みな我が意の勝手の良いように私の料見をもって理屈をつける故に、そのような人の学文は、名は学文をすると言っても、畢竟文盲と同じ事、俗に言う、論語よみの論語しらずなので、真の事ではない。学問をしたために人が悪くなるのではない。
・殊更日本武家の政治となって、師傅の役を立てる事もなく、その上軍学の功利陰謀の事を第一と心得、ただむきに武威をもって人を推し、権を取る風習となるため、人に知恵をつけられる事を卑下恥辱と覚え、威を張る事をのみ専らとする事によって、必ず学文は中国の事、武士には武士の道があり、聖人は昔の人であり、当代の風には合わぬ事と、いよいよ我慢の威風を張るようになるので、何があっても学文の方へは移らぬはずである。
・総じて何によらず、臭気のする物は悪いものであり、味噌の味噌臭き、鰹節の鰹臭き、人では学者の学者臭き、武士の武士臭きが、大方は胸の悪い気味がするものである。これが俗語にいえる、無い樽の鳴ると言うものであり、内にいっぱい物が詰まらず、いまだ不足なるため、少しある物ゆえ、人が知るまいかと思い、人に知られたくなり、ひけらかす心ができて、こちらから人に鳴らして見せるのである。また、ただ自慢高慢の心より、人を推して我を立てようと競う仕形と見える。無い樽の鳴るは、外からついその内が知れて、却って信向がさめるものである。ただただ心を公に平らかにして、少しでも我を立てて私意を指し出さぬようにしなかったら、真実に聖人の道は見つけられないだろう。
前回、宣長の筆写箇所を予想された方、結果はいかがでしたか。
つづく
(ムガク)
028-もくじ・オススメの参考文献-本居宣長と江戸時代の医学



















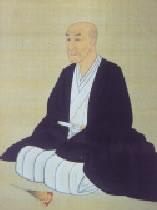

 後藤艮山
後藤艮山  香川修徳
香川修徳





