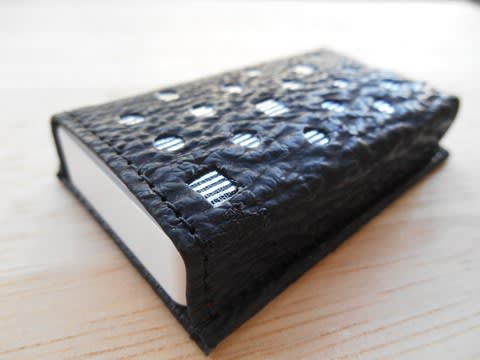二鶴工芸です。
下記の日程にて展示会に出展します。
お近くにお越しの際は是非、お立ち寄りください!!
上仲昭浩で出展しています。
この「京もの認定工芸士」の称号を授与された若手職人から構成され、来年度からの発足を目指す職人集団『響』
『響』正式結成前のプレイベントとして今回『aeru gojo』様にて展示会を開催することになりました。
京もの認定工芸士/有志の会『響』展示会
~ひびきはじめ~
期間:10月7日(土)~10月20日(金)...
場所:aeru gojo
〒600-8427 京都府京都市下京区下京区玉津島町298
松原通室町東入
時間:10:00~17:00 水曜定休日
トークショー
10月14日(土)18:30~19:30
ワークショップ
10月15日(日)
11:00~12:00
13:00~14:00
定員:5名様
費用:お一人様2,500円(税込)
講師:關 敬介 京仏具
漆で固めた蒔絵の研ぎと磨きの作業をして頂きます。
(研ぎ出し磨き技法)
お好みの色と蒔絵の絵柄が入ったコースターを一つ選んでもらい、漆で固めた蒔絵部分を砥いでピカピカにしていく内容になります。(水や磨き粉を使いますので、汚れてもよい格好できて下さい)
参加の申し込みはこちらへ
11:00~12:00
http://peatix.com/event/303185/view
13:00~14:00
http://peatix.com/event/303193/view
参加メンバー
上仲 昭浩 京友禅
横田 武裕 京友禅
佐藤 稚子 京友禅
上仲 正茂 京友禅
古橋 敏史 京友禅
平居 幹央 西陣織
山下 賢二 西陣織
岡山 高大 京焼・清水焼
並川 昌夫 京焼・清水焼
杉村 陽子 京焼・清水焼
關 敬介 京仏具
南篠 和哉 京仏具
藤澤 典史 京仏具
イベントページ:https://www.facebook.com/events/2041769366054291/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22bookmarks%22%2C%22surface%22%3A%22bookmarks_menu%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22dashboard%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22ref%22%3A46%2C%22source%22%3A2%7D&__mref=mb