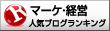***** 中小企業診断士仲間の山本哲史さんのブログから *****
新規事業を考えたり、新しい取組等を進める場合、とかくビジネスの基本を忘れがちになるものです。社会的課題を解決する場合も、収益を目的とする場合も、価値を受ける「顧客」が必ず存在するわけで、この顧客がその価値を認めるかどうか、がもっとも大切なポイントになります。
そもそもこの事業って何の目的なんだっけ?って疑問がわいてしまうと、この大切な部分がおきざりにされていることに気づかされます。
ビジネスシナリオは作成した者の論理で展開されますが、実際にふたをあけてみると、顧客の論理で展開していきます。売上が思うように伸びない、市場への展開が思うようにいかないのはまさにこのことです。とかく方法論の話になって改善措置を講じていきますが、価値の伝達、表現方法そのものをまずは振り返ってみることが大切なように思います。
ニーズをどのように見つけるのか、どのようにして創造するのか、みんな悩むテーマですが人間としての実体験からヒントを得ることが大部分なように思います。価値を「想い」に変えて、伝えて「共感」してもらうこと、そのあとに経済的価値を考えるのが一つの方法かもしれません。
***** 「価値」を「想い」に変え、「共感」を得る。山本さんが主宰するNPO社会起業ネットワークの事業「障がい者の工賃向上を目指す墓掃除代行サービス」で私も体感しました。*****
新規事業を考えたり、新しい取組等を進める場合、とかくビジネスの基本を忘れがちになるものです。社会的課題を解決する場合も、収益を目的とする場合も、価値を受ける「顧客」が必ず存在するわけで、この顧客がその価値を認めるかどうか、がもっとも大切なポイントになります。
そもそもこの事業って何の目的なんだっけ?って疑問がわいてしまうと、この大切な部分がおきざりにされていることに気づかされます。
ビジネスシナリオは作成した者の論理で展開されますが、実際にふたをあけてみると、顧客の論理で展開していきます。売上が思うように伸びない、市場への展開が思うようにいかないのはまさにこのことです。とかく方法論の話になって改善措置を講じていきますが、価値の伝達、表現方法そのものをまずは振り返ってみることが大切なように思います。
ニーズをどのように見つけるのか、どのようにして創造するのか、みんな悩むテーマですが人間としての実体験からヒントを得ることが大部分なように思います。価値を「想い」に変えて、伝えて「共感」してもらうこと、そのあとに経済的価値を考えるのが一つの方法かもしれません。
***** 「価値」を「想い」に変え、「共感」を得る。山本さんが主宰するNPO社会起業ネットワークの事業「障がい者の工賃向上を目指す墓掃除代行サービス」で私も体感しました。*****