
「実習でアセスメントが書けずに辛い」
「どうやって看護過程を書けばいいかわからない」
という「記録」に関して、看護学生は悩みます。
臨床に出て業務をするようになると、疾患の知識が身に付きます。
疾患が理解できると、治療プロセスの中で、ADLをどうやって自立させていくか?について考えていくことになります。
それが看護過程です。
現在では、平均在院日数がどんどん縮小されてきているため、リハビリのほとんどは理学療法士が担当します。
理学療法士は人間の重要なADLのうち、「移動」つまり「歩行や移乗」を中心として関わっています。
それ以外の部分についてのADLに関しては看護が担うため、その差別化をしなくてはいけません。
結論から言いますと、看護アセスメントを最初からできる人はいません。
ですから、担当の教員や実習指導者から「引き出していく」という作業が必要になります。
どのように引きだすのか?というと、
「①断片的な情報(情報収集)から、
受け持ち患者にとって、
「②何が問題で(解釈・推論)」
「③今後どういう援助が必要か?(仮説、方向性決定)」
という3つのプロセスを文章にして提示します。
そうすると、①②③のどこが違うのか?を教えてもらうことができます。
ポイントは、「①の情報が少なくても良いからどんどん②③へと進むこと」です。
なぜかというと、看護実習において、
「看護師として臨床経験がない人は
何が重要な情報か?わからないから」です。
ですから「わからないなり」に①②③を書いて、指導してもらえばいいのです。
一番良くないのが、情報だけ沢山とって、「自分の考え=アセスメントを書かない、白紙のまま」の状態です。
推奨するのは「まとまらないなりに、自分の考えを書いてくること」です。
そうすることで、指導する側は、学生にとって①②③のどれが足りないか?分かるため、答えに近いヒントを教えやすくなります。
「全然わからないから教えてください」
ではなく「ここまでは分かっています。完成できないので教えてください」
というメッセージを記録で示していけば良いのです。
#看護実習 #アセスメント #NANDA #ヘンダーソン #ロイ #基礎看護










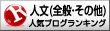

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます