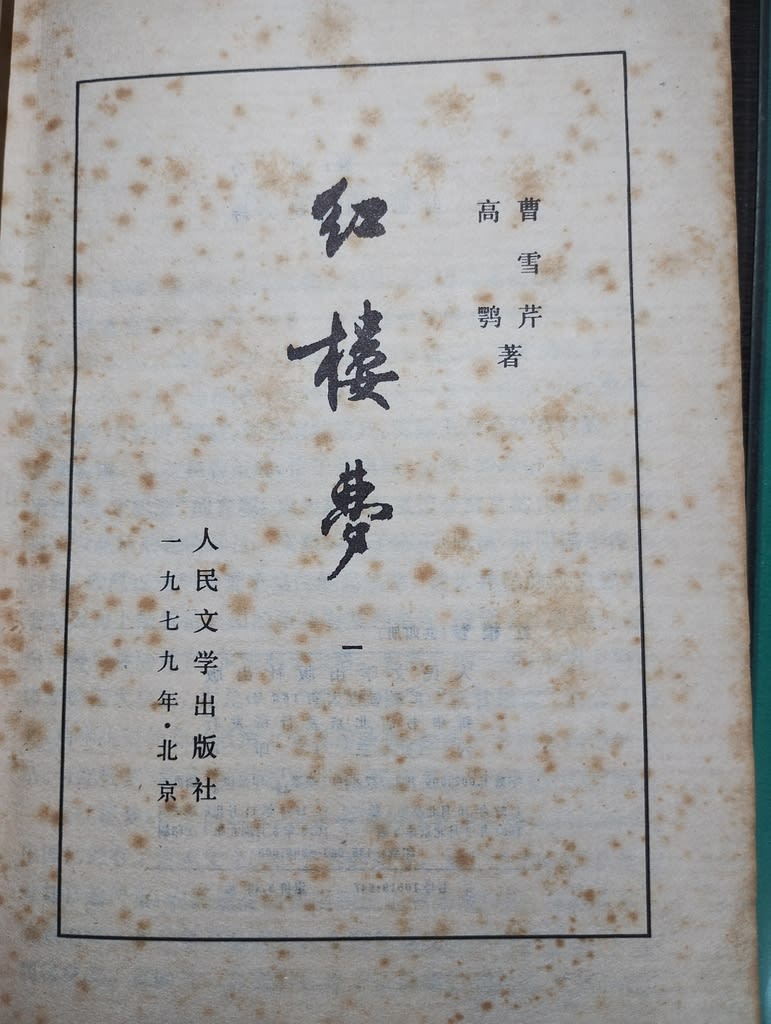
秦可卿の弟の秦鐘と仲良くなり、ふたりで一緒に賈家の家塾に通う約束をした賈宝玉。第八回では、薛宝釵の病気見舞いに行った宝玉が、自分が口に銜えて生まれてきた石に刻まれた文字と、宝釵のつけている金のネックレスに刻まれた文字が対句になっていることが分かります。さて、話はどう展開していくのでしょうか。『紅楼夢』第八回のはじまりです。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
賈宝玉は奇縁にて金鎖を識り、
薛宝釵は巧合(たまたま)通霊を認める
さて、宝玉と鳳姐は家に帰り、何人かの人に会ったが、宝玉は賈のお婆様に、秦鐘を家塾に入れてあげる約束をしたことを報告し、自分も一緒に勉強する友になり、ちょうど勉強に発奮できる。また秦鐘の人柄や振舞いをたいへん称賛し、たいへん好ましい人物だと言った。鳳姐もその横から助け船を出して言った。「日を改めて秦鐘にはまた、お婆様にお目にかかりに来させますわ。」そう言ったので、賈のお婆様は嬉しく思った。鳳姐はまたこの機に乗じて賈のお婆様に一緒に芝居を見に行こうと誘った。賈のお婆様は年齢はいっているが、たいへん芝居好きであった。後日、尤氏が来て誘ったので、遂に王夫人、黛玉、宝玉らを連れ、芝居見物に行った。昼になって、賈のお婆様は家に戻って休憩した。王夫人は元々静かなところに居るのが好きなので、賈のお婆様がお帰りになるのを見て、一緒に帰って来た。その後は、鳳姐が主賓の席に座り、そのまま夜まで芝居見物を楽しんだ。
さて宝玉は賈のお婆様を送って家に戻り、賈のお婆様が休んでお昼寝をされるのを待って、また戻って芝居を見るつもりだったが、秦氏らの人の手を煩わすのを恐れ、また宝釵が最近家で病気療養しているのを思い出し、まだお見舞いに行っていないので、宝釵の顔を見に行こうと思った。もし母屋の裏口から出て行くと、他の事で邪魔される恐れがあり、また父親の賈政に出逢うと、更に都合が悪いので、むしろ遠回りをして行った方がよいと思った。この時、乳母や女中たちが宝玉に着替えさせようと控えていたが、宝玉は着替えをせず、そのまま門を出て行った。乳母や女中たちは宝玉に付いて出て来て、宝玉があちらのお屋敷で芝居を見るものとばかり思っていたが、あろうことか穿堂のところまで来ると、東北の方へ向け広間の後ろを回って行った。するとたまたま向こうから賈政の下で居候している食客の詹光、単聘仁のふたりがやって来るのに出くわし、宝玉を一目見ると、急いで近づいて来て、笑いながら、ひとりは腰を抱き抱え、ひとりは手を差し出しながら言った。「これはこれは、お坊ちゃま。良い夢を見たと言っていたら、なんとあなたにお目にかかることができました。」そう言いながら、またぶつぶつとしばらく言ってから、ようやく行こうとした。年配の乳母が呼び止め、尋ねた。「あんたたちふたりは、旦那様のところに行ったのかい。」ふたりは頷いて言った。「そうです。」また笑って言った。「旦那様は夢坡斎の書斎の中でお昼寝されていますので、お邪魔をされませんように。」そう言いながら、行ってしまった。それを聞いて、宝玉もにっこり笑った。そして向きを変えて北に向かい、梨香院へ行った。ちょうど、蔵の管理の責任者の呉新登と、蔵の頭(かしら)で戴良という名の者が、何人かの執事の頭目と一緒に、全部で七人が、帳場から出て来た。一目宝玉を見ると、急いで一斉に両手を垂らして立ち、うやうやしく控えた。その中のひとりの買辦(ここでは、宮廷内で使う物品を納入する商人)で、名を銭華というのが、しばらく宝玉に会っていなかったので、急いでやって来て、身体を屈めて礼をすると、宝玉は微笑みながら手を伸ばして彼を立ち上がらせた。周りの人々は皆笑って言った。「この間、あるところで若様が書かれた斗方(四角の赤い紙に書や文字を書いたもの)をお見受けしましたが、益々お上手になられて。いずれ、わたしたちのところにも何枚か貼っていただき、眺めたいものです。」宝玉は笑って言った。「どこで見たの。」皆が言った「あちこちにありますよ。皆、すばらしいと褒めていて、わたしたちにも問い合わせがありますよ。」宝玉は笑って言った。「そんな大層なものじゃないよ。おまえたち、僕付きの小者に言ってもらえば、準備させるよ。」そう言いながら、前へ進んだ。人々は宝玉が行ってしまうのを待って、それぞれ分かれて行った。
閑話休題、さて宝玉は梨香院に到り、先ず薛叔母さん(薛姨媽)の部屋に行くと、薛叔母さんが女中たちと一緒に針仕事をしていた。宝玉が急いで挨拶をすると、薛叔母さんは急いで宝玉を抱きしめ、胸の中に抱きかかえながら笑って言った。「こんな寒い日に、坊や。来るとは思っていなかったわ。早くオンドルにお座りになって。」人に命じて「熱々のお茶を淹れて来て。」宝玉はそれで尋ねた。「兄さんは家におられますか。」薛叔母さんはため息をついて言った。「あの子はまるで轡(くつわ)の外れた馬で、何の束縛も受けず、毎日勝手にほっつき歩いてるわ。どうして一日家にいるものかね。」宝玉は言った。「姉さんの具合はどうですか。」薛叔母さんは言った。「それがね。あんた、前に人を遣ってあの子の様子を見てくれただろ。あの子は中にいるんじゃないかね、あんた見てみておくれ。あの子はあちらに居る方がこちらより楽だったんじゃないかね。あんた、中で座っていて、わたしもここを片付けたら、中に入って話をするから。」
宝玉はそう聞くと、急いでオンドルを降り、奥の部屋の入口の前に来ると、お古の赤い繻子の柔らかい帷(とばり)が掛けれれていた。宝玉が帷をめくり上げて中に入ると、最初に宝釵がオンドルの上に座って裁縫をしているのが眼に入った。頭には黒くつやつやした髷(まげ)を結び、黄色味を帯びた白色(蜜合色)の綿入れの上着、玫瑰紫の生地に金糸銀糸で紋様を縫い込んだチョッキ、浅い黄色の綾衣のスカートを身に着けていた。どれも新品ではないが古くはなく、見たところ贅沢ではないが、ただ上品に感じられた。言葉数が少なく、他人は彼女がわざと愚鈍を装っていると言う。自らの本分を守るも世俗に順応し、自らは「出しゃばらず分に安んじる」と言う。
宝玉は宝釵の様子を見ながら、尋ねた。「姉さん、具合は良くなられたの。」宝釵は首を上げて宝玉が入って来るのを見ると、急いで身体を起こし、笑みを浮かべて答えて言った。「もう随分良いのよ。お心遣いいただき、ありがとう。」そう言いながら、宝玉をオンドルの端に座らせ、鶯兒に「お茶を淹れてきてちょうだい」と命じた。一方でまた、お婆様や叔母様はお元気か、女兄弟たちはお元気か、尋ねた。また一方、見ると宝玉は頭に金糸で編み、宝石を象嵌した冠を被り、額には二匹の龍が珠を捧げ持つ図柄の鉢巻を締め、身体には淡いオリーブ色の生地に蟒蛇(うわばみ)の図柄が描かれた白狐の腋の毛で作られた筒袖の上着を着、五色の蝶々の柄が縫われたベルトを締め、首には長命鎖(南京錠の形のペンダントを付けた首飾りで、子供の長寿を願うお守り)、記名符(子供が無事育つよう祈るお札)を掛け、これ以外に例の生まれた時に銜えていた宝玉を身に着けていた。宝釵はそれを見て、笑って言った。「いつも、あなたのその玉を、まだじっくりと鑑賞したことがないわね、と言っていたのよ。今日はちょっと見せてちょうだい。」宝釵はそう言って、宝玉に近づいた。宝玉もまたそれに応え、玉を首からはずして、宝釵に手渡した。宝釵はそれを手のひらに載せて見ると、雀の卵くらいの大きさで、夕焼け雲のように明るく輝き、バターのようにしっとりつやつやし、五色の模様がまとわりついていた。
読者の皆さんは既にご存じの通り、これは大荒山中青埂峰下のあの石ころの幻相(まぼろし)であり、後の人が詩で嘲(あざけ)って言った。
女媧氏が煉った石は已に荒唐、また荒唐に向け大荒を演ず。
本来の真の面目を失い、幻は新たに臭き皮嚢に就く。
好く知る運命の衰敗し金も彩無きを、嘆くに堪ゆ時運に乖(そむ)き玉も光(ひか)らず。
白骨は山の如く姓氏を忘る(死んだ者はもはや誰とも分からぬが)、公子、紅粧(美しく化粧した公女)に非ざるは無し。
かの石ころはまた曾てこの幻相を記録し、またしらくも頭の坊さんが篆文を刻んだのだが、今また後ろの図絵のようになっていたが、真にたいへん小さなもので、やっと胎内から小さな子供が口に銜えて出てきたもので、今もしその様式で描き出しても、恐らく文字の筆跡があまりに微細であるため、見る者の眼光を損ね、また煩わしいので、多少拡大して示すことで、灯火の下で酒に酔っていても見れるようにした。今このいきさつを注釈するすることで、はじめて胎内から子供が口に、どうしてこんなかさばって重いものを銜えて出てくることができたのかという思いは消すことができるだろう。

宝釵は見終わると、またもう一度おもてにひっくり返して子細に見て、口の中で唱えて言った。「莫失莫忘(失う莫れ忘るる莫れ)、仙寿恒昌。」二度唱えると、振り返って鶯兒の方を向いて笑って言った。「あなた、茶を淹れに行かないで、ここでぼおっとしてどうしたの。」鶯兒もにこにこ笑って言った。「わたしこのふたつの文句を聞いて、ちょうどお嬢さんのネックレスの上のふたつの文句と一対になっているように思えたのですが。」宝玉はそう聞くと、急いで笑って言った。「なんと姉さんのネックレスの上にも文字があったの。僕にも見せて見せて。」宝釵は言った。「あの子の話を真に受けないで。字なんて書かれていないから。」宝玉は頼み込んで言った。「姉さんお願い、どうか僕に見せてちょうだい。」宝釵は宝玉があまりにしつこいので、こう言った。「これも人がくれた二句の縁起の良いことばで、彫ってあるの。だから毎日着けているのよ。そうでないとこんな重たいもの、好んで着けたりしないわ。」そう言いながら、ホックをはずし、中の赤い上着の上から、その真珠や宝石がきらきら輝き、黄金がきらびやかに輝く瓔珞(ようらく。珠玉や貴金属に糸を通して作った装身具で、首に掛ける)を掴み取った。宝玉が急いで鎖を手のひらに載せて見てみると、果たして一面に四つの文字、両面で八つの文字で、合わせて二句の吉祥の予言であった。またその様式通りに外観を以下に描く。

不離不棄、芳齢永継
宝玉はそれを見て、二回唱え、また自分のものも二回唱え、それで笑って尋ねた。「姉さん、この八文字はやはり僕のと対になってる。」鶯兒が笑って言った。「これはしらくも頭の坊さんがくれたもので、あの人は必ず金の器の上に彫らないといけないって言われてました。」宝釵は鶯兒が言い終わるのを待たずに、茶を淹れに行かないのを怒り、一方でまた宝玉にこの玉がどこから来たのか尋ねた。
宝玉はこの時、宝釵と肩を寄り添い座っていたが、ふとひとしきり香りが漂ったが、何の香りか分からなかったので、尋ねた。「姉さん、これ何の香りなの。僕、こんな香り嗅いだことがないよ。」宝釵が言った。「わたし、燻した香りが一番苦手なの。すばらしい衣裳なのに、どうしてそれを燻すの。」宝玉は言った。「それだったらこれは何の香りなの。」宝釵はちょっと考えていたが、言った。「そうだ、これはわたしが朝飲んだ冷香丸の香りだわ。」宝玉は笑って言った。「どこの「冷香丸」がこんな良い香りがするの。姉さん、お願いだから、僕に一錠試させて。」宝釵は笑って言った。「また無茶言って。薬まででたらめに食べるのかい。」
それから一言も発せられないうち、ふと外の人の声が聞こえた。「林お嬢様が来られました。」声がまだ終わらぬうち、黛玉がもうよろよろとした歩調で入って来たが、宝玉を一目見ると、笑って言った。「あらまあ、わたし悪いタイミングで来たわね。」宝玉らは急いで立ち上がり、黛玉を座らせると、宝釵は笑って言った。「それってどういうこと。」黛玉は言った。「この人が来ていると知っていたら、わたし来なかったわ。」宝釵は言った。「それどういうこと。」黛玉は言った。「どういうことかって。来るんだったら一緒に来るし、来ないんだったら誰も来ないわ。今日は宝玉が来て、明日はわたしが来る。時間をずらしたら、毎日誰かが来ることになるんじゃない。冷遇され過ぎる訳でもないし、にぎやか過ぎる訳でもない。姉さん、何か理解できないことがあって。」
宝玉は黛玉が上着の上に真っ赤な羽毛の前身ごろ(衣服の胸前の部分)が真ん中で割れた外套を羽織っていたので、尋ねた。「雪が降っていたの。」女中たちが言った。「この半日、降っていました。」宝玉は言った。「僕の外套を取って来て。」黛玉は笑って言った。「ほら、そうでしょ。わたしが来たら、宝玉は帰らないといけないんだから。」宝玉は言った。「僕がいつ帰るって言った。準備しておくだけだよ。」宝玉の乳母の李ばあやが言った。「外はまだ雪が降るかもしれないので、時間を見ないといけませんから、ここで姉さんや妹と一緒に遊んでいてくださいまし。薛の叔母様のところでお茶請けの準備をされていますよ。わたしが女中に言って外套を取りに遣りますから、小者たちには帰るように言いましょうか。」宝玉は頷いた。李ばあやは外に出て、小者たちに、「みんな、帰っていいよ」と命じた。
こちらでは薛叔母さんがいくつか手の込んだお茶請けを準備し、宝玉たちに茶を飲み菓子を食べさせた。宝玉は先日東府(寧国府)で賈珍の奥さんのガチョウの水掻きが美味しかったと褒めていたので、薛叔母さんは急いで自分が酒に漬けたものを取って来て、宝玉に味見させた。宝玉は笑って言った。「こいつは酒と一緒に食べたら美味しいよ。」薛叔母さんは人に命じて上等な酒を淹れさせた。李ばあやがやって来て言った。「奥様、酒はもう注がないで。」宝玉は笑って懇願して言った。「ばあや、後生だから、僕に一杯だけ飲ませて。」李ばあやは言った。「この役立たず。大奥様や奥様の前だったら、たとえ酒を一甕飲んだって構わないさ。いつだったか、わたしがちょっと眼を離した隙に、誰がうちのきまりを理解していなかったのか知らないが、ただあんたの歓心を惹きたいがために、あんたに酒をひと口飲ませて、おかげであたしゃ二日も罵られたんだから。薛叔母さん。あんたはこの子の性質をご存じないんだ。酒を飲むと大暴れするのよ。そのうち、大奥様がご機嫌な時に好きなだけ飲ませたら、次からもう二度と飲ませてもらえなくなるわよ。わざわざあたしに要らぬ面倒をかけないでくれない。」 薛叔母さんは笑って言った。「老いぼれ。安心して自分の分だけ飲んだらいいわよ。わたしもこの子に余り飲ませないから。奥さん、あんたに言っとくけど、わたしがいるから大丈夫よ。」一方で女中に命じて、「さあ、皆さんがたにも一献さしあげて、寒さをしのいでください。」かの李ばあやはこのように言われると、周りの人たちと一緒に酒を飲むしかなかった。
ここで宝玉はまた言った。「燗をしなくていいよ、僕は冷やで飲むのが好きだから。」薛叔母さんが言った。「それはだめよ。冷たい酒を飲むと、字を書く時に手が震えるわよ。」宝釵が笑って言った。「宝兄さん、あなたは毎日家でいろんな雑学を学んだおかげで、まさか酒の性質は最もものを温めるから、熱くして飲むと、発散が速くなる。冷たいまま飲むと、体内で凝結され、五臓に持って行ってこれを温めてやらないといけないから、身体を傷めるという道理を知らないってことはないわね。この説はまだ改められていないわ。もうそんな冷たいもの、飲んじゃだめ。」宝玉はこの話を聞いて道理だと思い、冷や酒を下に置くと、人に命じて燗をさせてから飲んだ。
黛玉は瓜子(ヒマワリやスイカの種を炒ったもの)を歯先で割って食べていたが、ただ口をすぼめて笑って見ていた。ちょうど黛玉の小間使いの雪雁がやって来て、黛玉に手あぶりの小炉を手渡した。黛玉はそれで笑みを浮かべて雪雁に尋ねた。「誰がおまえに持って来させたの。心配させちゃったわね。あっちでは、わたしが凍え死んでいるんじゃないかって。」黛玉は受け取ると、胸の中に抱いて、笑って言った。「またあなたに要らない話を聞かせてしまったわ。わたしが普段あなたに言っていることは、いつも馬耳東風なんだから。どうしてあの人の言うことには、天子様の命令のように従うの。」宝玉はこの話を聞いて、黛玉がこの場を借りて皮肉を言っていると知り、返すことばも無く、ただにこにこ笑っていただけだった。宝釵はもともと黛玉にこんなことを言う習慣があると知っていたので、相手をしなかった。薛叔母さんはそれで笑って言った。「あなたはもともと身体が弱いから、寒さに耐えられないと、皆があなたのことを気にかけてくれるのを、戸惑っているのね。」黛玉は笑って言った。「叔母様はご存じないの。幸い叔母様はここに住んでおられるけど、もし他所の家におられてこんなことがあったら、相手が困られるでしょう。どうしてその家には手あぶりも無いからって、急いで家から届けさせるようなことをするでしょう。女中たちがあまりに細かいことを気にしすぎるとは言いませんが、わたしが平素軽はずみで傲慢だと思われるかもしれませんわね。」薛叔母さんは言った。「あなた、考え過ぎよ。そんなこと考えて。わたしはそんなふうに思ってはいませんよ。」
話している間に、宝玉はもう酒を三杯飲んでしまった。李ばあやがまた近寄り、飲むのを止めさせようとした。宝玉はちょうど酒に酔って気持ちよくなっている時だったので、また周りの女性たちと談笑し、どうして酒をすすんで止めるだろうか。ただへりくだり懇願して言った。「ばあや、お願い。あと二杯飲んだら止めるから。」李ばあやは言った。「坊ちゃん、今日は旦那様がご在宅ですからね。坊ちゃんのお勉強のことを細かく尋ねられますよ。」
宝玉はこの話を聞いて、心中あまり愉快でなく、ゆっくりと酒を置くと、首を下に垂れた。黛玉は急いで言った。「皆をしらけさせないで。叔父様に呼ばれたら、叔母様に引き留められたと言えばいいわ。この叔母さんったら、わたしたちをからかっているだけよ。」一方ではこっそり宝玉をけしかけ、宝玉をいこじにさせ、一方ではぶつぶつ独り言をつぶやいた。「あんなポンコツの言うことなんか気にしない。わたしたちは自分たちが楽しむことだけ考えよう。」かの李ばあやも素より黛玉の人となりを知っているので、こう言った。「林お嬢様、宝玉様を助けるようなことを言わないでください。あなたがお諫めすれば、宝玉様も少しは聞いていただけると思います。」黛玉は冷ややかに笑って言った。「わたしがどうしてこの方を助けるの。わたしもこの方を諫めるに値しませんわ。この叔母様は用心深過ぎるわ。いつもお婆様もこの方にお酒をお出しになるから、今晩薛叔母様のところでちょっと飲み過ぎたからといって、特に問題はないと思います。きっと薛叔母様のところは赤の他人だから、ここで酒を飲んではいけないということかもしれないわね。」李ばあやはそれを聞いて、急いで、また笑って言った。「本当にこの林お嬢様というお方は、おっしゃる一言が、ナイフより鋭いんですね。」宝釵も我慢できず笑いながら、黛玉の頬っぺたをちょっとつねって言った。「本当に、この眉を顰めたお嬢ちゃんのお口から出ることばは、人に嫌われるでもなく、好かれるでもないわね。」
薛叔母さんは一方で笑いながら、またこう言った。「びくびくしないで、子供たち。こちらに来て、悪いものを食べさせられるんじゃないかと、ちょっとした心配でもあるように感じられるなら、わたしは不安です。安心して食べていただいたら、責任は全てわたしが取ります。さあ、晩御飯を食べましょう。酔っぱらったら、わたしと一緒に寝ましょう。」そして命じた。「もっとお酒を燗して来てちょうだい。薛叔母さんが一緒に飲みますよ。ご飯も食べてちょうだい。」宝玉はそれを聞いて、ようやくまた気持ちが掻き立てられた。李ばあやはそれで女中に言いつけた。「あんたたち、ここで気を付けていてちょうだい。わたしは家に帰って着替えてまた来るから。」そっと薛叔母さんに挨拶して言った。「薛叔母様、宝玉様にあまり酒を飲ませないでください。」そう言って、家に帰った。
ここにはまだ二三の年寄りの女中が残っていたが、皆このお話の筋とはあまり関係が無い。李ばあやが帰ったので、彼女たちもそっと自分の用を済ましに行った。ふたりの子供の女中が残り、宝玉の歓心を惹こうとした。幸い、薛叔母さんが精一杯なだめて、宝玉に何杯か酒を飲ませると、急いで酒を片付けさせた。酸笋鶏皮湯(タケノコの漬物と鶏皮のスープ)が出ると、宝玉は何杯か痛飲し、またお茶碗半分余り碧粳粥(碧粳米(河北省玉田県で取れる青みを帯びたうるち米)で作ったお粥)を食べ、しばらくして宝釵、黛玉のふたりも食事を終え、濃いお茶を何杯か飲んだ。薛叔母さんはようやく安心した。雪雁ら数人も、食事をして部屋に入って来てかしずいた。黛玉はそれで宝玉に尋ねた。「もう帰りませんか。」宝玉はうとうと眠気がさしてきて、眼を細めて言った。「君が帰るなら、僕も一緒に帰るよ。」黛玉はそれを聞くと、立ち上がって言った。「わたしたち、今日一日おじゃましましたが、もう帰らないと。」そう言うと、ふたりは暇乞いをした。
子供の召使たちが急いで笠を捧げ持って来たので、宝玉は頭を少し下に下げ、笠を被せさせると、その召使はこの真っ赤なフェルトの笠をちょっと払った。それでようやく宝玉の頭の上に乗ったのだが、宝玉は言った。「もういい、もういい、このへたくそ。もうちょっとやさしく。まさか他の人が被るのを見たことがないの。僕、自分で被るよ。」黛玉がオンドルの縁の上に立って言った。「こっちに来て。わたしが被せてあげる。」宝玉は急いで近づいた。黛玉は手で軽く髪の毛を束ねた冠を覆うと、笠の縁を額の鉢巻の上に固定し、その胡桃の大きさの赤い綿の髪留めを支えて、ゆさゆさ揺すぶって笠の外に露出させた。頭の上を整え終わると、しばしよく確認してから、言った。「いいわ、マントを被って。」宝玉はそれを聞くと、ようやくマントを受け取って被った。薛叔母さんは急いで言った。「あなたがたの乳母の叔母さんたちがまだ戻って来られていないわ。ちょっと待ってなさい。」宝玉は言った。「僕たち、どうして叔母さんたちを待っていないといけないの。召使たちがお伴してくれればいいよ。」薛叔母さんは心配なので、ふたりの女中に言いつけ、この兄弟たちを送って行かせた。
ふたりはお礼を言って、まっすぐ賈のお婆様の部屋に帰った。賈のお婆様はまだ晩御飯を食べていなかったが、薛叔母さんのところから帰って来たと知り、一層嬉しくなった。宝玉が酒を飲んで来たのを見て、宝玉を部屋に戻って休ませ、再び出て来るのを許さなかった。また召使たちにちゃんと世話をするよう言いつけた。ふと宝玉に付いて行った者のことを思い出し、皆に尋ねた。「乳母の李ばあやはどうしていないの。」周りの人々は直接李ばあやが家に帰ったと言う勇気がなかったので、ただこう言った。「戻って来たところで、用事を思い出して、また出て行ったのでしょう。」宝玉は千鳥足で歩きながら、振り返って言った。「李ばあやはお婆様よりもっと役に立ちますよ。あの人に何を聞くの。あの人がいなかったら、おそらく僕はもう二日長く生きていられますよ。」そう言いながら、自分の寝室に戻った。見ると筆と墨が机の上に置かれていた。晴雯(せいぶん)が先ず出迎え、笑って言った。「ごきげんよう。わたしに墨を磨らせて、今朝ご機嫌で、三つ文字を書かれ、筆を投げ捨てて出て行かれ、わたしに言いつけられたので、今日一日ずっと待っていました。早くわたしにこの墨で書き終えていただけば、仕舞えるんですが。」宝玉はようやく今朝の出来事を思い出し、それで笑って言った。「僕が書いた三つの文字って、どこにあるの。」晴雯は笑って言った。「この方は酔っぱらっているのね。あなたは前もってお屋敷の方に行って、門斗(部屋の門の外に設けた風除けの小部屋)の上に貼るよう言いつけられました。わたしは他人に頼むと貼り損なう恐れがあるので、自分で上まで登って、しばらく貼っていて、それで手がかじかんで動かなくなったんですよ。」宝玉は笑って言った。「忘れていたよ。おまえの手が冷えたんなら、僕が代わりに握ってあげる。」そう言って手を伸ばし、晴雯の手を引き、一緒に 門斗の上に新たに書いた三つの文字を見た。
しばらくして黛玉が来たので、宝玉は笑って言った。「いい娘だから、嘘を言っちゃあだめだよ。見て、この三つの字でどの字がいいかな。」黛玉が首を上げ見えたのは「絳芸軒」(こううんけん)の三文字であったが、笑って言った。「一字一字皆いいわ。どう書いたらこんな良い文字が書けるの。明日は代わりに扁額を揮毫してもらおうかしら。」宝玉は笑って言った。「君、また僕によいしょするんだから。」そう言ってまた尋ねた。「襲人(しゅうじん)姉さんはどうしたの。」晴雯は部屋の中のオンドルの方に向けて口を突き出して示した。宝玉が部屋の中を見てみると、襲人が服を着たまま眠っていた。宝玉は笑って言った。「分かったよ。こんなに早く寝ちゃったんだ。」また晴雯に尋ねて言った。「今日僕があちらで朝食を食べた時、一皿豆腐皮(湯葉)の包子(饅頭)があったんだ。僕はおまえが好きだろうと思ったんで、珍叔父さんの叔母さん(珍大奶奶。尤氏のこと)に、僕が今晩食べたいから、誰かに届けさせてほしいと言ったんだ。おまえ、見なかったかい。」晴雯は言った。「もうそんなことおっしゃらないで。届けられるとすぐ、これはわたしにだなと分かりましたが、ちょうど食事を食べたばかりだったので、そこに置いておきました。その後、乳母の李ばあやが来てそれを見つけ、こう言われました。「宝玉坊ちゃんはお食べにはならないだろうから、持って帰って自分の孫に食べさせよう。」そう言って、人に言って家に届けさせていました。」ちょうどそう言っていると、茜雪(せんせつ)が茶を捧げ持って来たので、宝玉はまた「林ちゃん、お茶をお飲み。」と勧めた。周りの人々は笑って言った。「林お嬢様はとっくに行かれましたよ。まだお勧めするんですか。」

宝玉はお茶を茶碗に半分飲むと、ふとまた今朝飲んだ茶のことを思い出し、茜雪に尋ねて言った。「朝起きた時に楓露茶を淹れてくれたけど、僕はあのお茶は三四回目でようやく色が出ると思うんだけど、今回どうしてまたこのお茶を淹れたの。」 茜雪は言った。「実は残しておいたのを持ってきました。あの時、李ばあやが来られて、飲んで行かれたんです。」宝玉はそう聞くと、手の中に持っていた茶碗をそのまま地面に投げつけると、ガチャンと音がして、粉々に壊れ、茶が茜雪のスカートにかかった。宝玉はまた跳びかかるように茜雪に尋ねて言った。「李ばあやはおまえたちと一緒に仕えてくれている乳母だけど、おまえたちはあの人をそんなに敬っているのかい。僕が小さい時に何日かあの人のおっぱいを吸っただけなのに、今やご先祖様より大きな顔をしやがって、追い出してやったら皆せいせいするよ。」そう言うとすぐに賈のお婆様のところへ戻ろうとした。
元々 襲人は寝ていなかったが、わざと眠ったふりをし、宝玉をからかおうとしていた。先ず字のことを言ったり包子のことを尋ねたりで、起き出さなくても良かった。その後宝玉が茶碗を投げつけ、怒り出したので、急いで起き上がってなだめに行った。早くも、賈のお婆様のところの人が来て尋ねた。「どうされたのですか。」襲人は急いで言った。「わたしが今さっきお茶を淹れたのですが、雪で滑って転んでしまい、うっかり茶碗を落としてしまいました。」一方ではまた宝玉をなだめて言った。「あなたが本心からあの人を追い出されたいなら、それも結構ですが、それならわたしたちも皆お暇(いとま)をいただきたく存じます。それでも、この場の勢いで皆が一斉に追い出されるよりましですし、あなたももっと良い召使が来て、あなたのお世話をしてくれないと悩む必要もないですよ。」宝玉はそう聞くと、ようやく何も言わなくなった。 襲人らは宝玉に手を貸してオンドルの上に連れて行き、服を脱がせた。宝玉は口の中でまだ何か言おうとしていたようであったが、ろれつが回らなくなり、意識が益々朦朧としてきたので、急いで宝玉を介抱して寝かせてやった。襲人はあの「通霊宝玉」をはずして、ハンカチでちゃんと包むと、敷布団の下に押し込み、翌日宝玉がこれを身に着け、首を冷やすことのないようにした。かの宝玉は頭を枕にして眠りについた。この時乳母の李叔母さんらは既に部屋に入って来ていたが、宝玉が酔っぱらっていると聞いていたので、敢えて前には出て来ず、ただそっと彼の寝息を聞いて、ようやく安心して家に帰った。
翌日目覚めると、取り次ぎの者がこう申し上げた。「あちらの蓉旦那様が秦鐘様をお連れになり、ご挨拶にお見えです。」宝玉は急いで出迎えに行き、秦鐘を連れて賈のお婆様にお目にかかった。賈のお婆様は秦鐘の容貌が美しく、ふるまいがやさしく、宝玉の勉強のお伴に堪え得ると思ったので、心の中ではたいへん嬉しく思い、それで彼を引き留めお茶や食事を摂らせ、また人に言いつけて王夫人らに会いに行かせた。周りの人々は秦氏のことが好きだったので、秦鐘がこのような人柄であるのを見て、皆嬉しく思い、彼が帰る時には、皆お土産を持って帰らせた。賈のお婆様はまた荷包(小物を入れる小さなきんちゃく袋で、刺繍が施してある)と金魁星(黄金で鋳造した北斗七星の第一星の魁星(かいせい)の神像)をくださり、これにより「文星和合」(科挙の試験に無事合格する)というおめでたい意味になった。また秦鐘にこう言いつけた。「あなたは遠くにお住まいだから、一時的には身体が慣れないかもしれないが、わたしたちのところで暮らしなさい。どうかあなたと宝玉が一緒に勉強し、その他の努力せず進取の気持ちの無い学生の影響を受けないようになさい。」秦鐘は一々頷き、家に帰って父親に報告した。
彼の父親の秦邦業は現在営繕司郎中に任じられ、年齢は70歳に近く、夫人は早くに亡くなっていた。年齢が50歳になるまで息子、娘がおらず、養生堂(捨て子を収容して育てる機関)から男の子をひとり、女の子をひとり、もらって養育した。ところが思いがけず男の子は死んでしまい、女の子だけが残った。この女の子は幼名を可兒といい、また正式な名前を兼美と名付けた。成長すると、姿かたちがしなやかで、立ち居振る舞いがさっぱりし、元々賈家と多少の縁故があったことから、賈家に嫁入りした。(秦可卿のこと。)秦邦業は53歳にして秦鐘が生まれ、今年12歳となった。昨年家塾の恩師が南方へ戻られ、家で以前勉強した内容を復習するだけであったが、ちょうど親戚の賈家と賈家の家塾に入れてもらう相談をしていた。たまたま宝玉に出会ったこの機会に、また賈家の家塾で塾を司っているのは、今の老儒(年寄りの学者)、賈代儒であることを知り、秦鐘が塾に入ると、学業の進歩が見込め、これによって名声を得ることができれば、たいへん喜ばしいことであった。ただ経済的に手元不如意で、賈家の人々は富や地位を重んじ、貧しい者を蔑(さげす)んだ。このため息子の一生の大事に関することであるので、やむを得ず無理やり算段して、うやうやしく二十四両の初対面の贈り物の金を包み、秦鐘を連れて賈代儒の家を訪問し、その後宝玉が選んだ吉日を聞き、一緒に入塾した。塾の中ではこれより騒動が持ちあがるのであるが、それがどのようなものであったのか、次回に詳しく説き明かします。
さて次回は、賈宝玉と秦鐘が賈家の家塾に通うことになりますが、どのような「騒動」が起こるのか、次回第九回をお楽しみに。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます