









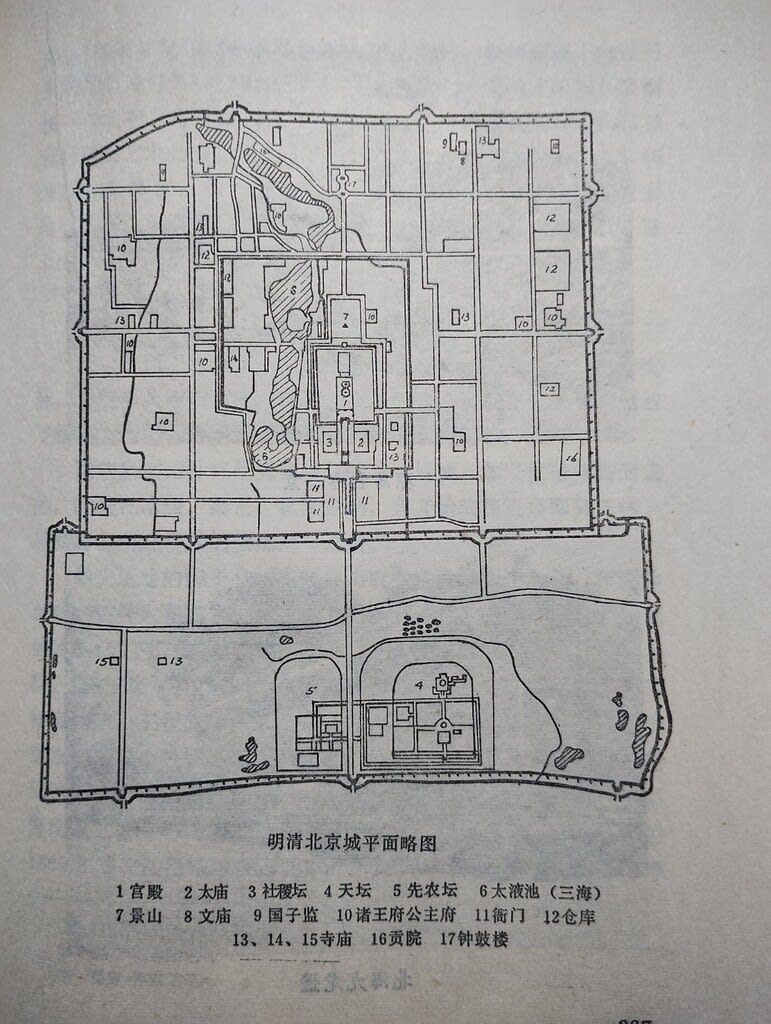



万斯同
第五節 清前期の北京の学術と文芸活動
北京の学者や文士
北京は清朝の首都になり、全国各地の学者、文士がこの地に集まった。彼らはある者は科挙の試験に合格し、翰林院に入った。ある者は或いは招聘を受け、或いは遊学のため、北京に来た。こうした学者たちは互いに親しくなり、議論を戦わせ、北京の文化的繁栄や学術の発展に重要な影響をもたらせた。
康熙帝は三藩の平定(1681年。清朝の建国を助け、各地に独立政権となって藩王と称された漢人武将、雲南の呉三桂(平西王)、広東の尚可喜(平南王)、福建の耿継茂(靖南王)を滅ぼした)後、学問を重んじ、学識のある名士が争って都、北京に集まってきた。平民階級で、徐元文の招聘に応じて北京で主に『明史』を編纂した万斯同(ばんしどう)は、毎回講義の度に、翰林、部郎、処士が4、50人を率いて、車座になって聴講した。宮闕(宮殿)、地理、倉庫、河渠、水利、選挙、賦役、朝儀、兵刑など諸項目で、どの講義も、瓶から水が注がれるようにすらすらと語られた。(『李恕谷年譜』巻3)著名な学者で、「顔李学派」の創立者、李塨(りきょう)が講義に参加した時、万斯同は彼を講義参加者に紹介し、また彼を招聘して講義に登壇してもらった。こうした学術活動は、北京の文化に対し推進作用を起こした。
『四庫全書』を編纂する過程で、清の統治者はたくさんの学者を北京に集めたが、その中には載震、庄存与、翁方綱、朱珪、任大椿、邵晋涵、周永年、姚鼐、王念孫、紀盷等の人が含まれていた。彼らは『四庫全書』の各巻の出典(淵源)、テキスト(版本)、内容について、細かく考訂(考証と訂正)を行い、『四庫全書総目提要』を作成したが、これは重要な目録学の著作である。載震、 王念孫と著名な学者の銭大昕は更に北京で多くの経史、音韻、地理、歴算考証の学術著作を作成した。
北京でも有名な学者を輩出した。例えば満州正黄旗人、阿什坦は、満州語で『大学』、『中庸』、『孝経』を翻訳し、漢軍鑲白旗人、劉淇の著作に『助字辨略』、漢軍旗人、傅澤洪の著作に『行水金鑑』、大興県人、劉献廷の著作に『広陽雑記』、 翁方綱の著作に『両漢金石記』、王源撰『明史・兵志』、礼親王代善后昭槤の著作に『嘯亭雑録』があった。著名な学者、徐松も大興人であった。
文士の中で、大詩人王士禛は長期で北京に居留し、各地から北京に来て彼を尋ね教えを求める者が頗る多かった。清朝宗室(皇室、皇帝の一族)の著名な詩人、文昭はそこで「爵を辞して読書し、王士禛から遊」んだ。(『清史稿・文昭伝』)王士禛は北京で文社を組織し、兄の士禄、弟の士祐、及び宋琬、施閏章、厳沆、丁澎らと互いに詩文のやりとりをし(酬唱)、「燕台七子」と呼ばれた。
北京の満州族貴族、八旗の子弟の中にも文士が出現した。その中で最も有名なのは性徳と曹雪芹である。性徳、姓は納喇氏で、隷満州正黄旗、康熙帝の寵臣、明珠の子であった。1675年(康熙14年)進士に合格し、康熙帝の侍衛に任じられた。彼は詩を善くし、とりわけ詞に長じ、「著すところの『飲水』、『側帽』二集、清新にして秀隽(抜きん出て優れ)、垢ぬけて」いた。(『清史稿・文苑伝』)性徳と朱彝尊、陳維崧は清代の「詞家三絶」と称せられた。
曹雪芹、名は霑(てん)、祖先は漢人で、捕虜にされ旗に編入され、満州正白旗に入り 包衣になった。正白旗は上三旗で、このため、代々皇帝の家奴(下僕)をしていた。曹璽、曹寅、曹顒、曹頫父祖(祖父と父)兄弟は続けて江寧の織造官に任ぜられ、曹璽の妻、孫氏はまた康熙帝、玄燁(げんよう)の乳母(保母)をしており、皇室との関係は密接で、それゆえ栄華富貴の家柄になった。康熙末年の皇子の間の皇位争奪に巻き込まれたため、雍正即位後に曹家は取り調べを受け財産を没収され(査抄)、これ以降、家は没落した。乾隆帝の時に少し暮らし向きが好転したが、雪芹の成長とともに、家の境遇はまた少しずつ落ちぶれ困窮するようになってしまった。

曹雪芹
曹雪芹は長期間北京に居留していた。北京は当時の清朝統治の中心で、満州貴族と大官僚の傲慢、奢侈、腐敗と小作人、庄丁に対する残酷な搾取は、北京が最も際立っており、曹雪芹自身が封建貴族階級の出身で、しかも家庭の災難を経験していた。こうした客観的な環境と彼自身の体験は、彼の思想や感情の変化に決定的な影響を与え、このため彼の現実主義的な大作、『紅楼夢』の中で、当時の封建社会のありさまを反映しただけでなく、同時に北京の社会のありさま、とりわけ八旗貴族と京城の市民の貧富の差が極めて大きい生活や階級関係を反映した。
『紅楼夢』は当初は写本しかなく、北京の廟会で販売された。その後、木版刷りのものが刊行され、浙広地域で流通し、芝居で演じられるようになり、代々伝わり広く知られるようになった。
清代北京に生まれた有名な作家には、他に大興県人の李汝珍がおり、嘉慶、道光年間に流行した長編小説『鏡花縁』は、彼の作品である。
戯曲
清代、北京の芝居はたいへん発展した。それは明代のものを継承してさらに発展させ、宮廷から民間に広まり、その脚本、俳優、上演する劇場、何れも明代よりも優れていた。
皇宮と円明園には大型の壮観な劇場(戯楼)があり、「同楽楼」と名付けられ、皇帝や后妃、及び大臣たちの歓楽に供ぜられた。ここでの演目は多くが正月や節句のお祝いや長寿のお祝いで、このため内容の多くは神話の物語、例えば『群仙慶賀』、『羅漢渡海』などの劇であった。清の統治者は関外にいた時代に既に小説『三国演義』を熟知していて、芝居に書かれ、その名を『鼎峙春秋』といい、昆曲の節回し(昆腔)で演じられた。『水滸伝』も『忠義璇図』に改編され、宮廷で上演された。宮廷演劇の規模は大きく、舞台衣装は新しく、脚色が多く、民間の劇団とは比べものにならなかった。
しかし民間の芝居は規模も大小様々、節回しは自由で、制約を受けなかったので、そのためより多彩になり、強い生命力を備えていた。清朝前期に北京で流行した芝居は、先ず昆曲、その少し後に梆子腔(ほうしこう。陝西省から流行した拍子木で拍子をとり歌う芝居)、乱弾腔、弋陽腔(よくようこう。江西省弋陽(よくよう)県から始まった節回しの芝居)が増え、その後、皮黄調が現れた。皮黄は各種の節回しを最も良く吸収でき、また改善するのに都合がよく、例えば初め、これは昆曲と同様、楽器は笛を主にしていたが、後に胡弓(胡琴)を用いるように改められた。これが以後北京で流行した京劇である。
北京の民間の芝居の組織には、乾隆時代には宜慶、萃慶、集慶、歓慶などの部、道光時代には四喜、三慶、春台、和春の四部があった。戯班の俳優は多くが各地の農家から契約して(立券)買われて来た。最初は年齢がたいへん若かったが、その後経験を積んで「出師」(一人前の役者)になり、親方(師匠)に贖金(礼金)をたくさん支払わねばならなかった。親方と役者の父母が契約を交わす時、契約書の上に墨で一本の線を引き、これを「一道河」と呼び、十年内の役者の生死存亡は、父母が口出しするのは許されなかった。芝居を演じる過程では、常に権勢を持った人の侮辱を受けた。役者の生活や境遇は、皆極めて悲惨であった。
劇団が上演する地方劇場には、初期には査楼、月明楼があり、その後は三慶園、慶楽園、広徳楼、広和楼(すなわち元の査楼)があった。劇団は内城、外城何れにもあったが、外城にあるものが多かった。乾隆、嘉慶時代は外城に十数ヶ所あり、そのうち正陽門(前門)外の大柵欄には5ヶ所あった。芝居の演目は大多数が明代の昆曲の演目で、『浣紗記』、『牡丹亭』、『義侠記』、『西厢記』などの伝奇小説の中から一幕の芝居にできるものを選んで上演し、また新たに創作したものもあった。上演の時には一二幕の立ち回りのある芝居も必要だった。王侯や地位の高い人は、屋敷の中に自分の劇団を持っていて、大臣官僚を会館に呼び寄せて上演し、劇場に行くことなく芝居を見ることができた。

広和楼(すなわち査楼)
北京の雑曲は種類がたいへん多く、「八角鼓」、「什不閑」、「蓮花落」などの名称があり、八旗の子弟が作ったと言われる。その曲や歌詞を見ると、北京地区に元々あった民間の歌曲や民謡を混ぜ合わせて作ったものであるに違いない。その曲目には上品なものも大衆的なものもあり、『帰去来詞』、『長坂坡』、『游寺』などがあった。
琉璃廠
北京の文化生活の中で、無くてはならない場所として、「琉璃廠」が挙げられる。 琉璃廠は明、清の両時代、北京で書店の集まった場所で、その所在地は外城の西寄りで、元々明代に琉璃瓦の窯があったことからそう名付けられた。李文藻、繆荃孫の記述によれば、乾隆時代、四庫館を開いて史書全書を編纂するため、全国各地から文士が集まり、書籍が北京に集められ、琉璃廠の書店は数十店を数えた。(『琉璃廠書肆記』、『 琉璃廠書肆后記 』)当時、書店や出版業を営む者は、その多くが書籍の版本の良し悪し、国内の蔵書家の蔵書情況、著述家の原稿の保存状況などに通暁していた。書商の中には書籍の内容に精通している者もいた。四庫館の編纂官、周書昌は、以前、呉才老の『韻補』を他人が買って行くのを見たことがあったが、鑑古堂の書商、老韋は彼に、邵子湘の『韻補』は既に尽く買われてしまったと言った。周書昌は、なるほど、その通りだと見做した。こうした書商はまたしばしば各地の書籍を保有する家に行って書籍を購入し、書籍の伝播の上で発揮した効果はたいへん大きかった。慈仁寺(南城)、隆福寺(東城)などの場所では、また本を売る屋台が出て、小説、戯曲、唱本を販売した。当時、学者や文士はしばしばこうした本屋や本を売る屋台に出入りしていた。

琉璃廠
林清
天理教の蜂起、林清の紫禁城攻撃
1813年(嘉慶18年)、林清の率いる天理教徒が紫禁城を攻撃したのは、歴史上前例のない反乱活動であった。それは黄巣や李自成のように数十万の農民蜂起軍を率いて京城を攻撃したのではなく、百人、二百人の教徒が紫禁城に乱入し、宮殿の守備兵らと死闘を展開した。
天理教は白蓮教の一派で、その組織は八卦に基づき編成され、それゆえ八卦教とも呼ばれる。天理教の派別は様々で、北京で組織されたものの多くは「龍華会」に属し、その中には更に紅陽派と白陽派の区分があった。この秘密の宗教教団は、北京、直隷、河南、山東、山西一帯で活動していた。彼らは「無生老母」を信奉し、「真空家郷、無生父母」の八字の口訣(信者に覚えやすいように口調よくまとめた語句)を伝授した。天理教のこの組織は、最初から清朝の政治権力を奪おうと意図していた。それゆえ入信時に、教徒は分相応に資金を出し、これを「種福銭」、または「根基銭」と呼んだ。毎年清明と中秋の節句には、教徒たちは更にその資金力に応じて献金をし、これを「跟賑銭」と称した。彼らの中では、百銭を納めた者は、事が成就した暁には1ヘクタールの土地を得ることができるとした。事が成就するとは、政権を奪うことである。
北京の天理教徒には様々な労働階層が含まれていた。郊外の貧困農民や手工業者が基本構成員であった。城内には奴僕、雇用人、厨役、行商人、職人、店員、更に下層の宦官、貧困旗人がいた。明らかに、天理教は当時の北京の労働階層の重要な政治組織であった。
北京天理教の首領は林清であった。林清(1770ー1813年)は、宛平県黄村宋家庄の人で、暮らし向きは困窮し、北京西単牌楼南側の一軒の薬屋で丁稚をしていたことがあり、また順承門(宣武門)の街路で夜回りをし、後に役所で使い走りをし、また運河で船の牽引夫をしていたなど、困難に満ちた生活の中で鍛えられた人であった。
1806年(嘉慶11年) 林清は天理教に入信した。後に逮捕され、「棒打ちの刑」に処せられた。釈放後、引き続き活動し、教徒の人数を増やし、組織を拡大した。 林清は勇敢で、弁舌が巧みで、気前が良く義理堅く、心から教徒たちを擁護した。彼は教徒たちにより「坎卦」(『易经』六十四卦の一)首領に推挙された。当時、宛平、大興一帯では「若要白面賎、除非林清坐了殿」(白顔が卑しいと言うなら、林清を帝位に就けねばならない)という歌謡が広まっていた。天理教の教徒たちは皆「林清は聖人だ」と称した。このことは、林清が清政権を打ち倒そうと考えていることを表していた。
北京天理教蜂起は林清が「坎卦」教徒たちを指導して発動したものだ。林清は河南の「震卦」教首李文成と時期を約して蜂起し、互いに支え合い、互いに声援し合った。李文成は河南滑県謝家庄の人で、木工出身で、人々は「李四木匠」と呼んだ。彼は算学に少しだけ通じ、人々を大いに心服させ、数万の教徒たちは彼を極めて敬愛し、彼を「李自成の生まれ変わり」と言った。北京と滑県の二大勢力は、滑県の教徒が人数が多く、蜂起の中心勢力であった。
1811年(嘉慶16年)秋、林清と李文成は河南道口鎮で会見し、併せて八卦教教首会議を開催した。道口鎮会議では反清蜂起の策略と準備等の問題を討議した。会議では清朝を打ち倒し、「大明天順」政権を打ち建て、蜂起成功後、林清を天王とし、馮克善を地王とし、李文成を人王とすることを決定した。以後、林清はまた河南に二度行き、李文成も北京に一度やって来た。彼らは「八月中秋、中秋八月、黄色い菊の花が至る所に咲き誇る」と宣伝し、「酉の年、戌の月、寅の日、午の時」、すなわち嘉慶18年(1813年)9月15日午(うま)の時刻に共に大事を起こした。彼らはまた林清の指導する坎字卦教徒による紫禁城攻撃を議定し、また河南から教徒を北京に派遣し支援させた。
李文成が指導する教徒たちは河南で蜂起の準備活動を行った。この教団の重要な幹部である牛亮臣は大坯山で兵器を製造したが、うっかりと滑県の知県強克捷に発見されてしまった。9月3日、李文成は逮捕され投獄され、罰としてその脛を切断された。教徒たちは蜂起の前倒しを迫られ、滑県を攻撃し、強克捷を殺害し、李文成を救出した。山東で相次いで呼応したが、遂には滑県を死守するも、大量の清軍の包囲攻撃に遭い、城は敗れ、李文成は敗走し死亡した。
林清は教徒の中の宦官に手引きさせ、少数の人数で先ず皇宮を占拠し、その後北京城を占領し、且つ嘉慶帝顒琰(ぎょうえん)が熱河から北京に戻る機会に乗じて、その途中に兵を伏して攻撃する計画を立てた。
林清は河南が期日前に蜂起したものの失敗したことを知らず、依然予定日時に紫禁城攻撃を発動した。彼は2百人を派遣して正面作戦の任務を担当させた。これを二隊に分け、一隊は東華門を攻撃、一隊は西華門を攻撃させ、各隊二人を首領とした。十人を一組とし、各組に頭目を一人置いた。蜂起に参加する教徒は白布で頭を覆い、白帯を腰に絞め、「得勝」の二字を連絡の合言葉とした。
15日早朝、彼らは密かに武器を帯び、城外の指定場所に集合した。東華門を攻撃する者は董村から出発し、西華門を攻撃する者は黄村から出発した。彼らは柿を担いだ行商人の扮装をして城内に紛れ込み、午の刻以前に紫禁城付近に到着した。地安門付近にも伏兵を投入し、呼応する準備をした。隊伍を率いる大首領の陳爽、祝顕などは前日に既に城内に入り、正陽門外に教徒が開設した慶隆戯園内で戦闘準備作業を行った。
正午に、蜂起者は「大明天順、開天行道」と書いた白い旗を振り、紫禁城攻撃の戦闘を開始した。東路は陳爽を先鋒とし、劉呈祥を殿(しんがり)とし、宦官の劉得財、劉金が道案内をし、東華門を攻撃した。彼ら30数人は南河沿の酒舗に集合後、北に向け進んだ。東華門前に到ると、何人かの教徒が不注意にも隠し持った武器をさらけ出したので、門の守備兵に発見され、急いで城門を閉ざした。蜂起軍は小人数が門内に駆け込み、残りは門外に足止めされた。門内に駆けこんだ人数は少なかったが、戦いぶりはたいへん勇敢であった。彼らは歩きながら攻撃し、協和門と蒼震門を過ぎ、そのまま内廷東門の景運門まで攻め込んだが、何人かの清朝廷の護衛軍により殺され、護衛軍の統領楊述曽により次々敗退した。

天理教蜂起軍紫禁城攻撃
西路の蜂起軍は陳文魁を先鋒とし、劉永泰を殿(しんがり)とし、宦官の張太、高広福が道案内をし、西華門を攻撃した。彼ら70人余りは菜市口に集合後、西華門外に到り、柿の籠を蹴り倒すと、武器を取り出し、西華門に攻め込むと、すぐさま城門を閉ざし、外から官兵が来るのを拒んだ。西路の戦闘は最も激烈であった。蜂起軍は続けざまに文頴館、造辧処、内膳房を攻撃し、そのまま養心殿、中正殿に到った。蜂起軍の一部は慈寧宮に攻め込んだ。大部分の蜂起軍兵士は内廷の西門の隆宗門外で宮門争奪の戦闘を展開し、たくさんの清兵を殺害し、その中には頭等侍衛の那倫らが含まれていた。

隆宗門扁額に残る弓矢
この時ちょうど内廷で勉強していた皇次子の旻寧(みんねい。すなわち後の道光帝)が、内宮の宮門を固く閉ざすよう命令を発し、援兵が来て救助してくれるのを待った。
清廷は火器を調達し1千名余りの官兵を使って蜂起軍を鎮圧した。双方の力量には大きな差があったけれども、蜂起軍はこのために少しも弱気になること無く、猛烈な火力と数多くの敵兵に対して、依然頑強に戦闘を堅持した。宦官の高広福は蜂起軍を手引きして馬道より登城し、彼は「順天保民」の旗を高く掲げ、士気を激励したが、不幸にも弓矢に当り犠牲となった。
その日の晩、護衛軍は紫禁城の城門を隙無く守備し、蜂起軍は紫禁城内に閉じ込められた。彼らは五鳳楼に火をかけ、混乱に乗じて包囲を突破するつもりであったが、突然大雨が降り、包囲突破計画は実施できなかった。16日、蜂起軍の戦士は空腹で疲労困憊していたが、尚頑強に戦った。夜になり、皇宮内での戦闘はようやく終息を告げた。
9月15日から17日まで、北京城は完全に戦争状態にあった。17日、曹福昌が組織した蜂起支援兵力が、依然城内で継続して活動しており、統治者を恐怖で不安にさせ、甚だしきは午門を守る軍官は異変を聞くや、「門を開け真っ先に逃げ出した」。
この時、嘉慶帝顒琰(ぎょうえん)はちょうど北京に戻る途中で、天理教蜂起軍が皇宮を攻撃しているとの奏上を聞き、すぐに燕郊外に停留して敢えて前進せず、19日になってようやく宮殿に帰った。
黄村宋家庄で戦闘を指揮していた林清は戦闘が不利な情勢にあるとの知らせを聞くと、教徒たちに命じて村落を固く守らせ、河南の援兵の到着を待った。17日早朝、清軍は宋家庄を包囲し、林清は逮捕された。嘉慶帝は自ら林清を尋問してから、彼の殺害を命じた。大部分の教徒たちはこっそり隠れ、祝顕、劉第五らは他郷へ逃げ、時を見計らって再挙を図った。
嘉慶帝時代、清の統治はまだ相当に強固で、清朝廷は依然相当大きな鎮圧力を保有し、これが林清の蜂起が失敗した客観的な原因である。林清は広範に深く群衆を発動し、力を蓄えることができず、紫禁城攻撃の戦闘を発動し、清宮廷を打ち負かしさえすれば、北京を掌握することができ、全国を制御できると考えていた。こうした敵を軽んじるというリスクを冒したことが、おそらく蜂起が失敗した主観的な原因である。同時に、河南の李文成の蜂起が失敗し、兵を派遣し北京を支援することができなくなった。北京の蜂起もあまり周到に組織することができず、蜂起部隊と部隊の間の連携が欠乏し、城内では統一した指揮を執ることができなかった。地安門外に埋伏した兵力は未だ動きが見られないだけでなく、支援部隊も時間通りに機能を発揮することができず、遅れて17日になって、曹福昌の支援要員はようやく行動を開始した。こうして、各路の部隊は孤軍奮闘したが、瞬く間に敵軍にそれぞれ分割して包囲され、あっという間に失敗に終わった。
この度の蜂起が、清の統治者に与えた打撃は極めて深刻なもので、嘉慶帝は、これは「漢、唐、宋、明も未だ為し得なかった事である」と言った。そしてより意義深かったのは、この度の蜂起により、全国各民族の間で、圧迫された人々が皇宮であっても攻撃ができると考えれるようになった。これにより人々の反清への闘志が大いに増すようになった。
順天府衙署
第四節 清朝の政治体制と民衆の蜂起
清朝の北京での地方行政組織
清代の北京の地方行政組織は、互いに独立した三つの部分で成り立っていた。すなわち、民政を管理する順天府、主に警備の責任を負う九門提督、治安の掌握を主とする五城御史である。
順天府 清は明に倣い、依然順天府を北京に置いた。衙署(役所)は地安門外にあり、鼓楼の東、すなわち明代の順天府旧址であった。大興、宛平の両県を管轄した。順天府尹(知事)は正三品官(一般の知府は従四品)であった。府尹の下属官には府丞、治中、通判、経歴などがあった。順天府の職権は「京畿治理」(北京首都圏の治安維持)、「刑名銭谷」(刑事訴訟、地租や税金の徴収)などの事務の掌握であった。清の統治者は毎月1、15日に、全国各州、府、県は、郷約(郷里で皆が遵守すべき規約)により人々全般に康熙皇帝の『聖諭広訓』を読み聞かせなければならないと規定し、京師が所在する順天府はそのうえ「先為開導」(先に諭し導く)し、全国の模範となるよう要求した。科挙の試験では、順天府は郷試、会試の事務を負う以外に、殿試の傳臚日、すなわち殿試の後、皇帝が進士に合格した席次を公布する日にちになると、更に長安門外に榜(掲示)を貼り出し、進士に合格した人の名簿を公布した。府尹、府丞が榜を貼り出すところで、上位三名(状元、榜眼、探花)の合格者に、「髪に花を挿して赤い襷を掛け、府宴(役所主催のお祝いの宴会)へ連れて行って、宴会が終わると、状元をその人の屋敷まで送った」。

清順天府行政管轄区略図
九門提督 九門提督は、正式な職称が「提督九門巡捕五営歩軍統領」と言い、俗に 九門提督と言った。衙署(役所)は地安門外にあった。九門とは内城の九門、すなわち徳勝門、安定門、東直門、朝陽門、崇文門、正陽門、宣武門、阜成門、西直門を指した。 九門提督は正二品の武官であり、専ら満州族の皇帝の腹心(親信)の大臣が兼務した。その職責は「守衛巡警」(守衛と警官)、「城門合閉」(城門を閉ざす)、「分訉巡緝」(うわさを調べ、捜査して逮捕する)を掌握することだった。
「儀仗の棍棒を手に、駕籠は前進をせきたてる。横丁を曲がり、振り向いて雷のように叫ぶ。更に鞭を振るって叱咤する。灰色の街並みに威風が沸き起こる。」
これは 九門提督の城をパトロールしている様子であった。
九門提督とそのグループの権力はたいへん大きく、人々の面前で威風を振りかざし、京城で綿密な統制を行った。北京城はいたるところに堆拨房、つまり巡察兵の歩哨所があり、内外城、及び城壁上に全部で1100ヶ所、城外を併せると1461ヶ所になった。城内の大通りや胡同には方々に柵が立てられ、柵は全部で1746ヶ所あった。どの柵にも出入りするための門があり、起更(最初の夜番が回る時刻で、午後7時)を過ぎると門を閉ざし、「皇帝の命令(奉旨)で遣わされた緊急の軍務であれば、直ちに門を開く」が、それ以外は「王以下の人々は、官民問わず、一律に通行することができず、歩軍校(八旗歩軍営を主管する官職)などはそれぞれ通りを指定して、交替で宿直し、歩軍協尉は引き続きパトロールを行」わねばならず、全城で夜間の外出禁止(宵禁)を実行した。京師の警戒を強化するため、白塔山(すなわち北海の瓊華島)上、及び内城の九門にはそれぞれ信炮(号砲を鳴らす大砲)五門を設置し、旗竿を五基立てた(その後、内城の九門にはそれぞれ大砲を十門、外城の七門には大砲を五門設置することが定められた)。緊急事態になると、号砲を撃って警報を表し、一ヶ所で大砲を撃てば、他の場所の号砲も皆それに呼応した。官兵は砲声を聞くと、直ちにそれぞれ武器を準備し、出撃の命令を待った。
五城御史 都察院に隷属する五城を巡視する御史で、略称が 五城御史である。京師(首都)は東、南、西、北、中の五城に分かれ、各城毎に満・漢の御史が各一人設けられ、全部で十人である。その下には五城兵馬司指揮、副指揮などの属員がいた。主要な任務は「綏靖地方(地方の支配権を保ち)、厘剔奸弊(不正行為を取り除く)」、「巡緝盗賊(盗賊を捜査して捕まえ)、稽検囚徒(囚人を審査、検査する)」(『清史稿・職官二』)ことであったが、実際には大衆が蜂起し反抗するのを防ぐことだった。このため、 五城御史は「非合法の悪質分子」を逮捕しなければならず、無為、白蓮、聞香など群衆の秘密宗教結社を取り締まった。こうしたいわゆる「邪教」に参加している者に対しては、「設法緝拿(なんとかして捕まえ)、窮究奸状(徹底して偽りの行為を追求し)」、「加等治罪(罪を一等加えて処罰)」しなければならなかった。 五城御史は更に一定の訴訟処理の権利を持ち、懲役刑以上を刑部に送るのを除き、「五城の訴訟は、御史が直接担当し、審査、判決」した。
康熙帝以後、京師の五城に司坊官(刑務官)を設け、全部で15名いて、これがつまり「司坊分理」(監獄を別に管理する)である。司坊管轄区域には城門外の通りや住民の居住地区、郊外の一部を含み、清河、海淀は何れもこの管轄内であった。これは人々に対し厳密に管理を行うためだった。乾隆以後、特に門牌、戸冊を重視し、司坊官に所轄地を厳しく調べるよう要求し、「外来の人に遇えば、詳しく来歴を調べなければならず、不法の徒が市塵に紛れ込ましむことなかれ」。京師の戸口門牌に対しては「随時稽査更正(随時審査、校正し)、核実辧理(事実を確かめ、処理)」した。
清の統治者は群衆が集まり騒ぎを起こすのを恐れ、芝居小屋まで厳しく制限した。清初の規定では、京師内城は「常に戯館の開設を禁止」し、それ以後には更に外城に対して「一律に夜唱を禁じ」、また当時人々に最も喜ばれた新しい節回しである秦腔(陝西省の地方劇)を禁じた。更に八旗官兵、一般の官吏、宦官が芝居小屋に行って芝居を見るのを許さないとの命令を何度も下した。もし違反者があれば、 五城御史は軍の統領(旅団長)、順天府と歩調を合わせ、厳しく取り調べ、名指しで糾弾した。
順天府、九門提督、 五城御史、これらはそれぞれ専門職で互いに協力し、北京城の人々を統治する職能部門を形作り、清の統治者が北京の人々に対する警備、鎮圧を強化する重要な措置で、これによって幅広い人々が清統治者の厳しい監視の下に置かれ、反抗を企てるのが難しかった。
清朝中期、北京の民衆の貧困と統治階級の堕落
清朝が入関、北京を首都に定めて40年後、中国国内は新たに統一が実現した。この後の百年間、社会は安定し、人々は生産に努め、物質的な富は絶えず増加し、国が繁栄し富み強くなる局面が出現した。しかし18世紀中葉以後、つまりおおよそ乾隆末期から嘉慶に到る時代、土地所有の集中が加速し、統治階級の生活は日増しに腐敗し一般大衆の境遇は更に悪化した。各地で大規模な人々の蜂起が起こった。例えば、苗疆(湖南墻西部、貴州省ミャオ族居住地区)、川楚五省(四川、湖北、陝西、河南、甘粛)で白蓮教の蜂起が、続けざまに起こり、勇猛に清政権を攻撃した。清朝の統治は既に至るところに危機をはらんでいた。
北京は貧富の格差が甚だしいところである。北京城の労働者の人々は、「西山から石炭を運搬する者が多く」、「顔は竈(かまど)の底の鍋のよう」に真っ黒な石炭運搬の苦力(クーリー)であろうと、「街頭で寒さに耐え」他人のため古着を繕う「お針子の貧しい婦人」、それとも「婦女子が三年間冬に頑張って、夜通し休まず集めた」都市郊外の貧しい家でも、休まず血を流し汗をぬぐって働かぬ者をいなかったが、それでも生活は楽にならなかった。「普通に暮らしても金が残らず、日1日と高利貸しから借りた金を引き出しては返済に当てないといけない」、このように高利貸しの厳しい搾取を受けていた。「可哀そうに搾り取られてすっからかんで、怒りをこらえてじっと我慢しても、どうにもならない。」毎日貧困にあえぎ、生命線上であえぐしかなかった。
これだけでなく、この時期北京城では更に何千何百の民衆が、絶え間なく流民となって現れた。このことは、土地が併合され、毎年水害や日照りの災害が続き、農民たちを甚だしい貧困に陥れ、次々と土地を失い、ふるさとを追われたことによりもたらされた。北京城の流民は乾隆晩期以後益々増加した。清の統治者はこうした情況を目の当たりにして、警備を強化して用心し、「無職の浮浪者」を「本籍地に送り帰らせた」が、防ごうとしても防ぎきれず、問題を解決しようにも解決しきれなかった。激しい変化を防ぐため、同時にまた五城御史に命じて救済して落ち着かせた。早くも順治初年(1643年)から粥廠を設け、木綿の衣服を置き、栖流所(難民、流民を収容する専門機構)を建立したが、焼け石に水で、何の問題も解決できなかった。道光年間、五城粥廠の数は清初と同じで、依然として各城に二ヶ所で、ただ米を炊く量が一石から二石に増えただけであった。冬になって放出された木綿の衣服も、普及するには遠く及ばなかった。道光帝旻寧(みんねい)は一度は勅諭の中で承認したが、各廠の身寄りのない老人、弱者は「千名から3、4千名と各々異なり」、置いている木綿の衣服は「250件余りに過ぎず、回しても貧しい人々に行き渡らせることができなかった」。ここからも問題の厳しさを見て取ることができた。そして決められた各城に一ヶ所設けた栖流所では、その人数が十数万と見積もられる流民、貧民に対しては、なおさらものの役にも立たなかった。
「やせ細った人々は通りの辺にいて、乞食たちは争って列侯の銭を取る」
「金橋玉洞は俗世間を隔て、蔵すを得たり乞食のかさぶただらけのライ病の身、
もう三旬(30日)も米粒を絶たれても訴えるところもなく、人に丘長春のようだと指さされた」
北京の街頭には昼間は乞食、夜には野宿をする者が、そこかしこに見られた。ものの本に依れば、1796年(嘉慶元年)2月のある寒い夜、街角で野宿していて凍死した者は8千人に達したと言うが、実際の状況はもっとひどかった。
北京では、漢族、回族などの貧富の格差が甚だしかっただけでなく、満州族内部も急激に分化が進んでいた。旗人下層で土地を失う者が次第に増加していた。清の入関時、満州族の兵丁(兵士)と家族は均しく内城に住み、彼らは北京周辺で囲い込んだ土地を分け与えられ、漢人の奴僕(しもべ)を遣って耕作をさせ、その収穫物を享受した。しかし兵役が多くて負担が重く、八旗の兵丁は兵役に服する時に馬、食糧や馬の餌、兵器は全て自分で用意しなければならず、ひいては八旗の兵丁をして「借りると言えど返す能わず、遂には困窮し切羽詰まった状態になる」者が益々増えていった。同時に人口が増加し、兵役に就いて兵糧を受け取ることのできない八旗の余剰者が益々増加したのに、土地を分けて相続させる元の土地の面積は増やすことができなかった。おまけに奴僕が逃亡し、彼らはまた「身は京城に在って自分では作物の種を蒔くことができず、限られた土地では荘園の管理人を設けることもできず、人を遣って小作料を取り立て、往復の旅費や所得は勝手に使われるに任せた」(『清世祖実録』巻127、順治16年8月壬辰)。然るにその生活は「日々贅沢を続け」、「少しも節約をすることがなく」(『清仁宗実録』巻113、嘉慶8年5月)、金が足りなければ、漢人に旗地を質入れするのが「必然の情勢となった」(『八旗公産疏』、『清朝経世文編』巻35参照)。清初の規定によれば、満州族、漢族間で土地取引きは禁じられ、旗人の土地は漢人に売ることはできず、且つ清統治者は「八旗の生計」が困窮することで統治に危機が及ぶのを危惧したので、康熙帝政権以来、絶えず国庫の銀(帑銀)を出し、八旗の兵丁(兵士)に下賜(賞賜)したり、(質草に入れた)旗地を請け出し(贖出)たりしたが、何の足しにもならな(無済于事)かった。兵丁は賞銀を手にしても、「わずか数か月で、すっかり使い果たしてしまい(罄尽無余)」、請け出した旗地は元の持ち主が買い戻す力が無いため、必ずや別の旗人が「買うことに同意(認買)」し、こうして地主に土地を兼併する機会を提供した。このため益々多くの旗下の人が土地を失い、生活に困窮し(衣食拮据)、没落して貧民となった。嘉慶時代になると、国庫が空っぽになったため、朝廷はもはや大量に国庫銀を支出して下賜したり土地を請け出す力が無くなり、 八旗の生計問題は一層厳しくなり、一部の清王室一族の子孫(覚羅)は内城にも「身を寄せる場所が無かった(栖身無所)」。清政府はこの大量に出現した八旗の仕事が無く遊んでいる(閑散)人丁の重い負担から脱却するため、彼らを東北に移して開墾をさせざるを得なかった。この作業は1741年(乾隆6年)に八旗の余丁3千人を吉林に移すことから始まったが、大規模に実施したのは嘉慶時代以降のことである。1812年(嘉慶17年)に命令を発し、駐京八旗で仕事の無い人員を双城(今の黒竜江省ハルピン市)堡(砦)に移し駐屯、開墾をさせた。翌年、京師宗室の仕事の無い人々を盛京(瀋陽)小東門外に移し、土地を選んで家を建て住まわせた。1824年(道光4年)、また駐京八旗の仕事の無い人丁を伯都納(吉林扶余)に移し、駐屯、開墾をさせた。しかし行きたがる者は「あまり進んで出ては来ず」、「人数は甚だ少なかった」。乾隆初めから道光中期まで東北各地に移って開墾をした旗人はわずかに5千戸余りに過ぎず、そのうちの相当多くはまた北京に逃げ帰った。北京城内の仕事の無い八旗の人丁は依然たいへん多く、それに加えて大量に集まった漢族の貧民、流民が、清中葉以降の重大な社会問題であった。
上で述べたことと明らかに対照的なのだが、北京はまた高位高官(達官顕貴)の楽園であった。こうした北京に住む満州、蒙古の王公貴族、漢族の大官僚、大地主、大商人たちは大量の土地や家屋を保有していた。例えば懐柔の大地主、郝(かく)氏は「肥沃な田地を数多く持ち(膏腴万顷)」、京師の糧商、祝氏は「富は王侯を越え、所有する家屋は千間以上に達し、園亭はたいへん美しく、十日遊覧して回っても、見尽くすことができなかった」。けれども祝氏と肩を並べる大富豪として、他にも査氏、盛氏がいた。懐柔の郝氏は乾隆帝弘歴を接待したことがあり、お上に水陸の珍味を献上すること、百品以上に及んだ。その他の王公や近習、及び下層の人々(輿台)や奴隷に到るまで、皆にごちそうを供し、一日の食事の費用が十万余りに達した。(昭槤『嘯亭続録』巻2、本朝富民之多条)こうした一族は上記の貧民と比べると、まるで雲泥の差(天壌之別)があった。
乾隆帝弘歴を首とする統治グループは、更に極めてぜいたくで糜爛(びらん)した生活を送っていた。1798年(嘉慶3年)ちょうど北京の街頭で飢えた人々が群を成し、西南の苗族や四川や湖北の白蓮教の反乱軍が清統治者に猛烈に攻撃を仕掛けていた時、太上皇となった乾隆帝が宮殿内に鰲山(ごうざん。陝西省宝鶏市の秦嶺山脈の主峰)に似せた築山を築き、花火を上げ、宴席を催しほうびを下賜し、ほとんど手持無沙汰にしている間が無かった。
この当時、全国の大小の官吏の間で汚職が習慣となり、乾隆後の二十年は和珅(ヘシェン。わしん)が権力をほしいままにし、大いに賄賂をむさぼり、一家の財産の額が敵国に数倍し、搾り取って収蔵した真珠の逸品だけでも2百串以上、皇室の収蔵品の数倍に達し、「且つ真珠の大玉は皇帝御用の冠の頂に使われたものより尚大き」く、各種の珍宝は数えきれず、捜査し没収された金銀は白銀換算で4百万両あった。この他にも家屋が1千間以上、土地1260ヘクタール以上、質屋20軒あった。その家族も数十万の財産を保有していた。和珅の不正や賄賂の収受により、国全体で不正がはびこり、ほとんど大吏で汚職をしない者は無く、その中には大がかりな案件も多々あり、このような事態は歴史上も稀であった。

和珅