◆自民党現職国会議員の「劣化」が、問題化してきた。これは、最近の国会議員が、いわゆる「帝王学」(為政者の心得=権力の学問=エリートの人間学)を学んでいないことに起因している。
為政者になろうとする者は古来、人民統治の法則を説く中国の四書五経(儒教の経書の中でとくに重要とされる四書と五経の総称。四書は「論語」「大学」「中庸」「孟子」、五経は「易経」「書経」「詩経」「礼記」「春秋」をいい、五経を以て四書よりも高しとする。「楽経」を含めて四書六経ともいう。君子が国家や政治に対する志を述べる大説として日常の出来事に関する意見・主張や噂話など虚構・空想の話を書く小説と区別される)を学んでいた。「修身斉家治国平天下」の完成を目指す。「帝王学」は、具体的には「原理原則を教えてもらう師をもつこと」「直言してくれる側近をもつこと」「よき幕賓をもつこと」を説く。
◆小沢一郎代表は、「帝王学」を心得ている。仁徳天皇の「カマドの煙」⇒「国民の生活が第1」=「生活の党」に活かされており、小沢一郎元代表が、「国民生活第一」を政治信条の中核に据えているのは、決して単なる思いつきからではない。「総理大臣小沢一郎」(板垣英憲著、サンガ刊)は、「第二章 新しい『絆』を構築し、『結』を蘇生させる」の「仁徳天皇の『民のかまど』のエピソード」の節で、以下のように記述している。
「仁徳天皇の『民のかまど』のエピソード=田中角栄直系が中心を占めるようになった民主党が、ここで決定的な経済・景気政策を打ち出すことができれば、政権奪取の足がかりをつかむ可能性は十分にある。小沢一郎の言う『絶対生活感』が、小泉元首相-安倍前首相の構造改革路線を打ち負かすときが迫っている。かつて、三木武夫元首相が『政治は生活の謂いである』と喝破していた。三木が衆議院議員に立侯補したときから演説でよく口にしていた名言である。このフレーズを踏襲してきたのが、小沢一郎であった。著書『小沢主義(オザワイズム)』(集英社インターナショナル刊)のなかで、小沢一郎は、『民のかまど』(第二章)と題して、『日本書記』に登場する仁徳天皇のエピソードを紹介している。
『ある日、仁徳天皇が皇居の高殿に登って四方を眺めると、人々の家からは少しも煙が立ち上がっていないことに気づいた。天皇は《これはきっと、かまどで煮炊きできないほど国民が生活に困っているからに違いない》と考えて、それから三年の間、租税を免除することにした。税を免除したために朝廷の収入はなくなり、そのために皇居の大殿はぼろぼろになり、あちこちから雨漏りがするほどになった。しかし、その甲斐あって、三年の後には国中の家から煮炊きの煙が上るようになった。このときに詠んだとされるのが、
高き屋に のぼりて見れば 煙立つ 民のかまどは にぎはひにけり
という歌である。こうして高殿の上から、あちこちの家のかまどから煙が立っているようすを確認した天皇は皇后にこう語った。
《私は豊かになった。もう心配ないよ》
それを聞いた皇后が、
《皇居がこのように朽ち果て、修理する費用もないというのに、なぜ豊かとおっしゃるのでしょうか。今お聞きしたら、あと三年、さらに無税になさるというお話ではないですか》
と聞き返すと、
《天皇の位は、そもそも人々のために作られたもの。だから、人々が貧しいということはすなわち私が貧しいということであり、人々が豊かであるということはすなわち私が豊かになったということなのだ》と仁徳天皇は答えた』
小沢は、続いて『政治とは生活である』と題し、次のようにまとめている。
『《天皇とは、そもそも人々のために立てられたもの》この仁徳天皇の言葉こそ、僕は政治の本質が隠されていると思う』
まさにこの通りである。この感覚こそ、政治の『本質』あるいは『要諦』であろう。政治の最高目的は、『経世済民』にあると言われる。小沢が『絶対生活感』を持ち、その感覚に基づいて政治を行っていると評価される所以である」
為政者は、「徳政」を行ってこそ、「君子」と言える。神の声=民の声をよく聞くことができる君子(為政者)を聖人という。
君子=君(会意)「尹+口」尹は神杖をもつ聖職者。口は、祝詞を収める器。巫祝(ふしゅく=みこ。はふり。かんなぎ)の長をいう字。
聖人=聖(会意)「耳+口+壬」。壬(人の挺立する形)の上に耳をそえた形に作り、神の声を聞きうる人をいう。口は祝祷を収める器の形で、その神の声を聞きうる人を聖という。英国では、立派な人物のことを「紳士(ジェントルマン)」という。
◆為政者に示された「先憂後楽」(常に民に先立って国のことを心配し、民が楽しんだ後に自分が楽しむこと)は、北宋の忠臣・范仲淹(はんちゅうえん、989年~ 1052年、政治家、文人)が自著「岳陽楼記」のなかで為政者の心得を述べた言葉であり、転じて、先に苦労・苦難を体験した者は、後に安楽になれるということ。(中国は、小平「先に豊かになれる者から豊かになれ」。その後段に「落伍した者を助けよ」とあるのを忘れている)
東京都文京区の小石川後楽園「涵徳亭」の広間の床の間には、「先憂後楽」(平沼騏一郎書)の掛け軸が、掛けられている。
「涵徳亭」は、江戸時代前期・中期の儒学者である林鳳岡(はやし ほうこう、寛永21年12月14日=1645年1月11日)~享保17年6月1日=1732年7月22日)が名づけた。林鳳岡は、大学頭としてとくに元禄時代の将軍・徳川綱吉のもと江戸幕府の文治政治の推進に功績があったひとりである。父は林鵞峰。名は又四郎・春常・信篤。字は直民。号は鳳岡・整宇。
「民信なくば立たず」《「論語」顔淵から》社会は政治への信頼なくして成り立つものではない。孔子が、政治をおこなう上で大切なものとして軍備・食生活・民衆の信頼の三つを挙げ、中でも重要なのが信頼であると説いた。〔ちなみに、日刊ゲンダイは、7月3日から毎週金曜日に「小沢一郎 戦争法案を潰す秘策を話そう」(暴走が続く安倍政権。野党の無力で戦争法案は強行採決の勢いだが、小沢一郎の見方は違う。最後の大仕事に賭ける意気込みと戦略)を強力連載する〕
三木武夫元首相、小泉純一郎元首相らが、座右の銘としていた。坂田道太元文相は、西郷隆盛が書に認めていた「敬天愛人」を好んでいた。
小沢一郎代表の座右の銘は「百術は一誠に如(し)かず」(百もの権謀術数もたった一つの「誠意」には及ばない)。
小沢一郎代表が尊敬している西郷隆盛は、「南洲翁遺訓」のなかで、こう諌めている。
「三十四 作略は平日致さぬものぞ。作略を以てやりたる事は、其迹を見れば、善からざること判然にして、必したり之れ有るなり。唯戦に臨みて、作略無くばあるべからず。併し平日作略を用れば、戦に臨みて作略は出来ぬものぞ。孔明は平日作略を致さぬゆえ、あの通り奇計を行はれたるぞ。予嘗て東京を引きし時、弟へ向ひ、『是迄少しも作略をやりたる事有らぬゆえ、跡は聊か濁るまじ、夫れ丈けは見れ』と申せしとぞ」
(策略は普段は用いてはならない方が良い。策略をもって行なった事は、その結果を見れば良くない事がはっきりしていて、必ず判るものである。ただ戦争の場合だけは、策略が無ければいけない。しかし、かねて策略をやっていると、いざ戦いという事になった時、上手な策略は決して出来るものではない。諸葛孔明(古代中国の宰相)はかねて策略をしなかったから、いざという時、あのように思いもよらない策略を行うことが出来たのだ。自分はかつて東京を引揚げたとき、弟(従道)に向かって『自分はこれまで少しも、謀ごとを、やった事が無いので、ここを引揚げた後も、跡は少しも濁ることはあるまい。それだけはよく見ておけ』と言っておいたという事である)
◆なお、自民党はかつて、安岡正篤(やすおか まさひろ、陽明学者・思想家。1898年2月13日~1983年12月13日、大阪市中央区に生まれる。東京大学で上杉慎吉に師事、「東洋思想研究所」を設立、1931年には三井や住友などの財閥の出資により埼玉県に「日本農士学校」創設し、教化運動に乗り出した)や拓殖大学海外事情研究所の佐藤慎一郎の両先生らから教えを受けていた。
福田赳夫首相は日中平和友好条約締結に当たり、自民党内で反対論が湧き上がった際、
安岡正篤先生を首相官邸に招き、教えを乞うた。安岡正篤先生は、「王道と覇道」について説き、「王道を歩むよう」指南した。
佐藤慎一郎先生は、著書「佐藤慎一郎選集」のなかで、「王道と覇道」について、以下のように解説している。
王道と覇道(「皇」「帝」「王」の道を志向するものを「王道」と言い、「覇」者の道を志向するものを「覇道」と言う。「覇」とは「これ三月、載(はじ)めて覇を生ず」(書経・康浩)=三月の初めに、細い新月が出る。そしてその新月に、薄くほの白い月の全輪郭が浮かんで見える。そのほの白い部分を、覇という。
要するに、お月様は、自分自身で光り輝くだけの力をもっていない。太陽の力を借りて、はじめて光り輝くことができる。それなのに、あだかも、俺自身が光り輝いているんだぞと、ぶんぞり返っているのが覇である。しかも力による政治を行いながら、表看板だけは、素晴らしい王道楽土だとか、日満一徳一心だとか、大義名分を、ふりかざしている者を覇者という。「天に逆らう者は滅びる」
本日の「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」
週刊文春と週刊新潮が、そろって「安倍自民党」を叩き潰す論調、谷垣禎一幹事長は、どう出るか?
◆〔特別情報①〕
ついに週刊文春と週刊新潮が、そろって「安倍自民党」を叩き潰す論調を強めてきた。とくに駐日米大使館と密接な関係にある週刊文春が7月9日号で「自民党は死んだ」と引導を渡している。週刊新潮は7月9月号で「うぬぼれ『自民党』の構造欠陥」と例によって斜交いから批判して見限っている。「1強多弱」下では、野党が不甲斐ないので、自民党は、一体、どうやって起死回生を図るつもりなのか? 谷垣禎一幹事長は、どう出るか?
つづきはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
携帯電話からのアクセスはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
携帯電話から有料ブログへのご登録
「板垣英憲情報局」はメルマガ(有料)での配信もしております。
お申し込みはこちら↓

blogosでも配信しております。お申し込みはこちら↓
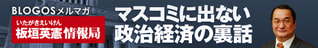
「まぐまぐ」からのご購読は下記からお申し込み頂けます。

板垣英憲マスコミ事務所からも配信しております。
お申し込みフォーム

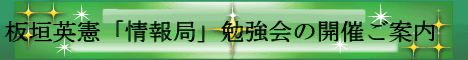
第43回 板垣英憲「情報局」勉強会のご案内
平成27年7月4日 (土)
「史上最古の天皇家と世界の王室」
~小沢一郎代表の日本国憲法改正試案と象徴天皇制
ヒカルランドパーク「板垣英憲 単独講演会 講師:板垣英憲 7/10」

◆新刊のご案内◆
**********板垣英憲『勉強会』の講演録DVD販売********
板垣英憲・講演録DVD 全国マスコミ研究会
 6月開催の勉強会がDVDになりました。
6月開催の勉強会がDVDになりました。
第42回 中国 「第3次世界大戦」と「400年戦争のない平和な時代」、二者択一の岐路に立つ ~日本列島を襲う「天変地異」の下、世界を救う指導者が登場する
(平成27年6月7日開催)
その他過去の勉強会もご用意しております。遠方でなかなか参加できない方など、ぜひご利用下さい。
板垣英憲・講演録DVD 全国マスコミ研究会
【板垣英憲(いたがきえいけん)ワールド著作集】
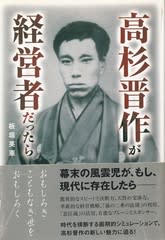
『高杉晋作が経営者だったら』(2008年3月25日刊)
目次
第四章もし晋作が起業家だったら
再生医療開発を進め難病治療に力を注ぐ
高杉晋作は明治維新を見ることなく、肺結核により夭折しています。
つづきはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)ワールド著作」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
携帯電話からのアクセスこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)ワールド著作」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
※ご購読期間中は、以下過去の掲載本全てがお読み頂けます。
『小泉・安倍 VS 菅・小沢 国盗り戦争』(2003年10月25日刊)
『スラスラ書ける作文・小論文』(1996年4月20日刊)
『目を覚ませ!財界人』(1995年9月25日刊)
『東京地検特捜部』鬼検事たちの秋霜烈日(1998年4月5日刊)
『誠』の経営学~『新撰組』の精神と行動の美学をビジネスに生かす
『忠臣蔵』が語る組織の勝つ成果Q&A
『風林火山』兵法に学ぶ経営学~人は石垣、人は城
『未来への挑戦「坂本龍馬」に学ぶ経営学』
『人生の達人~心に残る名言・遺訓・格言』(2000年6月11日刊)
『細川家の大陰謀~六百年かけた天下盗りの遺伝子』1994年1月5日刊(2000年6月11日刊)
『大富豪に学ぶ商売繁盛20の教訓―商機をつかむ知恵と決断』(2010年1月20日)
『内務省が復活する日』(1995年10月25日刊)
『情報流出のカラクリと管理術』(2003年3月10日刊)
『利権はこうしてつくられる』(1991年3月25日刊)
「『族』の研究~政・官・財を牛耳る政界実力者集団の群像」(1987年3月9日刊)
『愛する者へ遺した最期のことば』(1995年6月10日刊)
『自民党選挙の秘密』(1987年12月15日刊)
『小中学校の教科書が教えない 日の丸君が代の歴史』(1999年7月8日刊)
『大蔵・日銀と闇将軍~疑惑の全貌を暴く』(1995年5月26日刊)
『小泉純一郎 恐れず ひるまず とらわれず』(2001年6月15日刊 板垣英憲著)
『戦国自民党50年史-権力闘争史』(2005年12月刊 板垣英憲著)
『小沢一郎 七人の敵』(1996年2月6日)
『小沢一郎の時代』(1996年2月6日刊 同文書院刊)
『小沢一郎総理大臣』(2007年11月10日)
『小沢一郎総理大臣待望論』(1994年11月1日)
『ロックフェラーに翻弄される日本』(20074年11月20日)
『ブッシュの陰謀~対テロ戦争・知られざるシナリオ』2002年2月5日刊
『民主党派閥闘争史-民主党の行方』(2008年9月16日)
『民主党政変 政界大再編』(2010年5月6日)
『国際金融資本の罠に嵌った日本』(1999年6月25日刊)
『政治家の交渉術』2006年5月刊
『カルロス・ゴーンの言葉』(2006年11月刊)
「孫の二乗の法則~ソフトバンク孫正義の成功哲学」(2007年7月刊)
板垣英憲マスコミ事務所

為政者になろうとする者は古来、人民統治の法則を説く中国の四書五経(儒教の経書の中でとくに重要とされる四書と五経の総称。四書は「論語」「大学」「中庸」「孟子」、五経は「易経」「書経」「詩経」「礼記」「春秋」をいい、五経を以て四書よりも高しとする。「楽経」を含めて四書六経ともいう。君子が国家や政治に対する志を述べる大説として日常の出来事に関する意見・主張や噂話など虚構・空想の話を書く小説と区別される)を学んでいた。「修身斉家治国平天下」の完成を目指す。「帝王学」は、具体的には「原理原則を教えてもらう師をもつこと」「直言してくれる側近をもつこと」「よき幕賓をもつこと」を説く。
◆小沢一郎代表は、「帝王学」を心得ている。仁徳天皇の「カマドの煙」⇒「国民の生活が第1」=「生活の党」に活かされており、小沢一郎元代表が、「国民生活第一」を政治信条の中核に据えているのは、決して単なる思いつきからではない。「総理大臣小沢一郎」(板垣英憲著、サンガ刊)は、「第二章 新しい『絆』を構築し、『結』を蘇生させる」の「仁徳天皇の『民のかまど』のエピソード」の節で、以下のように記述している。
「仁徳天皇の『民のかまど』のエピソード=田中角栄直系が中心を占めるようになった民主党が、ここで決定的な経済・景気政策を打ち出すことができれば、政権奪取の足がかりをつかむ可能性は十分にある。小沢一郎の言う『絶対生活感』が、小泉元首相-安倍前首相の構造改革路線を打ち負かすときが迫っている。かつて、三木武夫元首相が『政治は生活の謂いである』と喝破していた。三木が衆議院議員に立侯補したときから演説でよく口にしていた名言である。このフレーズを踏襲してきたのが、小沢一郎であった。著書『小沢主義(オザワイズム)』(集英社インターナショナル刊)のなかで、小沢一郎は、『民のかまど』(第二章)と題して、『日本書記』に登場する仁徳天皇のエピソードを紹介している。
『ある日、仁徳天皇が皇居の高殿に登って四方を眺めると、人々の家からは少しも煙が立ち上がっていないことに気づいた。天皇は《これはきっと、かまどで煮炊きできないほど国民が生活に困っているからに違いない》と考えて、それから三年の間、租税を免除することにした。税を免除したために朝廷の収入はなくなり、そのために皇居の大殿はぼろぼろになり、あちこちから雨漏りがするほどになった。しかし、その甲斐あって、三年の後には国中の家から煮炊きの煙が上るようになった。このときに詠んだとされるのが、
高き屋に のぼりて見れば 煙立つ 民のかまどは にぎはひにけり
という歌である。こうして高殿の上から、あちこちの家のかまどから煙が立っているようすを確認した天皇は皇后にこう語った。
《私は豊かになった。もう心配ないよ》
それを聞いた皇后が、
《皇居がこのように朽ち果て、修理する費用もないというのに、なぜ豊かとおっしゃるのでしょうか。今お聞きしたら、あと三年、さらに無税になさるというお話ではないですか》
と聞き返すと、
《天皇の位は、そもそも人々のために作られたもの。だから、人々が貧しいということはすなわち私が貧しいということであり、人々が豊かであるということはすなわち私が豊かになったということなのだ》と仁徳天皇は答えた』
小沢は、続いて『政治とは生活である』と題し、次のようにまとめている。
『《天皇とは、そもそも人々のために立てられたもの》この仁徳天皇の言葉こそ、僕は政治の本質が隠されていると思う』
まさにこの通りである。この感覚こそ、政治の『本質』あるいは『要諦』であろう。政治の最高目的は、『経世済民』にあると言われる。小沢が『絶対生活感』を持ち、その感覚に基づいて政治を行っていると評価される所以である」
為政者は、「徳政」を行ってこそ、「君子」と言える。神の声=民の声をよく聞くことができる君子(為政者)を聖人という。
君子=君(会意)「尹+口」尹は神杖をもつ聖職者。口は、祝詞を収める器。巫祝(ふしゅく=みこ。はふり。かんなぎ)の長をいう字。
聖人=聖(会意)「耳+口+壬」。壬(人の挺立する形)の上に耳をそえた形に作り、神の声を聞きうる人をいう。口は祝祷を収める器の形で、その神の声を聞きうる人を聖という。英国では、立派な人物のことを「紳士(ジェントルマン)」という。
◆為政者に示された「先憂後楽」(常に民に先立って国のことを心配し、民が楽しんだ後に自分が楽しむこと)は、北宋の忠臣・范仲淹(はんちゅうえん、989年~ 1052年、政治家、文人)が自著「岳陽楼記」のなかで為政者の心得を述べた言葉であり、転じて、先に苦労・苦難を体験した者は、後に安楽になれるということ。(中国は、小平「先に豊かになれる者から豊かになれ」。その後段に「落伍した者を助けよ」とあるのを忘れている)
東京都文京区の小石川後楽園「涵徳亭」の広間の床の間には、「先憂後楽」(平沼騏一郎書)の掛け軸が、掛けられている。
「涵徳亭」は、江戸時代前期・中期の儒学者である林鳳岡(はやし ほうこう、寛永21年12月14日=1645年1月11日)~享保17年6月1日=1732年7月22日)が名づけた。林鳳岡は、大学頭としてとくに元禄時代の将軍・徳川綱吉のもと江戸幕府の文治政治の推進に功績があったひとりである。父は林鵞峰。名は又四郎・春常・信篤。字は直民。号は鳳岡・整宇。
「民信なくば立たず」《「論語」顔淵から》社会は政治への信頼なくして成り立つものではない。孔子が、政治をおこなう上で大切なものとして軍備・食生活・民衆の信頼の三つを挙げ、中でも重要なのが信頼であると説いた。〔ちなみに、日刊ゲンダイは、7月3日から毎週金曜日に「小沢一郎 戦争法案を潰す秘策を話そう」(暴走が続く安倍政権。野党の無力で戦争法案は強行採決の勢いだが、小沢一郎の見方は違う。最後の大仕事に賭ける意気込みと戦略)を強力連載する〕
三木武夫元首相、小泉純一郎元首相らが、座右の銘としていた。坂田道太元文相は、西郷隆盛が書に認めていた「敬天愛人」を好んでいた。
小沢一郎代表の座右の銘は「百術は一誠に如(し)かず」(百もの権謀術数もたった一つの「誠意」には及ばない)。
小沢一郎代表が尊敬している西郷隆盛は、「南洲翁遺訓」のなかで、こう諌めている。
「三十四 作略は平日致さぬものぞ。作略を以てやりたる事は、其迹を見れば、善からざること判然にして、必したり之れ有るなり。唯戦に臨みて、作略無くばあるべからず。併し平日作略を用れば、戦に臨みて作略は出来ぬものぞ。孔明は平日作略を致さぬゆえ、あの通り奇計を行はれたるぞ。予嘗て東京を引きし時、弟へ向ひ、『是迄少しも作略をやりたる事有らぬゆえ、跡は聊か濁るまじ、夫れ丈けは見れ』と申せしとぞ」
(策略は普段は用いてはならない方が良い。策略をもって行なった事は、その結果を見れば良くない事がはっきりしていて、必ず判るものである。ただ戦争の場合だけは、策略が無ければいけない。しかし、かねて策略をやっていると、いざ戦いという事になった時、上手な策略は決して出来るものではない。諸葛孔明(古代中国の宰相)はかねて策略をしなかったから、いざという時、あのように思いもよらない策略を行うことが出来たのだ。自分はかつて東京を引揚げたとき、弟(従道)に向かって『自分はこれまで少しも、謀ごとを、やった事が無いので、ここを引揚げた後も、跡は少しも濁ることはあるまい。それだけはよく見ておけ』と言っておいたという事である)
◆なお、自民党はかつて、安岡正篤(やすおか まさひろ、陽明学者・思想家。1898年2月13日~1983年12月13日、大阪市中央区に生まれる。東京大学で上杉慎吉に師事、「東洋思想研究所」を設立、1931年には三井や住友などの財閥の出資により埼玉県に「日本農士学校」創設し、教化運動に乗り出した)や拓殖大学海外事情研究所の佐藤慎一郎の両先生らから教えを受けていた。
福田赳夫首相は日中平和友好条約締結に当たり、自民党内で反対論が湧き上がった際、
安岡正篤先生を首相官邸に招き、教えを乞うた。安岡正篤先生は、「王道と覇道」について説き、「王道を歩むよう」指南した。
佐藤慎一郎先生は、著書「佐藤慎一郎選集」のなかで、「王道と覇道」について、以下のように解説している。
王道と覇道(「皇」「帝」「王」の道を志向するものを「王道」と言い、「覇」者の道を志向するものを「覇道」と言う。「覇」とは「これ三月、載(はじ)めて覇を生ず」(書経・康浩)=三月の初めに、細い新月が出る。そしてその新月に、薄くほの白い月の全輪郭が浮かんで見える。そのほの白い部分を、覇という。
要するに、お月様は、自分自身で光り輝くだけの力をもっていない。太陽の力を借りて、はじめて光り輝くことができる。それなのに、あだかも、俺自身が光り輝いているんだぞと、ぶんぞり返っているのが覇である。しかも力による政治を行いながら、表看板だけは、素晴らしい王道楽土だとか、日満一徳一心だとか、大義名分を、ふりかざしている者を覇者という。「天に逆らう者は滅びる」
本日の「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」
週刊文春と週刊新潮が、そろって「安倍自民党」を叩き潰す論調、谷垣禎一幹事長は、どう出るか?
◆〔特別情報①〕
ついに週刊文春と週刊新潮が、そろって「安倍自民党」を叩き潰す論調を強めてきた。とくに駐日米大使館と密接な関係にある週刊文春が7月9日号で「自民党は死んだ」と引導を渡している。週刊新潮は7月9月号で「うぬぼれ『自民党』の構造欠陥」と例によって斜交いから批判して見限っている。「1強多弱」下では、野党が不甲斐ないので、自民党は、一体、どうやって起死回生を図るつもりなのか? 谷垣禎一幹事長は、どう出るか?
つづきはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
携帯電話からのアクセスはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
携帯電話から有料ブログへのご登録
「板垣英憲情報局」はメルマガ(有料)での配信もしております。
お申し込みはこちら↓

blogosでも配信しております。お申し込みはこちら↓
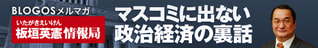
「まぐまぐ」からのご購読は下記からお申し込み頂けます。

板垣英憲マスコミ事務所からも配信しております。
お申し込みフォーム
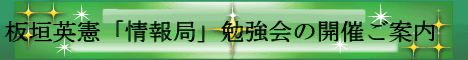
第43回 板垣英憲「情報局」勉強会のご案内
平成27年7月4日 (土)
「史上最古の天皇家と世界の王室」
~小沢一郎代表の日本国憲法改正試案と象徴天皇制
ヒカルランドパーク「板垣英憲 単独講演会 講師:板垣英憲 7/10」

◆新刊のご案内◆
 | 2度目の55年体制の衝撃! あのジャパンハンドラーズが「小沢一郎総理大臣誕生」を自民党に対日要求! 日本国の《新生となるか、終焉となるか》ついに来た《存亡大選択の時》 (超☆はらはら) |
| クリエーター情報なし | |
| ヒカルランド |
 | ゴールドマン?ファミリーズ?グループが認める唯一の承認者(フラッグシップ) 吉備太秦(きびのうずまさ)が語る「世界を動かす本当の金融のしくみ」 地球経済は36桁の天文学的数字《日本の金銀財宝》を担保に回っていた |
| 板垣 英憲 | |
| ヒカルランド |
 | 地球連邦政府樹立へのカウントダウン! 縄文八咫烏(じょうもんやたがらす)直系! 吉備太秦(きびのうずまさ)と世界のロイヤルファミリーはこう動く 人類9割が死滅! 第三次世界大戦は阻止できるか?! (超☆はらはら) |
| 板垣 英憲 | |
| ヒカルランド |
 | 中国4分割と韓国消滅 ロスチャイルドによる衝撃の地球大改造プラン 金塊大国日本が《NEW大東亜共栄圏》の核になる (超☆はらはら) |
| 板垣 英憲 | |
| ヒカルランド |
 | NEW司令系統で読み解くこの国のゆくえ ロスチャイルドの世界覇権奪還で日本のはこうなる(超☆はらはら) |
| 板垣 英憲 | |
| ヒカルランド |
**********板垣英憲『勉強会』の講演録DVD販売********
板垣英憲・講演録DVD 全国マスコミ研究会
 6月開催の勉強会がDVDになりました。
6月開催の勉強会がDVDになりました。第42回 中国 「第3次世界大戦」と「400年戦争のない平和な時代」、二者択一の岐路に立つ ~日本列島を襲う「天変地異」の下、世界を救う指導者が登場する
(平成27年6月7日開催)
その他過去の勉強会もご用意しております。遠方でなかなか参加できない方など、ぜひご利用下さい。
板垣英憲・講演録DVD 全国マスコミ研究会
【板垣英憲(いたがきえいけん)ワールド著作集】
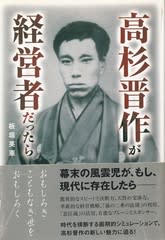
『高杉晋作が経営者だったら』(2008年3月25日刊)
目次
第四章もし晋作が起業家だったら
再生医療開発を進め難病治療に力を注ぐ
高杉晋作は明治維新を見ることなく、肺結核により夭折しています。
つづきはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)ワールド著作」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
携帯電話からのアクセスこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)ワールド著作」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
※ご購読期間中は、以下過去の掲載本全てがお読み頂けます。
『小泉・安倍 VS 菅・小沢 国盗り戦争』(2003年10月25日刊)
『スラスラ書ける作文・小論文』(1996年4月20日刊)
『目を覚ませ!財界人』(1995年9月25日刊)
『東京地検特捜部』鬼検事たちの秋霜烈日(1998年4月5日刊)
『誠』の経営学~『新撰組』の精神と行動の美学をビジネスに生かす
『忠臣蔵』が語る組織の勝つ成果Q&A
『風林火山』兵法に学ぶ経営学~人は石垣、人は城
『未来への挑戦「坂本龍馬」に学ぶ経営学』
『人生の達人~心に残る名言・遺訓・格言』(2000年6月11日刊)
『細川家の大陰謀~六百年かけた天下盗りの遺伝子』1994年1月5日刊(2000年6月11日刊)
『大富豪に学ぶ商売繁盛20の教訓―商機をつかむ知恵と決断』(2010年1月20日)
『内務省が復活する日』(1995年10月25日刊)
『情報流出のカラクリと管理術』(2003年3月10日刊)
『利権はこうしてつくられる』(1991年3月25日刊)
「『族』の研究~政・官・財を牛耳る政界実力者集団の群像」(1987年3月9日刊)
『愛する者へ遺した最期のことば』(1995年6月10日刊)
『自民党選挙の秘密』(1987年12月15日刊)
『小中学校の教科書が教えない 日の丸君が代の歴史』(1999年7月8日刊)
『大蔵・日銀と闇将軍~疑惑の全貌を暴く』(1995年5月26日刊)
『小泉純一郎 恐れず ひるまず とらわれず』(2001年6月15日刊 板垣英憲著)
『戦国自民党50年史-権力闘争史』(2005年12月刊 板垣英憲著)
『小沢一郎 七人の敵』(1996年2月6日)
『小沢一郎の時代』(1996年2月6日刊 同文書院刊)
『小沢一郎総理大臣』(2007年11月10日)
『小沢一郎総理大臣待望論』(1994年11月1日)
『ロックフェラーに翻弄される日本』(20074年11月20日)
『ブッシュの陰謀~対テロ戦争・知られざるシナリオ』2002年2月5日刊
『民主党派閥闘争史-民主党の行方』(2008年9月16日)
『民主党政変 政界大再編』(2010年5月6日)
『国際金融資本の罠に嵌った日本』(1999年6月25日刊)
『政治家の交渉術』2006年5月刊
『カルロス・ゴーンの言葉』(2006年11月刊)
「孫の二乗の法則~ソフトバンク孫正義の成功哲学」(2007年7月刊)
板垣英憲マスコミ事務所



















