しゃっくり(吃逆)はなぜおこるのでしょう。吸気運動(横隔膜収縮)と吸気停止(声門閉鎖)
は、なぜ同時発生しなければならないのでしょう。
実は興味深いことに、それは鰓呼吸ながら肺を持ち始め、しかもなお鰓呼吸を守ろうとしたオタマジャクシの呼吸様式の再演なのです(ヒトの胎児でも、羊水に浸かりながら、胎生8週頃から吃逆は見られます)。水中で肺呼吸の運動=横隔膜の収縮がうっかり始まってしまったとき、肺に水が入るのを阻止するために、声門をただちに閉じること・・・ヒックヒックと咽喉では喘ぎながら、横隔膜は痙攣のようにさかんに収縮するのは、まさにその現われです。
だとすれば、声帯とはそもそも、発声以前にまず、気道閉鎖の役割を担って登場した一種の防衛器官だったのではないかと考えられます。しかもそれは当初は、厳重に組み上げられた喉頭蓋・仮声帯・声帯の堅牢な3段階構造の1つでした。
それをあえてまた、発声器官として華々しく開花させた哺乳類、なかでもヒトの創造力には、あらためて舌を巻かずにいられません。
しかしさらに驚くべきことには、この防衛反応は、個体発生的にみればこのようにオタマジャクシが典型ですが、もっと前身の肺魚は成体でこれを年周的に行ない(乾季は眠りながら肺呼吸、雨季は水中で鰓呼吸)、さらには三木成夫がくり返し強調するように、“上陸革命”のその頃、ヴァリスカン造山運動の猛烈な大地殻変動に曝された他の多くの脊椎動物も、海に戻るか陸に上がるか逡巡しながら、次第に肺を備え、ある時は鰓で呼吸し、ある時は肺で呼吸し、長い間浜辺で迷い暮らした数千万年の歴史があったのでした。最古の両生類、鰓も肺も持つアカントステガ
(Acanthostega)は、水中で鰓呼吸し、時に水面から上体を持ち上げて肺呼吸を行なっていました。系統発生的にみるなら、しゃっくりは、まさにこの“上陸革命”という一大革命前夜のクライマックスの再演でもあるのです。











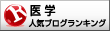


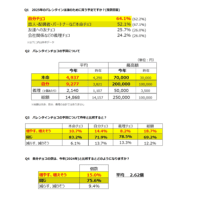
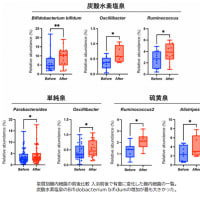


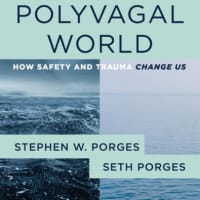
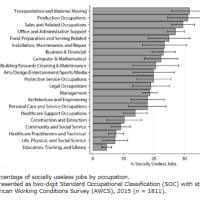
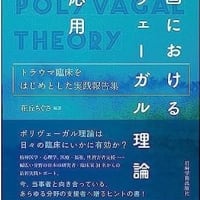
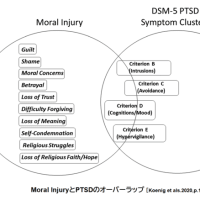
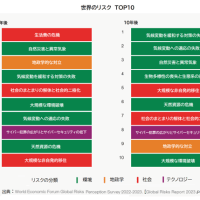






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます