






































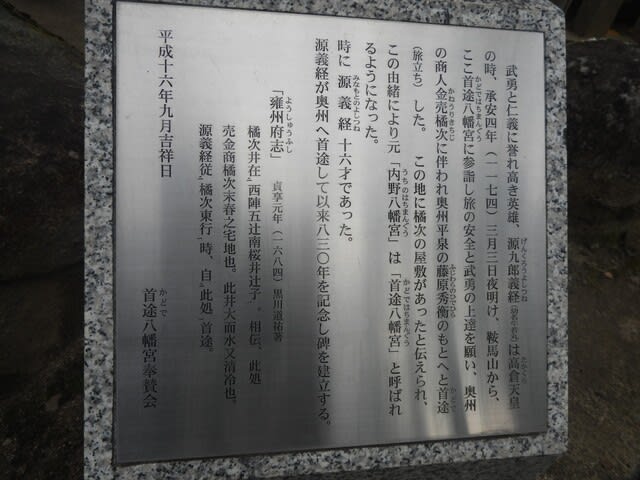







今週も一週間が始まりました。
年末ですが、まだまだ仕事が続きます。
なんと30日の月曜日も仕事があり、31日の大晦日から年末の休みに入ります。
今週は頑張って出勤しようと思いますが、孫が冬休みで泊りに来ることもあって、途中に有給休暇をとったりしているので、お休みも多いです。


この間、毎日のように散歩コースでマガモを見かけます。
マガモは留鳥なんですが、この場所には冬にしかやってきません。
夏の時期は、別の場所にいるんでしょうね。
なぜか、冬になるとやってきます。

マガモは夏場は頭の部分が青くなっていなくて、冬場になると青くなるそうです。
きれいな色をしているのが、オスでメスは茶色なんですね。


空気が澄んでいるせいなのか、きれいな色に写っています。
川の色とマッチして、良い感じに写っていました。


オスとメスとで、仲良く魚を探しているみたいです。
朝に見かけて、夕方の散歩でも同じ場所にいました。
一日中、この場所で餌を探しているんですね。

きっと魚たちも、つかまっては大変と逃げているでしょうね。
カモの世界もなかなか大変なんですね。。。
一日遅くなりましたが、昨日は「冬至」でしたね。
いよいよ、折り返し地点かと思いますが、これからが本格的な冬の時期がやってくるんですね。


昨日は、冬至のことを書かないといけないと思っていたのですが、今年唯一の「忘年会」があり、家に帰るのが遅くなりました。
久しぶりに、昔の職場の方とお話をして、長い話をしていました。
頑張ってきた時代のことが思い出されて、懐かしく思いました。
いろいろなことがありました。
そんな余韻に浸っていると、今朝は今年初めてのツグミを見つけました。


とうとうやってきてくれました。
冬鳥なので、もうそろそろ見かけてもいい頃なのに、なかなかやって来ないのでどうしたんだろうと思っていました。
昨年も12月に初めて見つけたので、あまり変わらないのかもしれませんが、今年は暑い時期が長かったので、紅葉も遅くなり、冬鳥も遅いのかと心配していました。

この茶色に黒い模様は間違いなくツグミでした。
先日から、イカルは何度か見かけています。


この黄色いくちばしがトレードマークですね。


きれいだった木々の葉がすべて散ってしまったので、鳥が見えやすくなりました。
冬は野鳥観察には最適のシーズンです。
先日から見かけていたジョウビタキ君も枝の上から地面に降りてくるようになりました。



かなり人にも慣れてきたのかもしれません。
私が近づいても、すぐには逃げなくなりました。


このオレンジ色がトレードマークです。。。
きれいなので、我が家では人気者です。
寒い季節に入りますが、野鳥撮影にも出かけたいところです。
昨日と今日は、気温が低くなり、本格的な冬が近いと感じました。
仕事に行く時には、シャツの下にもう一枚シャツを着て、貼り付けるカイロをシャツに貼って、腰を温めるようにしました。
ズボンも二枚はいて、足が冷えないように気を付けました。
これくらい対策をしていれば、寒くありません。
むしろ体を動かしていたら、ホカホカしてきました。
冬場は、対策ができるので、まだまだ工夫の余地がありそうです。
さて、もう先週の日曜日になりますが、史跡ウオークで嵯峨嵐山を歩きました。
最後に到着したのが、観光地として有名な嵐山の渡月橋です。

渡月橋の近くは、人が多かったのですが、さすがに紅葉のピークは過ぎたようで、人通りも少なくなっていました。
この手前の川は、亀岡方面から流れてくる川で、「保津川下り」で有名です。
しかし、この渡月橋の近くになると、保津川から名前が変わり「大堰川(おおいがわ)」となります。
渡月橋を過ぎると、次は桂川となるという不思議な川です。
この川は、昔はもっと狭く船が通りにくかったようなのですが、江戸時代の初期の豪商、角倉了以さんが掘削して船が通れるようにしたそうです。
角倉了以さんは、他にも高瀬川など、多くの河川の改良をしたそうで、水運の父とも呼ばれています。


大堰川が見下ろせる高台に、角倉了以さんの銅像が建てられています。
三条大橋の高山彦九郎、円山公園の坂本龍馬・中岡慎太郎とともに、京都の三大銅像にも数えられていますね。

開発にかかる巨額の費用はすべて自費で賄ったそうですが、その後の水運業の船賃などにより、すべて回収できたそうです。
すごい人なんですね。


そんな歴史を知ってか知らずか、ヒドリガモがのんびりと泳いでいました。
そんなこと、知るわけないですね。


川面が太陽の光でピカピカ輝いて、きれいでした。
気持ちの良い、日曜日のお昼でした。

渡月橋にはいかずに、そのまま家に帰りました。。。
嵯峨嵐山編・・・おわり・・・