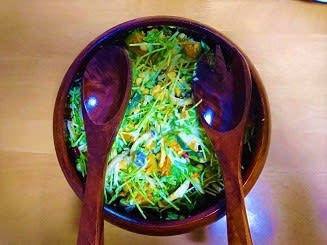カフカ著『禿鷹』には、ボルヘスによる序文と、「禿鷹」「断食芸人」「最初の悩み」「雑種」「町の紋章」「プロメテウス」「よくある混乱」「ジャッカルとアラビア人」「十一人の息子」「ある学会報告」「万里の長城」の11編が収録されている。
本書はボルヘス編集の“バベルの図書館”の4巻目にあたる。私にとっては27冊目の“バベルの図書館”の作品だ。
カフカは『変身』と『城』くらいしかまともに読んだことがないと思う。
訳者の池内紀氏が、付録の「ふたたび、野心家カフカ」で、“もつれにもつれた糸をほどいて、また一段ともつれさせるたぐいのカフカ解釈はもう沢山だ”と述べている。
私はこれまでカフカの作品そのものより、この手の解釈論争が苦手でカフカから距離を置いてきた。「ふたたび、野心家カフカ」で例に挙げられている研究者たちの「雑種」の解釈なんかまさにそうで、言い方は悪いが個人的な感想の域を出ていないと思うのだ。カフカの作品からその人たちに都合の良いパーツを摘まんで、見たいようなカフカ像を組み立てているだけではないか。カフカの作品は心理描写が削ぎ落とされている分、読み手の願望を差し挿める隙間が多いのだろう。深読みしようと思えば、無限に深読み出来るのだ。その深読み合戦は、外野から見ていると大変疲れる。
池内氏は、マックス・ブロートが作り出そうとしたカフカ像に疑問符を投げかけている。
ブロートが世間一般に見せたがっているカフカ像〈孤独に書いて、ひっそりと死んでいった聖なる人物。死後に始まった名声に誰よりも驚いているカフカ〉は、私の好みではないので、池内氏のいう〈野心家カフカ〉に与したくなる。が、カフカ本人がそのあたりについて明言していない以上は、私もまた、見たいようにカフカを見ているだけなのだ。
カフカが死の床で友人ブロートに作品一切の焼却を依頼した、というエピソードはあまりにも有名だが、その事実から何を読み取るかも人それぞれだ。
ボルヘスは序文の冒頭で、ウェルギリウスが臨終の際に友人たちに『アエネーイス』の未完の草稿を焼却してくれるよう頼んだという逸話を挙げ、“ウェルギリウスが友人たちの情け深い不服従を、カフカがブロートのそれを、当てにしていることを自覚していなかったはずがない”と、述べている。つまりは、カフカが自作の破棄を本気で望んでいた訳ではないということだ。ボルヘスの考えるカフカ像は、どちらかといえば池内氏寄りのようだ。
真実のカフカ像とか、原稿焼却依頼の本当の意図とかは、永遠に正解の出ない謎なので、この辺で話を変える。
ボルヘスは、カフカの作品は、「服従」と「無限」という二つの強迫観念に支配されているという。
カフカの作品の殆どすべてに位階制というものがあり、それらは無限に続いている。位階制への服従に基づき、目的への到達・達成は無限に遅延される。ボルヘスは、本書収録の「万里の長城」について、“無限は幾重にも輻輳していて、無限に遠い辺境の軍の行路を阻むために、時間的にも空間的にも遠い存在である皇帝が、無限に続く世代に対して、彼の無限に広大な帝国を囲み込む無限の城砦を無限に積み上げるよう命じるのである”と述べている。茫洋と掴みどころのない、感想を纏め難い作風だ。
無限に遠ざかっていく結果に対して、原因の扱いはどうだろう。
カフカの作品の殆どが、登場人物が尋常でない状況に置かれているところから始まるが、何でそんな事になったのかの明確な説明はされない。入り口も出口も曖昧な迷宮、それがカフカの世界だ。
ボルヘスは、“(カフカの作品において)肝心なのはプロットと環境であり、寓話の展開でも心理的洞察でもない。だからこそ彼の短編物語のほうが彼の小説よりも優れているのであり、だからこそこの短編選集はかくも特異な作家のスケールを十全に示していると断言する正当性がある”と結論付けている。
「禿鷹」は、語り手が生きながら禿鷹に肉体を抉られ続けている場面から始まる。
通りかかった紳士に、なぜ我慢しているのかと問われば、語り手は、「仕方がないではありませんか」と答える。最期に、禿鷹の嘴に喉を深く抉られた語り手は、どっと血を吹き出しながら仰向けに倒れる。溢れる血の中で禿鷹が溺れていく。
“それをみて私はほっと安堵した。”
現実とは、悪夢を絶えず提供し続けるものだと考えているカフカには、語り手が救済される姿を描くことができない。彼の誠実さが、この結末以外を許なかったのだろう。
「断食芸人」は、かつてはヨーロッパ中で人気を博した断食芸人の話。
断食などという芸の無い芸が大当たりする社会って、どんなのなのと思う。檻に閉じ込められた状態で、40日間断食する。それだけである。何がウケたのかはよく分からないが、時勢は変わり、断食芸人の檻の前に人々が群がっていた日々は遠い昔の話になった。
年老い、落ちぶれた断食芸人は、サーカスの動物小屋の隅に檻を置いてもらうことになる。断食芸人の檻は、動物を見に来た客達の移動の邪魔にしかならない。しかし、誰も見る者の無い中、断食芸人は全力を尽くして断食を続け、この上なく見事にやってのけた。そこに何の意味があったのだろう。サーカスの監督の問いに、断食芸人はこう答えた。
“断食せずにいられなかっただけのこと。ほかに仕様がなかったもんでね”
“自分にあった食べものを見つけることができなかった。もし見つけていれば、こんな見世物をすることもなく、みなさん方と同じように、たらふく食べていたでしょうね”
断食芸人が息絶えると、彼の亡骸は速やかに藁くずと一緒に葬られた。
断食芸人の入っていた檻には、一匹の精悍な豹が入れられた。生きのいい豹の姿は多くの見物客を引き寄せ、檻は本来の使われ方を取り戻したのだった。
「町の紋章」は、無限に遅延し続けるバベルの塔の建設の話。
僅か2ページの掌編の中に、人類の駄目なところが粗方詰め込まれていて憂鬱になる。
この手の遅延は現実社会にもよくあることなのだが、人類が人類である限り、それが改善されることはないのだろう。
人類がバベルの塔の完成を見る日は、多分永遠に来ない。だからと言って、人々が何かアクションを起こす気配はない。届かない、伝わらない、辿り着けない、完成しない、そして、そのことについて、何も説明しない、何も起こらないのが、カフカの作風なのだ。カフカの作品においては、障害はプロットを作るためのものではなく、障害そのものが作品の本質なので、障害から何かが起きるはずもないのである。
が、この町に生まれた伝説や唄は、どれといわず、予言に語られる日を待ち焦がれている。それは、巨大な拳が現れて町を打ち、木っ端みじんにしてしまうという予言だ。そんな訳で、この町の紋章には一つの握り拳が描かれているのだ。
「プロメテウス」は、プロメテウスに纏わる四つの言い伝えについて。
“言い伝えは不可解なものを解きあかそうとつとめるだろう。だが、真理をおびて始まるものは、しょせんは不可解なものとして終わらなくてはならないのだ。”
これからカフカを読もうという人は、この「プロメテウス」を始めに読むべきなのだろう。そして、カフカを何度も読んでいる人も、折に触れて「プロメテウス」を思い出すべきなのだろう。カフカに関するこんがらがった解釈なんて、神々も鷲もきっと飽き飽きしていることだろうから。
本書はボルヘス編集の“バベルの図書館”の4巻目にあたる。私にとっては27冊目の“バベルの図書館”の作品だ。
カフカは『変身』と『城』くらいしかまともに読んだことがないと思う。
訳者の池内紀氏が、付録の「ふたたび、野心家カフカ」で、“もつれにもつれた糸をほどいて、また一段ともつれさせるたぐいのカフカ解釈はもう沢山だ”と述べている。
私はこれまでカフカの作品そのものより、この手の解釈論争が苦手でカフカから距離を置いてきた。「ふたたび、野心家カフカ」で例に挙げられている研究者たちの「雑種」の解釈なんかまさにそうで、言い方は悪いが個人的な感想の域を出ていないと思うのだ。カフカの作品からその人たちに都合の良いパーツを摘まんで、見たいようなカフカ像を組み立てているだけではないか。カフカの作品は心理描写が削ぎ落とされている分、読み手の願望を差し挿める隙間が多いのだろう。深読みしようと思えば、無限に深読み出来るのだ。その深読み合戦は、外野から見ていると大変疲れる。
池内氏は、マックス・ブロートが作り出そうとしたカフカ像に疑問符を投げかけている。
ブロートが世間一般に見せたがっているカフカ像〈孤独に書いて、ひっそりと死んでいった聖なる人物。死後に始まった名声に誰よりも驚いているカフカ〉は、私の好みではないので、池内氏のいう〈野心家カフカ〉に与したくなる。が、カフカ本人がそのあたりについて明言していない以上は、私もまた、見たいようにカフカを見ているだけなのだ。
カフカが死の床で友人ブロートに作品一切の焼却を依頼した、というエピソードはあまりにも有名だが、その事実から何を読み取るかも人それぞれだ。
ボルヘスは序文の冒頭で、ウェルギリウスが臨終の際に友人たちに『アエネーイス』の未完の草稿を焼却してくれるよう頼んだという逸話を挙げ、“ウェルギリウスが友人たちの情け深い不服従を、カフカがブロートのそれを、当てにしていることを自覚していなかったはずがない”と、述べている。つまりは、カフカが自作の破棄を本気で望んでいた訳ではないということだ。ボルヘスの考えるカフカ像は、どちらかといえば池内氏寄りのようだ。
真実のカフカ像とか、原稿焼却依頼の本当の意図とかは、永遠に正解の出ない謎なので、この辺で話を変える。
ボルヘスは、カフカの作品は、「服従」と「無限」という二つの強迫観念に支配されているという。
カフカの作品の殆どすべてに位階制というものがあり、それらは無限に続いている。位階制への服従に基づき、目的への到達・達成は無限に遅延される。ボルヘスは、本書収録の「万里の長城」について、“無限は幾重にも輻輳していて、無限に遠い辺境の軍の行路を阻むために、時間的にも空間的にも遠い存在である皇帝が、無限に続く世代に対して、彼の無限に広大な帝国を囲み込む無限の城砦を無限に積み上げるよう命じるのである”と述べている。茫洋と掴みどころのない、感想を纏め難い作風だ。
無限に遠ざかっていく結果に対して、原因の扱いはどうだろう。
カフカの作品の殆どが、登場人物が尋常でない状況に置かれているところから始まるが、何でそんな事になったのかの明確な説明はされない。入り口も出口も曖昧な迷宮、それがカフカの世界だ。
ボルヘスは、“(カフカの作品において)肝心なのはプロットと環境であり、寓話の展開でも心理的洞察でもない。だからこそ彼の短編物語のほうが彼の小説よりも優れているのであり、だからこそこの短編選集はかくも特異な作家のスケールを十全に示していると断言する正当性がある”と結論付けている。
「禿鷹」は、語り手が生きながら禿鷹に肉体を抉られ続けている場面から始まる。
通りかかった紳士に、なぜ我慢しているのかと問われば、語り手は、「仕方がないではありませんか」と答える。最期に、禿鷹の嘴に喉を深く抉られた語り手は、どっと血を吹き出しながら仰向けに倒れる。溢れる血の中で禿鷹が溺れていく。
“それをみて私はほっと安堵した。”
現実とは、悪夢を絶えず提供し続けるものだと考えているカフカには、語り手が救済される姿を描くことができない。彼の誠実さが、この結末以外を許なかったのだろう。
「断食芸人」は、かつてはヨーロッパ中で人気を博した断食芸人の話。
断食などという芸の無い芸が大当たりする社会って、どんなのなのと思う。檻に閉じ込められた状態で、40日間断食する。それだけである。何がウケたのかはよく分からないが、時勢は変わり、断食芸人の檻の前に人々が群がっていた日々は遠い昔の話になった。
年老い、落ちぶれた断食芸人は、サーカスの動物小屋の隅に檻を置いてもらうことになる。断食芸人の檻は、動物を見に来た客達の移動の邪魔にしかならない。しかし、誰も見る者の無い中、断食芸人は全力を尽くして断食を続け、この上なく見事にやってのけた。そこに何の意味があったのだろう。サーカスの監督の問いに、断食芸人はこう答えた。
“断食せずにいられなかっただけのこと。ほかに仕様がなかったもんでね”
“自分にあった食べものを見つけることができなかった。もし見つけていれば、こんな見世物をすることもなく、みなさん方と同じように、たらふく食べていたでしょうね”
断食芸人が息絶えると、彼の亡骸は速やかに藁くずと一緒に葬られた。
断食芸人の入っていた檻には、一匹の精悍な豹が入れられた。生きのいい豹の姿は多くの見物客を引き寄せ、檻は本来の使われ方を取り戻したのだった。
「町の紋章」は、無限に遅延し続けるバベルの塔の建設の話。
僅か2ページの掌編の中に、人類の駄目なところが粗方詰め込まれていて憂鬱になる。
この手の遅延は現実社会にもよくあることなのだが、人類が人類である限り、それが改善されることはないのだろう。
人類がバベルの塔の完成を見る日は、多分永遠に来ない。だからと言って、人々が何かアクションを起こす気配はない。届かない、伝わらない、辿り着けない、完成しない、そして、そのことについて、何も説明しない、何も起こらないのが、カフカの作風なのだ。カフカの作品においては、障害はプロットを作るためのものではなく、障害そのものが作品の本質なので、障害から何かが起きるはずもないのである。
が、この町に生まれた伝説や唄は、どれといわず、予言に語られる日を待ち焦がれている。それは、巨大な拳が現れて町を打ち、木っ端みじんにしてしまうという予言だ。そんな訳で、この町の紋章には一つの握り拳が描かれているのだ。
「プロメテウス」は、プロメテウスに纏わる四つの言い伝えについて。
“言い伝えは不可解なものを解きあかそうとつとめるだろう。だが、真理をおびて始まるものは、しょせんは不可解なものとして終わらなくてはならないのだ。”
これからカフカを読もうという人は、この「プロメテウス」を始めに読むべきなのだろう。そして、カフカを何度も読んでいる人も、折に触れて「プロメテウス」を思い出すべきなのだろう。カフカに関するこんがらがった解釈なんて、神々も鷲もきっと飽き飽きしていることだろうから。