
『真夏の方程式』 のDVDを見ました。
福山雅治主演のガリレオシリーズの映画化作品です。
昨年、同じ福山主演の 『そして父になる』 のほうは映画館で見たんですが、
『真夏の方程式』 のほうはあまり触手が伸びませんでした。
東野圭吾の原作はすでに読んだことがあってそれなりに面白かったんですが、
結末まで知ってしまっているこの物語をわざわざ映画で見たい気にはならなかったのです。
当時すでに放映されていたドラマ 『ガリレオ』 の第2シーズンが、
第1シーズンと比べてものすごくクォリティが低かったということも一因です。
ただまあ、映画館で見たいほどではありませんでしたが、
DVDを借りて見るぐらいの興味がなかったわけではないので、
今回、だいぶ経ってしまってアウト・オブ・シーズンという感じではありますが、
今さらながら見てみたわけです。
全体としてはなかなかよく映画化できているなというのが正直な感想です。
第2シーズンのダメさ加減とは比べものにならないくらいのいい出来です。
原作はけっこう分厚い本でしたので、削るべきところは削り、残すべきところは残す、
ひじょうにうまく脚本化し映画化していたと思います。
原作をすでに読んだ人が映画を見てもガッカリしないですむという最低ラインは軽くクリアしています。
さらにそれを越えてけっこう私の琴線に触れるプラスアルファも用意されていました。
『そして父になる』 はもろ親子の血のつながりをテーマにしていて、
子どもの取り違えから発して、本当の (血のつながっている) 子や親を求めていくのだけれど、
最終的には、血がつながっていなくても親子は親子だよね、
という私の大好物の話にまとまっていました。
小説 『真夏の方程式』 はだいぶ前に借りて読んだだけだったので、
映画化されたときには原作の内容はうろ覚えで、
湯川准教授と子どもの交流を描いた物語だという印象しかもっていませんでした。
しかし、今回DVDを見てみてこちらも親子の血のつながりを問題にしていたことを思い出しました。
ただ原作では、本当の血のつながった親子という部分にのみ焦点が当たっていたと思うのですが、
映画のほうはそうではありませんでした。
血のつながった親子の愛も描かれているのですが、
それだけではなく、血のつながらない親子の絆という部分も同じくらいか、
あるいはそれ以上の比重で描かれていたのです。
こんな描写は原作にはなかったよなあと思い、
気になったので Book Off で原作も買ってしまいました。
読み直してみたところやはり、血のつながらない親子の話は原作ではほとんど触れられておらず、
映画が原作を越えて付け加えていたということがわかりました。
なんだそうだったのかあ。
映画は私好みに作りかえてあったんじゃありませんか。
こんなことなら去年、映画館で見てあげればよかったです。
この点では映画に軍配を上げてもいいように思います。
とはいえ今回久しぶりに原作も読み返してみると、やはり小説のほうが情報量も多いし、
映画を見ただけだと細部で気になる部分もあったのだけれど、
そういうところもちゃんと辻褄があうように描かれていて得心がいきました。
それに最後の湯川のセリフは映画で見るより活字で読んだほうが、より深く共感できました。
今日の話はどのカテゴリーに入れようか悩みましたが、
湯川の最後のセリフを引用することで 「教育のエチカ」 のカテゴリーに入れることにいたします。
湯川のセリフだけ抜粋して引用します。
「この世界には現代科学では解けない謎がいくつもある。しかし科学の発展と共に、いずれはそれらも解かれていくだろう。では科学に限界はあるのだろうか。あるとすれば、何がそれを生み出すのだろうか。それは人間だ。人間の頭脳だ。たとえば数学の世界では、何か新しい理論を発見した時には、正しいかどうかをほかの数学者たちに検証してもらう。だが発見される理論は益々高度化していく。そうなると当然、検証できる数学者もかぎられてくる。ではもし理論が難解すぎて、ほかの誰も理解できなかったらどうだろう。それが理論として定着するには、別の天才が現れるまで待たねばならない。人間の頭脳が科学の限界を生み出すというのは、そういう理由からだ。わかるかい? どんな問題にも答は必ずある。だけどそれをすぐに導き出せるとはかぎらない。人生においてもそうだ。今すぐには答えを出せない問題なんて、これから先、いくつも現れるだろう。そのたびに悩むことには価値がある。しかし焦る必要はない。答えを出すためには、自分自身の成長が求められている場合も少なくない。だから人間は学び、努力し、自分を磨かなきゃいけないんだ。今回のことで君が何らかの答えを出せる日まで、私は君と一緒に同じ問題を抱え、悩み続けよう。忘れないでほしい。君は一人ぼっちじゃない。」
さすがは湯川准教授、名セリフです。
小学校5年生に向かって言うようなセリフかどうかはビミョーなところですが、
悩みと不安を抱えている恭平君にとってはとても大切なアドバイスとなりました。
同じセリフを福島大学や各地の看護学校その他に入学してきた新入生たちに捧げたいと思います。
すぐには答えを出せない問題に答えを出せる日が来るまで、悩み、学び、考え続けてください。










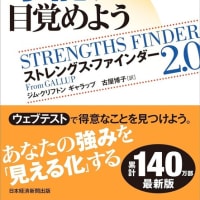









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます