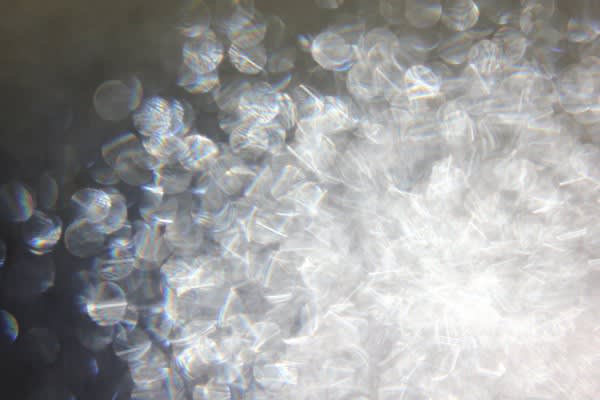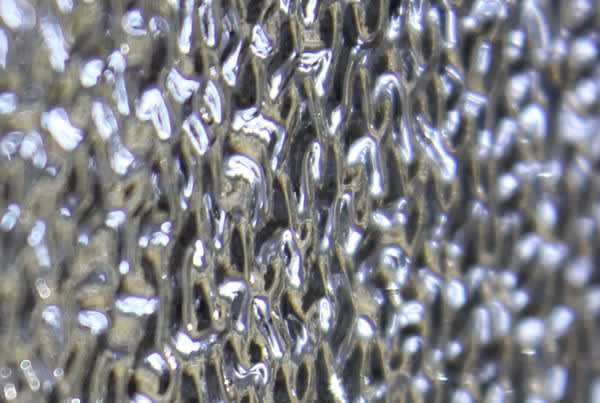薪ストーブの煙突掃除をした。
これでやっと冬を向かえることができる。
ストーブの前でうたた寝をしたり・・・
本を読んだり・・・
竹細工をしたり・・・
ストーブで純米酒を手作りの徳利で熱燗にして、
自前のぐい吞みでちびりちびりと呑んだり・・・
そんな楽しい冬を迎えることができる。
ところで冬というと何月?
新暦だと12月・1月・2月・・・だよね。
でも旧暦だと10月・11月・12月。
そして12月が終わると1月、春がやってくる!
1月・2月・.3月が春。
旧暦の方がずっと季節がわかりやすい。
正月を「新春」というと、なんか変だけど、
旧暦だと2月15日ころから3月15日ころまでが1月・睦月。
元旦は梅がぼちぼち咲きだすころ・・・
まだ寒いけど「新春」という言葉がすんなり受け入れられる。
3月15日ころから4月15日ころまでが2月・如月。
桜が咲き桃が咲き、春真っ盛り!
4月15日ころから5月15日ころまでが3月・弥生。
若葉が萌えいずる、1年でもっとも楽しい季節。
3月というとまだ寒い!なんて思ってたら大間違いだよ。
「春の弥生の曙に・・・」という歌を聞く時、今の新暦の3月を想像してはだめだよ。
春の弥生の曙・・・は、もう5月なんだよ。
4月・5月・6月~は夏。
5月15日ころから6月15日ころまで・・・4月・卯月。
卯の花(ウツギ)が咲きホトトギスが鳴きだし早乙女が田植えをする頃・・・
夏は来ぬ!の季節が始まる。
6月15日ころから7月15日ころまで・・・5月・皐月。
五月雨の季節。
五月雨を集めて早し最上川
そう五月雨って梅雨なんだよ。
そして7月15日ころから8月15日ころまでが6月・水無月。
えっ、なんで6月の梅雨の頃に水がない?
それは新暦の感覚。
梅雨がどうにか終わり猛暑になって・・・
う~~~ん、水が欲しい!!
そんな季節が水無月!
そして盆が明け、
ツクツクボウシに急き立てられて、ようやく夏が終わる。
7月・8月・9月~秋がやってくる。
8月15日ころから9月15日ころまでが7月・文月。
虫が鳴きだす、朝顔が咲く。
朝顔が秋の季語だということを不思議に思っている人、自分で路地に種をまいて、そだてて見てくださいね。
すると朝顔は夏の終わりに咲く花だということが、盆を過ぎて咲く花だということがわかるでしょう。
そう朝顔は秋の季語。
そして9月15日ころから10月15日ころまでが8月・葉月
秋の花が咲き乱れるころ。
収穫の秋。
10月15日ころから11月15日くらいまでが9月・長月
短い秋を精いっぱい生きる季節。
間もなく命が終る冬が来る・・・
そして冬、10・11・12月
11月15日ころから12月15日ころまでが10月・神無月。
落葉の季節。
山は色づき1年で最も美しい季節。
そして木の葉は落ちて、神々もいなくなる・・・
そんなことを感じさせる・・・命の終わりの季節。
11月・霜月。
12月15日ころから1月15日ころ。
毎朝霜に覆われる。
山は無彩色、あるいは茶色の世界。
厳しい冬が続く。
12月・師走。
1月15日ころから2月15日ころ。
何かとあわただしく今年も終わる。
でももう間もなく春の気配。
梅の蕾も膨らんだ。
そう、間もなく新春が、春がやってくる!!
旧暦で読もう、日本の古典は・・・
旧暦で暮らそう、日本の暮らしは・・・