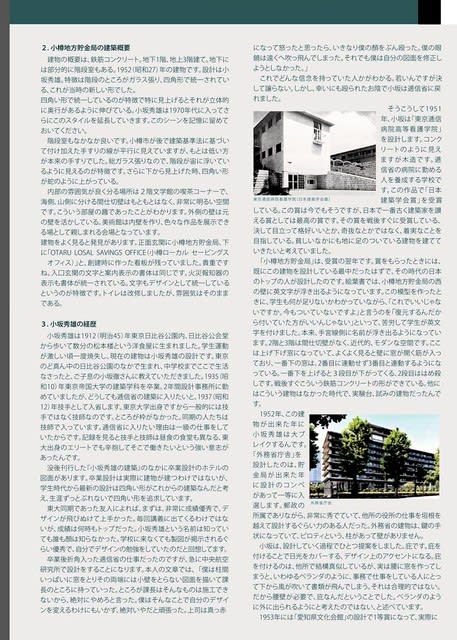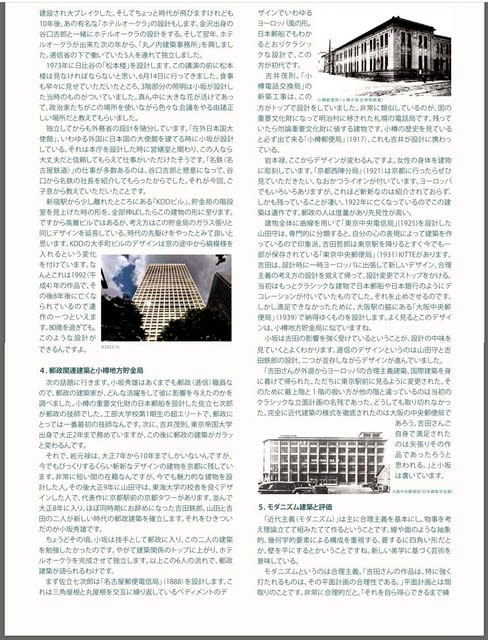今回は、珍しくちょっと政治的発言をします。私は、私自身において純粋な自由なアーティストでありたいため、政治的発言はパブリックにはしません。どうか、この記事に関しての財源確保のアドバイス等は、個人メッセージにてお願いします。
-----------
市立小樽美術館・文学館周辺の「歴史を活かしたまちづくり(文化庁)」について
論点:「市立小樽美術館・文学館の動態保存の建設的な可能性と、その根拠」
下に掲載させていただいたアオバト臨時増刊号(市立小樽美術館報)で、駒木氏が述べられるように、現在の小樽市色内の一角は上記文化庁の括りに値すると強く思われます。本州における文化的歴史とは、一線を違える「北海道の近代文化の保存継続」は、超少子高齢化/不景気/過疎化の波を受けて、全国区またはワールドワイドに『助け』を必要としています。私は、「動態活用されている優れた建築物・その街並み」については、最優先で動態活用されている今の状況を改善すべきと考えます。何故ならば、観光都市宣言をしている小樽市が、国内はもとより世界中からの観光客を小樽に集め、実質「また訪れたい世界の街」№10以内に入っているからです。(今、この根拠となるソースは、示すことが出来ませんが、全日空ANAの今年のカレンダー12分の1に小樽運河が載っている例があります)
また、高度経済成長期に市民運動から発した地方小都市の「市立美術館・文学館」の開館は、全国的に多いと思われることから、その「括り」は申し訳ありませんが「北海道という特別枠」で、テストケースとして【小樽美術館・文学館の動態保存及び、博物館法に則る在り方】改善を求めます。つまり、一昔前に外地扱いだったここに於いて、今そこにある危機「修繕及び維持管理の財源をどうやって確保するか」が問題だからです。
東北大震災や毎年の台風などをはじめ被災地の地方都市の博物館(美術館)は、保険や個人の寄付・文化庁の助成金・企業の助成金などによって、復興の優先順位最下位でありながら、残ったものを保つべくある程度の財源が確保できます。このことは、地方行政において、文化芸術の保存が、直接的に住民の「生きる誇り・財産」であるからでしょう。高齢化や不景気にて(被災地ではない)小都市の財源は、それら住民の健康や「今日一日の生活」のフォロー中心に周ることは当然です。しかし、もしこの文化の修繕が成し遂げられずパブリックに博物館[格]を持った美術館がゼロ(閉館など)になったとしたら・・・あくまでもテストケースとして、日本の文化的損失は非常に教育上よろしくないと思うのです。本当の健康とは、精神に根差した「心意気・志」を育み続けることです。そしてその象徴的な遺産(財産)として、芸術・文学は位置すると考えます。だからこそ、文化庁は様々な手立てを提案しているのでしょう。
さて、実は美術館・博物館の収蔵品については、「収蔵」か「永久収蔵/パーマネントコレクション」に分かれます。美術業界では、「収蔵=死蔵」とも言われて四半世紀以上たちます。美術館・博物館の基本法(例えば、湿度管理や温度管理が適正であること)は、現段階で罰則規定がないことから、維持管理を含めてあいまいになり地方行政優先順位の最下位となっているのが現状です。(日本で5館目の国立美術館である国立新美術館{2007開館}は、収蔵品を持ちません。収蔵の維持管理は経費が莫大にかかるので経営のコストパフォーマンスを考えて設立されたのでしょう)
例として、有名な「松方コレクション」も、その行方については以下の通りです。
----
松方は共楽美術館という美術館を設立する構想を持っており、ブラングィンが設計図を作成していた(ブラングィンが描いた共楽美術館の構想図は現在、国立西洋美術館が所蔵している[4])。しかし、1927年に世界恐慌の影響で川崎造船所の経営が破綻し、負債整理のため松方も私財を提供せざるを得なくなった。そのため、日本にあったコレクションは十五銀行、藤木ビル等の担保となり、売立てにより西洋美術1000点以上が散逸[2]してしまった(その一部が現在、ブリヂストン美術館、大原美術館に収蔵されている)。浮世絵のコレクション約8,000点は、昭和13年(1938年)に皇室へ献上され、昭和18年(1943年)に帝室博物館(現在の東京国立博物館)へ移管された。
一方、日本国外で保管していたコレクションは散逸を免れたが、1924年に実施された10割関税(関東大震災の復興資金のため、買値の10割の関税、つまり買値と同額の税金がかかった)が日本移送の障害となった。昭和初期に軍国主義、国粋主義的風潮が強まる中で、西洋美術のコレクションは軍部に悪印象を与えるのを恐れたこと等もあって、そのまま日本国外に保管されていた。
ロンドンで保管されていたコレクション(約900点と推測されている)は1939年に火災で焼失してしまった。パリにあった400点以上のコレクションはロダン美術館に預けられていたが[2](428点との説がある)、第二次世界大戦のナチス・ドイツのフランス侵攻により、元大日本帝国海軍大尉の日置釭三郎の尽力によりパリ近郊のアボンダンに疎開させられた。ナチス・ドイツによる略奪は免れたものの、ナチス・ドイツと同盟して枢軸国であった日本は、本国を奪還したフランスにとって敵国かつ敗戦国となったため、在仏の松方コレクションは敵国財産としてフランス政府に接収されてしまった。
松方は1950年に死去するが、孫の松本健の回想によると、晩年はフランスからの返還に備えて受け取りサインを書く練習をしていたという。------
https://ja.wikipedia.org/wiki/松方コレクション
私も「松方コレクションは偉大で、小樽市立美術館のコレクションとの比較にならない」ことは、十分に承知しています。しかし、短い北海道近世文化史の中で小樽市が「北海道の文化の中心地だったことがある史実」から、市立小樽美術館・文学館の収蔵品数は、道内の他の館に比べて北海道発の公募展創立会員作品をはじめ、きわめて豊富なことを知っています。 そして、その多くは作家本人や遺族からの「寄贈」の賜物なのです。「国内作家の知的財産です」とすると、地方都市にとっては、松方コレクション以上の教育的価値があると考えるのです。
残念ながら、「今、現在」に奔走している地方都市行政は、その文化遺産の危機をアピールすることが出来ません。また、私個人としては、駒木氏が語る100年構想には賛成しかねます。地方行政は常に選挙権のある住民の意思が最優先されます。そこには、今日の生活をどうしようか?という『問の解決』を催促されている現状があるのです。そこで、市民の「暮らしの潤い」くらいの感覚に位置している美術館・文学館の【文化的アピール】は、「贅沢な我がまま」に見過ごされるのです。これからも、少子高齢化は進むと予想される令和元年において、私は5年スパンの維持管理修繕・記録を提案したく思います。そこには、市の5年スパンの人口確保や地域再生の税収見込み計画も当然含まれます。一方、本来市税収入の生産部門ではない市立美術館(博物館)は、積極的な来館者数増や動産(お金)策構築が必要になってくるでしょう。現収蔵品の例えば1割をオークションにかけて、その所在を追跡できる状況に誘導する財源の確保の仕方もありますし、全ての収蔵品をデジタル記録保存し、万が一「館」が無くなっても「知的財産」が形を変えて残るようにする仕様も含まれます。(例えば、バチカン博物館はNTT日本のスタッフのもとで収蔵品のデジタル化に取り組んでいます) 但し、そのハイテク記録への置き換えにも財源が必要なのです。
こと美術品のまとまったコレクション管理に関しては、古今東西、メジチ家末裔などのお金持ちの「お家の財産維持」に関する強力な意志(なるべく分散させないで永い間、お家の財として持つ)、または強大な宗教・政党などによって、現代でも国レベルを超えて賄われています。国や地方の自治に基づく知的財産の保持は、部分的であって、総合的ではありません。(例えば、大英博物館は英国民は無料で観覧できますが、その維持管理については英国国家予算からよりも貴族や分散財産管理意欲のある元所有者有志の財源からなされています)そして、館の知的財産の維持管理が総合的であるかどうかなどは、まずは半世紀たたないとわからないことなのです。
このスピードを加速する時代に、漏れてしまう近世文化を「どうするのか?」が、持てる者持たざる者の責任比に関わらず、問われ続けると私は考えます。

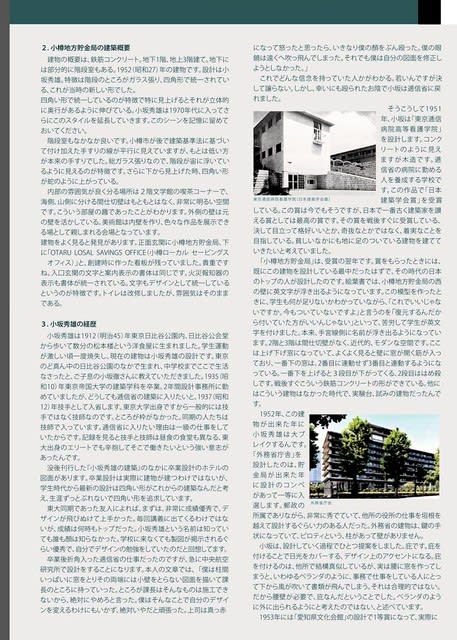
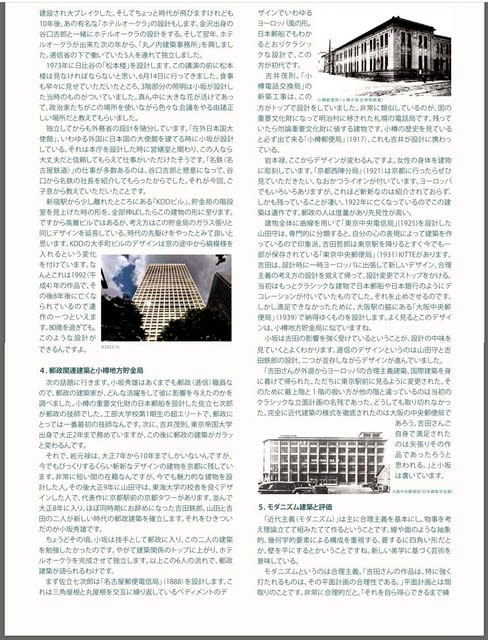

ナカムラアリ
(アーティスト・教育学士・小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観審議委員)
(アーティスト・教育学士・小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観審議委員)
-----------
市立小樽美術館・文学館周辺の「歴史を活かしたまちづくり(文化庁)」について
論点:「市立小樽美術館・文学館の動態保存の建設的な可能性と、その根拠」
下に掲載させていただいたアオバト臨時増刊号(市立小樽美術館報)で、駒木氏が述べられるように、現在の小樽市色内の一角は上記文化庁の括りに値すると強く思われます。本州における文化的歴史とは、一線を違える「北海道の近代文化の保存継続」は、超少子高齢化/不景気/過疎化の波を受けて、全国区またはワールドワイドに『助け』を必要としています。私は、「動態活用されている優れた建築物・その街並み」については、最優先で動態活用されている今の状況を改善すべきと考えます。何故ならば、観光都市宣言をしている小樽市が、国内はもとより世界中からの観光客を小樽に集め、実質「また訪れたい世界の街」№10以内に入っているからです。(今、この根拠となるソースは、示すことが出来ませんが、全日空ANAの今年のカレンダー12分の1に小樽運河が載っている例があります)
また、高度経済成長期に市民運動から発した地方小都市の「市立美術館・文学館」の開館は、全国的に多いと思われることから、その「括り」は申し訳ありませんが「北海道という特別枠」で、テストケースとして【小樽美術館・文学館の動態保存及び、博物館法に則る在り方】改善を求めます。つまり、一昔前に外地扱いだったここに於いて、今そこにある危機「修繕及び維持管理の財源をどうやって確保するか」が問題だからです。
東北大震災や毎年の台風などをはじめ被災地の地方都市の博物館(美術館)は、保険や個人の寄付・文化庁の助成金・企業の助成金などによって、復興の優先順位最下位でありながら、残ったものを保つべくある程度の財源が確保できます。このことは、地方行政において、文化芸術の保存が、直接的に住民の「生きる誇り・財産」であるからでしょう。高齢化や不景気にて(被災地ではない)小都市の財源は、それら住民の健康や「今日一日の生活」のフォロー中心に周ることは当然です。しかし、もしこの文化の修繕が成し遂げられずパブリックに博物館[格]を持った美術館がゼロ(閉館など)になったとしたら・・・あくまでもテストケースとして、日本の文化的損失は非常に教育上よろしくないと思うのです。本当の健康とは、精神に根差した「心意気・志」を育み続けることです。そしてその象徴的な遺産(財産)として、芸術・文学は位置すると考えます。だからこそ、文化庁は様々な手立てを提案しているのでしょう。
さて、実は美術館・博物館の収蔵品については、「収蔵」か「永久収蔵/パーマネントコレクション」に分かれます。美術業界では、「収蔵=死蔵」とも言われて四半世紀以上たちます。美術館・博物館の基本法(例えば、湿度管理や温度管理が適正であること)は、現段階で罰則規定がないことから、維持管理を含めてあいまいになり地方行政優先順位の最下位となっているのが現状です。(日本で5館目の国立美術館である国立新美術館{2007開館}は、収蔵品を持ちません。収蔵の維持管理は経費が莫大にかかるので経営のコストパフォーマンスを考えて設立されたのでしょう)
例として、有名な「松方コレクション」も、その行方については以下の通りです。
----
松方は共楽美術館という美術館を設立する構想を持っており、ブラングィンが設計図を作成していた(ブラングィンが描いた共楽美術館の構想図は現在、国立西洋美術館が所蔵している[4])。しかし、1927年に世界恐慌の影響で川崎造船所の経営が破綻し、負債整理のため松方も私財を提供せざるを得なくなった。そのため、日本にあったコレクションは十五銀行、藤木ビル等の担保となり、売立てにより西洋美術1000点以上が散逸[2]してしまった(その一部が現在、ブリヂストン美術館、大原美術館に収蔵されている)。浮世絵のコレクション約8,000点は、昭和13年(1938年)に皇室へ献上され、昭和18年(1943年)に帝室博物館(現在の東京国立博物館)へ移管された。
一方、日本国外で保管していたコレクションは散逸を免れたが、1924年に実施された10割関税(関東大震災の復興資金のため、買値の10割の関税、つまり買値と同額の税金がかかった)が日本移送の障害となった。昭和初期に軍国主義、国粋主義的風潮が強まる中で、西洋美術のコレクションは軍部に悪印象を与えるのを恐れたこと等もあって、そのまま日本国外に保管されていた。
ロンドンで保管されていたコレクション(約900点と推測されている)は1939年に火災で焼失してしまった。パリにあった400点以上のコレクションはロダン美術館に預けられていたが[2](428点との説がある)、第二次世界大戦のナチス・ドイツのフランス侵攻により、元大日本帝国海軍大尉の日置釭三郎の尽力によりパリ近郊のアボンダンに疎開させられた。ナチス・ドイツによる略奪は免れたものの、ナチス・ドイツと同盟して枢軸国であった日本は、本国を奪還したフランスにとって敵国かつ敗戦国となったため、在仏の松方コレクションは敵国財産としてフランス政府に接収されてしまった。
松方は1950年に死去するが、孫の松本健の回想によると、晩年はフランスからの返還に備えて受け取りサインを書く練習をしていたという。------
https://ja.wikipedia.org/wiki/松方コレクション
私も「松方コレクションは偉大で、小樽市立美術館のコレクションとの比較にならない」ことは、十分に承知しています。しかし、短い北海道近世文化史の中で小樽市が「北海道の文化の中心地だったことがある史実」から、市立小樽美術館・文学館の収蔵品数は、道内の他の館に比べて北海道発の公募展創立会員作品をはじめ、きわめて豊富なことを知っています。 そして、その多くは作家本人や遺族からの「寄贈」の賜物なのです。「国内作家の知的財産です」とすると、地方都市にとっては、松方コレクション以上の教育的価値があると考えるのです。
残念ながら、「今、現在」に奔走している地方都市行政は、その文化遺産の危機をアピールすることが出来ません。また、私個人としては、駒木氏が語る100年構想には賛成しかねます。地方行政は常に選挙権のある住民の意思が最優先されます。そこには、今日の生活をどうしようか?という『問の解決』を催促されている現状があるのです。そこで、市民の「暮らしの潤い」くらいの感覚に位置している美術館・文学館の【文化的アピール】は、「贅沢な我がまま」に見過ごされるのです。これからも、少子高齢化は進むと予想される令和元年において、私は5年スパンの維持管理修繕・記録を提案したく思います。そこには、市の5年スパンの人口確保や地域再生の税収見込み計画も当然含まれます。一方、本来市税収入の生産部門ではない市立美術館(博物館)は、積極的な来館者数増や動産(お金)策構築が必要になってくるでしょう。現収蔵品の例えば1割をオークションにかけて、その所在を追跡できる状況に誘導する財源の確保の仕方もありますし、全ての収蔵品をデジタル記録保存し、万が一「館」が無くなっても「知的財産」が形を変えて残るようにする仕様も含まれます。(例えば、バチカン博物館はNTT日本のスタッフのもとで収蔵品のデジタル化に取り組んでいます) 但し、そのハイテク記録への置き換えにも財源が必要なのです。
こと美術品のまとまったコレクション管理に関しては、古今東西、メジチ家末裔などのお金持ちの「お家の財産維持」に関する強力な意志(なるべく分散させないで永い間、お家の財として持つ)、または強大な宗教・政党などによって、現代でも国レベルを超えて賄われています。国や地方の自治に基づく知的財産の保持は、部分的であって、総合的ではありません。(例えば、大英博物館は英国民は無料で観覧できますが、その維持管理については英国国家予算からよりも貴族や分散財産管理意欲のある元所有者有志の財源からなされています)そして、館の知的財産の維持管理が総合的であるかどうかなどは、まずは半世紀たたないとわからないことなのです。
このスピードを加速する時代に、漏れてしまう近世文化を「どうするのか?」が、持てる者持たざる者の責任比に関わらず、問われ続けると私は考えます。