
友達と飲んでいて、突然ひらめいたことを口にした。
私の晩年は『ルービックキュー完成達成型』を目指すと宣言。
私は多趣味多芸で、沢山の別個のフィールドを持っているのではなく、六面あるものの相互に関連していて、こっちをいじっていたら、あっちがなんとなくよくなったり、ということで結果的に1個の完成したブロックが出来上がるということ。
この酔っ払いの仮説を正当化する論文を見つけた。
「上達のコツは」医学博士 立身政信
上達のコツを脳の働きから考えてみよう。
どんなことでも練習を重ねることによって少しづつ上手にできるようになってくる。
学習によって習得するということですが、脳科学から見ると、思考と行動のパターン化ができてくるということ。
ところが、ある程度上達したところで、ほとんどの人が壁にぶつかります。
プラトー(高原という意味)と呼ばれる停滞状況ですが、努力を続けることによって乗り越えることができます。
その後再び上達してまた停滞するということを繰り返しながら、少しづつ実力がついてくる。
ところが、停滞することで迷ったり悩んだりするうちに逆に技術が低下することがある。
これがスランプに陥った状態です。
スランプは、ある程度上達した段階で起こるもので、未熟な状態ではほとんど見られません。
子供がスランプに陥ることは少ないといわれています。
なぜなら固定観念にとらわれることなく新しい方法を取り入れる柔軟な脳を持っているからです。
ここにスランプを乗り越えて飛躍的な進歩を勝ち取るヒント「上達のコツ」が隠されている。
思考と行動のパターン化ができて、技術がある程度上達すると、脳の働きが固定化されます。
これがプラトーやスランプを生むもとになる。
このとき脳に別な情報を与えてやると、脳はこれまでの固定化された思考と新しい情報の似ている部分や違う部分から、新しい発想を生み出すようになる。
つまり、別の世界を追求することで、プラトーやスランプを超えて物事をより深めることができる。
これはシャベルで土に穴を掘ることと似ている。
最初と同じ穴の広さで掘り続けても早晩限界がきます。
そのとき穴の広さを大きくすることで、より深く掘り進むことができる。
上達のコツの一つは「視野を広げること」
私の晩年は『ルービックキュー完成達成型』を目指すと宣言。
私は多趣味多芸で、沢山の別個のフィールドを持っているのではなく、六面あるものの相互に関連していて、こっちをいじっていたら、あっちがなんとなくよくなったり、ということで結果的に1個の完成したブロックが出来上がるということ。
この酔っ払いの仮説を正当化する論文を見つけた。
「上達のコツは」医学博士 立身政信
上達のコツを脳の働きから考えてみよう。
どんなことでも練習を重ねることによって少しづつ上手にできるようになってくる。
学習によって習得するということですが、脳科学から見ると、思考と行動のパターン化ができてくるということ。
ところが、ある程度上達したところで、ほとんどの人が壁にぶつかります。
プラトー(高原という意味)と呼ばれる停滞状況ですが、努力を続けることによって乗り越えることができます。
その後再び上達してまた停滞するということを繰り返しながら、少しづつ実力がついてくる。
ところが、停滞することで迷ったり悩んだりするうちに逆に技術が低下することがある。
これがスランプに陥った状態です。
スランプは、ある程度上達した段階で起こるもので、未熟な状態ではほとんど見られません。
子供がスランプに陥ることは少ないといわれています。
なぜなら固定観念にとらわれることなく新しい方法を取り入れる柔軟な脳を持っているからです。
ここにスランプを乗り越えて飛躍的な進歩を勝ち取るヒント「上達のコツ」が隠されている。
思考と行動のパターン化ができて、技術がある程度上達すると、脳の働きが固定化されます。
これがプラトーやスランプを生むもとになる。
このとき脳に別な情報を与えてやると、脳はこれまでの固定化された思考と新しい情報の似ている部分や違う部分から、新しい発想を生み出すようになる。
つまり、別の世界を追求することで、プラトーやスランプを超えて物事をより深めることができる。
これはシャベルで土に穴を掘ることと似ている。
最初と同じ穴の広さで掘り続けても早晩限界がきます。
そのとき穴の広さを大きくすることで、より深く掘り進むことができる。
上達のコツの一つは「視野を広げること」

















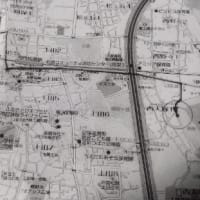



六面八臂?を目指します。