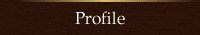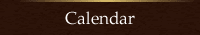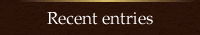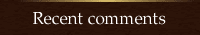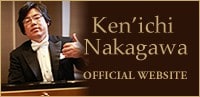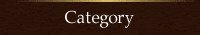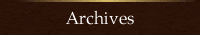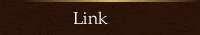水戸芸術館に参りました!
素晴らしいホールです!!
明日本番。
とてもたのしみです!
発見はケージの「ピアノのための電子音楽」がかなり面白い!!
皆様お待ちしております!
以下詳細。
1964 音風景
アンサンブルノマド出演
公演日 2021年7月11日(日)14:00
会場 水戸芸術館コンサートホールATM
価格 【全席指定】一般 3,000円 U-25(25歳以下)1,000円
チケット
お問い合わせ
問:水戸芸術館 チケット予約センター
TEL: 029-231-8000 (営業時間 9:30〜18:00/月曜休館)
https://www.arttowermito.or.jp/hall/lineup/article_4273.html
【プログラム】
湯浅譲二:ホワイト・ノイズによる〈プロジェクション・エセムプラスティック〉(1964)
高橋悠治:クロマモルフⅡ(1964)
ジョン・ケージ:〈ピアノのための電子音楽〉(1964)より
一柳 慧:弦楽四重奏曲 第1番(1964)
テリー・ライリー:インC(1964)
【出演】
アンサンブル・ノマド
佐藤紀雄(音楽監督・指揮・ギター) 木ノ脇道元(フルート)
菊地秀夫(クラリネット) 野口千代光(ヴァイオリン) 花田和加子(ヴァイオリン)
甲斐史子(ヴィオラ) 松本卓以(チェロ) 佐藤洋嗣(コントラバス)
宮本典子(パーカッション) 中川賢一(ピアノ)
磯部英彬(エレクトロニクス)
片山杜秀(企画監修・おはなし)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )


明日水戸で演奏します!!
私は高橋悠治さんのピアノソロ「クロマモルフⅡ」と同じくジョン・ケージのピアノソロ「ピアノのための電子音楽」、そしてアンサンブルメンバーとしてテリー・ライリーの「インC」を演奏します!
是非皆様のご来場をお待ちしております。
以下詳細です。
1964 音風景
アンサンブルノマド出演
公演日 2021年7月11日(日)14:00
会場 水戸芸術館コンサートホールATM
価格 【全席指定】一般 3,000円 U-25(25歳以下)1,000円
チケット
お問い合わせ
問:水戸芸術館 チケット予約センター
TEL: 029-231-8000 (営業時間 9:30〜18:00/月曜休館)
https://www.arttowermito.or.jp/hall/lineup/article_4273.html
【プログラム】
湯浅譲二:ホワイト・ノイズによる〈プロジェクション・エセムプラスティック〉(1964)
高橋悠治:クロマモルフⅡ(1964)
ジョン・ケージ:〈ピアノのための電子音楽〉(1964)より
一柳 慧:弦楽四重奏曲 第1番(1964)
テリー・ライリー:インC(1964)
【出演】
アンサンブル・ノマド
佐藤紀雄(音楽監督・指揮・ギター) 木ノ脇道元(フルート)
菊地秀夫(クラリネット) 野口千代光(ヴァイオリン) 花田和加子(ヴァイオリン)
甲斐史子(ヴィオラ) 松本卓以(チェロ) 佐藤洋嗣(コントラバス)
宮本典子(パーカッション) 中川賢一(ピアノ)
磯部英彬(エレクトロニクス)
片山杜秀(企画監修・おはなし)
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )


練習していたら突然弦が切れてしまいました。
と言うのが20時半。そのあとさらにもう一本切れ・・。
翌日の11時には弦を張り替えにきていただけました。
いつも超速でメンテナンスをしていただけるチームタカギクラヴィアの皆様に本当に感謝しております!!
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
夏休みはオンライン音楽ワークショップで一緒に楽しみましょう!
私とフルーティストの荒川洋さんで行います!
申し込みが定員40名のところすでに190名になりました!
申し込みは18日まで。
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/curiostep/activity/summerchallenge/info.html?s_tc=curiostepsummer_smf&fbclid=IwAR2v3AruBxzetsalOL6h3rEzuR7gj2_chK_s_35_ZU2Wa4cj5AQlWD9gaps
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )


素敵な幸田町滞在、帰り新幹線泊、帰宅のあとはお茶の水女子大学で指揮法の授業、翌日は母校でレッスン。
毎回演奏ツアーでは色々勉強になり、様々なスキルが身に付いてくるのですが、それを伝える重要な時間です。
指揮法教程はこの時代によくここまで体型的に書いたと思える素晴らしい本なのですが、そのまま振ってみるのと、実戦ではこのようにも振ることがあると言う二種類を常に私自身振ってみて示すことを心がけております。
こういったことも実際の演奏経験から導き出されることが多いです。
それを言語化、視覚化するのはとても自分自身にとって勉強になり、重要なことですね。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )