リオ五輪開幕前、選手の親を対象に、子育てに関する意識調査を実施。〈1〉子供が競技を始めたきっかけ〈2〉親の競技経験の有無〈3〉家庭教育で心がけたこと――などについて尋ね、選手106人の親から回答を得た。
競技を始めたきっかけは、「きょうだいがしている」が31人、「親の勧め」は26人、「テレビや本の影響」は3人だった。「その他」は46人で、友人や先輩らの影響を受けたという回答が目立った。親の競技経験では、「両親とも経験なし」が78人で7割超を占めた。「両親とも経験」は14人で、「父親のみ」は10人、「母親のみ」は4人だった。
■心がけたこと
家庭教育で心がけたことについては、「やりたいことをやらせる」「嫌々させず、自主性に任せる」など、子供の気持ちを尊重するという意見が36人で目立った。
「子供がしたいことを尊重して後押しし、環境を整えた。前向きな言葉をかけ、褒めて伸ばした」と、体操の団体総合と個人総合で金メダルに輝いた内村航平選手(27)の両親は回答。競泳で金銀銅の3個のメダルを獲得した萩野公介選手(22)の母・貴子さんは、「本人の好きなように決めさせる。頑張っていることには協力を惜しまない」と答え、200メートル平泳ぎで優勝した金藤(かねとう)理絵選手(27)の父・宏明さんも「子供の自己責任で物事を決めさせる。そうすると、練習を続けて上達し、その満足感が次の練習につながる」と振り返った。
一方、柔道70キロ級の金メダリスト、田知本遥(はるか)選手(26)の父・又広さんは柔道経験者で、娘の才能を見抜き、「お父さんの頼みだから我慢してやってくれ」と競技を続けることを後押しし、「柔道なら世界一、エベレストの頂点に立てる可能性がある」と励まし続けたという。
■避けたこと
家庭教育であえてしなかったことは何かとの問いには、「強制しない」「親の考えを押しつけない」などの意見が36人と最多で、子供の気持ちを尊重する傾向がこの質問でも見て取れた。また、「重圧を与えない」「競技の話を家庭でしない」などと10人が答えた。
競泳200メートルバタフライで銀メダルの坂井聖人(まさと)選手(21)の両親は、水泳に関しては「頑張れ」という言葉を使わず、「楽しみなさい」としか言わなかったという。家の中では水泳の話はせずにリラックスさせることを心がけ、「居心地の良い場所作りが大事」と話した。体操の団体総合で金メダルの田中佑典(ゆうすけ)選手(26)の父・章二さんも、「家では体操の話はあまりせず、自由な時間に口出ししなかった」と回答。田中選手の兄・和仁さんと姉・理恵さんも体操選手だったが、「きょうだいで比較しない。その子のプライドを大事にする」との教育方針だった。
■やる気アップ
また、やる気を起こさせる方法については、「褒める」15人、「応援する」7人、「目標を作る」5人など、回答はさまざまだった。
競泳の800メートルリレーで銅メダルの松田丈志選手(32)の父・公生さんは「親が一生懸命に応援すると、子供は頑張り、親子の絆が深まる」と力説した。レスリングのグレコローマンスタイル59キロ級で銀メダルに輝いた太田忍選手(22)の父・陽一さんは「このままじゃやばいと感じさせ、『自分でやらなきゃ』と思わせた」と回答。太田選手は危機感からか、他の選手の技を目で盗んで貪欲に自分のものにしていったという。
◇サポートあれば誰にでも可能性
元プロテニス選手の杉山愛さんの母で、「一流選手の親はどこが違うのか」(新潮新書)などの著書がある杉山芙沙子さんは、「スポーツは本人が楽しまないと上達しにくいため、自主性を尊重しつつ、しっかりとサポートすれば、両親に競技経験がなくてもオリンピアンが生まれる可能性は十分にある」と話す。
(8月18日付読売新聞 社会面「[Rio2016]五輪選手の育て方…選手106人の親に聞く」より)
以上はオリンピック選手を育てた親の方針、やり方ですが、これはそのまま子育て全般、家庭での教育環境作りにも当てはまり、私がこれまでこのブログで繰り返し述べてきたこととまったく同じです。
基本・原則に従ってやっていたら、どんなことでも実を結ぶことができるのです。
ちなみに、私は、小学生のころ、かけっこが遅くいつも後ろのほうだった。
でも、遊ぶ時は人よりも疲れずに最後まで遊んでいた。
中学に上がり、授業のサッカーをしたところ最後まで疲れずに走れ回れた。
学校の帰りは、いつも1.5kmを走って河内方面に坂道を上る
バスがあったが、バスよりも走ったほうが早かった。(当然かばんは背負ったまま)
今の走りはこの時のフォームが身についたと思う
体育祭の走り高跳びに出たらいきなり中学1年で140cm跳べた!
2年時には、150cm
3年時には160cm、通信陸上に推薦で出場する。
高校では175cmまでに伸び、このころ中距離を先輩から走らされる
800mで2分ちょい、1500mで4分10秒くらいを出す。
練習は、短距離の先輩との150m走のみ
毎日10回くらいこれをやらされ、雨が降ると階段ダッシュを4階まで100往復
筋トレ
高校までに、指導者はいなかった。
要は適当な練習でした
今は思う、クラブチームなどがあったらすごいことになっていただろうなと。
今の子は、外で遊びに何キロも歩いていくことはない
私たちのころは、1日10kmくらいは移動していた。
ちょっと、皿倉山までと走っていったものだ。
身体の基礎を作るのは、遊びの中が良い。
自然とできるようになることが良い
だから、ルーティーンなことが良いのでクラブなどを経験すると見違えるほどに成長する。
もし、今クラブをしているのなら、親は、最初に始めたころの子供と今の子供を比べてみてください。
別人になっているはずです。
私は、競技はもちろん大事ですが、心の成長と自立できること、自分のやりたいころ見つけが大事と考えています。
それを見つけるために一緒に頑張っています。
自分のできなかったことを、子供たちに。
競技を始めたきっかけは、「きょうだいがしている」が31人、「親の勧め」は26人、「テレビや本の影響」は3人だった。「その他」は46人で、友人や先輩らの影響を受けたという回答が目立った。親の競技経験では、「両親とも経験なし」が78人で7割超を占めた。「両親とも経験」は14人で、「父親のみ」は10人、「母親のみ」は4人だった。
■心がけたこと
家庭教育で心がけたことについては、「やりたいことをやらせる」「嫌々させず、自主性に任せる」など、子供の気持ちを尊重するという意見が36人で目立った。
「子供がしたいことを尊重して後押しし、環境を整えた。前向きな言葉をかけ、褒めて伸ばした」と、体操の団体総合と個人総合で金メダルに輝いた内村航平選手(27)の両親は回答。競泳で金銀銅の3個のメダルを獲得した萩野公介選手(22)の母・貴子さんは、「本人の好きなように決めさせる。頑張っていることには協力を惜しまない」と答え、200メートル平泳ぎで優勝した金藤(かねとう)理絵選手(27)の父・宏明さんも「子供の自己責任で物事を決めさせる。そうすると、練習を続けて上達し、その満足感が次の練習につながる」と振り返った。
一方、柔道70キロ級の金メダリスト、田知本遥(はるか)選手(26)の父・又広さんは柔道経験者で、娘の才能を見抜き、「お父さんの頼みだから我慢してやってくれ」と競技を続けることを後押しし、「柔道なら世界一、エベレストの頂点に立てる可能性がある」と励まし続けたという。
■避けたこと
家庭教育であえてしなかったことは何かとの問いには、「強制しない」「親の考えを押しつけない」などの意見が36人と最多で、子供の気持ちを尊重する傾向がこの質問でも見て取れた。また、「重圧を与えない」「競技の話を家庭でしない」などと10人が答えた。
競泳200メートルバタフライで銀メダルの坂井聖人(まさと)選手(21)の両親は、水泳に関しては「頑張れ」という言葉を使わず、「楽しみなさい」としか言わなかったという。家の中では水泳の話はせずにリラックスさせることを心がけ、「居心地の良い場所作りが大事」と話した。体操の団体総合で金メダルの田中佑典(ゆうすけ)選手(26)の父・章二さんも、「家では体操の話はあまりせず、自由な時間に口出ししなかった」と回答。田中選手の兄・和仁さんと姉・理恵さんも体操選手だったが、「きょうだいで比較しない。その子のプライドを大事にする」との教育方針だった。
■やる気アップ
また、やる気を起こさせる方法については、「褒める」15人、「応援する」7人、「目標を作る」5人など、回答はさまざまだった。
競泳の800メートルリレーで銅メダルの松田丈志選手(32)の父・公生さんは「親が一生懸命に応援すると、子供は頑張り、親子の絆が深まる」と力説した。レスリングのグレコローマンスタイル59キロ級で銀メダルに輝いた太田忍選手(22)の父・陽一さんは「このままじゃやばいと感じさせ、『自分でやらなきゃ』と思わせた」と回答。太田選手は危機感からか、他の選手の技を目で盗んで貪欲に自分のものにしていったという。
◇サポートあれば誰にでも可能性
元プロテニス選手の杉山愛さんの母で、「一流選手の親はどこが違うのか」(新潮新書)などの著書がある杉山芙沙子さんは、「スポーツは本人が楽しまないと上達しにくいため、自主性を尊重しつつ、しっかりとサポートすれば、両親に競技経験がなくてもオリンピアンが生まれる可能性は十分にある」と話す。
(8月18日付読売新聞 社会面「[Rio2016]五輪選手の育て方…選手106人の親に聞く」より)
以上はオリンピック選手を育てた親の方針、やり方ですが、これはそのまま子育て全般、家庭での教育環境作りにも当てはまり、私がこれまでこのブログで繰り返し述べてきたこととまったく同じです。
基本・原則に従ってやっていたら、どんなことでも実を結ぶことができるのです。
ちなみに、私は、小学生のころ、かけっこが遅くいつも後ろのほうだった。
でも、遊ぶ時は人よりも疲れずに最後まで遊んでいた。
中学に上がり、授業のサッカーをしたところ最後まで疲れずに走れ回れた。
学校の帰りは、いつも1.5kmを走って河内方面に坂道を上る
バスがあったが、バスよりも走ったほうが早かった。(当然かばんは背負ったまま)
今の走りはこの時のフォームが身についたと思う
体育祭の走り高跳びに出たらいきなり中学1年で140cm跳べた!
2年時には、150cm
3年時には160cm、通信陸上に推薦で出場する。
高校では175cmまでに伸び、このころ中距離を先輩から走らされる
800mで2分ちょい、1500mで4分10秒くらいを出す。
練習は、短距離の先輩との150m走のみ
毎日10回くらいこれをやらされ、雨が降ると階段ダッシュを4階まで100往復
筋トレ
高校までに、指導者はいなかった。
要は適当な練習でした
今は思う、クラブチームなどがあったらすごいことになっていただろうなと。
今の子は、外で遊びに何キロも歩いていくことはない
私たちのころは、1日10kmくらいは移動していた。
ちょっと、皿倉山までと走っていったものだ。
身体の基礎を作るのは、遊びの中が良い。
自然とできるようになることが良い
だから、ルーティーンなことが良いのでクラブなどを経験すると見違えるほどに成長する。
もし、今クラブをしているのなら、親は、最初に始めたころの子供と今の子供を比べてみてください。
別人になっているはずです。
私は、競技はもちろん大事ですが、心の成長と自立できること、自分のやりたいころ見つけが大事と考えています。
それを見つけるために一緒に頑張っています。
自分のできなかったことを、子供たちに。


















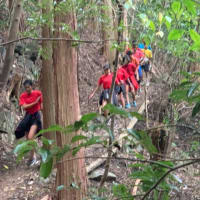


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます