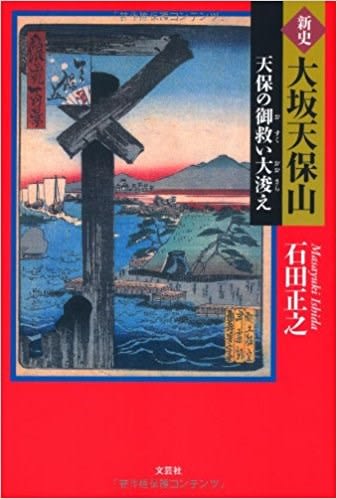【ビワトロマスが誕生】
長浜バイオ大学の河内浩行研究室が(株)びわ鮎センタ
ーと共同で琵琶湖の固有種・ビワマスの餌を開発。この
餌で養殖したビワマスは、従来のものより脂の乗りが良
く、天然ビワマスにも匹敵する量となっている。この養
殖ビワマスの食味試験と試験出荷の様子を、2017年7月4
日、NHK 大津放送局「おうみ発630」で紹介。
これより先立つ、2013年10月から県醒井養鱒場(米原市)
が開発した新たな養殖品種「全雌(ぜんめす)三倍体ビ
ワマス」の出荷開始で大幅な増産と年中安定した供給が
見込まれ、湖国特産として県内外で売り出す動きが進ん
でいた。ここでは、年間を通じ水温12度という霊山山
系の湧水を引いた醒井養鱒場の池で、水しぶきを上げて
全雌三倍体ビワマスが泳ぐ。10月1日から出荷を始め
る養殖2年物は最大1・4キロと従来の養殖物の2倍近
い重さで、担当者は「マグロのトロ以上と言われるほど
脂が乗ったビワマスを年中味わえる。

因みに全雌三倍体ビワマスとは、同養鱒場が約20年前
から研究してきた卵を持たない雌の品種で、2011年
に生産技術を確立した。産卵期に脂が落ちて肉質が劣化
することなく、より大きく成長するのが特長で、旬が6
~8月に限られ漁獲量、品質の確保が難しい天然物や既
存養殖種に対し、年間を通じて質量とも安定した供給が
可能になる。
民間の業者と共同開発した特製のエサを使ってビワマスを養
殖し、「ビワトロマス」と名付けて来年3月から出荷を始める。
びわ湖固有の魚「ビワマス」は、その美しい姿から”びわ湖の
宝石”とも呼ばれ、脂が乗った身は刺身などでもおいしいと
人気を集めている。
一方で、去年のビワマスの漁獲量は20トンと、昭和30年代
の20%程度にまで落ち込んでいて県や民間の業者が養殖
に取り組んできた。こうした中、滋賀県長浜市にある長浜バ
イオ大学の河内浩行准教授の研究室では、地元の養殖業者
と共同で廃棄される魚の骨や内臓を使った特製のエサを開
発。このエサは従来の魚を原料にした「魚粉」のエサに比べ、
価格が安い上に栄養も豊富。実際にこのエサで養殖したビワ
マスは脂の乗りがよく、飲食店からの評価は上々。大学では、
このビワマスを「ビワトロマス」と名付けてブランド化し、来年
3月から年間およそ3000匹を出荷する予定。河内准教授
は、「多くの人においしさを感じてもらいたい。安価なエサで
養殖に成功した新たなビワマスの価値を高めていきたいと抱
負を語る。
【エピソード】

「海の魚は5年で枯渇 養殖あるのみ」とは、近大ナマ
ズ産みの親、有路昌彦教授の言葉である。だとすれば、
鯰だけでなく、鯉、鮒も同じだろう。泥臭い、小骨が多
いなどいう意見が帰ってきそうだが、餌をハーブなどを
くわえるとか、環境――例えば、ニゴロブナは百メート
ル水深で生活するため柔らかくなる。気圧で言えば10
気圧の環境下で養殖すれば柔らかくなるように――を変
えれば問題ないだろう考えている。勿論、加工段階で加
圧・加熱処理することも可能だが。
【脚注及びリンク】
------------------------------------------------
- ビワマス Wikipedia
- ビワマス|滋賀県|全国のプライドフィッシュ|
プライドフィッシュ - 長浜バイオ大学発の養殖ビワマスを試験出荷 – 長
浜バイオ大学 2017.07.04 - 京都新聞|しがBiz - 「全雌三倍体ビワマス」
出荷へ 2013.09.15 - 琵琶湖の個性的な魚介類8種の利活用を促進~「琵
琶湖八珍(びわこはっちん)」のブランド化事業
を開始 2016.01.19 - ビワマス物語 | 琵琶湖の固有種ビワマスを使った
プレミアムで美麗な珍味『Biwamasu Premium -ビ
ワマス プレミアム-』の開発物語です。 - 森のビワマス 公式サイト 米原市商工会
- 養殖ビワマス、大学ブランドに 2017.07.01
- 水産物の内陸化:環境と食糧問題を同時解決 極東
極楽 2017.10.04 - 「人海の魚は5年で枯渇」養殖あるのみ 極東極楽
2017.10.08 - 滋賀県出身の人物一覧 Wikipedia
-------------------------;----------------------