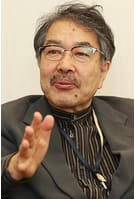福島第一原発4号機の設計者が断言! 「“汚染水の完全コントロール”は大ウソ」
週プレNEWS 1月25日(日)6時0分配信
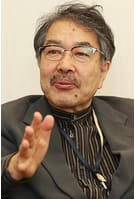
かつて、原子炉圧力容器の設計に関わり、国会事故調の委員も務めた田中三彦氏
昨年12月、福島第一原子力発電所4号機プールに残っていた使用済み核燃料の取り出し作業がすべて完了した。
作業を行なった東京電力は「大きな前進」とし、各メディアも「ひとつの節目を迎えた」と報じたが、廃炉に向けての道のりはいまだ険しいまま。
福島第一原発4号機などの原子炉圧力容器の設計に関わり、内実を知り尽くす田中三彦氏が、今後に待ち受ける困難を解説する!
* * *
●トレンチ止水の問題
福島第一原発の汚染水は完全にコントロールされている―。安倍晋三首相がIOC(国際オリンピック委員会)総会の壇上で、そう大見えを切ったのは2013年9月のことでした。
しかし、汚染水の完全なコントロールなど大ウソです。
福島第一原発を廃炉にするには、一日約300tずつ増える汚染水を除去しなければいけない。そのため、東京電力は原発の周りの土を凍らせて地下水の流入を抑える「凍土遮水壁」(以下、凍土壁)を築こうとしています。
ところが、その建設の前提となるトレンチ(タービン建屋と海側のポンプをつなぐ電源ケーブル類を通す、幅と高さが5mの地下道)内の汚染水処理にすら四苦八苦しているありさまです。
タービン建屋につながるトレンチには1万1000~1万2000tもの汚染水がたまっていて、地震や津波に襲われれば、汚染水の大量漏洩(ろうえい)もあり得るわけで、いつまでも放っておけない。
そこで東電は、タービン建屋とトレンチの接合部を凍結させて止水し、汚染水を抜き取ろうとしたのですが、うまくできなかった。水流によって汚染水の温度が十分に下がらず、凍結しなかったのです。そのため、東電は昨年11月末、大量のセメントを流し込み、トレンチ全体を埋める粗っぽい手法に切り替えざるを得ませんでした。とはいえ、この手法で完全に汚染水を遮断できるのか、まだはっきりしていません。
国と東電は汚染水対策として、(1)汚染源を取り除く、(2)汚染源に水を近づけない、(3)汚染水を漏らさない、という3つの基本方針の下、計9つのメニューを打ち出しています。
トレンチ内の汚染水抜き取りはその9つのメニューのひとつにすぎません。それすら、東電はうまくこなせていない。原子力規制委員会の某委員が「トレンチの止水もできないのに、凍土壁もへったくれもない」と呆れたのも無理はありません。
●“不確実”な凍土壁
凍土壁の造成は昨年6月から凍結管設置のための削孔作業が始まっており(昨年12月24日時点で1030本)、今年から本格的な工事に突入します。
ただ、土を凍らせて止水するという技術は不確実です。トンネル工事などで採用されたことはあるものの、それは小規模なもの。総延長約1.5�、合計で7万m3もの土を凍らせる大規模な工事例は過去にありません。
山側から流入する地下水量は1日800~1000t。それだけの水をせき止めるのだから、凍土壁にはそれなりの水圧がかかります。氷に力を加えると、ある時点でパキッと割れてしまう。
大きな地震が発生したとき、凍土壁が割れたり、ヒビが入ることはないのか? 確かなことは何もわかっていません。しかも汚染水処理が完了するまで、その凍土壁をこれから何年間も維持しないといけないのです。
国も東電も技術的な“実験”をこの機会にやってしまおうと考えているように見えます。コストの安い工法を試して、成功すれば新技術の確立になる。ダメなら別の方法を試せばよいという安易さを感じてしまいます。しかし、そんな悠長なことをやっている場合ではない。汚染水の海洋流出を防ぐためにも、少々コストがかかってもきちんと汚染水をコントロールできる設備を導入すべきです。
例えば、民主党は鉄板壁を提案したし、地盤工学会も凍土壁の性能や耐久性に疑問を投げかけ、今からでも遅くないと別の方法を提案しています。
それに、凍土壁さえできれば、「これで安心」とはなりません。凍土壁で山側からの地下水をシャットアウトすれば、原子炉建屋の地下などにたまっている超高濃度の汚染水が外に流れ出す危険性があるからです。
今、建屋内には一日300t前後の地下水が流れ込んでおり、東京電力はそれをくみ上げて浄化した上で、タンクにため続けています。水は高い所から低い所へ流れる。
つまり、地下水の水位は建屋にたまる汚染水の水位より高いということです。当然、水圧は地下水のほうが大きいので、建屋内の高濃度の汚染水は外に漏れ出ない。
ところが、凍土壁で地下水の流入を止めてしまうとどうなるか? 今度は建屋の水位が地下水の水位より高くなり、逆に危険な汚染水が外部に流れ出てしまうのです。
これを防ぐために、上流からの地下水の一部を、注水用井戸を使って建屋周辺の地盤に流し込み、原子炉建屋内の汚染水の水位より地下水の水位が高い状態になるようにしなくてはなりません。
つまり、凍土壁が完成したとしても、井戸や流量計を設置し原発敷地内のあちこちの水位を絶えず監視、コントロールしないといけないのです。理屈上は可能でも、実際にはとても難しい作業だと思います。
(取材・文/姜誠 撮影/ヤナガワゴーッ!)
●田中三彦(たなか・みつひこ)
1943年生まれ。68年に日立製作所の関連会社に入社。福島第一原発4号機などの原子炉圧力容器の設計に関わる。77年に退社後は、科学系の翻訳、評論、執筆などを行なっている。東日本大震災後は国会事故調(東京電力福島原子力発電所事故調査委員会)の委員を務めた
■週刊プレイボーイ5号「福島第一原発4号機の設計者が、国と東電が進める廃炉作業に緊急警告!」より