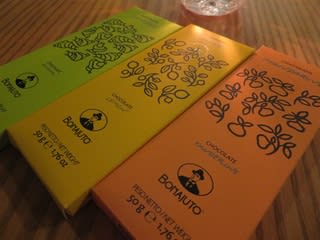
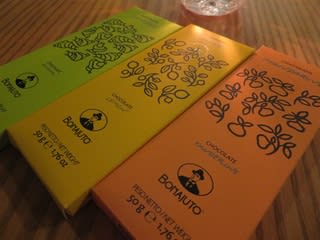
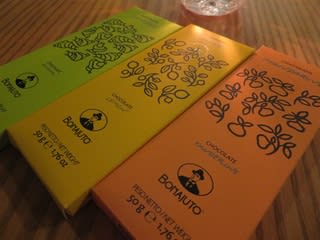
1989年産のカルヴァドス ルモルトン。
昭和から平成へと移り、高校を卒業〜浪人生活へと入った忘れられない年である。
ヴィンテージならではの歳月を味わおうと正月三が日に開栓した。
「シャンパン」がフランスはシャンパーニュ地方で造られたものに限定されるのと同様に、
「カルヴァドス」を名乗るにはノルマンディー地方が条件になるという。
この地方には約800種類ものリンゴがあると記載したサイトの真偽はともかく、
そのなかでカルヴァドス用として認められているリンゴは48種類、プラス数種類の洋ナシなのだとか。
調べていくうちに「ルモルトン」は、銘醸地ドンフロンテ地区で農園を営むルモルトン家が
自家醸造、自家熟成させて造るカルヴァドスであることが判った。
洋ナシの割合が高いのがこのエリアの特徴で、
リンゴ100パーセントのものよりも香りの幅が広いと感じる。
さて、飲みながら時の流れに思いを馳せようとしたものの、
偶然手に入れたボナイユート チョコレートとの相性があまりにすばらしく
意識はそちらに持っていかれてしまった。
鼻腔口腔への強烈なパンチに緩急を付けてくれる
シチリア産古代チョコレートの話しは次のエントリーで。
参考URL:
https://lemorton.com/en/home/
https://anyway-grapes.jp/producers/france/normandie/lemorton-/index.php
https://brandydaddy.com/entry/chishiki-20-calvados/

落ち葉のなかの松ぼっくりに薄霜が降りる。
大きなガラスのショーケースではこのモンブラン一種類が林立していたので、
単体で眺めると新しいイマジネーションが湧いてきた。
数日前に味わった栗きんとんが、栗への欲望に火を付けた。
今度はモンブランを食したいと思うようになり、久々のオフィス出社の帰りに立ち寄ったのがモリ・ヨシダ・パリ。
パリで認められた日本人パティシエ・吉田守秀の日本初出店は、
一年前の渋谷スクランブルスクエア開業時に話題となったものだ。
近年独創的なモンブランが巷間を賑わしているのを知ってはいたものの、
モリ ヨシダの意匠はその上を行く。
一体どのようなテクニックで松笠状にクリームを絞り出しているのだろうか?
思うに日本人パティシエの活躍は、和菓子文化の基盤のうえに成り立っている。
つまり、和菓子で表現される季節感が、松ぼっくりのモンブランに昇華されたと解釈する。
また、茹でた栗を潰して菓子にするという発想は、栗きんとんとモンブランに共通するもので、
そのような洗練された食文化を元から有していることも、日本人が洋菓子の本場で花開く理由に違いない。
さて、味の方は全体的に甘さ控えめで、落ち葉の部分の薄いパイ生地が食感のアクセントとなっている。
晩秋の小さきものに注がれたパティシエの眼差しを勝手にイメージしながら、栗の風味を堪能した。
https://moriyoshida.fr/ja/

一言でいえば、リンゴのあまりにも魅力的な変容。
1989年の開店以来この店で圧倒的な人気を誇っているという味をコンサートの前に確かめた。
ホームページによると「しっかりしたリンゴの素材感」を出すのに最適な品種を追い求めた結果、
「硬めの富士」という結論に至ったとのこと。
シンプルであるがゆえにものを言う素材選び。
甘酸っぱさと生クリームの相性がまた秀逸である。
この日は両親を招待し、後日談として母が絶品のタルトタタンを繰り返し話題にしていると父から聞いた。
どうやらコンサートの印象を上回ったらしい(笑)。
さて、そのコンサートはN響のオーチャード定期第81回。
お目当てはラフマニノフのピアノ協奏曲第2番である。
もはやこの曲を浅田真央のスケートと切り離して聴くことはできない。
ソチでは失意のショートがあったからこそ、フリーの偉業が際立ったのも事実。
彼女が一体どんな覚悟でフリーに臨んだのかを考えるだけで出だしから目頭が熱くなった。
重厚な旋律に乗って成し遂げられた最高難度のプログラム。
第3楽章では伊藤みどりのアルベールビルを思い出し、
R. I. のなかではもう完全に別名“トリプルアクセル・コンチェルト”なのである。
指揮者のレナード・スラットキンが健康上の理由でキャンセルとなったのは残念であったが、
代役のクリスティアン・アルミンクは同い年ということで注目した。
上背があるので手を伸ばすと管楽器の最前列にまで届きそうなダイナミックさがある。
例の浅田真央のステップの部分はテンポを落としてゆったりと荘重に聴かせてみせた。
ラフマニノフという作曲家はとにかく音が多い。
SACDで録音年度の新しいディスクを聴くと、こんなところでこんな音が鳴っていたのかという発見に都度出くわす。
この日座ったバルコニー席からはピアノのハンマーが大量の塊となって上下しているのが目に入った。
ピアノのオルガ・ケルンは抜群の安定感。
第1回ラフマニノフ国際ピアノ・コンクールの覇者だそうで、すでに十八番であることが窺えた。
N響オーチャード定期 第81回
2014 11.9 sun
Bunkamuraオーチャードホール
http://www.bunkamura.co.jp/magots/topics/post_10.html