5月16日の「折々のことば」は次のようでした。エッセイストでもある84歳のイラストレーター・田村セツコさんの言葉だそうです。
私、人生経験が薄っぺらで人生の幅が狭いのか、折々のことば、鷲田清一氏の解説があってもすっきり理解することができない時が多いのですが、これは普通の意味では理解できた気がしました。
「渋いものを味わったあと、他のものが甘く感じられたりするじゃない?」
この言葉を読んだとき、私の頭には実家の母の秋口に作るご自慢料理が目に浮かびました。
「秋ナスの麹づけ」。子どものこととて作り方をきちんと覚えていませんが、秋口になっても畑のなすはまだ勢いがよく、次々と実をならします。それを一口大に乱切りして塩を振り、一日くらい(?)おく。出てきた水分をしぼり、コメ麹と和がらしを混ぜ込む。味がなじむまで何日か置く。というようなものだったか。
この時の和がらし、畑での自家製。実を水でふやかして擂鉢でする。母のお決まりの言葉。「一寸隠し味に砂糖を入れるんよ。からしの辛さが引き立つけん」。縦長の湯のみのような器の底と内回りに塗りつけて、立ててておくのだった(と思う)。
わが家は父が酒をたしなまなかったから、特にこれを待つ人もなかったかと思うのですが、なんと子供の私が辛さを好みパクパク食べた麹のかすかな甘みに加わった、つ∼んと鼻に抜けるからさ。辛さ.
「まあ、この子は…呑み助になりそうじゃねえ」。これも母のお決まりの言葉。
わが家の二人の子は福島で生まれました。まだ幼稚園にもいかないころから、親の好みで寿司屋に連れて行って夕食を外食で済ませることがありました。この時、子どもたち一人前に
「カンカンと私、さび抜きおねがい」と注文するのでした。親父さんともおなじみ、これも大好きな卵焼きを付けて出してくれるのでした。
ワサビの辛さは食通ぶった我が子もお手上げだったのでしょう。
それが何年後でしょうか、なにが切っ掛けで食べられるようになったのか、さび抜かないで。食べられるようになったの、とにっこり注文したのでした。
その時の一人前の大人ぶった顔が忘れられません。ほこりがましい時でした。
子供から大人への入り口に壁を抜けるとき、がありますね。わが子を含めて、甥っ子やら姪っ子やらで経験したことですが、「ビールは苦いから飲めない」と言っていた子供が、是でなくっちゃ。この苦さがなんとも言えないとぐっと飲むときの誇らしい顔をするのです。


















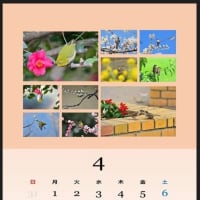


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます