昨年の暮れ、31日の天声人語が切り取ってありました。富山県高岡市の「老子製作所」(江戸時代から続く鋳物メーカー)の会長・元井秀治さんの文章です。
今夜は除夜の鐘、一年暮れるなと感慨深くスクラップしたものらしい。
お寺の鐘についての諸々の知識、雑学と言っては失礼ですが、面白いので書いておきます。
梵鐘は仏教とともに日本に伝わった。スリムなものが多かったが、時代とともに変化。裾に向かって分厚くなり、ずんぐり型が増えたのだと言います。
鐘の頭部・腹部・裾を、竜頭・池の間・駒の爪と呼び、突き棒が当たる部分を「撞坐」と呼ぶのです。「撞坐」は千年かけて下へ下へと位置を変えた。音色もジャーン・カーンからゴーンという重低音に変わった。
中国や、韓国の鐘はジャーンという銅鑼のような派手な音だけれど、日本では遠くまで届く穏やかな音が特徴。
国民性、民族の好み、面白いものですね。日本人の美意識ではやはりわびさびに向かっていくのですね(おせっちゃんの感想)
お寺の釣り鐘も、苦境に泣いた時もあります。廃仏毀釈で棄てられたこともあり、世界大戦の時は、金属類は回収されてしまったのです。
おせっちゃんの頭にある田舎のお寺、鐘撞き堂はあっても鐘は下がっていませんでした。
夏休みなどに、子どもたちが揃って帰省し、父を囲んで墓参り。そんな時父の一つ話が始まります。「まだ鐘があった頃、男の子を連れて墓参り、子どもたちは撞きたがった、撞け撞けと許したんじゃ。もっと前には自由につけたもんじゃったからの。ところがその頃は、この鐘は、村の非常事態を知らせる音になっちょったんよ。大叱られしたもんじゃ」。反省するというより自慢げでありました。
や〰まのお寺の鐘が鳴る♪♪夕焼けの色とともに思い浮かぶ日本人の原風景ですね。


















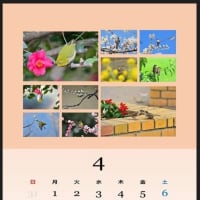


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます