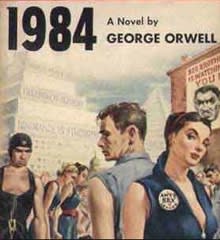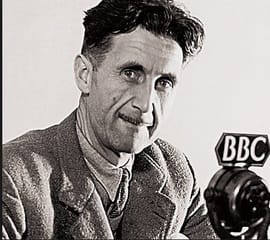書評「転生の秘密」ジナ・サーミナラ著 多賀 瑛訳 たま出版1985
1945年に世を去り、ケーシー療法として前世療法やリーディングによる不治の病に対する治療を行ったエドガー・ケーシーについての判り易い解説本です。執筆されたのは1950年であり、翻訳は1980年台なので内容的にはやや古いものですが、医学的なことではなく、「生きる意味」などについての本と考えると何ら古い内容ではないと言えます。
エドガー・ケーシー本人は平凡な人で種々の理論を確立したような教祖的な存在ではありません。本人の難治の病気をひょんなきっかけで催眠状態により解決法が判ったことから他人の難治の病気も自分が催眠状態になれば解決法が見つかるかもしれないと考えて試してみたら大成功、何千人という人達の病気を治す(治すといっても特定の場所をマッサージしたり、生活の習慣を変えたり、暗示をかけたりという方法ですが)ことにつながったということです。西洋医学的には全く受け入れられませんが、西洋医学自体が急性期疾患しか治せないのですし、科学的に原因がわからない病態も沢山あるので「病気を治す」という事が結果として行われたのであればそれは真実として考えるべきだと思います。
ケーシーについてのもう一つの特技は人の前世を見ることができるということです。病気の本態を視通すという行為を「フィジカルリーディング」と呼ぶならば、この前世の記憶を視通す行為を「ライフリーディング」と言って区別します。説明や記述によると、この前世を見るという行為は別にケーシーがとんでもない過去に行ってその人の行いを見てくるというのではなく、何回かの前世における人生でその人に無意識の中に記憶として残っている部分を抽出して読み出すということのようです。幼児の時の記憶は全て覚えている訳ではありません。しかし強烈な記憶や感情はその後の人生や行動にずっと影響を与える可能性があることは精神医学的にもよく知られています。人は魂として何回か生まれ変わっていて、新たに生まれた時には前世の記憶も持っているのですが、その後今生の記憶が積み重なるにつれて幼い時の記憶同様忘れ去られてゆくものの、前世における強い記憶や感情は今生における行動にも影響を与えている、というのが前世療法における基本になります。
輪廻転生が古今東西において伝承や宗教などの概念に取り入れられている事、前のブログで紹介したようにほぼ科学的に前世を覚えているという幼児が述べていることが事実であることが確認できる場合が多いことからも、私は輪廻転生というのは真実だろうと思います。歴史の浅いキリスト教やユダヤ教の教義で認められていないこと、霊魂の存在を科学では証明できないことから認めない人も多いと思いますが、日本人の心情では抵抗なく受け入れている人が多いように感じます。私は前世療法といったものを全面的に受け入れる気はありませんが、輪廻転生があるという前提で人生の生き方を考えてゆくことは大事だろうと思います。
この本で疑問に感ずるのは、フィジカルリーディングの場合、「ここが悪い」「こうやったら治る」とケーシーに知らせているのはいったい誰なのだろう、という疑問です。ライフリーディングにおいても数ある前世の記憶のなかから、現在のこの人がかかえる問題の原因になっているのはこれです、とケーシーに教えているのは誰なのか、についてこの本は教えてくれません(おそらく誰もわからない)。患者本人を催眠術にかけて、無意識の中に埋没している記憶について語らせるならばまだ理解できますが、他人であるケーシーがそれを語るためには、それを選択させる第三者(患者の守護霊とか)が必要だと思います。また語られる内容は必ず「現在の種々の状態は過去からの因果に基づく」としてかなり勧善懲悪的な教訓的内容になっています。人間にとっての「善」は時代とともに変化してゆくと思われますが、今現在の「善し」とする価値基準でそれを判断しても良いものなのかどうか(勿論時代を超えて善悪が変わらないことも一杯ありますが)も疑問に思うところです。
私にとって米国式の輪廻転生理論で共感できるところは、人生の意義を悪い状態であっても積極的に解釈して魂のステージを上げることに役立てようという発想です。また老いても人生の終わりではなく、次の人生の記憶や人生を超えて積み重ねられた技術(音楽や芸術など)に次に生まれ変わる際につながるのだから無駄な人生の時間などない、という思想です。死ぬまで人生現役という考え方は意義ある人生を送るうえで非常に大事であり、罪を犯してしまった人も死ぬまで魂のステージをあげるために今生でできることをやり続けることが大切であるという思想は尊重されるべきだと思います。不昧因果とは因果をおろそかにせず、ひとつひとつ丁寧に対応しなさい、不落因果とは因果に囚われて物事を諦めてはいけないと解釈していますが、これらの仏教用語も実はケーシー的な人生の捉え方に合致しているようです。その意味でも目先の利益を追い続けて十分稼いだら後は人生遊んで暮らすなどという現在の拝金資本主義の思想は屑であり、誤りであるとつくづく思います。