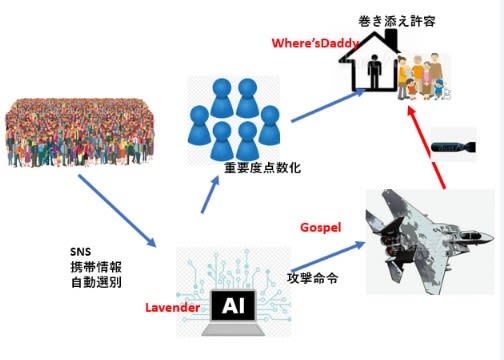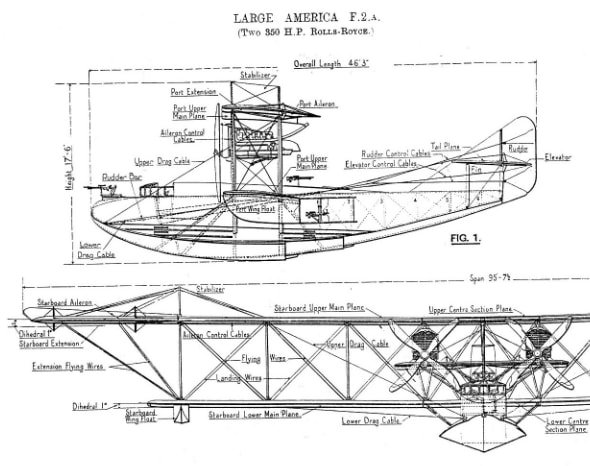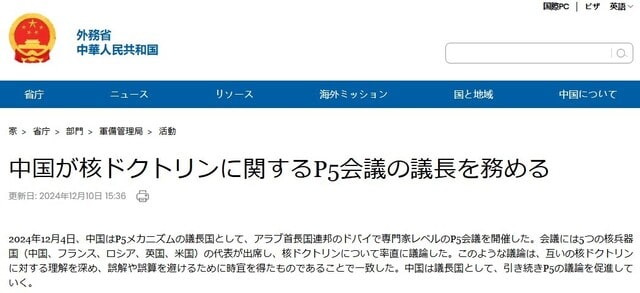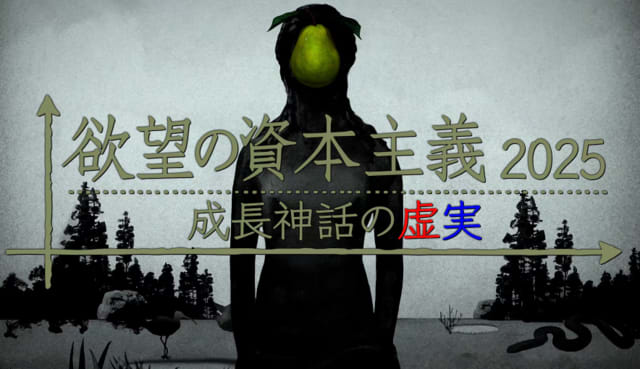中居正広氏の女性問題から派生したフジテレビバッシングは、局の執行部退陣のみならず存続まで危ぶまれる事態になりました。しかし混乱の文春が報じた元情報である「フジテレビ幹部のA氏が食事会をセットしてドタキャンすることで中居氏と女性のみが残る設定をした」が全く偽情報であったことが明らかとなると、10時間に及ぶ「吊し上げ中継会見が必要なモノだったのか?」を含めて出席していたジャーナリスト全員が情報の確認(ファクトチェック)さえせずに責任追及をしていた事が露呈してしまいました。正にフジから広告撤退した空き時間に放映されている「ACジャパン、決めつけ刑事」(嶋田久作氏出演、ハイ人生終了!というキャンセルカルチャー問題も盛り込まれている)の実写版が繰り広げられるという大型バラエティになってしまいました。しかも会見が長引いて中止になったものの記者会見後の番組が「全国女子アナ選手権」的な特番が予定されていたというから完璧です。


ACジャパンの傑作 決めつけ刑事
ヒトも組織も「良い点」「悪い点」があるのは言わば社会の常識に当たるモノですが、一部の悪い点をあげつらう事で対象の存在全てを否定する「キャンセルカルチャー」の流行は社会の幼稚化を表す現象です。上記決めつけ刑事の「ハイ、人生終了!」のセリフに象徴される批判される内容の意義付けや改善の機会などを考慮せずに「全否定」というのは善悪二元論に基づくものであり、携帯という小さい情報提供メディアで結論だけを得る事に慣れた現代人の知性劣化を物語るものでしょう。
〇 失敗を社会全体の改善につなげる根本原因分析

Root cause analysisの手法 Fishbone diagram
東京大学名誉教授の石川馨氏は、世界の見本となった日本のQCサークルの生みの親とも言われて、品質管理の向上に多用される根本原因分析(Root cause analysis)を1960年台に築き、それが世界中で建設、航空、医療などの安全管理にも応用されています。To err is human「ヒトは誰でも間違いを犯す」という前提で、個人の責任を問う事はせずに、間違いを犯しても大事に至らないシステムを作るFail safeとかFool proofといった改善が社会の安全に繋がるという思想が大事にされています。ブレーキが自然にかかるとか、逆の接続は端子自体がつながらない仕組みになっているといった事で至る所で応用されています。個人の責任を問わない文化が伸びた一方で「一事を持って全否定につなげるキャンセルカルチャー」が何故全盛になってきたかは主に政治的社会的理由が背景にありそうです。
〇 司法の政治利用 娯楽としての公開裁判(炎上)


キャンセルカルチャーは善悪二元論による全否定と安易な娯楽としての公開裁判の意味を持つ
巨大資本でメディアと米国民主党を牛耳るグローバリスト権力層にとって、米国をグローバリズムの中心ではなく、多極化を認め、米国を極の一つとして再構築しようとするトランプ大統領は「政治生命を消したい対象」でしかありませんでした。2020年選挙時の「議事堂襲撃扇動問題」や「機密書類持ち出し」、「ロシア疑惑」、果ては「ポルノ女優口止め料問題」と数々の無理筋提訴でトランプ氏の政治生命を絶つ事をグローバル陣営は試みましたが結局失敗、暗殺も2回試みて失敗し結局トランプ氏は大統領に返り咲きました。CNNのファリード・ザカリアはハリスの敗因の一つが「司法の武器化」に米国市民が拒否反応を示した事だと明確に評しましたが、こういった指摘は日本のメディアで聞いたことがありません。「トランプはレイシスト」「トランプはヒトラーと同じファシスト」「分断を煽る」などという「社会正義に反する」という印象操作による政敵排除を目的としたキャンセルカルチャー発動をメディアは繰り返してきましたが結局失敗に終わっています。
日本のメディアも同様の印象操作を繰り返してきましたが、「社会正義に反する」と規定した「芸能人」や「贅沢な立場にある者」を公開の場で吊るし上げる「公開裁判」は日本のメディアにとって「金のかからないバラエティ」としてワイドショーの時間つぶしにこの10年以上使われてきたネタと言えるでしょう。今回のフジテレビの一件はその「悪しき集大成」と言えるように思います。メディア全体が「安易な自らの在り方」を真剣に反省し、新たな「ジャーナリズムの規範」を作って立ち直れるか否かに既存メディア再生存続の可能性が問われていると私は思います。