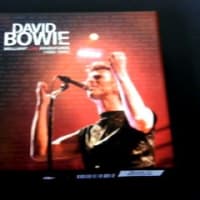三嶋大社
中世伊豆国の一宮であり、頼朝旗揚げ成功以来、武門武将の崇敬が篤かった。

源頼朝・北条政子 腰掛石
「治承4年(1180年)5月平家追討の心願を込めて百日の日参をした折、腰を掛けて休息した」

宝物館
太刀 銘 平安城藤原則定作之他
江戸時代初期、山城の刀工・則定の作。
寛永十四年(1637)二月、将軍・徳川家光により奉納された。
三島千句 宗祇作
文明三年(1471)宗祇は三島にて東常縁より古今和歌集の講釈を受けている。その頃常縁の子・竹一丸が風邪を患い、宗祇はその平癒を祈り三嶋明神に発句を捧げたところ快方に向かったので祈願成就のお礼に独吟千句を奉納した。この千句には関東を転戦していた東常縁の戦勝祈願の意味も込められていたとの説もある。
新三島千句(出陣千句) 宗長作
永正元年(1504)9月今川氏親と北条早雲は扇谷上杉朝良に加勢し武蔵国立河原にて山内上杉顕定・足利政氏連合軍と戦い勝利した。この千句連歌は今川氏親の戦勝報賽として宗長が独吟し三嶋明神に奉納されたもの。今川氏に仕える宗長の役割の一端が窺える。
宗長・宗碩両吟百韻連歌懐紙
大永二年(1522)八月宗長・宗碩により伊勢神宮奉納の千句連歌が詠まれた(伊勢千句)。これはその一部(第三百韻)で発句は宗碩。
伊勢千句は管領細川高国が一時都を追われ近江に逃亡、政権奪回を願い後に叶った事から伊勢神宮に千句連歌の奉納を思い立ち宗長に依頼、宗長も大徳寺真珠庵の傍らに住んでいた修行時代に高国の世話を受けていた事からそれを引き受けたもの。
高齢であった宗長は独吟を不安に思い同門の宗碩との両吟となった。ちなみに第一百韻の発句は細川高国、巻軸の発句(第十百韻)は三条西実隆の作。
この他にも後水尾院和歌懐紙、烏丸光広詠草、北条早雲判物など拝見できました。