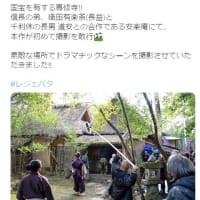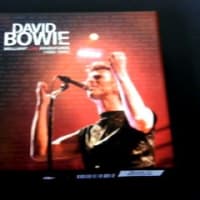石水博物館

企画展「津観音大宝院の歴史と美術」
期間:3/13(金)~5/17(日)
「「津の観音さん」と親しまれ、古くより多くの信仰を集めてきた津観音(恵日山観音寺)大宝院は、津市大門にある真言宗の古刹です。津観音の歴史は和銅2年(709)にまで遡ると伝わり、1300年もの間庶民の心のよりどころとしてあり続けてきました。大宝院はその本坊で、文安元年(1444)に開創し、長い歴史とともに貴重な文化財が、歴代院家によって引き継がれてきました。本展では、近年三重県および津市の文化財指定を受けた寺宝を中心に、同寺に伝わった貴重な密教美術をはじめ、地元津に関係が深い歴史資料、近世絵画や工芸、茶道具などを公開します。」(公式より)

羽柴秀吉書状
大宝坊宛、六月十二日付。天正12年(1584)小牧・長久手の戦いの最中、秀吉の陣中に見舞いの品を届けた大宝坊への礼状。
白衣観音像 狩野探幽筆
岩の上に悠然と座る観音の姿を描いた作品。背景には大きな円光のみを表し瀟洒な表現となっている。
「法印探幽行年六十七歳筆」の落款がある事から寛文8年(1663)の作と分かる。
探幽は狩野永徳の次男・孝信の子で母親は佐々成政の娘と伝わる。探幽は茶の湯とも関係が深く大名物の種村肩衝を所持しており、茶釜の下絵を手掛けている。
千利休書状
松井友閑宛、十月廿一日付。堺代官・松井友閑に宛てた手紙。内容は大墨屋が虚堂墨蹟を持ってきた事。立村の井戸茶碗は未だ見ていない事。暇がなく伺えないが忘れてはいませんと伝えている。
古田織部書状
横浜一庵宛、六月一日付。横浜一庵より直衣を貰った事への礼状。
横浜一庵は豊臣秀長の家臣。娘のひとりが小堀遠州の父で同じく豊臣秀長の家臣であった小堀正次の側室になっている。一庵は慶長元年(1596)の大地震で亡くなっているので、この書状はそれ以前のもの。
石水博物館は川喜田半泥子の作品を収蔵・展示していますが、現在は巡回展の最中。なので津観音大宝院の宝物の展示となったのでしょうか。展示室はあまり広くないので、次回機会があれば津観音に行って他の宝物も拝見してみたいと思いました。