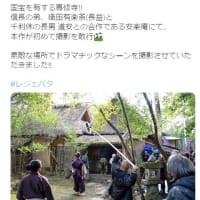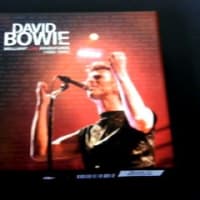最初はここ

小山市立博物館
1983年開館。

企画展 「戦国の装い」
期間:6月4日(土)~7月18日(月)
「室町時代から江戸時代初期にかけての足軽胴や甲冑などを展示する」
(*所用者は博物館の表記による)
森蘭丸所用 金箔押色々威伊予札胴丸具足
阿古陀形兜に「南無阿弥陀仏」の前立。
ある意味で有名な甲冑。一度は観ておきたかったものだ。
小幡信貞所用 黒漆塗二枚仏胴具足
前立は銀箔押しの天衝。胴には金箔で六柏葉紋が描かれている。
ちなみに小幡の家紋は軍配団扇紋で六柏葉紋ではないそう。
小幡信貞(信真とも)は武田家家臣として赤備えの軍勢率いていた。
小幡信貞所用 赤羅紗地陣羽織
上記の具足に添う品。赤羅紗に白の六柏葉紋が縫いつけられている。
稲葉貞通所用 黒漆塗三十二間筋兜
大鍬形の脇立。貞通が関ヶ原の戦いで使用したと伝わる。
稲葉貞通は稲葉一鉄の子で信長・秀吉に仕える。関ヶ原合戦後に臼杵藩主となり、明治維新まで稲葉家が治めた。
北条氏康所用 十二間筋兜
並角元があるが立物は無い。吹返に北条家の家紋・三鱗紋がつく。
九鬼嘉隆所用 旗印
紺絹地に金泥で「あら波」の文字。
水軍だけに荒波とは良く考えられています。
黒漆塗胸取藍韋威二枚仏胴具足
なんと胴まわりが132cmもある巨大具足。
この時代の人物としては破格の大男が着けていたようです。