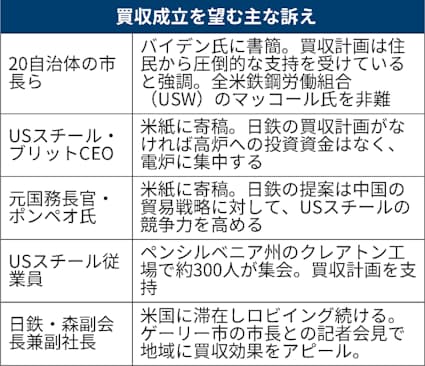日本のエネルギー自給率はたった15%だ。電力の安定供給はかねて国家の生命線だが、同時に脱炭素との両立が世界的な課題になった。
経済成長も求められている。安全保障、産業競争力に目配りしつつ地球温暖化対策を着実に進める方策について、国際エネルギー機関(IEA)の元事務局長、田中伸男氏に聞いた。
原子力の新ビジョン示せ
日本の貿易は昨年、化石燃料の赤字額が26兆円になった。自動車や機械の輸出で稼いだ黒字のほとんどが帳消しになる勘定だ。
――燃料輸入による国富の流出をどう食い止めるか。
「国富の流出は輸入している限り続く。といってエネルギーがないと経済も生活も成り立たない。
第1次石油危機以来、日本がしてきた重要なことの一つに省エネがある。
もう一つは石油やガスや石炭に代えて国内でつくれる再生可能エネルギーだ。太陽光、風力、地熱をいかに安く大量に使えるようにするかという政策が重要だ」
「大きいのが原子力だ。新たに原子力発電所を建てるのはコストがかかるが、既存の原子炉でつくるエネルギーは安い。米国では事故後に閉鎖されたスリーマイル島原発を再稼働し、マイクロソフトに電力を供給しようとしている」
「日本も原発再稼働へ政府が努力しているが、うまくいっていない。持続可能な原子力の活用策を打ち出さないといけない
。地震で万が一事故が起きても影響がそこまで大きく及ばない小型炉や、核のごみを減らしていく方法などを考え、原子力の新しいビジョンを打ち出さないと、国民は再稼働しても結構だとは言わないかもしれない」
「新しいエネルギーの技術や使い方を日本から海外に売れれば、逆に国富を増やすことになる。大きな絵で日本のエネルギー政策を変えていくことが必要だ」

「日本には非常に大きなチャンスがある」と語る
――自然災害が多く原発事故も経験した日本で原発への慎重論は強い。
「原子力と発言すると票が減ってしまうので(政治家が)言いたくない気持ちはよく分かる。
しかし言わないと、政府が目指す2050年までのネットゼロ(温暖化ガスの実質排出ゼロ)はできない。大きな変革をしないと脱炭素は無理だ。知恵もイノベーションも技術も持つ日本は非常に大きなチャンスがある」
「核のごみの放射能レベル低減にかかる時間を高速炉で300年に短縮できるという議論がある。
核のごみの処理もできると政府がきちんと説明することで、国民は納得できるのではないか」
――欧州など海外ではエネルギー政策が政治主導で大胆に変わる。
「日本は9つの電力会社が安定した電源を供給し、戦後の経済成長に成功した。
大型の発電所から供給するモデルは、地域分散型の風力や太陽光などを大量に使うとなるとうまくいかない。そのゆがみが起こっている」
「欧州ではドイツが最大の切り替えを実行した。原子力をやめ、風力や太陽光を増やすために分散型システムにした。
足りない電源はフランスの原子力や北欧の水力から調達した」
「メルケル独首相(当時)になぜ原子力を使わないのか尋ねると『私は科学者で原子力の重要性をよく知っている。
しかしそれを使うには票が必要だ』と答えていた。メルケル氏は国民がどう言っているかに敏感に反応しながら政策を変えた。もっとも、ロシアの天然ガスに依存したことで今の危機(ウクライナ侵略による供給不安)を招いた反省は必要だろう」
「エネルギー安全保障は重要だ。政治家がよく理解してやらなければいけない。
変化、競争を起こしながら安定供給する、風力、太陽光、原子力もうまく使っていくシステムが日本に求められている。今が絶好のチャンスという気がしている」
ガソリン補助金を水素に
政府は次期エネルギー基本計画を年度内に決める。電源構成の目標や脱炭素のシナリオは産業界にも大きく影響する。
――脱炭素電源は産業競争力を左右する。足りないと日本企業の足かせになる。
「日本の産業がよりグリーンにならないと、製品が海外に売れなくなる。
米アップルは全製品を2030年までにカーボンニュートラルにするとし、供給企業にも呼び掛けている。独メルセデス・ベンツグループも、39年までに供給網全体でカーボンニュートラルにすると表明した」
「日本企業もそうしないと世界のマーケットに入っていけない。国内にグリーンな電源がないと海外に生産を移すことになりかねない。
日本で風力、太陽光、原子力で安い電力をつくっていかないと産業が逃げていく」
「二酸化炭素(CO2)を回収して地下に埋める『CCS』ができる場所、クリーンな電気がある場所に産業は移っていく。
電力消費の多い半導体製造や、脱炭素へ高炉から電炉に転換する鉄鋼業が典型だ。過去に日本の電力コスト上昇でアルミニウム製錬業はすべて海外に出た。同じことが起こる可能性は十分ある」

――次期エネルギー基本計画で考えるべき変数は多い。電力需要が人工知能(AI)の普及で増える一方、再生エネのコストは高止まりしている。
「2050年のネットゼロは大前提だ。そのために何が必要か、逆算して政策を考えるべきだ。再生エネを分散型で増やすと同時に、原子力活用のビジョンを示す。
政府が議論中のカーボンプライシングでは、将来のCO2の値段を示す必要がある。さもないと本格的な投資が起こらない」
「半世紀前に日本が液化天然ガス(LNG)を輸入したとき、高くてできるはずがないといわれた。できたのは(コストから料金水準をはじく)総括原価方式だったからだ。
今の自由化された市場ではなかなかできない。水素供給の新プロジェクトについて(既存燃料との)価格差を支援するとしているが、一つ二つだけやっても意味が乏しい。増やすには財源が全く足りない」
「財源の議論は政治が担わなければならない。ひとつの財源は、電気やガソリンにかけている補助金をやめることだ。
CO2の値段を上げていくときに、値下げする補助金は全くナンセンスだ。その数兆円を水素の補助金に回すとはっきりさせないと、水素経済はなかなか立ち上がらない」

日米韓の原子力協力を訴える
――トランプ次期米大統領は化石燃料の増産を打ち出し、脱炭素が減速する懸念が強い。日本は巧みな協調が必要だ。
「トランプ政権は国連気候変動枠組み条約から再離脱するだろう。化石燃料を復活させるとも主張している。
日本は天然ガスを脱炭素の移行期の燃料としてうまく使い、投資する必要がある。天然ガスの利用をトランプ氏と一緒にやるのは面白い。共和党の地盤でもあるアラスカ州の天然ガスの開発や輸入で協力していくのは十分あり得る」
「米国と一緒にできる大きな柱の一つは原子力だ。トランプ氏はもともと原子力好き。日本は韓国と組んで米国と原子力で協力してはどうか。
日本とエネルギー構造のよく似た韓国は小型炉に特化すると決め、売り出そうとしている。福島の核のごみの処理などで日米韓が協力するのは十分ありうるオプションだ。小型炉のビジョンを日米韓でつくるのは地政学的にも面白い」
たなか・のぶお 1950年生まれ。東大経卒、73年通商産業省(現経済産業省)入省。通商機構部長などを経て2007〜11年に国際エネルギー機関(IEA)事務局長。笹川平和財団理事長などを務め、現在タナカグローバル最高経営責任者(CEO)。
脱炭素を脱皮のバネに(インタビュアーから)
化石燃料高は日本のアキレス腱(けん)を再認識させた。輸入に巨額を費やし、国際情勢に揺さぶられるもろさを抱えたままだ。
再生可能エネルギーへの移行は弱点を克服する手掛かりになる。これに逆行するガソリン補助金を「ナンセンス」と断じた田中氏の指摘は重要だ。ゆがんだ資源配分を続ける余裕はないはずだ。
脱炭素は今や個々の企業にとって差し迫った要請になった。電化がもたらす変化にも取り残されてはならない。
欧州やアジアの一部では越境売電が活発になり、石油やガスに恵まれない国であっても発電と送電網の力で優位に立つ時代が来た。
環境変化を逆手にとって劣勢をはね返す道を探りたい。半世紀前、石油危機に苦しんだ日本は省エネを磨き原発を活用して、資源が乏しくても繁栄するモデルをつくってみせた。難題だらけの今も脱皮の好機だ。
(編集委員 久門武史)
写真 宮口穣 映像 小倉広志
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5642963019112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=426&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=3e8def7a36446d43db8be818f160f62a 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5642963019112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=852&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=49a008ddf0f34ef0e4b8d92eba630eda 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5642963019112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=426&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=3e8def7a36446d43db8be818f160f62a 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5642963019112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=852&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=49a008ddf0f34ef0e4b8d92eba630eda 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5642963019112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=400&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=dd6f45b33acf37174e3a832cc8984b98 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5642963019112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=801&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=2f7240f711d21f0320847b55f32490ca 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5642963019112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=400&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=dd6f45b33acf37174e3a832cc8984b98 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5642963019112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=801&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=2f7240f711d21f0320847b55f32490ca 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5642963019112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=400&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=dd6f45b33acf37174e3a832cc8984b98 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5642963019112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=801&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=2f7240f711d21f0320847b55f32490ca 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>