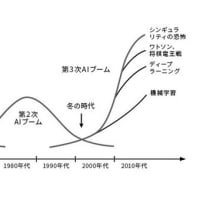この記事の3つのポイント
- 文科省は半世紀ぶりに教員給与を引き上げる方針を固めた
- ただし残業は規制されないままで、若手教員への恩恵は少ない
- 若手教員が精神疾患で休職する割合も増えている
ついに教員にも賃上げの波――。8月下旬、残業代の代わりとして上乗せされる「教職調整額」の割合を、文部科学省が基本給月額の4%から13%へ引き上げる方針を固めたことがわかった。
公立学校の教員給与システムを定める「教職員給与特別措置法(給特法)」の改正案を2025年の通常国会に提出する。法案が成立すれば、約半世紀ぶりの大きな変更となる。
ただし現場の教員は厳しい視線を向ける。
教員の長時間労働改善に向け活動をしてきた岐阜県立高校の西村祐二教諭らは、8月下旬の記者会見で「教員の手取りを増やす文科省の努力は腐したくない 」とした上で、残業時間数に応じた手当てが支払われない現行の仕組みを変えなければ「意味がない」(西村教諭)と批判した。
教育社会学を専門とする早稲田大学の菊地栄治教授も「残業時間が実質的に規制されない点で、根本的に誤っている」と指摘する。

4月に会見で「教職調整額」について話す西村教諭(写真=共同通信)
海外を見ても圧倒的な長時間労働
教員の長時間労働は深刻だ。文科省の22年度の調査によると、残業時間が国の過労死ラインである月80時間を超える教員の割合は、小学校で約14%、中学校で約37%に上った。
ちなみに、全日本教職員組合(全教)が22年に全国の教諭など2000人以上に行った調査では、持ち帰り業務にかかる時間も含めると、過労死ラインを大幅に超過する約96時間の残業が平均となっていることがわかった。
海外と比べても圧倒的な長時間労働だ。経済協力開発機構(OECD)が18年に各国の教員にアンケートした結果によると、週当たりの勤務時間は小中学校ともに、日本が調査した国の中で最長となった。特に中学校教員は48カ国・地域の平均と比べて約18時間も多かった。
その背景には、教員は一部の業務を除き、時間外の勤務は「自主的・自発的な活動」と見なされ、労働時間に含まれないという点がある。民間企業は労使間で結ぶ「36協定」で時間外労働の上限が定められるが、教員はたとえ過労死ラインを超えて働いていても自己責任となる。
仕組み上、現場の管理職が部下である教員の勤務外労働の実態を把握する必要性も低い。
教員の働き方が他の公務員と比べて働き方が特殊で、勤務時間管理がなじまないという考え方が、教員の給与システムを定める給特法のベースにある。こういった給特法のあり方が、教育現場の負荷軽減を阻む。
今回文科省は、半世紀ぶりの改正により教職調整額の引き上げ方針を固めたが、勤務時間に応じた残業代を支払わない枠組みは維持した。
結局、教員の残業時間は実質的には規制されないままであり、長時間労働の根本解決には至っていない。
西村教諭とともに会見に出席した川崎市立小学校の齋賀裕輝教諭は「聖職だから残業代が支払われなくて当然と考える教員は皆無だろう。
やらなくてはならない仕事で残業をしているのに、なぜきちんとした対価が払われないのか」と投げかけた。
若い教員にしわ寄せ
中でも昨今、特に現場で疲弊しているのが若手の教員だ。そもそも、今回の教職調整額の引き上げは、基本給月額が低い若手教員にはメリットが小さい。

業務の負荷も重い。文部科学省の22年度の調査によると、男女ともに、30歳以下の教員の平日1日当たりの勤務時間は全年代で最も長い。
20代の教員が精神疾患で休職する割合は、22年度に0.84%となり、15年前の2倍以上に増えている。
早稲田大学の菊地教授は「若手教員の育成を支える余裕を学校が失ってしまっている。
教職の重要な社会的価値に応じた政策的配慮を怠ってきた証し」と分析する。19年には、小学校の24歳新任教員が教室で自ら命を絶った。
時間外労働が月100時間を超える月が2カ月続き、職場内では厳しい𠮟責を受けていたとされる。
教員は1年目から「先生」と呼ばれ、担任学級を受け持つなど独り立ちを求められる。
そんな中で、立場上、色々な業務を断れずに抱え込んでしまうリスクが高い。

小中連携や保護者への対応、ICT(情報通信技術) を活用する授業など、教員に求められるスキルや業務範囲は年々「足し算」(早稲田大学・菊地教授)されてきた。
時代とともに増えた教員の負荷をどう軽減するのか、学校現場だけの問題ではなくなりつつある。
岐阜県立高校の西村教諭は、「例えばICT教育では、教員が専用端末の使い方を一から勉強しなくてはならない。
それなら外部からエンジニアなど専門家に来てもらう形をとれば、子供たちはより詳しいことを学べて、私たちも授業の準備に時間を充てられる」と話す。
教員は次世代の育成を担う上で不可欠な職種だ。国として、企業として長期的な成長を目指す上でも、日本の教員の働き方を社会全体で再考する時期が来ている。