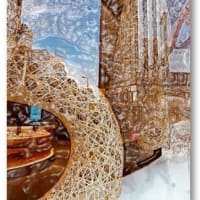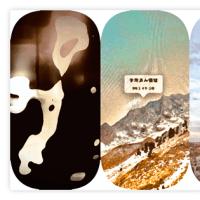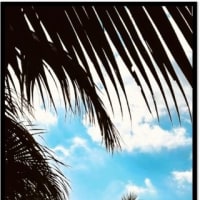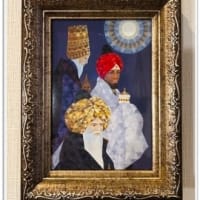「音楽にオリジナリティを求めて」/キリシャラブ『商品』とYackle『FRANK THROW』を聴いてみました。若いアーティストなので、常軌を逸した鳥肌の立つようなことしてくれてるかな、全く触れたことのない音世界を見せてくれるかな、という期待感がありましたが、特になく、残念でした。(因みに、ベテランだからいいとか、若いからダメとかいう偏見はないです。念の為。)/オルタナティブな音楽を作るバンドって、立ち位置が本当に難しい。/これまでにないテクを持つギタリストだとか、抜群に個性的な声を持つヴォーカリストというのは、今後とも現れると思いますが、楽曲創作に関しては、多岐にわたるジャンルの音楽を聴き込み、ある程度、過去にも遡って渉猟しなくては、特定のバンドやアーティストに似てしまうのがオチです。UVERworld、ワンオク、アジカンやくるり、はたまたはっぴいえんどのどれかに似るか、あるいはそれらを軽く混ぜ合わせたものになってしまう。/「自分たちは純粋な気持ちで、オリジナルを書いている」と意気込んでみても、既存の膨大な「音楽文化遺産」のまえでは高が知れてしまう。「無意識に」聴いてきた音楽って、どうしてもどこかで自然と耳に入ってくるある時期のヒット曲や、カラオケでみんなが歌う曲が中心になってしまうので、とかく範囲が狭くなりがち。/J-POP以外の内外の音楽を普段からよく聴いているひとであれば、J-POPの狭さや偏りも見えているはずです。/ではどうすればいいのか。様々なジャンルの音楽間の透き間や融合を狙うことを意識することが大事だと思います。似たようなバンド間の差異ではなく、異なるジャンル間の透き間を研究することです。/これと同じことを考えているジャンルレス、ボーダレスなアーティストは日本を含め、世界に少なからずいるわけですが、そういうアーティストを自ら探し出し聴き倒すこと。安心印の音楽ではなく、巷ではめったに耳にしない、カラオケのソングリストにも存在しない、違和感のある音楽を求め続けること、それが楽曲のオリジナリティの萌芽になるのではないかな。/BGB:『共感障害:「話が通じない」の正体』(黒川伊保子著、新潮社、2019年)