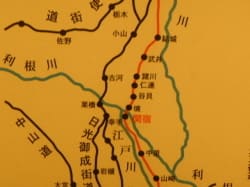有楽町駅前にある交通会館に用事があり行った。
この地下には、チャンポンで有名な“桃園”があり、
食べたかったが、
夕方から、1店1品会といって、
1店でその店の一番うまいものを食する食べ歩きの会を行うので断念せざるを得なかった。
今回は、神田“きくかわ”のうなぎと“まつや”の日本ソバのコースを予定していた。
そのあとは、神田錦町の“エブラック”で酒を飲む。
待ち時間の間に、
オープンになって1週間が経過した有楽町イトシアを観察した。

開店後の風景 工事中の風景


駅前から、イトシア及びその先の銀座プランタン方面に向かって
ヒトがあふれており、かつてないほどの賑わいとなっていた。
あまりヒトがいない交通会館まで恩恵を受けており、
イトシア効果は間違いなくありそうだ。
有楽町イトシアの建物構造を簡単に紹介すると
2つの建物があり1つは丸井(〇1〇1)
もう一つが性格がよくわからなかったイトシアプラザ。
この地下にフードアベニューがある。
丸井(〇1〇1)にはヒトがあふれていたが、5階までのレディーズフロアーまでであり、
6~7階のメンズフロアーはすいていた、
品揃えは、松屋対抗の銀座ではなく、原宿の表参道ヒルズに近そうだが
ややカジュアルだろうか?
丸井(〇1〇1)のこれまでからみて、いい店作りだと思う。
ただし、客層が六本木型のオミズ系と下町のおばちゃん風が混在しており、
主力の有楽町を利用する堅実なOLとの3層構造で
これからが決まるだろうが、
イトシアだけでは
これから持たないのではないかと思った。
理由は、熱海を作ってしまった。ということだろうか。
館内に全ての機能を取り込み、街を作らなかったために熱海は飽きられてしまった。
表参道ヒルズは、小道と個店が多い原宿・表参道という基盤の上に
さらにヒルズの中にストーリー・ロードを持ち込んだ。
有楽町は、駅前に汚い個店が集積していて、人間臭い魅力を放っていたが
この個店をゴミとして取り払い、巨大なビルというゴミ集積所を作ってしまった。
いわば無味乾燥で、どこにでもある街を作ってしまった感がある。
唯一、丸井(〇1〇1)とイトシアプラザとの間の小道に
甘味処“おかめ”が道から入れるように健在だったのでホッとした。
日比谷・丸の内を含めて、30分歩ける街づくりが必要かなと思った。
クリスピィ・クリーム・ドーナッツが話題のトップであることが端的に
未来を暗示しているような気がする。
これは私だけの印象だろうか?
クリスピィ・クリーム・ドーナッツ 甘味処 おかめ


一店一品会は、
待ち合わせの神田“きくかわ”が電気工事での臨時休業のため、
急遽、あんこう鍋の“いせ源”からスタートすることになった。
鍋の後は、雑炊を食べたかったが、“まつや”のソバが待っているので断念。
分を知るというか、欲望をセーブするというか、
思いを断念することは大切な経験だ。
たかが食だが・・・・・・・。