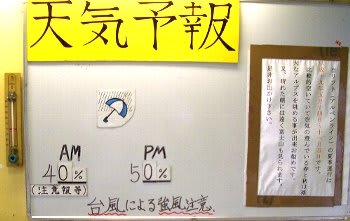信州からの帰途は、松本に出て高山に出る。そこから「せせらぎ街道」とも呼ばれる「郡上街道」を走ることが多い。途中明宝村を通過する。そこには岩魚を焼いてる道の駅がある。
明宝村は、かの宇治川の合戦で先陣争いをした源氏の武将の一人が騎乗した名馬「磨墨(するすみ)」の生まれた村である。
道の駅の駐車場には、馬上の梶原源太景季(かげすえ)とともに名馬のモニュメントが立っている。生まれた場所はここから3kmほど山中で立派な墓がある。
ちなみに相手の名馬「生月(いけづき)」は四国の生まれである。(先陣争いにまつわる話は、またの機会にします)
磨墨は先陣争いには勝てなかったのである。

400番台の国道とはいえ、いい道で、しかも信号がないので快適に走る。

もう夕方で閉店をしてもよい時間で、誰も客はいない。店に立ち寄ると、おばあさんがまだ、せっせと岩魚を焼いている。

囲炉裏の四隅のコーナーには、板で火からの仕切りをした影に串刺しが沢山立っている。

さすがに火は落としかけである。この残った岩魚はどうするのかと尋ねると、骨酒用にするのだと言う。あまり喋らない人だった。昔はおじいさんが焼いていたのだが・・。

囲炉裏の屋根裏を見上げると、煤で真っ黒に輝いている。蓑笠までが黒くなったままである。

この炭素で黒くなって光るのを見ていると、ダイヤモンドは炭素で出来ているのが判る気もする。(笑)

明宝村は、かの宇治川の合戦で先陣争いをした源氏の武将の一人が騎乗した名馬「磨墨(するすみ)」の生まれた村である。
道の駅の駐車場には、馬上の梶原源太景季(かげすえ)とともに名馬のモニュメントが立っている。生まれた場所はここから3kmほど山中で立派な墓がある。
ちなみに相手の名馬「生月(いけづき)」は四国の生まれである。(先陣争いにまつわる話は、またの機会にします)
磨墨は先陣争いには勝てなかったのである。

400番台の国道とはいえ、いい道で、しかも信号がないので快適に走る。

もう夕方で閉店をしてもよい時間で、誰も客はいない。店に立ち寄ると、おばあさんがまだ、せっせと岩魚を焼いている。

囲炉裏の四隅のコーナーには、板で火からの仕切りをした影に串刺しが沢山立っている。

さすがに火は落としかけである。この残った岩魚はどうするのかと尋ねると、骨酒用にするのだと言う。あまり喋らない人だった。昔はおじいさんが焼いていたのだが・・。

囲炉裏の屋根裏を見上げると、煤で真っ黒に輝いている。蓑笠までが黒くなったままである。

この炭素で黒くなって光るのを見ていると、ダイヤモンドは炭素で出来ているのが判る気もする。(笑)