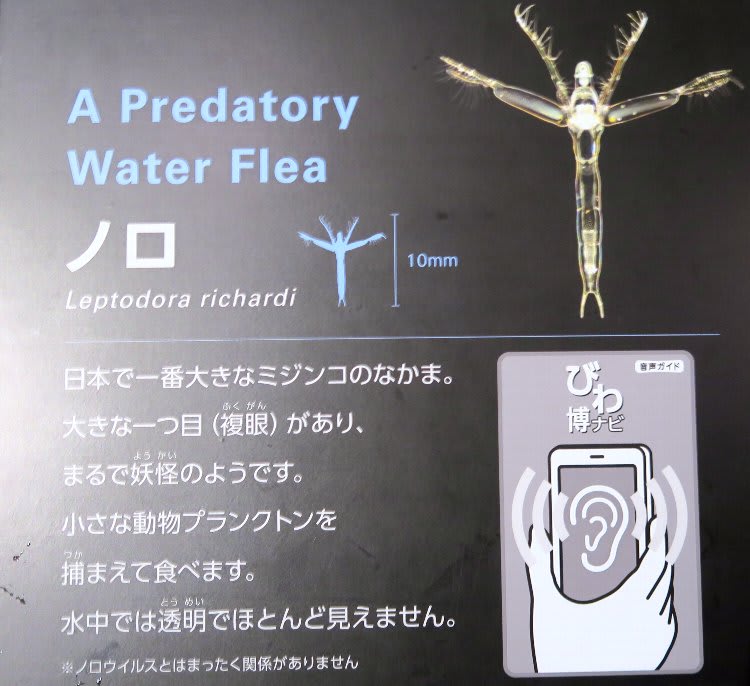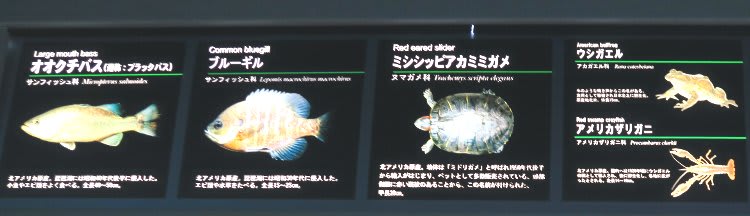天高く馬肥ゆる・というほどの天気ではなかったのですが、丹波路をさまよう。
結局は春日ICのそばの道の駅「おばあちゃんの家」という道の駅でした。「現在地」表示。

レストランの壁には秋の味覚の3種類(栗は絵だけ見える)

プレハブの小屋の中のポスターの写真4枚です 。真っ赤なコスモス。

但馬の南の入り口、但馬盆地です。山陰線と播但線の交点です。

隣では犬たちの運動会です。円盤を追いかける黒い犬。

飼い主よりも円盤に集中しています。

円盤しか目に入っていませんね。

手から放たれた円盤に、文字どうり食らいつく。

空には大きな斑点のいわし雲。地にコスモス。