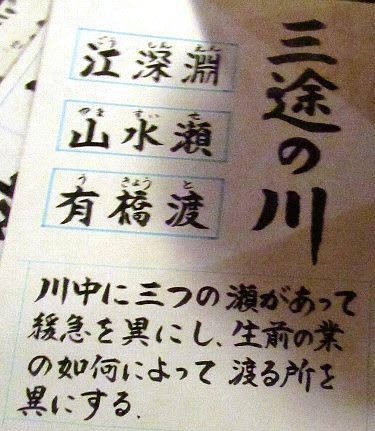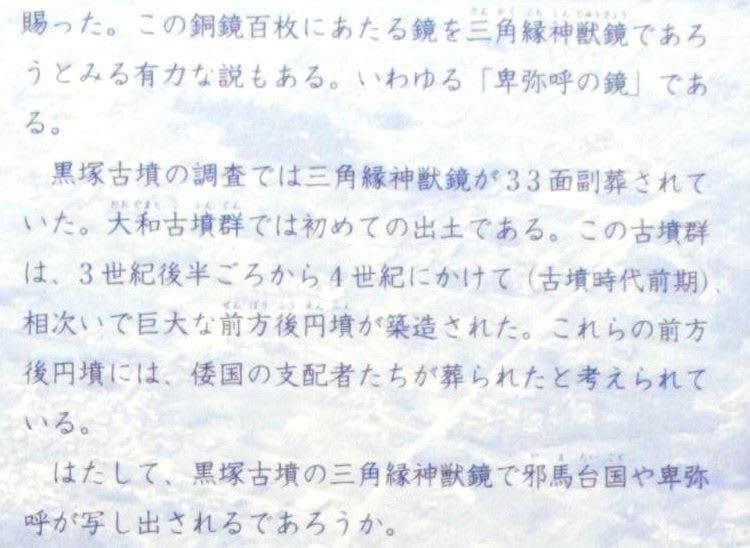紅葉一日の古刹。
奈良からJR桜井線で二つ目の駅に帯解(おびとけ)駅がある。
南北に走る「山の辺の道」とクロスした東方に正歴寺(しょうりゃくじ)がある。
ナンテン寺としても知られている。
ここは知る人ぞ知る紅葉の名所で、臨時バスが増発される。
谷を埋める紅葉は見ものである。

谷川を挟んで寺の本堂がちらと見えている。

更に100m、紅葉の谷を進むとナンテンの赤い実が見られる寺域に出る。

昔は大きな伽藍を持つ寺院であったという。

谷の奥にある伽藍は、石垣の上にある。

少し高台にある境内には、紅葉の古木が枝を広げる。講堂である。

この赤さは見事です。

本堂に戻ってきて、縁側に拡がる前栽です。塀の外のモミジが、庭を覗きこんでいるような…。

枯山水の庭の奥にサザンカと、ナンテンが見える。左手にマンリョウの赤い実。

以前来た時は、人で一杯だったが、午後も遅くなった今は少ない。
奈良からJR桜井線で二つ目の駅に帯解(おびとけ)駅がある。
南北に走る「山の辺の道」とクロスした東方に正歴寺(しょうりゃくじ)がある。
ナンテン寺としても知られている。
ここは知る人ぞ知る紅葉の名所で、臨時バスが増発される。
谷を埋める紅葉は見ものである。

谷川を挟んで寺の本堂がちらと見えている。

更に100m、紅葉の谷を進むとナンテンの赤い実が見られる寺域に出る。

昔は大きな伽藍を持つ寺院であったという。

谷の奥にある伽藍は、石垣の上にある。

少し高台にある境内には、紅葉の古木が枝を広げる。講堂である。

この赤さは見事です。

本堂に戻ってきて、縁側に拡がる前栽です。塀の外のモミジが、庭を覗きこんでいるような…。

枯山水の庭の奥にサザンカと、ナンテンが見える。左手にマンリョウの赤い実。

以前来た時は、人で一杯だったが、午後も遅くなった今は少ない。