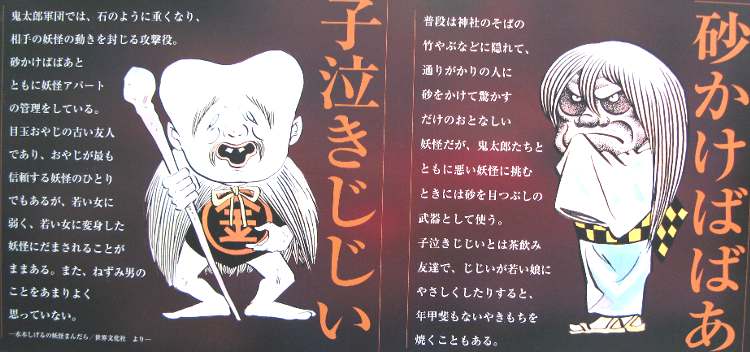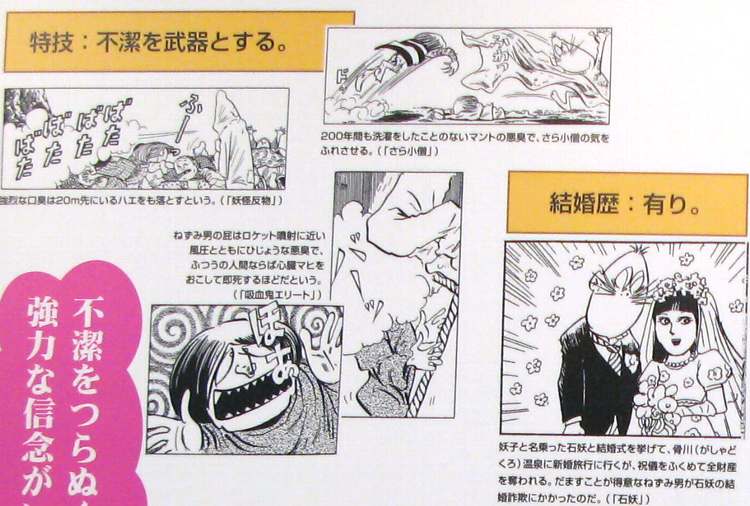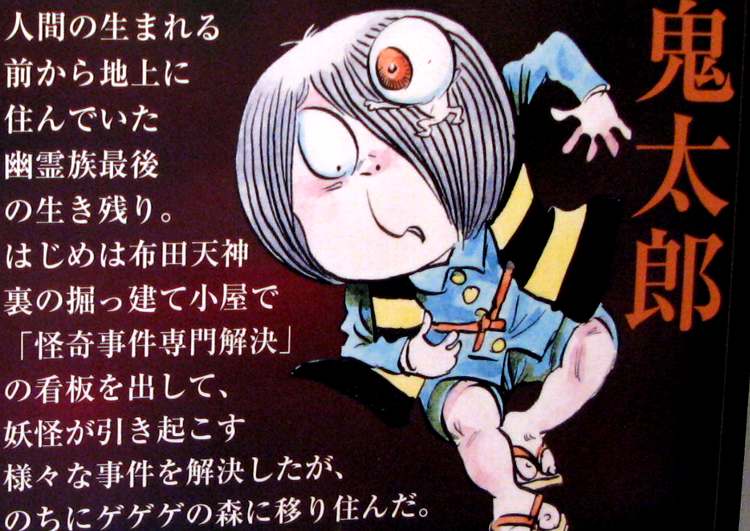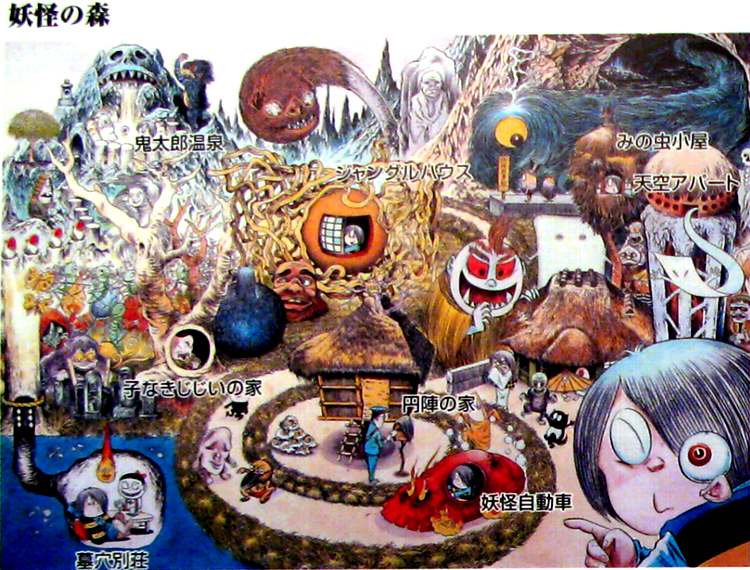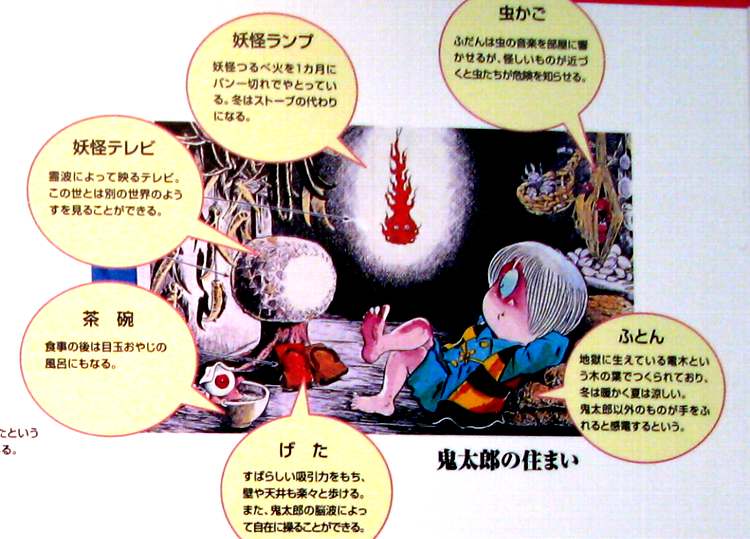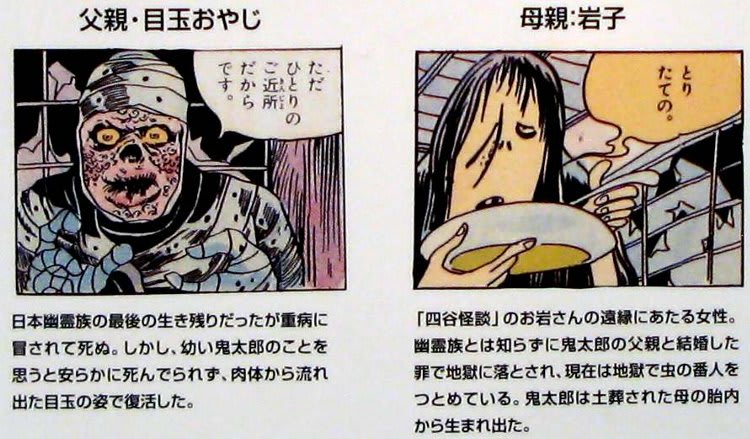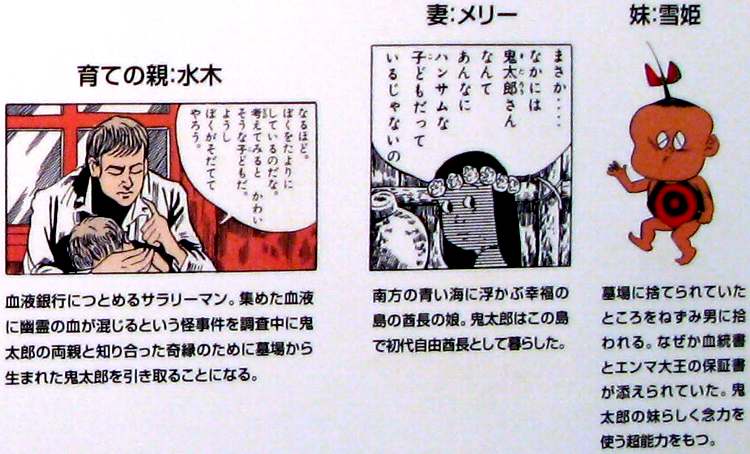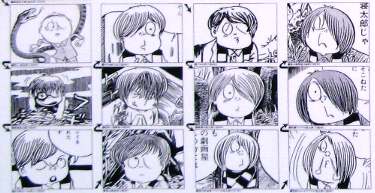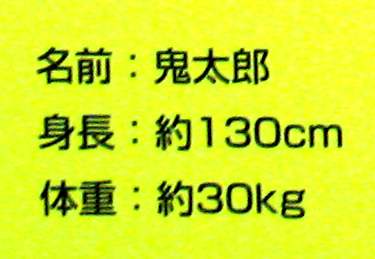神武東征の神話伝説以来、熊野地方は賑わってきました。
世界遺産の熊野古道に付随する多くの史跡は枚挙に暇がありません。
今回は「川の熊野古道」と言われる熊野川の瀞(どろ)八丁を訪ねました。
熊野三山の本宮大社から熊野川河口に鎮座する速玉大社に向う善男善女が船便を利用したかもと考えると楽しい。山中の古道を歩く人がはるかに多かったでしょうが・。
写真は上瀞・下瀞・奥瀞のうち、上瀞の入口の景観です。左の崖が三重県、正面の崖が和歌山県、手前の岸辺が奈良県です。
世界遺産の熊野古道に付随する多くの史跡は枚挙に暇がありません。
今回は「川の熊野古道」と言われる熊野川の瀞(どろ)八丁を訪ねました。
熊野三山の本宮大社から熊野川河口に鎮座する速玉大社に向う善男善女が船便を利用したかもと考えると楽しい。山中の古道を歩く人がはるかに多かったでしょうが・。
写真は上瀞・下瀞・奥瀞のうち、上瀞の入口の景観です。左の崖が三重県、正面の崖が和歌山県、手前の岸辺が奈良県です。