

あっちこっちで集中豪雨があって、あっちこっちで電車が止まっている。
電車の運転を見合わせる理由は、雨量計のメーターが基準以上になったからだと言う。何か違うような気がする。雨量計のメーターは人間が判断する参考にはなるが、最終的に判断するのは人間で、責任を持って判断して決心した人間は責任を免れるものではない。雨量計のメーターが基準以下であれば何も考えずに運行すると言うのも無謀だ。場所によっては基準以下であっても障害が発生する可能性はある。
だいたい「基準」は誰が決めたのだろう。
単なる申し合わせに過ぎないし、一旦決めた「基準」は一人歩きして絶対的な数字として変質してしまう。確かにある程度以上は絶対に運行停止と言うレベルもあるだろうが、普通はあいまいな基準をなくすため一定レベルの数字を決めて、YESかNOかの判断を迫ることになる。この弊害は現場での判断事項を一切なくしてしまうことになる。現場は何も考えずに基準にしたがって行動すればいいことになる。
「基準」は人間が判断するための基準でなければならないと思う。
人間の判断は少なくとも積極策か消極策かその中間策かという3つの選択肢を持つ。「雨量計がある基準以上になったら運行停止」というのは、あまりにも乱暴な気がする。極端な積極策が運行を通常通り継続するであり、極端な消極策が運行を停止するであり、中間が安全を確認しながら危険度にあわせて運行するであろう。最も現実的に有り得るのは中間策である。そして中間策の判断を確かにするのが雨量計の数値基準である。
「基準」は個々の特性に応じて変わるだろう。
全く同じと言う事は有り得ない。地盤の弱いところもあるだろうし、風雨に弱い路線もあるだろうし、危険な箇所が多いところもあるだろう。それを一つの基準で縛ってしまうのも考えものである。個々に「基準」を定めるべきだし、個々に定めた「基準」にはそれぞれが責任を持つべきである。そうでないと意味のない基準に振り回されて誰も責任を取らない状況が派生する。これは困った事である。
雨量計の数値基準は絶対に必要である。
過去の反省で集中豪雨の短期間の雨量を現場で把握できていなかったために雨量計を整備して広域の降雨状況が把握できるようになったのは素晴らしい事であるが、だからといって雨量計の数値に基づいて自動化してしまうことはちょっと考える必要がある。災害は自然を相手にしている。自然現象そのものを数値化することには無理があり、やはり最終的には人間による判断がどうしても大切になると思う。その部分が抜けてしまうとシステムそのものが成り立たなくなる。
数値基準を厳格に守る事は消極的な対策に徹する事になる。
そして障害を全てなくそうとすれば、数値基準はますます厳しくなり、最終的には「雨が降ったら運行停止」みたいな笑い話にもなりかねない。最終目標は「安全に運行する」であり、「安全」と言う事は危険をある程度内包している。常に危険は存在するのである。だから現場では危険を察知してこれを回避する判断力と対応力が求められるし、これが現場に任された責任だし、これが現場の仕事そのものである。これを放棄して全部数値基準に依存してしまったら危なくて電車に乗ってられない。数値基準を満足していても危険は存在するのである。
あちこちで「基準」とか「マニュアル」が取り沙汰される。
そして「基準」とか「マニュアル」を厳格に守らないと、すぐに叩かれる。これを徹底すると、「基準」とか「マニュアル」を守る事が最優先されて、結局は現場で対応している「担当者」は何も判断しなくなるし、何も考えなくなるし、細部のノウハウは積み上がっていかないし、基準の見直しもできなくなってしまう。そして想定外の事故が起きた時は「専門家」や「有識者」が登場して、一般的な原理・原則をいじくりまわして、非現実的な結論が出されて、これがオーソライズされ、新たな基準として大手を振ってまかり通る事になる。現実的な基本的な部分はみんな抜けてしまい、一面的な要素で全てが縛られて、ここに集約されてしまう。事故が発生した原因を追究すると、とんでもない基本的な判断ミスを犯していることとなる。個別の事故原因は各部署で取り除く努力をしなければならないし、そのための細かな判断基準は個別に現場で整備しなければ、いつまで経ってもいたちごっこが続くと思う。

















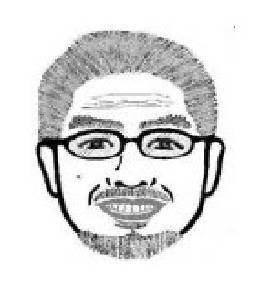





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます