
自己主張には2種類ある。
正の自己主張と負の自己主張である。正の自己主張とは周囲の集団より優れて目立つ自己主張であり、負の自己主張とは、周囲の集団に対抗して(又は劣って)目立つ自己主張である。集団との関係を絶って自分さえよければという考えに徹している人は、たまたま集団と個人の価値判断を合致できれば問題ないが、それ以外は独りよがりの甘えに通じた集団にとって役に立たない迷惑となる自己主張となる。通常の人間は常に集団との関係を維持して自分の価値観と集団の価値観が一致しているかどうかを確認しながら正の自己主張を試みる。これが本来の自己主張である。
負の自己主張は、集団からドロップアウトして、反体制的な自己主張をする。
体制批判の重要性は十分認識するが、批判の内容が普遍的に正しいかどうかは別の判断である。結果は時を経ないと判らないし、反体制的な自己主張には相当の努力と忍耐を必要とする。当然ながら、体制批判は体制を良くするために行うものであり、体制そのものを破壊してしまうものではない(破壊を目指す過激な集団も存在する)。集団からドロップアウトして対抗する集団側から批判するのも結構だが、その前に集団の中にあって集団を良い方向に牽引して行くやり方もある。ドロップアウト組はそのやり方を放棄した集団だろう。
自己規制のない自己主張は意味がない。
自由奔放で民主的に見えるが、統一された規範がないと自己主張が中身のない周囲から浮き上がった目立つだけの自己主張となる。新規性はあっても価値は認められず、引き続き自己主張をしようとすれば常に新しいものを打ち出さなければならない。そこには進歩も発展も見られない。普遍的な価値を持つのであれば、自己主張は一貫したものになるはずであり、何度も何度もしつこいくらい主張は繰り返されるはずである。特に少数派の自己主張は多大の努力を必要とし、時としてその努力が無駄になる覚悟をもってなされるべきである。
多数派や少数派であろうと、賛成派や反対派であろうと、
自己規制は常について回る。自己規制のもとに作り出された考え方に対して周囲のものが賛成するか反対するかは結果論であって、賛成されたからいいとか反対されたから悪いとか言うものではない。また、賛成されるように修正したり反対されるから諦めたりするのもおかしな話である。自己主張は確固として存在し、その存在そのものが価値であり評価の対象である。自己主張をよりよいものにするための周囲の意見は貴重であるが、周囲の意見で自己主張の存在そのものを変えてしまったのでは意味がなくなってしまう。ここで自己規制がどのように働くかがその後の成り行きに大きく影響してくる。
自由奔放に放任している環境ではいい意味での自己主張は育たない。
人間は他の動物と異なり、自己規制ができる唯一の動物である。この自己規制が文化を築き文明を切り開いてきたと言っても過言ではない。自由奔放に放任している環境とは自然そのままの環境であるが、自然環境も様々な規制を生み出し、生きるためには様々な努力を強いられる。動物たちはその規制(試練)に耐えて生き抜いている。しかし、人間はこれに加えて、自分自身を客観視し自分自身を規制することが可能である。我々が他人の立場に立って考えたり、主観のみならず客観的にものごとを見つめることも可能である。この客観的な立場から自己を見つめ直して自ら自己に対し規制をかけることができる能力が人間をここまで発展させてきたのである。自己規制を伴わない考え方は動物以下なのである。
自己主張をする過程において、
自分をひとつの型にはめ込んでみる必要がある。型にはめると自由な考え方ができないと思っている人もいるが、自己を失わなければ自由は確保できるし、型にはめることによって自分を再確認することができ、型にはまりきれない部分が自己主張として表出する。漫然としたまま放任している状態では何が自分の個性でどの部分を自己主張すべきかが見えてこない。型は窮屈であればあるほどその反発力は大きくなる。反発力は大事にすべきであり、その反発力を冷静に観察し探求し新たな型を生み出す自分がいなければならない。
そのためには、
まず窮屈であっても自分をひとつの型に押し込まなければならない。この努力は大変なもので、真剣に取り組めば取り組むほど成果は大きくなる。この部分が自己規制でもある。このタガをはずしてしまったのでは、苦労して作り上げた型がなくなってしまう。ということは、自己主張すべき個性そのものがなくなってしまう。自己主張には自己規制が必要不可欠なのであり、自己規制の欠落した個性は全体の中では異質であるが、主張のないただ存在するだけの個性でしかない。

















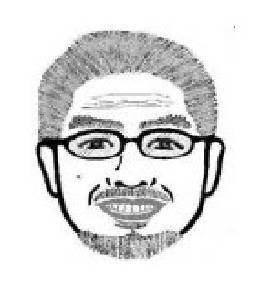





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます