「ラボオじーさんは後悔してたのかな」
小高い丘の上から石の町を見下ろしていたミカの背後で、ヒロがつぶやく。
風に揺れる事も、枯れる事もない、彫刻の桜を満開にしている枝に登って、一段上から
やはりミカと同じように町並みを眺めていたヒロ。
そのつぶやきには、
「さあな」
としか、返事のしようがない。
ヒロは、それを物足りないと感じたのか、枝にまたがったまま身を乗り出す。
「それとも単に、死ぬ前に一度帰りたかったのかな。あの頃に」
それにも答えられない。
本人はもうこの世にいない。いたところで、本人が答えてくれるとも思えない。
ただ、ヒロの口にした<後悔>という言葉は、酷く重い言葉だった。
後悔という執念、過去を作りだす狂想、それらがこの町を具現化したというなら
眼下の灰色は、無機物という存在ですら在りえなくて、薄気味が悪いとさえ思う。
思って、何故見知らぬ他人の行為にそれほど感情移入してしまうのか、
ミカは、気づいてしまった。
「…俺には解らねえよ、じいさんが何を思ってここを作ったのかなんて」
そう言ってミカは、ヒロがいる高い枝に繋がる桜の木の幹に、片手をのばす。
その石の温度を手のひらに感じれば、自然と気持ちは冷えていく。
「けど、自分もそこへ陥るかもしれない、という予感はある」
「へえ?」という、感情を消した<音>だけで、その続きを促されたようで、ミカはもう一度、
町へと目をやった。
「どうしたって選べないどちらかを、選べ、って強要されることはあるだろ」
「それは、まあ…、あるだろうけど」
「真剣に向き合って自分が選んだ道なら後悔はしない、ってのはよくある言い草だけどよ。
俺にはキレイゴトにしか聞こえねえよ」
それは、ヒロに向けた答えではない。この町に感化された、自身の独白だ。
最大の分岐点でただ一つの道しか許されないということは、自分の人生においてそれほど単純に決着できるものではない。
後悔しない、と言い切ることが美徳というなら、そんなものは「くそ食らえ!」だ。
そんな内面を他者に晒す行為はおろかであると解っていながら、口にしてしまったのはどうしてなのか。
ミカは、苦い気分に口を閉ざす。
ラボオという人間が、進むべき二つの道にどう向き合ったのか、何を決着したのか、
そんなことは、第三者である自分には興味はなかった。
ただ、自分にも必ず訪れる分岐点が在ることを、思い知らされたのだ。この、灰色の乱立に。
どちらかを選ばなくてはならない。
そうして片方を選び、片方を切り捨てたとして、後悔しない、なんて言えるとも思えない。
正道であるべき道しるべなど、自分にも、ましてや他人にも指し示すことはできない。
それを。
「ミカが、<選べないのに選ばないといけないもの>、って何だろう?」
ヒロの率直な疑問に、内心、舌打ちする。
本来、立ち入られたくないはずの領域を軽々しく口にしてしまった自分に。
そうして立ち入ってきたヒロを責めることもできない状況に。
しかも。
<何だろう?>って、どういうことだよ!どんだけ気弱な立ち入り方だよ!!
と、八つ当たりしかけ、今、自分が拳を預けている石の幹、その無機物さに気づいて
気を静める事ができた。
…これを殴ったら痛いだろう。
「…侯爵家だよ」
唸るように吐きだし、どうせ逃げ場もないなら奴も巻き込んでやれ、という
自暴自棄な気分に任せて、後を続けた。
「俺は跡継ぎなんだ。いずれ、侯爵家に戻らないといけねえんだよ」
身分を不問にする<冒険者>という立場を捨てて、あの貴族社会に帰る。
「戻りたくないのか?」
「あったりまえだ!…あんな胸糞悪いところに誰が」
だが。
連れ戻されなくても、自分は帰るだろう。分別ある子息として見事なまでの正道。
けれど、正道でありながら、冒険者であることを捨てた自身への後悔は付きまとう。
解りすぎるほどに、解る正道の結末。
だからと云って、侯爵家を捨てられるのかと、自問すれば、それもまた不毛の極みだ。
自由な道を選んでおきながら、侯爵家を捨てた自身への後悔からは、自由にはなれない。
なれるはずがない、と解ってしまうのだ。
どちらも選ばずにいることはできない、決して逃れられない選択。
柵も何もない純粋な本音なら、このまま名も無き冒険者のまま果ててしまいたいとさえ思うのに
それから逃れる術はない。
家が滅び、血族が滅び、自分自身が滅びて初めて、「侯爵」という鎖から解き放たれる。
そんな破滅は望んでも仕方が無い、と、ミカの言葉をじっと聞いているヒロも、いつになく神妙な面持ちであるのだろう。
仕舞いには相槌さえも返ってこなくなる。ミカの独白は、灰色の町に吸い込まれる。
それだけの空虚。今現在、これに向き合って目をそらさずにいる方法が見つからない。
それが腹立たしい。
そんな行き場の無い感情を、いつものように自身の奥底に仕舞い込もうとしていると。
「そっか」
と、何かを心得たような返事が上から降りてきた。
「じゃあ、俺は、ミカがそのどっちかを選ぶのに立ち合うわけだ」
ミカの自暴自棄さには全く取り合わないような、平静さで、
益も、無益もないヒロの台詞に思わず、仕舞い込もうとしていた感情がぶれる。
あえて視界に入れないようにしていたヒロの姿を目で追って、怒鳴っていた。
「お前にわざわざ立ち合ってもらうほど落ちぶれちゃいねえんだよ!!」
つい反射的に間髪入れずぶつけた感情は熱を持っていて。
「ええー? でもなあ…」
と、枝の向こうから、困惑したヒロの顔が振り向く。
こっちがどれだけ真剣に怒鳴ろうと、のらりくらりとかわすヒロの態度には慣れたつもりだったが。
慣れた、と思うほどには長く旅を共にしたと思ってはいるが。
「だって今、ミカと旅してるのは事実だし」
それをヒロに指摘されるのも腹立たしい。
「ミカが今から他のパーティに受け入れられるか、っていうと、それはちょっと無理っぽいし」
そんな図々しい事を平然と言わせていることも腹立たしい。
「ウイだって、そんなこと許さないと思うし」
調子にのりやがって!
「なんであいつの許可がいるんだよ、俺の行動に!」
「うん、ミカが本気で決意したことになら許可はいらないけど」
いらないけど、ともう一度繰り返したヒロが、身軽に枝の上に立ち上がった。
「俺もウイも、ミオちゃんも、ミカが本気で選ぶんなら、逃げずにちゃんと立ち合えるよ、って話!」
ミカの選択した答えを、仲間として、受け入れる覚悟があるのだ、と。
未来を分かつ、重大な運命を共にしているかのように、そんな意志を大声で放つ。
「な…」
ここにいない、残る二人の意思までも。
いつものヒロの、のらりくらりと調子を合わせるお気楽さで、無責任に全員の意見の代表であるかのような事を、
軽々しく言ってのける。
軽々しく、しかしその実、ヒロの意志は堅い真実。
嘘偽りなく、堅いのだ。
それを信じられる程には、共に旅をしてきた。間違いなく、彼らの意志は真実と共にあった。
(だから、自分はこの居場所を選んだ)
選んだからこそ、選んだものを、捨てるということはできない。
同じく、選ばなかったものを、「捨てた」と言うことができない自分。
それは成長が未熟だからか。心が弱いからなのか。
そう迷い続けているこの目の前に、沈黙して広がる町は、自分の何倍も生きたであろう老人が築いた「意志」。
刃を振り下ろして築き上げた彫刻。
ならば、自分もいつか人生の果てに気づくだろう、慟哭。
それを、ヒロが軽々と飛び越えて行く。
「よっ」
と、軽い掛け声で枝から飛び降りたヒロが、ミカの目の前に着地する。
着地して、しゃがみこんだまま、今度は下から見上げてくる。いつも通りの人懐っこい笑顔で。
「ミカが侯爵家を選んでもさ、俺はずっと冒険者をやってるんだよ」
なんだそれは。嫌味か。
そう吐きだすほど自虐的にはなれなくて、ただ無言でいると。
「どうせ侯爵家なんか、そのうち隠居するだろ。ミカの息子に後を継がせたら、戻ってきたらいいんだよ」
<ルイーダの酒場>に、とヒロが笑う。
「俺ならミカの事、ぜーんぜん待ってられるし。ウイもミオちゃんも、絶対ずっと待ってるよ」
「何言ってんだ、バカバカし…」
「だってミカしかいないじゃん?このパーティの面倒見るの」
まあ50歳そこそこで隠居するとして、あと30年くらい?なんて指を3本突き出してくる姿に、
思わず声を荒げる。
「おまえら50歳になってもまだ俺に世話焼かせる気か!!」
「そりゃそーだって、人間30年くらいでいきなり人が変わったりしないって」
お気楽そうに言われては、呆れて二の句が継げない。
彫刻の幹に寄りかかって溜息をひとつ、そのまま地面に目をやれば、視界の端でヒロが立ち上がる。
「…逆に、このまま冒険者を続けたとしてさ」
ミカの、運命の選択。
「いつか、侯爵家を選んどけば良かった、って思ったらさ」
選べないものと、選ぶべきもの。
その二つを両天秤にかけて、どちらかを重くしようとするミカに、ヒロは答えをくれる。
「俺の村に来たらいいんだよ」
「はあ?!」
「云ったろ。俺の村で、王様やってくれて良いって。侯爵より階級高いぞ?ぶっちぎりだそ?
侯爵家の領地を治めるのとは規模が違うぞ、国を作るんだから」
すげーやりがいあるぞ!と、いたって真剣に力説されて、呆れて、これ以上はないほど呆れて
…笑ってしまった。
「おまえ、ほんっとにバカだな」
「あー、なんだよ、俺真面目なのに。そういうこという?」
両天秤にかけて、わずかでも揺れ動くことなく等しく同じ重さにする。それがヒロの、答え。
そして、きっと自分でも認めたくなかった、真実。
どちらも大事なのだと、言ってしまえばそれは、ぴたりと釣り合う。
あんなにも捨てたくてたまらない侯爵家でも、「大事」なのだと、自由と同じ重さで大事なのだと、
釣り合って、認めてしまえば自身の平静を取り戻す。
その、新世界。
「ちげーよ。…俺が王で、お前が大臣をやる、ってんだろ」
「おう。ミカの下で働いてやるよ?」
「お前は、そういう腹黒いことは似合わねえよ」
「ええ?下で働くのって、腹黒いか?」
「だから、馬鹿って云ってんだ。王ってのは国の顔だからな。王が表向き清廉で大臣が裏で腹黒いんだよ」
「なにそれ!そんな怖い話さらっとするか?!」
「だから」
強く、言い聞かせるように言葉は重みを増す。
「お前には出来ねえって云ってるだろ。腹黒い部分は俺が引き受けてやるから…」
お前はそのままでいろよ、そう続けると、ヒロが驚いたように黙った。
いつまでも待っているから、と言われて、嬉しくなかったはずがない。
村に来い、と言われて、嬉しくなかったはずがない。
どちらも同じ重さで良いのだ、と許されて、嬉しくなかったはずがない!
そのヒロが放ったどちらの提案も、現実にするには子供じみている、と、一蹴することは容易い。
それはヒロにも解っているはずだ。
だが、子供じみているからと云って、選択肢に加える事すらせずにいることが、出来るだろうか?
こんなにも、心が躍るような非現実的な話を。
子供の夢物語だ、と一笑に付して、その実、つまらない現実的な夢を見るだけでいいのか。
ヒロの提案は、無限の可能性を、幾重にも示唆する始まりの一石だった。
いつも、何事にもとらわれないヒロの自由な思想には驚かされる。…良くも、悪くも。
自分には持ちえない、ヒロの柔軟性。
それが今は悔しいから、あえて言ってやる。
「バカ殿の方が、裏から操り易いからな」
その一言で、それまで意表を突かれていたようなヒロの表情は一変し、子供のように拗ねた。
そして、ぶすっと文句を言う。
「どーせ俺は、ミカの腹黒さには勝てませんよ」
「うるせえよ」
傷ついたふりして、さらっと何毒吐いてんだくれやがるんだコイツは、と睨んでみせると、
ヒロが笑った。
「ミカも俺のバカ殿っぷりには勝てないだろうしな。ま、引き分け?」
「あほか!勝たなくていいんだよ、そこは」
それにどっちかというと痛み分けだ。そんな事を口にしかけて、バカバカしくなる。
こんなバカを言い合あえる存在がいる。
手の届く現実に居る。
それが、昔の自分にとっては、気が遠くなるほど非現実的な、別世界の話だった。
出会えたのは奇跡、けれど、奇跡を起こすのは自分自身。
自分という領域から一歩踏み出した時に起こる現象こそを、人は、奇跡と呼ぶのだろう。
「ミカちゃーん!ヒロー!」
丘の下から、自分たちを呼ぶ声がする。
出発の号令をかけるウイがいる限り、この旅は続く。自分はそれを望んでいる。
「行くぞ」
「おう」
下草を踏み越えて、彫刻から離れる。
髪をなびかせる風に枝を見上げれば、そこには不動の意思が咲き誇っていた。
選ぶべきものを選べない愚かさ。
それを知りながら選ばなくてはならない滑稽さが、これまでの自分の全てだった。
それを覆したのは、この地。
選ばれなかったものへの執着を捨てられず、選んだものを疎かにすることこそ、愚かなものはない。
選ばれていながら捨てられている存在の虚しさは、見るに耐えられない。
この不動の桜は、それを教えるように下界を見降ろしているようにも見える。
次にこの町を訪れた時、
俺はまだ、この彫刻群を「見事だ」と称える事ができるだろうか。
後悔のあまり、自分で選んだ運命そのものを見誤っていなければ、それで良い。
見誤ることなくいれば、その選択は後悔に苛まれていながら、ゆるぎない。
そう気付かせてくれたこの仲間は、変わらず傍に居るだろうか。
この先も続く旅に、誰かが、秘められていた重い心を吐き出した時、
それに何を言ってやれるだろう。
どんなことにつまづき、癒せない傷に苦しみ、救いの声さえも出せずにいる時に、
どうすれば、その重みから解き放ってやれるだろう。
旅は翼、その羽を力強く羽ばたかせるために、誰一人欠けてはいられない。
そうだ。
その為の旅だ。
もうこれは、侯爵家を飛び出した自分の為の旅じゃない。
同じ翼に乗る仲間に、自分の心を与えられる言葉を探す旅だ。
今、自分だけの言葉を探す旅が始まる。

にほんブログ村 ←出会えた奇跡、ポチってくれる奇跡に有難う♪
![]()













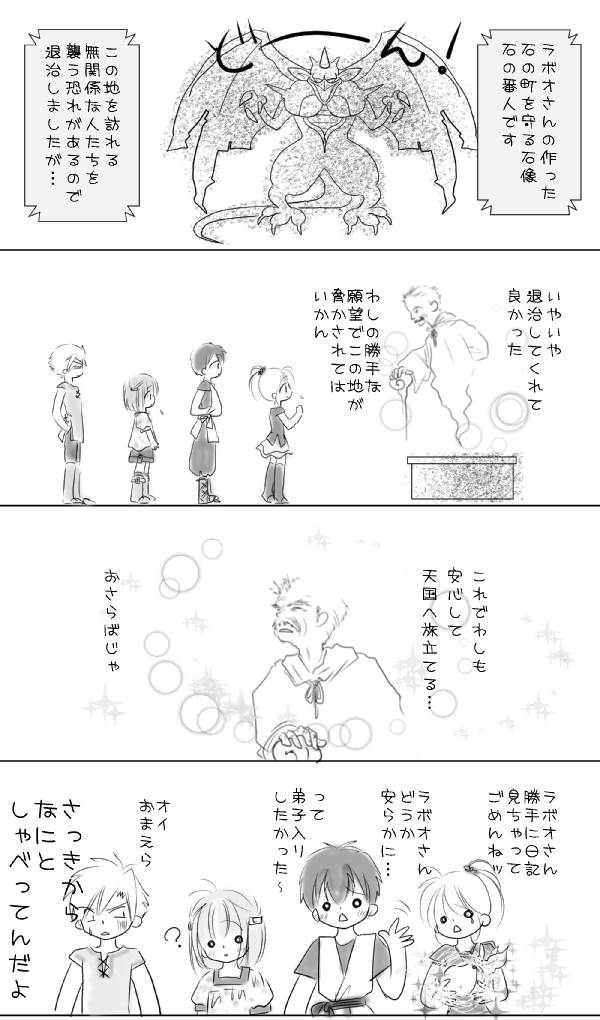
 」
」



 」
」 」
」












