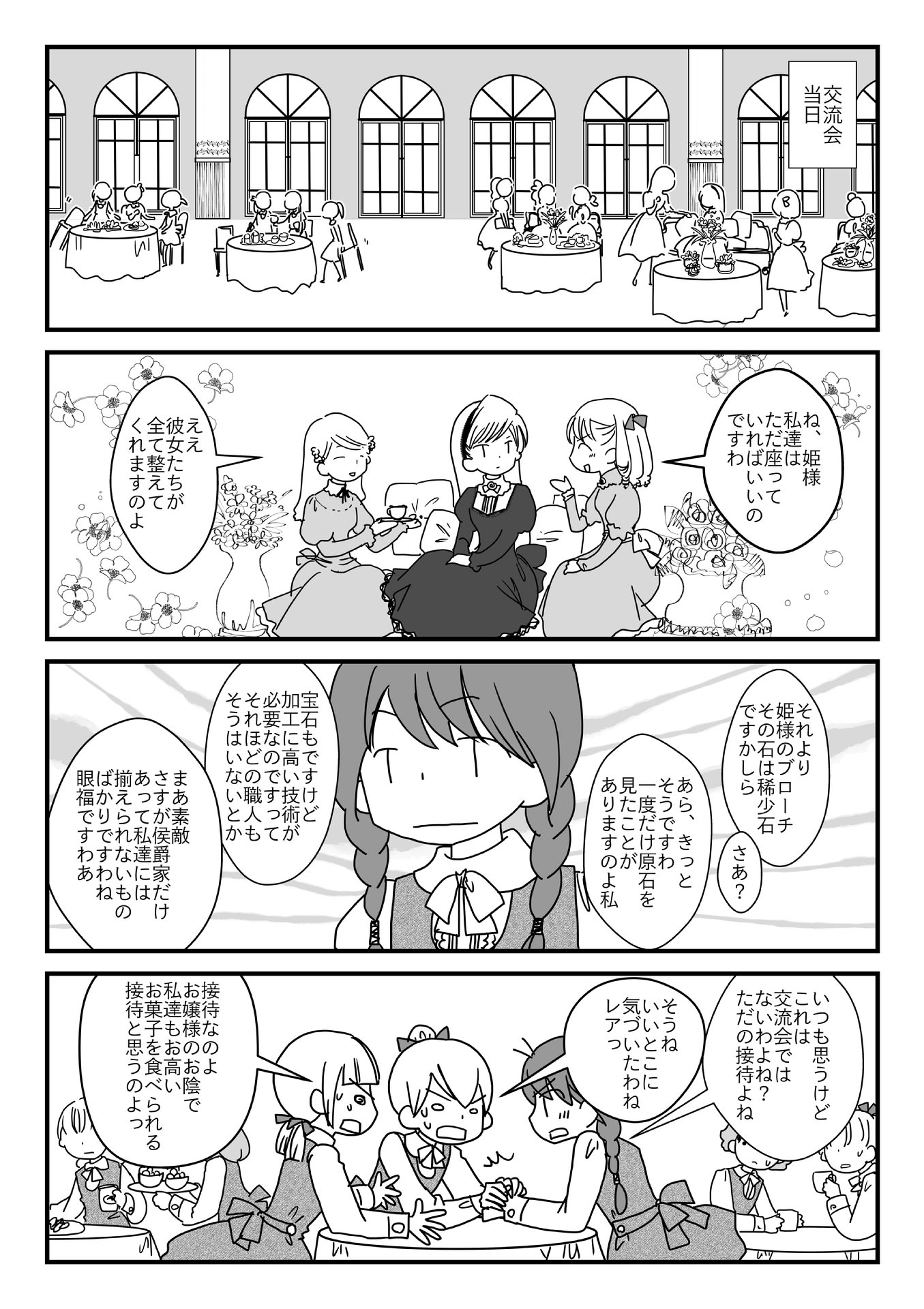その日、レアは偶然にも、王城でレネーゼ侯の子息ミカヅキの姿を見つけた。
偶然にも、というのは、レア自身、滅多にないことだが侯爵家の使いで単身王城を訪れていたという事と。
これまた滅多にない事に、世界の国々へと出かけて家を留守にしているはずのミカヅキが王城に立ち寄っていたという事の重なりによる。
(お声をおかけして良いものかしら)
王城という公式の場で、自分の立場とミカヅキの置かれている立場とを考える。
平民という身でありながら侯爵家の侍女という地位へと上り詰めてきたが、未だに公式の場での振る舞いには助言を必要とする事もしばしば。
特にこの場合、何か無作法があったとして上の方からお叱りを受けるのはミカヅキの方なのだ。
立派な成人であるレアのしくじりで未成年のミカヅキが叱責を負う。長くこの社会に身をおいていても、なんとも受け入れがたい慣例だ。
(侯爵家の方から正式に呼び出しは行っている事でしょうし、今私が関わらなくともミカヅキ様は家に戻られる…)
しかしとっくに呼び出しの連絡が行っていながら未だミカヅキがそれに応じていないことを考えると、単に連絡の手違いか、ミカヅキ自身の意思で応じない態度なのかは確認しておく必要があるかもしれない。
そう考えていた為にミカヅキから目を離せないでいると、ミカヅキに近づいていく人影に気付いた。
(あら、あれは)
ご友人だわ、とその微笑ましい光景に頬が緩んだ。
同じ年頃の少年と気兼ねなく雑談しているような姿は、自分が育った町で見慣れた少年たちと何も変わりはしない。
それを。
「ミカヅキ様が普通の少年であってはならぬ事です!」と、教育係であった当時の侍女頭に厳しく窘められた昔の事を同時に胸に思い描いてしまう。
それは許されない。決して許される世界に生きているのではない、と、教育係であった彼女にあれほど厳しく怒りを露わにされたのは、レアが侍女としての位について初めての事だった。
その剣幕には、そばにいた者たちに「レアが失踪してしまうのではないかと気が気では無かった」と後に打ち明けられた程だ。
(確かに震え上がった事は事実だけど)
今思い出しても、肝が冷えるのも事実だけど。
レアが侯爵家の侍女になったのは、侯爵家の為でも家の為でもない。自分の為だ。大切な人を守りたいと思い、その為の力を欲したが故なのだ。
(それを投げ出して失踪したりはしないわ)
と、幾度も言い聞かせてきた言葉を今また胸に落とし込んだ時。
レアの視界の中で、ミカヅキが振り返った。
隣にいる友人に何やら指図され、それを確認するかのような動作でこちらを向く。
とっさの事で、つい動揺し、それと分からないほどの軽い会釈を返したがミカヅキはすぐに視線を隣にいる友人に戻した。
(あら)
少し距離があるために気づかれなかったか、或いは、やはり公の場では良しとされない為になかった事にされたか、と考えていると、ミカヅキが友人と別れ、こちらへと向かって来るのが分かった。
侯爵家にいる時には考えられないほど簡素な服を着てはいるものの、その堂々たる姿は町にいる少年たちと比べられるものではない。
周囲の視線を集めながらその中心であることに僅かの疑問も持たせない存在でなければならない。
どんなに簡素な見かけでも優雅さをわずかでも損なってはいない一挙一動は、侯爵家の正当後継者として育てられた高き使命。それ以外の世界など存在しうるはずもない。そんな空気に威圧されるように、レアも知らず緊張を強いられ背筋を伸ばしていたが。
「お久しぶりです、夫人」
と、側まで来たミカヅキは単純明快な挨拶をした。
あまりにも率直なそれに拍子抜けして、レアも最低限のお辞儀をすることすら失念してしまったほど。
「ええ、月見の宴以来ですわね」
お元気そうで良かったわ、なんて口走りながら内心で焦る。
(ああビックリした、長々と登城の儀なんたらの口上でも述べられるのかと思ったわ)
前触れもなくそんな事になっていたら。
ただでさえ公式の場に馴染めない自分では、危うく失態に失態を重ねて王城中に広まってしまうだろう。
いや、王城の一広間で知人が顔をあわせるだけで、そんな格式張った口上を述べ合うことなど今の時代にはあり得ないとわかっている。
(だけど、そう思わせるほどの)
格式高い儀式での振る舞いであるかのようなミカヅキの雰囲気に飲まれたのだと思う。
いや、違う。これはミカヅキのせいではなく、普通の少年であってはならない、と言われたあの日のトラウマ。
この子供を、普通の少年と同じに見てはならない、と言う強迫観念が故の。
その動揺を、何気なくミカヅキの近況を尋ねたりしてやり過ごしているレアに気づくはずもなく。
それで、とミカヅキの口調がレアの言葉を押しとどめる。
「私を訪ねてこちらまでお越しいただいたのでしょうか」
「ええ、それが」
と事情を話し出そうとするレアを、ミカヅキが再び押しとどめる。今度は、言葉ではなく仕草で。
どうぞ、と無言で差し出された手はまだ少年のそれだが、多くの社交場で手慣れた感はあった。貴婦人を優雅に連れまわす、紳士としてのそれ。
ともすれば、自分の方がエスコートに慣れていないくらいだ、とレアは焦ってその手を取る。
「あ、ええと」
そんな大事ではないないのだが、と説明する前に、「この場を離れます」と短く告げてレアの足元を気にしてくれる。艶やかに磨かれた廊下や、洒落た作りのタイル張りの段差に気を配り、ドレスの裾捌きまで注意して、すぐそこの花園のベンチまで誘導された。
(まーすごいわーこんな事さらっとやっちゃうんだわー子供なのに紳士だわー上流階級のご子息ってみんなこうなのかしらー)
などと舞い上がっていたので、ミカヅキの意図を知れたのはベンチに腰を下ろした時。
「ここなら人の目もありますので」
と、レアの隣に座ったミカヅキの言葉に我に返り、そういえば、と今までいた場所を振り返る。
そろそろ帰ろうとしていたところでミカヅキを目にし、立ち止まった場所。
城内をめぐる入り組んだ通路が放射状にこの広間に集まってくる。豪勢な飾り付け柱や美術品がそこここに並べられ、それがあらゆる方向から視界の邪魔をする。多くを行き交う人々の視界には入りづらく、逆に忍んでいるようにも見えようものなら、有らぬ誤解を受けるだろう。ミカヅキはそれを危惧したのか。
円形の広間であるここは中央の花壇を囲うようにベンチが置かれ、視界は自然と広がり、何処からでも人の視線は自由に見渡されており、かつ人の導線の邪魔にもならない。
(そういう事なんだわ)
と辺りに目を配り、何気なく、ミカヅキといたあの町の少年を探していた。
その姿はもう何処にもなく、どうかされましたか、と隣から声がかかって、慌ててミカヅキに向き直る。
「あ、申し訳ございませんでした。まだ王城にはなれなくて」
ミカヅキの母親ほどの年齢でこれは恥ずかしい事だろう。
「だめね、配慮が足りなくて」
情けなく独り言のように口をついて出た言葉には、いえ、と短い返事ですますミカヅキ。
彼にとって、それ以上もそれ以下もないのがわかる。
(こんなところは、ミソカに似ているわ)
ミカヅキの母である女主人。彼女に長く使えていると、時折二人は重なって見える。
そう思えるのでミカヅキに苦手意識はない。むしろ今のように自分を異性として扱ってくれる分、ミカヅキの方が懇切丁寧なくらいだ。
そんな風に、今のミカヅキと同じ年だった頃の彼女の態度を思い返して比べてみては、微笑ましくなった。
「今日王城に来たのはミカヅキ様とは関係がないのですけれど」
と簡単に今日の用事を説明して、姿を見かけて声をかけようかと迷った原因を話しておく。
「お館様がミカヅキ様に言い渡すことがある、と仰っていたので」
おそらくその侯爵家からの知らせは行っているはずだが、とミカヅキを窺えば、まだ手元にはきていません、と言う。
「しばらく国を離れていました」
「あら、そうでしたの」
ならミカヅキがまだ知らなくても仕方がない。
「緊急ではない様でしたから、きっとミカヅキ様の事情を優先されたのでしょうね」
恐らくそのように指示が出ている。
ミカヅキが戻ったらことが進むよう手筈が整っているはずだ。
「それなのに私ったら」
「いいえ、夫人にお声がけいただけなかったら気づかぬまま国外へ出ているところでした」
「あら、間をおかずまた?それでは」
「いえ、知った以上は私の方で優先度合いを確認して対処します」
声をかけてもらって良かった、というミカヅキが微笑んでみせた気がした。
幼い頃から表情を変えることのない子供だった。感情をあらわにしない、それはそういう教育を受けているものだから、と分かってはいても親子間であってさえ淡々と接する上流階級のそれには未だ馴染めるものではない。
だが今のミカヅキからは、確実に親しみを込められた気がして。
「そう言っていただけて良かったわ、ミソカ様も気にかけておられたようですから」
と、つい余計な情報まで出してしまった。
「え?母上が?」
それほどの大事か、とミカヅキが身を乗り出したのに慌てる。
「あ、そうではありませんわ。いつもの親族会議の内容をお話ししておく、という事のようでしたから」
まだ成人していないミカヅキは参加できない会議だ。
だが正当後継者としてその内容を知っておくように、と老侯爵がミカヅキとの時間を設けて話し合うのはいつもの事。
「ではなぜ、母上が」
「お館様が先にミソカ様と話し合いを持たれましたの。ミカヅキ様がご不在だったから、という事ですけれど」
「代理を母上に任せてしまったのでしょうか?何かしらの決定を母上が?」
「ああ、いえいえ、決定はお館様が。その事後報告ですけど、ほら、ミソカ様は小さな事も先送りにするのがお嫌いな方ですし、単に気にされているだけなのですけれど」
「じゃあそれはすぐに戻ってあげた方が良いよねっ」
「!?」
と、突然割り込んで来た声に驚いて、レアとミカヅキは同時に背後を振り返る。
悪びれもなくベンチの後ろから二人の会話に割り込んで、ニコニコしている少女が一人。
「お」
いくら人の目があるとはいえ。
「お前なあ、堂々と人の話立ち聞するなって言ってるだろ!いつも!」
「やだなあ、知らない人の話は立ち聞きしないようになったよ?」
「なったよ、じゃねえよ!それが普通なんだよ、最低限の人としての礼儀だからな?!あ、あと師匠にも言っとけよ?」
お前らそれだから困るんだよ、と、あり得ないほどの口汚さで罵られているにもかかわらず、はあい、と機嫌よく返事した少女がレアをみる。
「ごきげんよう、レア様!」
「ごきげんよう、…ウレイ様」
思わず、勢いに押されて返事をしてしまったレアであるが。
レアにとって問題はもう突然割り込んできたこの少女の神出鬼没さではない。
ミカヅキのあり得ないほどの変貌だ。
「ごきげんようじゃねえよ、まず謝れ!」
と、少女の頭を片手で引っ掴む。それに無理やり頭を下げさせられて少女が。
「ミカちゃんが深刻そうだったので立ち聞きあそばしてしまいました!どうもごめんあそばせデスわ」
ほほほー、と上品そうに笑ってみせるそれは何処まで本気なのかは分からないものの。
ミカヅキの様子を心配して、というのはよく分かった。
「やめろ、無理にあそばすな」
「えーだってミカちゃんのお屋敷の女の人、みんなこんな話し方だしー」
真剣さが通じないかと思って、と訴えているその姿に、思わず吹き出していた。
この一連の大事件。
公人として美しく誇り高くあるはずの侯爵家の跡取りが、下町の雑多な少年らと交わった結果がこれだ。
嘆かわしい、という悲愴感が微塵もない。少なくともレアにとっては、二人のやりとりは痛快にすぎた。
(ああ、そうなんだわ)
ミカヅキが友人を紹介すると言って、以前、侯爵家に連れて来たうちの一人。そうだ、名前は確かウレイ。ここにはいないがもう一人の少女がミオ、先ほど目にした少年がヒロ。
それはレアにとっても、息子のように見守って来たミカヅキが初めて友人という存在を認めた事がただ嬉しく、忘れようはずもない名前だ。
レアの笑いが収まるまで二人が不可解そうにこちらを見ているのも、可笑しくてたまらない。
ただ一度、儀式の中で対面しただけでこんな風に言葉を交わすことなどもうないだろうと思っていたのに。
(そう、ミカヅキ様は普通の少年であってはならないから)
あってはならないと定められた運命の中で、それでもミカヅキ自らが欲し掴み取ってきたものを排除し葬り去ろうとするのは。
命運を定め、それを自在に操る残酷な神などではない。
人間だ。
「大丈夫」
だからこそ、言える。
「大丈夫ですわ。ミカヅキ様を心配して下さっている真剣さは十分、伝わりましてよ」
そう言えば、ウレイとミカヅキが顔を見合わせ。
ほらね、と笑ったウレイにミカヅキが調子にのるな、と渋面を返す。
そのとても自然な関係が、これから先もずっと続いていくだろう。ミカヅキがそれを願い、仲間がそれを望む限り、叶える力は彼らの手の中にある。
かつての自分たちがそうであったように。
(ミカヅキ様は普通の少年だわ)
何も変わらない。上流で生まれ上流で育ち、その責任を果たす為に普通の少年であってはならない、という事。
レアの教育係であったばあやの真意が今なら解る。
上流の人間である自分たちがミカヅキを惑わせ、その責任を放棄させることなどあってはならない。それはミカヅキの為にはならず、結果ミカヅキを苦しめる事にしかならない。
いずれ全ての領民の命運をその手一つで動かす地位にいる人間が、そこから降りる道など見つけてしまってはならないのだ。
(ばあや様はミカヅキ様を慈しんでおられるからだわ)
厳しい教育の中で、一切のわき目を振る事なくその頂点を目指して成長してきた彼の姿は、それを支える全ての人間たちの慈愛によってその場に立つ。
彼の立つその場が、僅かでも揺らいではならない。揺らがせてはならないという使命を追って、自分たちは頂点を支えている。
かつて、一人の公女を守りたいと思い、その力を手にするために遥か高みまで上り詰めた自分は今。
同じ様に、ミカヅキを守りたいと思い、それを実現させようとする幼い雛たちを見ている。
ミカヅキを自分たちと変わらない普通の少年だと認める存在だからこそ、自分たちと変わらない少年が到達するその高みが、恐れを抱く場所ではないと思えるだろう。
それは若さに他ならない。
これからどれほどの困難と苦境に挑むのか、具体的に考えることもできないそれも強みに変えていく若さ。
彼らが絶望し、諦めてしまうことのない様にレアが出来ることは一つ。
侯爵家の人間が出来ることは、昔から変わらずに一つ。
ミカヅキを普通の少年にしてはならない。その足元を揺らがせてはならない。
遥か高みに立つことのみを教え込まれてきたミカヅキなら、揺るがぬ地盤があるだけで、自分を追い求めてくる存在を引き上げることができるはずだ。
それを願う。
レネーゼ侯爵家の女性陣の守りは、母なる祈り。
我が子の未来だけを望み、厳しくある。
侯爵家の紋章を掲げた馬車は、王城から正当後継者を連れて戻る。
急ぎでない、とはいったが、ミカヅキはとりあえず家に戻る事になった。
屋敷に戻るレアを馬車の乗車まで見送りにきてくれた二人だったが、すぐに後から戻ります、というミカヅキに対してウレイがその背を押し込んだ。
「もー今ここに馬車があるんだから、そんなこと言わないで一緒に乗せてもらったらいーじゃない」
お堅い格式より大事なことってあるでしょー?という言葉に説得されたらしいミカヅキが、同乗させていただいてよろしいでしょうか、と聞いて来た時にはわずかな驚きがあったものの。
レアにとっても断る資格などない。主人はミカヅキだ。
ただ侯爵家へ戻る道中、ミカヅキと二人きりの馬車内で一度だけ口を開いた。
「格式より大事なものとは、何を指しておいでだったのかしら」
普段、ミカヅキが心を許している仲間と何を共有し、何処を目指しているのか。
おそらく部外者の自分には理解することもできないだろうけれど、それでも聞いてみたかったのだ。
「ああ」
と、ミカヅキが先ほどの言葉を考える様子を見せ、レアを見た。
「恐らくは、母上のことかと」
まあ、と内心で驚く。
そう言えば、直前に「ミソカ様が気にしている」ということを伝えたのだったか。
それを優先してミカヅキに戻るよう勧めた、と受け取るのは自然な事。
(初めて会見した時も、あの子たちはミソカに一切相手にされない状況だったんだわ)
そしてそれはこれからも変わらないだろう。
正当後継者の母親である彼女は、家に背くことはない。背けないのではない。背かぬ事で、ミカヅキを守っているのだ。
それは、ミカヅキにとっては厳しいものだろうと思える。
親と子としての二人の間に、レアは立ち入ることができない。
それは許されない。
(ミソカを悲しませることになる)
ミカヅキは普通の少年であってはならない、とレアがお叱りを受けた日の夜。
ミソカが泣いた。
「レアはあの子が普通でなければ幸せでないと思っているの?わたくしはそんな非情な世界にあなたを縛り付けてしまったの?わたくしが、ただ、あなたにそばにいて欲しいと思ってしまっただけで」
違う。そんなつもりじゃない。そんなつもりで言ったのじゃない、とどんなに言葉を尽くしてもミソカの涙は止まらなかった。
レアを哀れんで、それよりももっと自分を責めて、ミソカが泣いたのは学生の時とこの夜だけ。
レアは知らなかったのだ。上流社会がどんなものか。そこで育つということがどんなことなのか。多くを学び、この世界の住人になるため必死に努力を重ねても、生まれたままのレアの根底は決してミソカと同じにはなれない。
休む事なく後継者教育を詰め込まれ、大人たちの要求がどれほどの高みを指そうともそれを成し遂げ、数多の難関を次々と超えていくミカヅキの毎日を目にしていて、ふとミカヅキがとった些細な行動が、レアには愛らしく映った。その年齢にふさわしく、子供らしい単純な行動が、珍しくて可愛らしくて、つい言ってしまったのだ。
「ミカヅキ様も普通の男の子ですもの」と。
その言葉が禁忌だという感覚さえもない。知識はどれほど高められても、心からの支配にはなり得ない。感情は、心は、知識だけで導かれるものではないのだ、とあの時、レアは思い知らされた。
どれほど時を過ごしても、きっとこれだけはミソカと分かり合えない。
生まれと育ち。人を作るのは育ちと考えます、と侯爵家の礼儀の講師にも言われた事。
成人まで民間人として育った自分には、同じ期間を公人として育ったミソカには決して追いつけない部分がある、と自分を戒めてここまできたつもりだが。
「ミソカ様は、お立場上、ミカヅキ様のご友人をお認めになることができないだけですわ」
つい、そう、ミカヅキに進言する。
レアにとって唯一無二はミソカだ。ミソカがいればこそ、ミソカの子だからこそ、ミカヅキの事も我が子の様に思えるのだから。
二人の橋渡しになれれば、という、今まで封印してきた思いがここにきて溢れてしまった。
それは王城で見たミカヅキの変化があったがゆえに。
その思いをミカヅキが汲み取れるとは思っていない。今日から始めるのだ、という細やかな初手のつもりで。
それは分かります、とミカヅキが返し、この話はここで終わるはずだった。
だが、ミカヅキは続けた。
「侯爵家でも、ほかの家にも、彼らを認められるとは考えていませんし、私自身、認めてもらわなくてもいいと思っています」
その意志は、冷えた言葉とは裏腹に、確かな熱量があった。
今までのミカヅキとは明らかに違う、遥か高み以外の一切を必要ないと言い切る様なそれではない、と感じ取ってレアは息を飲む。
続けられた言葉は、さらに温もりをもたらす。
「ただ、母上にだけは認めてもらわなくては、と思っています」
そのために、こうして急ぎ館に戻るのだ、とでもいう様な意志。
「まあ、どうして」
驚くレアに向けられたミカヅキの視線は、親を慕う子のそれだった。
「彼らが、母親に心配かけさせるものじゃない、というので」
情、というものが人を動かす。
正しき道にも、過ちの道にも、柵はなく、ただ情という流れに沿って人は動かされて、その先にあるものを見る。
彼らは、ミカヅキは、自分たちの保身のために動いたのではなかった。
ただ母親を安心させるために、その存在を認めさせるという純粋な動機に触れて、レアはそれ以上何も言うことが出来ない。
ミソカとミカヅキの間にいて何をすることも許されず耐えるしかなかった日々は、とっくに終わっていたのだと知る。
友人に支えられて成長するミカヅキが、ミソカも、その間に立たされるレアの事も、その情に巻き込んで行く。
「そういうことでしたら」
ミカヅキは知らない事。
自分の母が、学生時代に民間人と交流を持とうとした事。そして交流の先に希望を見た事、夫を亡くし子のために上流社会でただ一人嵐に立ち向かうためにその手でレアにすがったこと。
レアが民間出である事さえも耳に入れられぬ環境で育った彼には、想像さえも出来ないだろう。
「陰ながら応援させていただきますわ」
レアとミソカの間にある決して埋められぬ溝。
それさえもミカヅキが埋めてくれるのではないかという希望をみる。
それほどに成長したミカヅキは、ありがとうございます、と微笑む。
二度目のそれは、今度こそ確実に受け止めることが出来た。
レアに向けられた親愛。
そして、同じく親愛をむけられるべき相手が待つ場所へ、馬車は走る。
(待っていてミソカ。私たちが身を置く世界は決して非情なんかじゃない)
それが分かった。レアにも、今日やっと。
分かり得る希望が、今、深い深い場所へ誘われた自分たちをしっかりと結びつけようとしている。

にほんブログ村