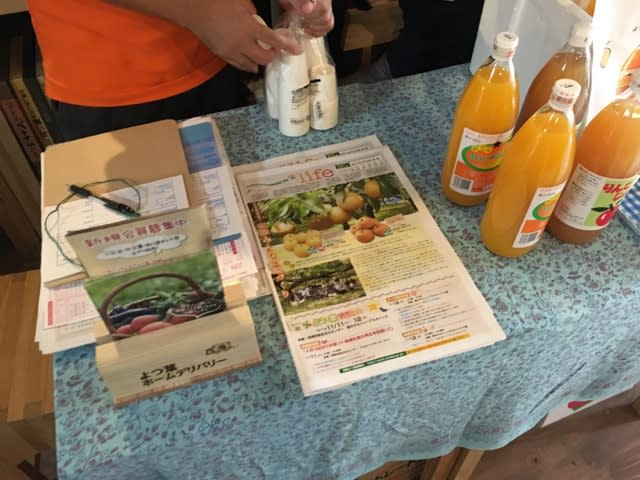のどが渇く、肌が乾燥する、めまい、かすみ目、空咳が出る、手のひら足の裏が暑い、ほてる、のぼせる、便秘、寝汗など体の潤い不足【陰虚(いんきょ)】の方は早く寝ましょう!
— CoCo美漢方(ここびかんぽう) (@mococo321) 2017年9月4日 - 10:12
夜は「陰」の時間。いつもより30分早く寝るだけでこれらの症状緩和… twitter.com/i/web/status/9…
肺は清気(酸素)と濁気(二酸化炭素)を交換する呼吸機能だけでなく、水分代謝を調節、体温調節、外邪を寄せつけない免疫といった様々な役割を担っています。
— CoCo美漢方(ここびかんぽう) (@mococo321) 2017年9月4日 - 10:43
健康な肺は体液や血液といった「陰液」で潤っていますが、これらの機能は、肺が十分に潤っている事でバランスよくその役割を果たします。
しかし、夏バテで栄養が十分に摂れていなかったり、夏の疲れをそのまま引きずったり、ストレスが溜まっていたりすると、身体の免疫力が低下し、肺は秋の「燥邪」の影響を受けやすくなってしまいます。
— CoCo美漢方(ここびかんぽう) (@mococo321) 2017年9月4日 - 10:47
燥邪によって潤いが不足すると、肺の機能が低下し、身体全体にさまざまな不調が現れます。
肺が燥邪の影響を受けると、のどや鼻、目の乾燥、乾いた咳、粘りのある痰、口の渇きといった呼吸器のトラブルのほか、寝汗、午後になると微熱が出る、皮膚の乾燥やかゆみを感じたり、体内の潤い不足から便秘しやすくなります。
— CoCo美漢方(ここびかんぽう) (@mococo321) 2017年9月4日 - 10:50
このような症状を感… twitter.com/i/web/status/9…
姫里ゲストハウスいこね&くじらカフェのFacebookページを作りました。
— あおぞら財団 (@aozorazaidan) 2017年9月4日 - 18:03
みなさま、「いいね」「フォロー」をよろしくお願いします。
facebook.com/iconekujiracafe... fb.me/3fQXEM7OU
秋といえば、さつまいもも美味しい季節☆
— イスクラ薬局【公式】 (@ISKRAkanpo) 2017年9月2日 - 10:40
腸の働きを活発にするため、便秘の解消や改善にオススメ!薬膳的には、胃腸の働きを元気にする「健脾(けんぴ)」「補気(ほき)」作用が期待出来ると言われています!
さつまいもに含まれるヤラピンは、さつまいもを切った時に見られる白い液体であり、ヤラピンは腸の働きを活発にし、食物繊維との相乗効果で便秘解消の働きがあるそうですよ☆
— イスクラ薬局【公式】 (@ISKRAkanpo) 2017年9月2日 - 10:41
秋の三ヶ月は実りと収穫の季節である。時に冷たい風も吹き、葉も枯れ落ちる。この季節の特徴に従って早寝早起きし、過労せず、気持ちを穏やかに保ち、冷たい空気にあまりさらされない様にするのがよい。これが秋の良い養生方法である。もしこれに逆… twitter.com/i/web/status/9…
— 漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2017年9月1日 - 18:20
秋は、夏の暑さで強まっていた陽気(陽)が影をひそめ、代わりに寒気や冷気(陰)が徐々に強まる陰陽転化の時期で、草木は枯れ生と死が交差する季節です。この変化に身体も順応しなくてはいけず、うまく対応できないと不安や怒り、悲しみなどの精神的な症状も現れやすくなります。
— 漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2017年9月1日 - 18:20
秋の養生としては、冷えるもの、冷たい風に気を付けること。そして、早寝早起きを心がけ、心は穏やかに過ごすことが大切です。朝のきれいな空気を肺一杯に取り込んで清気を養うことなども良いでしょう。
— 漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2017年9月1日 - 18:21
貝原益軒の養生訓の中では、“秋はまだ夏の間に開いていた肌(汗腺)がまだ閉じておらず、冷たい秋の風に痛められやすい”と述べられています。
— 漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2017年9月1日 - 18:21
やっと涼しくなって、心地よく感じられる秋の涼しい風ですが、暑い夏よりも影響を受けやすいので注意が必要といわれています。
中国の食の古典、『食経』では、〝秋の気は、燥なれば、よろしく胡麻を食ふべし。冷たい飲食や、寒すぎる衣服は禁ず。肺の病には、苦きものを食ふを禁ず。小麦、羊肉、杏、ラッキョウの類を食ふべし。気の病には、多く辛きものを食ふことなかれ。″とあるのでご参考に。
— 漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2017年9月1日 - 18:22
秋の養生は体液、血液を補い、体内の気を引き立たせ、肺の乾燥を予防することが大切です。
— 漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2017年9月1日 - 19:08
オススメ食材は、
・長芋類
・蓮根、百合根、梨、豆乳、松の実、銀杏、白きくらげなど白いもの
・ビワ、メロン、桃、ぶどうなど果実
・サンマ、牡蠣、タチウオ、エビなど
・蜂蜜、胡麻など
酢鯖*イライラ、ストレス、緊張などで気血の流れが悪く、冷え性・特に手足先が冷えたり、月経痛(血塊が出る)、頭痛などの症状にオススメ薬膳
— 漢方マイン堂 (@mine_kanpo) 2017年8月19日 - 13:56
サバが気血を補い血を巡らし、酢・玉ねぎは血流を促します。玉ねぎ・ミカンの皮は気を巡らせる効果あ… twitter.com/i/web/status/8…
*玉ねぎ[甘・辛味/温性/帰経:肺胃]
— 漢方マイン堂 (@mine_kanpo) 2017年8月19日 - 14:22
玉ねぎは滞った気血の流れに作用。精神的ストレスの解消、お腹の張り、頭痛や肌のくすみに◎
温性のため、肌の赤みなど熱症状がある方は取りすぎには注意しましょう。
玉ねぎの辛味は、酢などの酸味を効かせると和らぎます☺︎
*サバ[甘味/温性/帰経:脾胃]
— 漢方マイン堂 (@mine_kanpo) 2017年8月19日 - 14:24
サバは、元気が出ない・疲れやすいなど虚弱体質の方に特にオススメです。
中医学では体を温めて血の巡りを良くしますが、現代的にも血圧や血中コレステロールを低下させたり、DHA・EPA・ビタミンEなどの良質な脂質が、血管を拡張・血行を促します☺︎
慢性的な口内炎は栄養不足ではない場合も!?
— 吉祥寺東西薬局 (@KichiKanpo) 2017年8月3日 - 15:46
口内炎の原因も様々ありますが、胃腸の働きの低下が関わっている場合は多いです。
ビタミン剤飲んでるのに治らない、野菜とってるのに・・・・
そんな方は一度胃腸を休めてあげるとコロッと治ったりします。
あえて食べる量を減らすのも治療です。
夏場に冷たいものなど暴飲暴食の付けが回ってくる時期です。
— 吉祥寺東西薬局 (@KichiKanpo) 2017年9月2日 - 14:50
口内炎の相談も増えてますので、夏に無理したかなーって方は、早めに胃腸のケアを忘れずに! twitter.com/KichiKanpo/sta…
中医学では季節の変化は感情にも影響すると考えます。
— 漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2017年9月2日 - 15:47
秋と関連の深い感情は、「悲しみ」です。「悲則気消」と言って、悲しみは気を消耗しますので、悲しみ過ぎると、カゼを引きやすくなったり、春の花粉症が悪化したりします。悲しみに勝つのは… twitter.com/i/web/status/9…
秋の養生は特に、ゆったりとして、焦らず、出来なかったことも悔やまず、おおらかに構える心持が大事です。
— 漢方のミドリ薬品 (@PandaKanpo) 2017年9月2日 - 15:49
食では、乾燥を補うように潤いの食材を摂るようにします。梨や白菜、とうふ、松の実などの白い食材が良いですよ。ブドウも、柿も良いで… twitter.com/i/web/status/9…