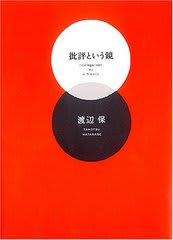
最近読んだというより、最近買った本なんだけど、じつはほとんど読んでいるってなんのこと?って言われそうですが…。
一部からは「やっぱり、これ?」と言われそうだけど、まあ行き掛り上しょうがないってことでこの本。この本は、演劇評論家の渡辺保氏が自身のHPでやっている歌舞伎の劇評を本にまとめたもの。
ほとんど読んでいるし、ほとんどの芝居は観ているので、この本というのは個人的にも感慨一入。しかし読み返してみると私と見解の違うところが随分ある。でもこの人の言い切りぶりには結構影響を受けていて、嫌いじゃないんですよね。
歌舞伎に限らず、演劇批評の問題点って、出版物の場合、上演期間に批評が間に合わないってところにある。その点、海外の新聞って初日に厳しい批評を書いたりして存在感あるようですが。日本の新聞(たいていは夕刊)に載ってる劇評って、短いせいもあるけど何を言いたいのかわからないものが多い。ほとんど旦那芸の世界というか、谷町批評という印象。といって、公演前の記事は結局のところ宣伝に過ぎないし…。(少なくとも文化面に関しては日本の新聞に信憑性ってないんじゃないですか?極端に言えば、もはや誰も読んでいないと思う。つまり、少なくとも日本では、新聞はその役目を終えつつあるというのが私の見方。)
というわけで、ネットと演劇批評というのはとても相性がよいものだと思う。しかも、すでに名のある評論家渡辺氏が字数を気にせず、言いたい放題書いているということに敬意を表したい。
だいたい歌舞伎を語る人って役者の知り合いぶりたがる輩が多すぎる。さもなければ、単なる「昔の役者はよかった」というような詠嘆調か。
CS歌舞伎チャンネルの登場で、過去の名演と最近の舞台を簡単に較べられるようになったし、これからは単純に「昔はよかった」は通用しなくなる。このあたり、記録メディアの登場とクラシックの関係に近いものなのかもしれない。あるいは、パソコンと将棋の関係とか…。確か、岡田斗志夫が「家庭用ビデオの普及でオタクは進化した。」と発言していたけど、歌舞伎批評にも同じような波が訪れようとしているかもしれない。
で、肝心のこの本について。2000年の新之助(当時)初役の『助六』に始まり、2004年6月の海老蔵襲名の『助六』で終わっている。いかに海老蔵という役者が若いにも拘らず大きな役者で、歌舞伎を語りたい人の心を揺さぶる存在かということが伝わってくる。この点は私も深く同意するし、<芝居体験の同時代性>を考える時に、「昭和の歌右衛門」と同じような意味を持つのが「平成の海老蔵」なんじゃないかと最近よく考えてしまう。(好き嫌いの感情を越えたところで。)
結局のところ、この本、私は自分の書かれざる日記を買うようにして買った。芝居という“ナマモノ”に同時期に触れ合った印として。所詮、<同時代性>なんて他人の肉体や他人の言葉を通してしか確認できないものなのだという思いに駆られながら…。
『批評という鏡』
・渡辺保氏のHP
一部からは「やっぱり、これ?」と言われそうだけど、まあ行き掛り上しょうがないってことでこの本。この本は、演劇評論家の渡辺保氏が自身のHPでやっている歌舞伎の劇評を本にまとめたもの。
ほとんど読んでいるし、ほとんどの芝居は観ているので、この本というのは個人的にも感慨一入。しかし読み返してみると私と見解の違うところが随分ある。でもこの人の言い切りぶりには結構影響を受けていて、嫌いじゃないんですよね。
歌舞伎に限らず、演劇批評の問題点って、出版物の場合、上演期間に批評が間に合わないってところにある。その点、海外の新聞って初日に厳しい批評を書いたりして存在感あるようですが。日本の新聞(たいていは夕刊)に載ってる劇評って、短いせいもあるけど何を言いたいのかわからないものが多い。ほとんど旦那芸の世界というか、谷町批評という印象。といって、公演前の記事は結局のところ宣伝に過ぎないし…。(少なくとも文化面に関しては日本の新聞に信憑性ってないんじゃないですか?極端に言えば、もはや誰も読んでいないと思う。つまり、少なくとも日本では、新聞はその役目を終えつつあるというのが私の見方。)
というわけで、ネットと演劇批評というのはとても相性がよいものだと思う。しかも、すでに名のある評論家渡辺氏が字数を気にせず、言いたい放題書いているということに敬意を表したい。
だいたい歌舞伎を語る人って役者の知り合いぶりたがる輩が多すぎる。さもなければ、単なる「昔の役者はよかった」というような詠嘆調か。
CS歌舞伎チャンネルの登場で、過去の名演と最近の舞台を簡単に較べられるようになったし、これからは単純に「昔はよかった」は通用しなくなる。このあたり、記録メディアの登場とクラシックの関係に近いものなのかもしれない。あるいは、パソコンと将棋の関係とか…。確か、岡田斗志夫が「家庭用ビデオの普及でオタクは進化した。」と発言していたけど、歌舞伎批評にも同じような波が訪れようとしているかもしれない。
で、肝心のこの本について。2000年の新之助(当時)初役の『助六』に始まり、2004年6月の海老蔵襲名の『助六』で終わっている。いかに海老蔵という役者が若いにも拘らず大きな役者で、歌舞伎を語りたい人の心を揺さぶる存在かということが伝わってくる。この点は私も深く同意するし、<芝居体験の同時代性>を考える時に、「昭和の歌右衛門」と同じような意味を持つのが「平成の海老蔵」なんじゃないかと最近よく考えてしまう。(好き嫌いの感情を越えたところで。)
結局のところ、この本、私は自分の書かれざる日記を買うようにして買った。芝居という“ナマモノ”に同時期に触れ合った印として。所詮、<同時代性>なんて他人の肉体や他人の言葉を通してしか確認できないものなのだという思いに駆られながら…。
『批評という鏡』
・渡辺保氏のHP



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます