
先週の日曜日はテレビもネットもやっていなかったので、深夜になって訃報を知りました。しばし、茫然・・・。公演中止のあたりから嫌な予感はしていましたが、まさか・・・。しかし、おおらかな人柄とは違い、波乱万丈の役者人生だったのではないでしょうか。ご冥福をお祈りいたします。
歌舞伎界最高の名跡継承者にして、おおらかで謙虚な人柄が愛された十二代目。今の海老蔵が襲名する際、松竹の故永山会長の元を訪れて、「今後のことはすべて必ずお父さんと相談すること」と説教されていたのが印象的でした。それくらい、永山会長からの信頼も厚かったってことでしょう。
また、若い頃、口跡の難を指摘された十二代目が常磐津一巴太夫に弟子入りを志願した話も有名で、一切の特別扱いを断って、一人の弟子として教えを請うたという逸話も、十二代目の謙虚な人柄を偲ばせるエピソードといえましょう。(一巴太夫の身内は皆、その人柄から團十郎のファンになってしまったとか。)
そんなわけで、花形役者ながら癇癪もちでトラブルメイカーの気味のあった先代十一代目の特質を隔世遺伝(?)で受け継いでいるのが息子・海老蔵で、十二代目はその癇癪持ちの夫を支えた十一代目夫人の特質を受け継いでいるという気がします。
(なお、十一代目夫人をモデルにしているという宮尾登美子原作の小説『きのね』は芸道物小説の金字塔。成田屋贔屓のなかにはこの作品を嫌う人もいますが、わたしは大好きです。)
さて、よくあるエピソード的、プロフィール的な話はこのあたりにして、やはり本格的に語らなければいけないのは、芸の話でしょう。
生前は、賛否両論、好き嫌いの分かれた十二代目の芸。その原因は独特の口跡にあったと思いますが、これは単なる声の問題ではなくて、芸の質に根ざしたものだったと思います。
九代目團十郎から六代目菊五郎にいたる心理主義、リアリズム系の芝居からすると、十二代目の声は動物的であり、ピリピリとした心理主義のそれとは相容れない鷹揚なものでした。つまり、平たくいえば、新劇的な演技の基準では大根役者にみえたということなんですが、そもそも、歌舞伎の演技における近代主義なんて、歌舞伎400年の歴史からすると、むしろ異端でしょう。
その点で、戦後歌舞伎の名優たちのなかでもとりわけ六代目菊五郎のリアリズム志向を受け継いだ二世尾上松緑が、十一代目の死後、十二代目にとって親代わりだったということは、若い頃の十二代目の悩みを深くしたのではないでしょうか?そして、十二代目の擁護者が、戦後歌舞伎のなかの「反近代主義の権化」六代目中村歌右衛門だったというのも、象徴的なことだったと思います。
と、少々わかりにくい表現が続いたので、極々簡単に要約すると、近代演劇の心理主義リアリズムと対極にあるのが十二代目の芝居の特徴で、具体的にいうなら、ミュージカル「ラマンチャの男」も演じる歌舞伎俳優松本幸四郎のアプローチとは正反対だっていうのがわたしの理解。神経症的性格俳優タイプではなく、ある種の仮面劇のような、明朗かつ太平楽な存在感が十二代目の舞台の真骨頂でした。それゆえに、「半七捕物帳」みたいなリアリズムの芝居には説得力がなかったかわりに、宇宙人的な不思議さの似合う荒事には、この人ならではの楽しさがあった。そして、その楽しさの源に、独特の鼻にかかったあのバリトンボイスがあったんですよね~。
で、このあたりで具体的な舞台の話に移って行きたいのですが、「勧進帳」、「助六」、「暫」については誰でも書くでしょうし、わたしはへそ曲がりなので、他の芝居から語っていこうと思います。
まず、個別の芝居でわたしが忘れられない第一は、国立劇場でやった「義経千本桜」の通し。渡海屋・大物浦の知盛は白装束の花道の出からして勇壮だったし、いがみの権太はいかにも十二代目らしい口跡の、陽性の権太。狐忠信は、「出があるよ」のところこそ(舞台正面の階段から仕掛けで出てくるところね)ちょっと白い牛みたいだったけど(笑)、狐の哀切さの残るよい舞台でした。というわけで、三役とも今なお記憶に残る!
次が、坂田藤十郎と共演した「毛剃(けぞり)」。勇壮で荒事味のある毛剃役の十二代目に、上方のつっころばしという感じの藤十郎の宗七。まさにこの二人のためにあるような芝居で、十二代目のもつおおらかさと、藤十郎のもつ楽天性があいまった素晴らしい舞台でした。こういう味のある舞台は、この二人以外考えられないですね~。
そして、現在では、吉右衛門、仁左衛門、幸四郎が得意とする「河内山(こうちやま)ですが、十二代目の舞台は独特でした。前記三人の舞台も傑作ですが、十二代目の特色は音楽性の一言に尽きる。「勧進帳」を除けば、もっとも十二代目の台詞の音響性が生かされた舞台で、個人的な好みでいうなら、晩年のものほど、実録風から離れていき、やりたい放題で楽しかったですね~。この舞台と比較すべきは、落語家三代目春風亭柳好の「野ざらし」あたりじゃないかと思います。或いは古今亭志ん朝の「夢金」とか「御慶」あたり。
国立劇場での「吃又」も坂田藤十郎との共演が素敵でした。この芝居だと、吉右衛門、三津五郎はリアリズム的な傑作で、富十郎と十二代目だと明るい「泣き笑い」の舞台になった。
また、「毛抜」の両刀使いのヒーロー粂寺弾正も、他の役者がやると真面目すぎておおらかさに欠けるんですが、十二代目だとパタリロ的な両性具有感がありましたね~。
そして、最後は歌舞伎じゃないのですが、新派100年記念公演の三島由紀夫原作「鹿鳴館」!善だか悪だかわからない異様なペルソナ影山伯爵役は、三島の意図を飛び越えた怪演だったと思います。
(わたしの印象に残った十二代目の舞台)*思いつくまま・・・
・「義経千本桜」通し(国立劇場)
・「毛剃」(歌舞伎座 團菊祭 坂田藤十郎)
・「河内山」(歌舞伎座)
・「吃又」(国立劇場、おとく=坂田藤十郎)
・「文七元結」(新橋演舞場 最初のガン治療からの復帰舞台)
・「勧進帳」(富樫=仁左衛門、大阪松竹座)
・「太功記 十段目」(光秀)
・「妹背山女庭訓」鱶七
・「毛抜」
・「髪結新三」(新三=菊五郎、大家=團十郎)
・「鹿鳴館」(新派)
ということで、富十郎がなくなったときには、花道逆七三から聞こえてくる、ピンと張った声がもう聞けなくなるんだという、落胆というか悲しみがあったんですが、十二代目團十郎の訃報に接し、あの独特の鼻から響かせたような太い声、おそらくは身内にも継承者をもたないあの声が、もう聞けないんだと、つくづく思いました。
そういえば、勘三郎も最晩年は声を失ってしまったというし、歌舞伎ばかりでなく、落語でも立川談志の最晩年は声を失ってしまったという話。(なお、ほとんど声の出ない、かすれ声で語った談志最後の「芝浜」を生で聞けたのは、わたしの良い思い出です。)
また、わたしが最後に観た十二代目の舞台は、くしくも十月後半(10月21日)の新橋演舞場(昼の部)「勧進帳」弁慶でした。十月前半(10月6日)に見た夜の部「勧進帳」富樫役では元気だった十二代目が、わたしが最後に観た月末の弁慶では疲労困憊ぶりが素人目にもわかる状況。そんな不十分な体調のなかでも、声を張るべきところとそうでもないところの緩急を使って、なんとか舞台を最後まで勤めようという十二代目の姿に、その日のわたしは感動したものです。談志最後の「芝浜」同様、万全の体調の舞台ばかりが、観客を感動させるものではないということですよね。
もちろん、十二代目の「勧進帳」弁慶としては、仁左衛門の富樫で観た大阪松竹座の舞台が個人的には最高でした。幸四郎、吉右衛門兄弟の腹芸タイプの弁慶でもなく、仁左衛門のさわやかな口跡の弁慶(今の海老蔵の弁慶はあえていうなら仁左衛門のタイプに近い。)とも違う、唸るような、独特の音楽的調子をもった、病気前の勢いのある弁慶!くどいようだけど、三代目春風亭柳好の「野ざらし」や「鰻の幇間」みたいな、言葉の意味がどうこうじゃない楽しさ・・・。(ちなみに、先代の十七代目中村勘三郎が知るひとぞ知る演芸通であり、なかでも三代目春風亭柳好を贔屓にしていたことは、もっと記憶されてもいいことかもしれない!)
そんなわけで、無理やりなこじつけかもしれませんが、生の体験とか記憶って、視覚より聴覚優先とでもいうのか、開高健の晩年の作品に『耳の物語』という作品がありますが、生の体験の本質は耳にあるんじゃないかと思ったりもします。歌舞伎の世界では、「一声、ニ顔、三姿」という言葉がありますが、ジャズミュージシャンのエリック・ドルフィー最後の言葉(「音楽は虚空に消え、二度ととらえることはできない」)じ ゃないけど、十二代目團十郎の声が虚空に消えていってしまったという喪失感。
このブログは、歌舞伎劇評を始めた当初、勘三郎(当時勘九郎)や福助、幸四郎・染五郎親子を激しく批判する一方、古い歌舞伎ファンからとかく批判もあった十二代目團十郎を断固擁護。全然普及していませんが、「團十郎=エーリッヒ・フォン・シュトロハイム説」なる新説を掲げたりもしたものでした。
しかし、この二ヶ月あまりで、勘三郎、團十郎が相次いでこの世を去り、個人的にも自分の観劇歴に一区切りがきたなあ~との感慨があります。
そして、思うのは、とにかく自分の観た舞台について記述していこうという、あらためての決意。今後、十二代目團十郎が歴代の團十郎の中でどう評価されていくのかわかりませんが、わたしのように観て感じた観客がいた証拠を残しておこう。そう決意させてくれた今回の訃報とこの数日でした。ありがとう、十二代目市川團十郎丈。あなたの声と姿をわたしは忘れない。
<過去に書いた記事>
・<私の役者寸評。>① 十二代目市川團十郎
・わたしの「團十郎=シュトロハイム論」

歌舞伎界最高の名跡継承者にして、おおらかで謙虚な人柄が愛された十二代目。今の海老蔵が襲名する際、松竹の故永山会長の元を訪れて、「今後のことはすべて必ずお父さんと相談すること」と説教されていたのが印象的でした。それくらい、永山会長からの信頼も厚かったってことでしょう。
また、若い頃、口跡の難を指摘された十二代目が常磐津一巴太夫に弟子入りを志願した話も有名で、一切の特別扱いを断って、一人の弟子として教えを請うたという逸話も、十二代目の謙虚な人柄を偲ばせるエピソードといえましょう。(一巴太夫の身内は皆、その人柄から團十郎のファンになってしまったとか。)
そんなわけで、花形役者ながら癇癪もちでトラブルメイカーの気味のあった先代十一代目の特質を隔世遺伝(?)で受け継いでいるのが息子・海老蔵で、十二代目はその癇癪持ちの夫を支えた十一代目夫人の特質を受け継いでいるという気がします。
(なお、十一代目夫人をモデルにしているという宮尾登美子原作の小説『きのね』は芸道物小説の金字塔。成田屋贔屓のなかにはこの作品を嫌う人もいますが、わたしは大好きです。)
さて、よくあるエピソード的、プロフィール的な話はこのあたりにして、やはり本格的に語らなければいけないのは、芸の話でしょう。
生前は、賛否両論、好き嫌いの分かれた十二代目の芸。その原因は独特の口跡にあったと思いますが、これは単なる声の問題ではなくて、芸の質に根ざしたものだったと思います。
九代目團十郎から六代目菊五郎にいたる心理主義、リアリズム系の芝居からすると、十二代目の声は動物的であり、ピリピリとした心理主義のそれとは相容れない鷹揚なものでした。つまり、平たくいえば、新劇的な演技の基準では大根役者にみえたということなんですが、そもそも、歌舞伎の演技における近代主義なんて、歌舞伎400年の歴史からすると、むしろ異端でしょう。
その点で、戦後歌舞伎の名優たちのなかでもとりわけ六代目菊五郎のリアリズム志向を受け継いだ二世尾上松緑が、十一代目の死後、十二代目にとって親代わりだったということは、若い頃の十二代目の悩みを深くしたのではないでしょうか?そして、十二代目の擁護者が、戦後歌舞伎のなかの「反近代主義の権化」六代目中村歌右衛門だったというのも、象徴的なことだったと思います。
と、少々わかりにくい表現が続いたので、極々簡単に要約すると、近代演劇の心理主義リアリズムと対極にあるのが十二代目の芝居の特徴で、具体的にいうなら、ミュージカル「ラマンチャの男」も演じる歌舞伎俳優松本幸四郎のアプローチとは正反対だっていうのがわたしの理解。神経症的性格俳優タイプではなく、ある種の仮面劇のような、明朗かつ太平楽な存在感が十二代目の舞台の真骨頂でした。それゆえに、「半七捕物帳」みたいなリアリズムの芝居には説得力がなかったかわりに、宇宙人的な不思議さの似合う荒事には、この人ならではの楽しさがあった。そして、その楽しさの源に、独特の鼻にかかったあのバリトンボイスがあったんですよね~。
で、このあたりで具体的な舞台の話に移って行きたいのですが、「勧進帳」、「助六」、「暫」については誰でも書くでしょうし、わたしはへそ曲がりなので、他の芝居から語っていこうと思います。
まず、個別の芝居でわたしが忘れられない第一は、国立劇場でやった「義経千本桜」の通し。渡海屋・大物浦の知盛は白装束の花道の出からして勇壮だったし、いがみの権太はいかにも十二代目らしい口跡の、陽性の権太。狐忠信は、「出があるよ」のところこそ(舞台正面の階段から仕掛けで出てくるところね)ちょっと白い牛みたいだったけど(笑)、狐の哀切さの残るよい舞台でした。というわけで、三役とも今なお記憶に残る!
次が、坂田藤十郎と共演した「毛剃(けぞり)」。勇壮で荒事味のある毛剃役の十二代目に、上方のつっころばしという感じの藤十郎の宗七。まさにこの二人のためにあるような芝居で、十二代目のもつおおらかさと、藤十郎のもつ楽天性があいまった素晴らしい舞台でした。こういう味のある舞台は、この二人以外考えられないですね~。
そして、現在では、吉右衛門、仁左衛門、幸四郎が得意とする「河内山(こうちやま)ですが、十二代目の舞台は独特でした。前記三人の舞台も傑作ですが、十二代目の特色は音楽性の一言に尽きる。「勧進帳」を除けば、もっとも十二代目の台詞の音響性が生かされた舞台で、個人的な好みでいうなら、晩年のものほど、実録風から離れていき、やりたい放題で楽しかったですね~。この舞台と比較すべきは、落語家三代目春風亭柳好の「野ざらし」あたりじゃないかと思います。或いは古今亭志ん朝の「夢金」とか「御慶」あたり。
国立劇場での「吃又」も坂田藤十郎との共演が素敵でした。この芝居だと、吉右衛門、三津五郎はリアリズム的な傑作で、富十郎と十二代目だと明るい「泣き笑い」の舞台になった。
また、「毛抜」の両刀使いのヒーロー粂寺弾正も、他の役者がやると真面目すぎておおらかさに欠けるんですが、十二代目だとパタリロ的な両性具有感がありましたね~。
そして、最後は歌舞伎じゃないのですが、新派100年記念公演の三島由紀夫原作「鹿鳴館」!善だか悪だかわからない異様なペルソナ影山伯爵役は、三島の意図を飛び越えた怪演だったと思います。
(わたしの印象に残った十二代目の舞台)*思いつくまま・・・
・「義経千本桜」通し(国立劇場)
・「毛剃」(歌舞伎座 團菊祭 坂田藤十郎)
・「河内山」(歌舞伎座)
・「吃又」(国立劇場、おとく=坂田藤十郎)
・「文七元結」(新橋演舞場 最初のガン治療からの復帰舞台)
・「勧進帳」(富樫=仁左衛門、大阪松竹座)
・「太功記 十段目」(光秀)
・「妹背山女庭訓」鱶七
・「毛抜」
・「髪結新三」(新三=菊五郎、大家=團十郎)
・「鹿鳴館」(新派)
ということで、富十郎がなくなったときには、花道逆七三から聞こえてくる、ピンと張った声がもう聞けなくなるんだという、落胆というか悲しみがあったんですが、十二代目團十郎の訃報に接し、あの独特の鼻から響かせたような太い声、おそらくは身内にも継承者をもたないあの声が、もう聞けないんだと、つくづく思いました。
そういえば、勘三郎も最晩年は声を失ってしまったというし、歌舞伎ばかりでなく、落語でも立川談志の最晩年は声を失ってしまったという話。(なお、ほとんど声の出ない、かすれ声で語った談志最後の「芝浜」を生で聞けたのは、わたしの良い思い出です。)
また、わたしが最後に観た十二代目の舞台は、くしくも十月後半(10月21日)の新橋演舞場(昼の部)「勧進帳」弁慶でした。十月前半(10月6日)に見た夜の部「勧進帳」富樫役では元気だった十二代目が、わたしが最後に観た月末の弁慶では疲労困憊ぶりが素人目にもわかる状況。そんな不十分な体調のなかでも、声を張るべきところとそうでもないところの緩急を使って、なんとか舞台を最後まで勤めようという十二代目の姿に、その日のわたしは感動したものです。談志最後の「芝浜」同様、万全の体調の舞台ばかりが、観客を感動させるものではないということですよね。
もちろん、十二代目の「勧進帳」弁慶としては、仁左衛門の富樫で観た大阪松竹座の舞台が個人的には最高でした。幸四郎、吉右衛門兄弟の腹芸タイプの弁慶でもなく、仁左衛門のさわやかな口跡の弁慶(今の海老蔵の弁慶はあえていうなら仁左衛門のタイプに近い。)とも違う、唸るような、独特の音楽的調子をもった、病気前の勢いのある弁慶!くどいようだけど、三代目春風亭柳好の「野ざらし」や「鰻の幇間」みたいな、言葉の意味がどうこうじゃない楽しさ・・・。(ちなみに、先代の十七代目中村勘三郎が知るひとぞ知る演芸通であり、なかでも三代目春風亭柳好を贔屓にしていたことは、もっと記憶されてもいいことかもしれない!)
そんなわけで、無理やりなこじつけかもしれませんが、生の体験とか記憶って、視覚より聴覚優先とでもいうのか、開高健の晩年の作品に『耳の物語』という作品がありますが、生の体験の本質は耳にあるんじゃないかと思ったりもします。歌舞伎の世界では、「一声、ニ顔、三姿」という言葉がありますが、ジャズミュージシャンのエリック・ドルフィー最後の言葉(「音楽は虚空に消え、二度ととらえることはできない」)じ ゃないけど、十二代目團十郎の声が虚空に消えていってしまったという喪失感。
このブログは、歌舞伎劇評を始めた当初、勘三郎(当時勘九郎)や福助、幸四郎・染五郎親子を激しく批判する一方、古い歌舞伎ファンからとかく批判もあった十二代目團十郎を断固擁護。全然普及していませんが、「團十郎=エーリッヒ・フォン・シュトロハイム説」なる新説を掲げたりもしたものでした。
しかし、この二ヶ月あまりで、勘三郎、團十郎が相次いでこの世を去り、個人的にも自分の観劇歴に一区切りがきたなあ~との感慨があります。
そして、思うのは、とにかく自分の観た舞台について記述していこうという、あらためての決意。今後、十二代目團十郎が歴代の團十郎の中でどう評価されていくのかわかりませんが、わたしのように観て感じた観客がいた証拠を残しておこう。そう決意させてくれた今回の訃報とこの数日でした。ありがとう、十二代目市川團十郎丈。あなたの声と姿をわたしは忘れない。
<過去に書いた記事>
・<私の役者寸評。>① 十二代目市川團十郎
・わたしの「團十郎=シュトロハイム論」

 | きのね〈上〉 (新潮文庫) |
| クリエーター情報なし | |
| 新潮社 |
 | きのね〈下〉 (新潮文庫) |
| クリエーター情報なし | |
| 新潮社 |
 | 歌舞伎一期一会 |
| 常磐津 一巴太夫 | |
| エヌティティ出版 |
 | 團十郎復活 |
| クリエーター情報なし | |
| 文藝春秋 |
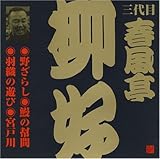 | ビクター落語 三代目 春風亭柳好 野ざらし、他 |
| クリエーター情報なし | |
| 日本伝統文化振興財団 |
 | 耳の物語 (文庫ぎんが堂) |
| クリエーター情報なし | |
| イースト・プレス |
 | ラスト・デイト |
| クリエーター情報なし | |
| ユニバーサル ミュージック クラシック |
 | 三遊亭円朝の遺言 |
| クリエーター情報なし | |
| 新人物往来社 |



























この文章に同感です。パパゲーノ
生前、賛否両論だった團十郎の口跡ですが、もう聞けないとなると実に寂しい限りです。
團十郎の物まねが巧いと評判の桂米團治のでもいいから、あの台詞回しが聞きたいと思う、今日この頃です。