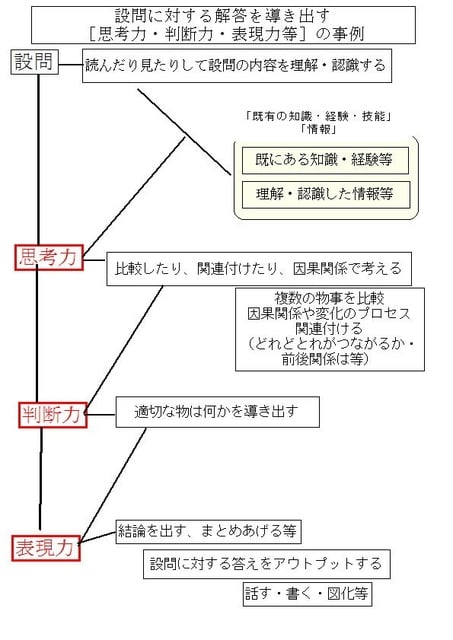「指導言」⇒「発問」「質問」「指示」「助言(ヒント)・示唆・補足」「説明・解説」「評価(称賛・認め)」
授業の成立は教師と子どもたちとの対話による。
文章、写真、絵、グラフ、事物・現象など学習の対象になるが、そこから「不思議や疑問、調べてみたい問題等」に気付かせ、本時のめあてである学習問題(課題)まで高めていくためには、教師の指示や助言、示唆などの指導言の言葉が当然必要になる。
授業のイントロは学習内容に関係する話題をまずは教師が投げ掛けることになる。この話題を豊富に持っていたり、イメージできたりすることは、授業づくりの武器になる。これができる教師は多様な生活経験や子どもとの遊びがものを言っていることが多い。
教師からの投げ掛けの話題が呼び水になり、子どもから関連する話が出てくる。こうなったら占めたもので、相槌を打ったりしながらいろんな子どもたちの声を聞かせることである。
その間、ニコニコしながら本時のめあてになりそうなものをキーワードで関係的・構造的に板書に表す。
「いろんなことに気付きましたね。話してくれた内容を黒板に短い言葉で表しました。これを見てこれから勉強したいことや、みんなで調べてみたい言葉はありませんか」と、発問する。子どもから取り上げられた言葉を赤色で囲み、そのわけも同時に言わせたい。幾つかの言葉が浮かび上がったところで、それらの言葉を活かして、学習問題(課題)を黒板に提示し、子ども達に確認もする。
学習問題(課題)の表示は、「~~調べよう」「~~を考えよう」のみではなく、「~~して、(それを使って)~~をする」にしたい。
一例をあげると、「ツツジの花を観察して、解剖図をつくり教室に掲示する」。次期学習指導要領では「問題解決を成し遂げる力」とうたわれている。
授業のめあてである学習問題(課題)を解決するまでの所要時間数は、1単位時間(45分間)であったり、3単位時間や単元全体の時間を使ったりする場合もある。