労働組合が原発再稼働の促進の署名活動に取り組み20数万人分が集まって政府に提出したと報道されました。福島では未だ8万以上の避難が続き、廃棄もできず、帰還もできない状況が続く中、再稼働を促す署名を労働組合がするというのは驚きです。
再稼働を強行した政府の背後には、財界と共にこのような労働組合の存在があったことが分かりました。
この労働組合は、電力総連と言い、全国の電力会社の組合で230組合、21万8千人を擁する産業別労働組合です。連合に加盟し、原発に反対の菅政権の折には一時対立したと言います。
この労働組合は、電力会社とは労使協調で原発を推進して来て、大きな事故を起こしてもなお再稼働を積極的に働きかけて来ていたのです。そこでは、原発再稼働の促進、もんじゅ活用と核燃料サイクル確立などを訴え、原子力規制庁が一刻も早く適合審査をするべきことなどを訴えています。
もんじゅに至っては国さえもが廃棄を決めなければならないほど税金の無駄使いと維持が困難ものだと言われているのにこの組合はその活用を唱えているのです。
多くの国民や福島の被災者が原発廃棄を呼びかけている中、労働組合員とその家族を動員しての原発再稼働と原発推進運動を全国規模で展開して来ているのでした。労働者の権利と生活のための労働組合が、国民の願いに反するこのような運動を展開しているということは、多くの国民は知らせられていません。一体労働組合の存在意義とはなんなのかと厳しく問いたいものです。
過日、この労働組合の上部団体である、連合の会長が安倍首相と会談をしました。
各新聞でもあまり大きくは伝えていませんが重大な内容を含んでいます。次回はそのことについて・・・。
と、ここまで書いてきて、2011年6月18日「東京新聞」の「こちら特報部」の下記の記事を目にしました。「東京新聞」はすごい!半ばタブーのようになっていることにも切り込んでいます。関心ある方はどうぞ。
(ブログ「日々坦々」より『東京新聞』2011年6月18日)
民主党内原発推進派の母体、電力総連の解剖
国会か地方かにかかわらず、議員にとって最も大切なのは選挙だ。それゆえ、その応援や日常の支援に利益団体は絡み付く。原発の推進については電力会社が自民党、その労働組合は民主党に働き掛けてきた。全国電力関連産業労働組合総連合(電力総連)は福島第一原発の事故後も、原発推進の旗を降ろしていない。そこから応援を受ける民主党。事故の検証などで公正さを貫けるのか。 (佐藤圭、中山洋子)
「福島の事故収束に全力を尽くすというなら、全国の原発を止めても、人員を回すべきでは」
衆院第二議員会館で十七日、ひどい内部被ばくが相次ぐ原発労働者の労働環境改善を国に求める交渉があった。迫ったのは労災被害者を支援する「全国労働安全衛生センター連絡会議」(東京)や市民団体。東電労組や同労組が加盟する電力総連ではなかった。
福島第一原発では事故後、労働者八人が被ばく線量の上限二五〇ミリシーベルトを超える被ばくをし、うち二人は六〇〇ミリシーベルト超もの線量を浴びた。さらに千人以上もの労働者の調査は手付かずの状態だ。
交渉では、緊急時作業の被ばく線量の上限を引き上げた問題に批判が集中した。「少人数の労働者に被ばくのリスクを負わせている」といった指摘に加え、何重もの下請け構造の中で、安全管理や雇用主の責任が確認できているのか、いう疑問の声も上がった。
これに対し、厚生労働省の担当者は「被ばく線量の引き上げは労働者保護の観点から本来あってはならない。緊急作業に限ったもので、拡大解釈は許されない」とし、東電に内部被ばく検査を徹底させると強調した。
原発事故対策では後手後手の国さえも、東電の労働者の安全管理に最低限の疑念を示しているのに比べ、当事者である電力総連や傘下の東電労組の動きは見えにくい。
ちなみに電力総連は二〇〇五年の国の原子力政策大綱についても「数多くの組合員が原子力発電所や再処理工場など原子力職場で働いており、日本のエネルギー政策の一翼を担っているということに自信と誇りを持っています」と、推進の立場を明確にし、今回の事故後もその姿勢を見直す気配はない。
近く原発推進方針を見直すよう電力総連に申し入れる予定という市民団体「福島原発事故緊急会議」のメンバー、岩下雅裕さんは「電力総連は会社と一体の労組。現場労働者の声を封じ込める重しになり、劣悪な労働環境が改善されない原因になっている」と語る。
「これだけの悲惨な原発事故に、海外でも脱原発の動きが進んでいる。電力総連も変わっていくことを期待している」
だが、電力総連の内田厚事務局長は「福島原発の安定化が最優先課題。事故原因が分かっていないのに、原発を見直すべきかどうかの議論はできない」と繰り返した。
「原子力発電は、議会制民主主義において国会で決めた国民の選択。もしも国民が脱原発を望んでいるなら、社民党や共産党が伸びるはずだ」
現場の労働者の健康管理については「電力総連としても、東電に労働者の安全確保の申し入れをしており、改善されてきた。東電は最善のことをしている」と話した。
電力総連は、日本の労働運動の主流派である日本労働組合総連合会(連合)の中核組織だ。旧同盟系で組合員数は約二十二万人。菅内閣の特別顧問を務め、今月四日死去した笹森清元連合会長は、東電労組委員長と電力総連会長を歴任した。
これまで民主党を「票とカネ」で全面的にバックアップし、政権交代で存在感を飛躍的に増大した。東電出身の小林正夫、関西電力出身の藤原正司両参院議員(いずれも比例代表選出)という二人の組織内議員を筆頭に、同党の多数の議員に影響力を及ぼしている。
昨年七月の参院選では、小林氏が約二十万票を獲得して再選。選挙区では四十七人の民主党候補らを推薦、蓮舫行政刷新担当相、北沢俊美防衛相、輿石東参院議員会長ら二十四人が当選した。
政治資金の流れはどうか。〇七~〇九年の三年分の政治資金収支報告書によると、電力総連の政治団体「電力総連政治活動委員会」から民主党議員側への資金提供(判明分、選挙資金含む)の合計額は小林氏四千万円、藤原氏三千三百万円、川端達夫前文部科学相十万円、近藤洋介衆院議員十万円、松本剛明外相五万円などとなっている。
ちなみに旧同盟系労組に後押しされた同党議員の拠点が民社協会だ。同党のグループ分けでは、旧民社党系。川端氏や高木義明文部科学相、中野寛成国家公安委員長ら約四十人が名を連ねる。
電力総連だけの集まりもある。「明日の環境とエネルギーを考える会」だ。電力総連の機関紙によると、〇九年十一月の会合には鹿野道彦農相や細野豪志首相補佐官ら民社協会以外を含む二十六人が出席していた。
電力総連の政治工作は、民主党政権の原発推進政策となって表れる。新成長戦略では「原発輸出」が柱の一つに位置付けられ、国内でも原発増設を目指す方針が打ち出された。電力各社でつくる電気事業連合会と二人三脚で原発を推進してきた自民党も顔負けだ。
なぜ、これほどの影響力を行使できるのか。木下武男昭和女子大特任教授(労働社会学)は「半世紀にわたる労使癒着の結果だ」とみる。 労働運動史をひもとくと、日本電気産業労働組合(電産)が一九四七年に結成されるが、まもなく分裂。六九年、電力総連の前身となる全国電労協が結成され、旧同盟に組み入れられる。木下氏はこう解説する。
「電産は左派的な産業別組合だったが、これを電力会社は嫌った。六〇年代には、労使癒着(協調)体制ができる。組合員が労組に逆らうことは会社に逆らうことと同じ。選挙運動もカンパも拒みにくい。旧同盟と旧民社党が巨大な集票マシンをつくった。民主党になってからは、原発推進が選挙で推薦するか否かの踏み絵になった」
政治評論家の森田実氏は、旧民社系勢力について「人数は多くないが、団結力の固さとベテラン議員の多さで要職に就いている。小沢一郎元代表にべったりかと思えば、菅直人首相を支援する。中間的なスタンスを取りながら最後はうまい汁を吸う体質」と断じる。
電力総連の影響下にある民主党に原子力政策の見直しや原発事故の公正な検証ができるのか。森田氏は悲観的だ。
「旧民社系や電力総連は、事故後も原発を推進し続けるだろう。労働者や国民の安全は二の次という政策が変わるとは思えない。見直しのふりをするのがせいぜいだ」
<デスクメモ> 一九七〇年代後半、山口県豊北町(当時)での原発計画を止めた主力は労働組合の「電産中国」だった。八〇年代前半も、下請け原発労働者を守るべく全日本運輸一般関西地区生コン支部に「原発分会」ができた。だが、そうした運動は次第に消える。原発建設の加速は労働運動の衰退と軌を一にした。 (牧)
再稼働を強行した政府の背後には、財界と共にこのような労働組合の存在があったことが分かりました。
この労働組合は、電力総連と言い、全国の電力会社の組合で230組合、21万8千人を擁する産業別労働組合です。連合に加盟し、原発に反対の菅政権の折には一時対立したと言います。
この労働組合は、電力会社とは労使協調で原発を推進して来て、大きな事故を起こしてもなお再稼働を積極的に働きかけて来ていたのです。そこでは、原発再稼働の促進、もんじゅ活用と核燃料サイクル確立などを訴え、原子力規制庁が一刻も早く適合審査をするべきことなどを訴えています。
もんじゅに至っては国さえもが廃棄を決めなければならないほど税金の無駄使いと維持が困難ものだと言われているのにこの組合はその活用を唱えているのです。
多くの国民や福島の被災者が原発廃棄を呼びかけている中、労働組合員とその家族を動員しての原発再稼働と原発推進運動を全国規模で展開して来ているのでした。労働者の権利と生活のための労働組合が、国民の願いに反するこのような運動を展開しているということは、多くの国民は知らせられていません。一体労働組合の存在意義とはなんなのかと厳しく問いたいものです。
過日、この労働組合の上部団体である、連合の会長が安倍首相と会談をしました。
各新聞でもあまり大きくは伝えていませんが重大な内容を含んでいます。次回はそのことについて・・・。
と、ここまで書いてきて、2011年6月18日「東京新聞」の「こちら特報部」の下記の記事を目にしました。「東京新聞」はすごい!半ばタブーのようになっていることにも切り込んでいます。関心ある方はどうぞ。
(ブログ「日々坦々」より『東京新聞』2011年6月18日)
民主党内原発推進派の母体、電力総連の解剖
国会か地方かにかかわらず、議員にとって最も大切なのは選挙だ。それゆえ、その応援や日常の支援に利益団体は絡み付く。原発の推進については電力会社が自民党、その労働組合は民主党に働き掛けてきた。全国電力関連産業労働組合総連合(電力総連)は福島第一原発の事故後も、原発推進の旗を降ろしていない。そこから応援を受ける民主党。事故の検証などで公正さを貫けるのか。 (佐藤圭、中山洋子)
「福島の事故収束に全力を尽くすというなら、全国の原発を止めても、人員を回すべきでは」
衆院第二議員会館で十七日、ひどい内部被ばくが相次ぐ原発労働者の労働環境改善を国に求める交渉があった。迫ったのは労災被害者を支援する「全国労働安全衛生センター連絡会議」(東京)や市民団体。東電労組や同労組が加盟する電力総連ではなかった。
福島第一原発では事故後、労働者八人が被ばく線量の上限二五〇ミリシーベルトを超える被ばくをし、うち二人は六〇〇ミリシーベルト超もの線量を浴びた。さらに千人以上もの労働者の調査は手付かずの状態だ。
交渉では、緊急時作業の被ばく線量の上限を引き上げた問題に批判が集中した。「少人数の労働者に被ばくのリスクを負わせている」といった指摘に加え、何重もの下請け構造の中で、安全管理や雇用主の責任が確認できているのか、いう疑問の声も上がった。
これに対し、厚生労働省の担当者は「被ばく線量の引き上げは労働者保護の観点から本来あってはならない。緊急作業に限ったもので、拡大解釈は許されない」とし、東電に内部被ばく検査を徹底させると強調した。
原発事故対策では後手後手の国さえも、東電の労働者の安全管理に最低限の疑念を示しているのに比べ、当事者である電力総連や傘下の東電労組の動きは見えにくい。
ちなみに電力総連は二〇〇五年の国の原子力政策大綱についても「数多くの組合員が原子力発電所や再処理工場など原子力職場で働いており、日本のエネルギー政策の一翼を担っているということに自信と誇りを持っています」と、推進の立場を明確にし、今回の事故後もその姿勢を見直す気配はない。
近く原発推進方針を見直すよう電力総連に申し入れる予定という市民団体「福島原発事故緊急会議」のメンバー、岩下雅裕さんは「電力総連は会社と一体の労組。現場労働者の声を封じ込める重しになり、劣悪な労働環境が改善されない原因になっている」と語る。
「これだけの悲惨な原発事故に、海外でも脱原発の動きが進んでいる。電力総連も変わっていくことを期待している」
だが、電力総連の内田厚事務局長は「福島原発の安定化が最優先課題。事故原因が分かっていないのに、原発を見直すべきかどうかの議論はできない」と繰り返した。
「原子力発電は、議会制民主主義において国会で決めた国民の選択。もしも国民が脱原発を望んでいるなら、社民党や共産党が伸びるはずだ」
現場の労働者の健康管理については「電力総連としても、東電に労働者の安全確保の申し入れをしており、改善されてきた。東電は最善のことをしている」と話した。
電力総連は、日本の労働運動の主流派である日本労働組合総連合会(連合)の中核組織だ。旧同盟系で組合員数は約二十二万人。菅内閣の特別顧問を務め、今月四日死去した笹森清元連合会長は、東電労組委員長と電力総連会長を歴任した。
これまで民主党を「票とカネ」で全面的にバックアップし、政権交代で存在感を飛躍的に増大した。東電出身の小林正夫、関西電力出身の藤原正司両参院議員(いずれも比例代表選出)という二人の組織内議員を筆頭に、同党の多数の議員に影響力を及ぼしている。
昨年七月の参院選では、小林氏が約二十万票を獲得して再選。選挙区では四十七人の民主党候補らを推薦、蓮舫行政刷新担当相、北沢俊美防衛相、輿石東参院議員会長ら二十四人が当選した。
政治資金の流れはどうか。〇七~〇九年の三年分の政治資金収支報告書によると、電力総連の政治団体「電力総連政治活動委員会」から民主党議員側への資金提供(判明分、選挙資金含む)の合計額は小林氏四千万円、藤原氏三千三百万円、川端達夫前文部科学相十万円、近藤洋介衆院議員十万円、松本剛明外相五万円などとなっている。
ちなみに旧同盟系労組に後押しされた同党議員の拠点が民社協会だ。同党のグループ分けでは、旧民社党系。川端氏や高木義明文部科学相、中野寛成国家公安委員長ら約四十人が名を連ねる。
電力総連だけの集まりもある。「明日の環境とエネルギーを考える会」だ。電力総連の機関紙によると、〇九年十一月の会合には鹿野道彦農相や細野豪志首相補佐官ら民社協会以外を含む二十六人が出席していた。
電力総連の政治工作は、民主党政権の原発推進政策となって表れる。新成長戦略では「原発輸出」が柱の一つに位置付けられ、国内でも原発増設を目指す方針が打ち出された。電力各社でつくる電気事業連合会と二人三脚で原発を推進してきた自民党も顔負けだ。
なぜ、これほどの影響力を行使できるのか。木下武男昭和女子大特任教授(労働社会学)は「半世紀にわたる労使癒着の結果だ」とみる。 労働運動史をひもとくと、日本電気産業労働組合(電産)が一九四七年に結成されるが、まもなく分裂。六九年、電力総連の前身となる全国電労協が結成され、旧同盟に組み入れられる。木下氏はこう解説する。
「電産は左派的な産業別組合だったが、これを電力会社は嫌った。六〇年代には、労使癒着(協調)体制ができる。組合員が労組に逆らうことは会社に逆らうことと同じ。選挙運動もカンパも拒みにくい。旧同盟と旧民社党が巨大な集票マシンをつくった。民主党になってからは、原発推進が選挙で推薦するか否かの踏み絵になった」
政治評論家の森田実氏は、旧民社系勢力について「人数は多くないが、団結力の固さとベテラン議員の多さで要職に就いている。小沢一郎元代表にべったりかと思えば、菅直人首相を支援する。中間的なスタンスを取りながら最後はうまい汁を吸う体質」と断じる。
電力総連の影響下にある民主党に原子力政策の見直しや原発事故の公正な検証ができるのか。森田氏は悲観的だ。
「旧民社系や電力総連は、事故後も原発を推進し続けるだろう。労働者や国民の安全は二の次という政策が変わるとは思えない。見直しのふりをするのがせいぜいだ」
<デスクメモ> 一九七〇年代後半、山口県豊北町(当時)での原発計画を止めた主力は労働組合の「電産中国」だった。八〇年代前半も、下請け原発労働者を守るべく全日本運輸一般関西地区生コン支部に「原発分会」ができた。だが、そうした運動は次第に消える。原発建設の加速は労働運動の衰退と軌を一にした。 (牧)










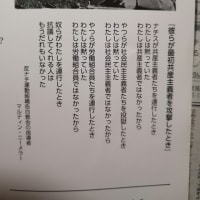










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます