「舟を編む」(三浦しをん著・光文社)を読みました。
辞書づくりの本と聞いてすぐあの『新明解国語辞典』を思い出しました。
編集者の感性までが伝わってくるような言葉の解説が魅力的で他の辞書と比較したくなる辞書です。
この「舟を編む」にも編集者たちの言葉への熱い思いが随所にあり
、登場人物の人物描写の面白さとともにぐいぐい読んでしまう作品。
タイトルは本の帯にある「辞書とは言葉という大海原を航海するための舟」という言葉からうかがえます。
言語学者の松本先生、一見あまりうだつの上がらないようなマジメさん(姓が馬締!)、斜めに構えている感じだが活躍する西岡さんなど魅力的なキャラクターを配置。
言葉にこだわる様々な面白さもさることながら、
会社にとっては非生産的で日の当たらない部署で十数年かけて辞書作りに励む彼らを見出してエンターテイメントとして楽しませてくれた作者の温かいまなざしを感じます。
また、しばしば吹き出すような登場人物たちのやり取り、その中にも辞書が国によって作られると大きな予算がつくだろうが、それでは国家による言語の統制につながるということ、市民が自由に作ることの大切さが伝わってくる部分もあり、笑いの中にも含蓄のある内容だと思いました。
なお、この本は2012年度の本屋大賞に選定されたということです。
辞書づくりの本と聞いてすぐあの『新明解国語辞典』を思い出しました。
編集者の感性までが伝わってくるような言葉の解説が魅力的で他の辞書と比較したくなる辞書です。
この「舟を編む」にも編集者たちの言葉への熱い思いが随所にあり
、登場人物の人物描写の面白さとともにぐいぐい読んでしまう作品。
タイトルは本の帯にある「辞書とは言葉という大海原を航海するための舟」という言葉からうかがえます。
言語学者の松本先生、一見あまりうだつの上がらないようなマジメさん(姓が馬締!)、斜めに構えている感じだが活躍する西岡さんなど魅力的なキャラクターを配置。
言葉にこだわる様々な面白さもさることながら、
会社にとっては非生産的で日の当たらない部署で十数年かけて辞書作りに励む彼らを見出してエンターテイメントとして楽しませてくれた作者の温かいまなざしを感じます。
また、しばしば吹き出すような登場人物たちのやり取り、その中にも辞書が国によって作られると大きな予算がつくだろうが、それでは国家による言語の統制につながるということ、市民が自由に作ることの大切さが伝わってくる部分もあり、笑いの中にも含蓄のある内容だと思いました。
なお、この本は2012年度の本屋大賞に選定されたということです。










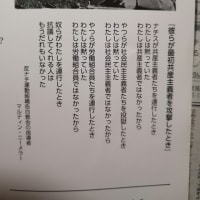










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます