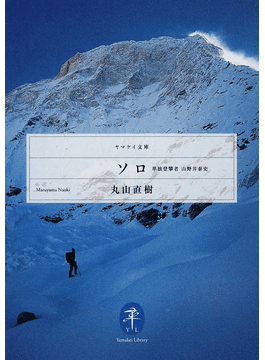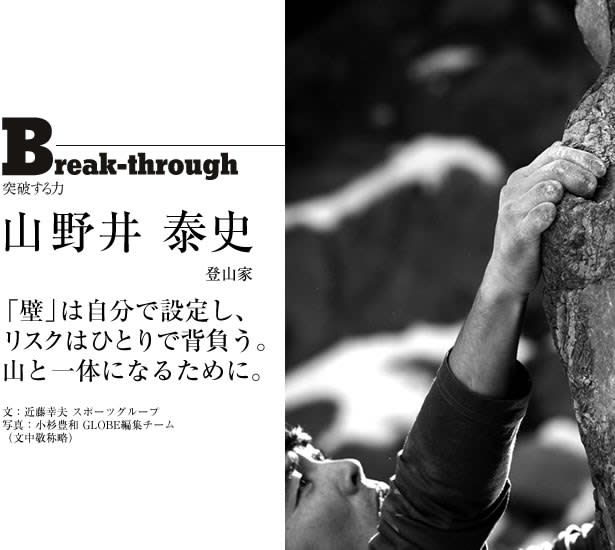吉田修一
『最後に手にしたいもの』★★
もう一冊対になっている赤vr.
ANA『翼の王国』
こちらの装丁もステキ
大掃除も半分済み、昨夜眠る前のひととき電話待ちにさらっと読んでしまった。
白いカーテンを半分だけ洗って、洗っていない方と比べてみた(ただ忘れただけだけど・・)
一年間の汚れをキレイに落とす。
断捨離は思ったより少なく、今年は物をそんなに増やさなかったことを実感
(又は収納がかなり充実している とも言う?)
こちらはほぼ旅行記となっていたけど、伊勢神宮をゆっくり巡ってみたくなった。
内宮と外宮
前回は確か奈良の帰りに立ち寄った記憶
メインで伊勢はどうかしら?
---
自分の好きなものを、「好きだ!好きだ!好きだ!」と堂々と言えることの、なんと気分のいいことか、自分にとって大切なものを、「大切だ!」と叫ぶことの、なんと晴れ晴れすることか。
騙されたと思って、ぜひ読者のみなさんも一度どこかでやってみてほしい。別にエッセイなんか書く必要はない。もちろん誰かのことを犠牲にしないという大前提な話だが、ぜひ自分の好きなものを「好きだ!」と堂々と口にしてみてほしい。大切なものを、「大切だ!」と叫んでみてほしい。
---
よいね「好きだ!」「大切だ!」
(笑)
---
望みを手にするために、誰かの承認を求める必要なんてない。
誰かを羨んだりせず、今の自分自身に満足する。
ユニークで、レアで、大胆な自分自身に。
---
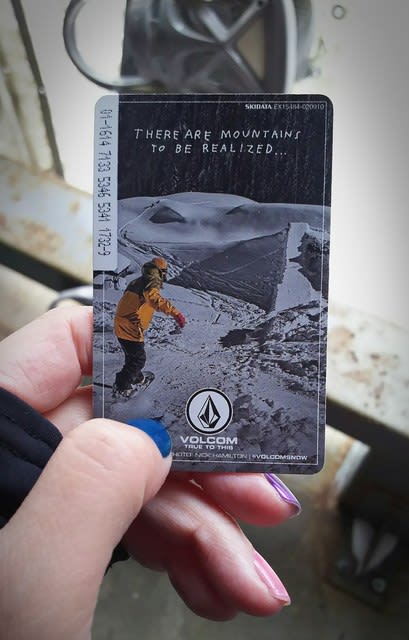
今朝は初雪*
さておせちも取りに行ってきたし(豪華三段重ね♪)
レアな日本酒も既に届いている。
クリスマスに飲めなかったヴーヴは冷やしてね+GODIVA