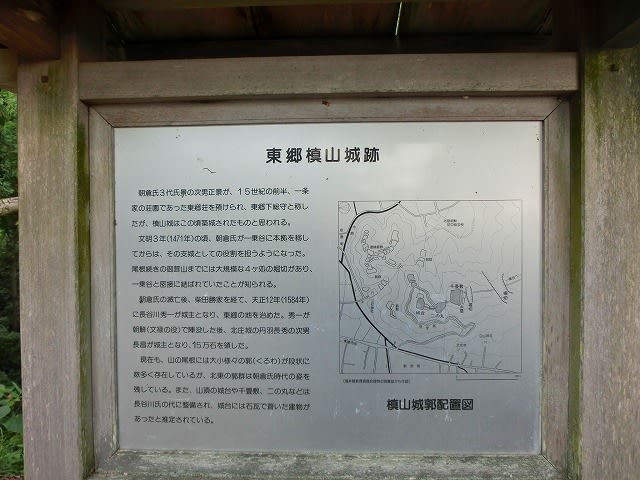2013年9月28日(土)
地形図で兵庫県と岡山県の県境辺りを見ていると、駒の尾山、後山など標高1000mを越える山の名前が並び、中国自然歩道が整備されて道もしっかりしているようだ。ネット検索をすると後山から長義山までの縦走も出来そうだったので行ってみた。
前夜京都を出て宍粟市の道の駅「みなみ波賀」で仮眠。翌朝、ちくさ高原めざして車を走らせ県境の峰越峠手前の長義山登山口に自転車をデポした。鍋ヶ谷林道には船木山の表示があったが、事前の調査でそこまで把握できなかったので、林道入口の少し上にある駒の尾山登山口の看板から登り始めることにする。登山口向いには駐車場も整備されていた。
駒の尾山登山口の大きな標識、船木山登山口も併設
登山道は良く踏まれた道で、「大海里峠」への標識も設置されている。大海里峠で後山からダルガ峰に続く中国自然歩道に取り付く。地形図にある岡山県への道は見当たらなかった。
大海里峠への古道を思わせる道
大海里峠
大海里峠から先ずは南への道を行く。中国自然歩道は始めて歩く道だが、よく整備された道で標識も適度に設置されている。ただ、所々ピークへの距離や方向など?と思う標識も混在していた。
駒の尾山への自然歩道、階段もある
駒の尾山(1281m)は県境からほんの少し西に入った岡山県側にある。展望は360度開けており時間があればゆっくりしたい所だった。430Mhzで神戸市のJG3CCD局と交信する。
避難小屋の建つ駒の尾山山頂への分岐
駒の尾山山頂
山頂から後山方面を見る
縦走路へ戻り後山方向への道を進む。鍋ヶ谷山(1253m)は縦走路の途中にある小ピークだが、樹木に取り付けられた小さなプレート以外に表示は見当たらなかった。144Mhzで姫路市のJI3WBP局と交信する。
鍋ヶ谷山の小さなプレート
次の船木山へも快適な縦走路を進む。途中にある三角点(1235.3m)は見つけることが出来なかった。県境の山には兵庫県宍粟市と岡山県美作市の設置した標識が仲良く並んでいた。船木山ではJI4IVW局とJO4FNP局の交信にブレイクを入れて何とかQSOできた。感謝。
船木山山頂手前から岡山県方面の展望
船木山山頂、宍粟50名山の4番目
後山(1345m)も県境の山だが、岡山県の最高峰になるようだ。山頂には宍粟市、美作市の標識他小さな社もあり展望も良い。明石市からCQを出していたJI3ZOX局を呼んで山ラン終了。
後山山頂
岡山県最高峰の標識
後山での山ランを追え来た道を戻る。船木山手前には鍋ヶ谷林道からの道が来ていた。こちらを使ったほうが時間は短縮できたかも知れない。
船木山山頂南にあった鍋ヶ谷林道に降りる道の標識
大海里峠まで戻って昼食休憩とする。本日5座目のダルガ峰(1163m)への道は倒木で掘り返された根っこの多い道だった。1206.8mの三角点ピークは通らずに岡山県側の巻き道となっている。ダルガ峰手前で中国自然歩道を離れて「ちくさ高原」を示す標識に従う。18Mhzのアンテナを張ってみるが入感局はないようだ。50Mhzに変えて岡山県伊原市移動のJH4NIA局と何とか交信できた。
自然歩道を離れてちくさ高原へ直進
ダルガ峰山頂
本日最後の予定である長義山にさらに県境の道を進む。ちくさ高原スキー場のリフト降り場に着いた後は少しゲレンデの中を歩く。しかし、長義山への道ははっきり分からず、適当に尾根筋に取り付くと長義山への標識があった。その後一部道の不鮮明なところもあり道を失ったりもするが、何とか復帰して長義山に到着した。144Mhzで香川県多度津町移動のJF5KJJ局を呼んで本日の6座を完了することが出来た。
長義山への標識
長義山山頂
長義山から自転車をデポした登山口までススキの踏み跡を下った
今回のコースタイム
駒の尾山登山口→(42分)→大海里峠→(26分)→駒の尾山→(22分)→鍋ヶ谷山→(22分)→船木山→(18分)→後山→(20分)→船木山→(60分)→大海里峠→(20分)→ダルガ峰→(70分)→長義山→(10分)→長義山登山口 (*休憩時間含まず。AM8:00登山開始、PM3:10下山終了。自転車10分の下りで駐車場へ)